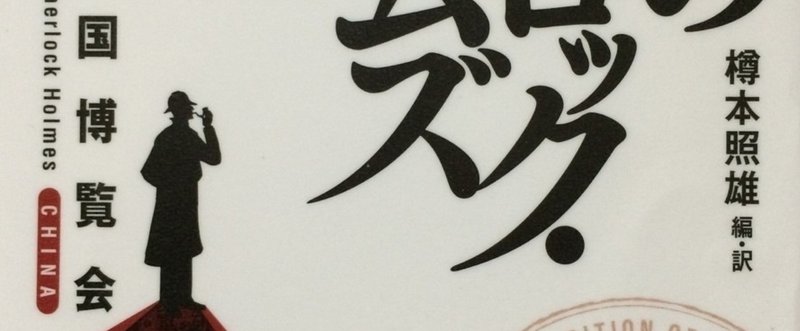
中国のシャーロック・ホームズと中国の翻訳文学の摩訶不思議
「上海のシャーロック・ホームズ(ホームズ万国博覧会:中国編)」(樽本照雄編訳:国書刊行会)を読んで
今更言うまでもないことですが、世に名探偵は数いても、シャーロック・ホームズほどファンが多く、原作からその伝記、生活など様々なことを研究するシャーロッキアンなる人種を生み出しているのが、この名探偵のユニークさなのは明らかです。
今回紹介する、樽本照雄編訳「上海のシャーロック・ホームズ」はなんと清朝末期、まだイギリスではホームズシリーズが盛んに発表されていた時期に中国で書かれたホームズ譚のパロディ、パスティーシュを集めた、という貴重な本です。編者も書くように日本でこのような本が纏められることが信じられないことであると同時に、中国ではありえないことなのだそうです(これについては後でもふれます)。
そして、私がこの本を読んで驚いたのは、まとめられた作品たちの奇妙さだけではなく、編者による作品解題とあとがきに書かれた中国におけるホームズ譚などの翻訳された海外小説の扱いだったのです!
ちょっとびっくりでした、、、
ほんまかいな、って感じ。
▶︎ホームズ譚は世界初の世界規模のパロディ対象
ホームズファンにとって悩ましいのは、コナン・ドイルが書いたホームズ譚が長編4作、短編56作しかないことで、これも、もっと読みたい感と相まって大量のパロディやパスティーシュが生まれる理由でしょう。
ストランド誌にホームズシリーズの短編連載が始まって、わずか数カ月後に最初のパロディは書かれたというのもそれほど人気があったのか(長編「緋色の研究」はそれ以前に発表されていますが)、ホームズの造形がすぐに茶化されるような要素があったというか、、、
それこそ海外でもディクスン・カーを筆頭に有名なミステリー作家がホームズ・パスティーシュを書いていますが、日本でも数多くのパスティーシュは書かれています。木々杢太郎、山田風太郎、甲賀三郎あたりから、加納一郎、柄刀一、芦辺拓、島田荘司など錚々たるミステリー作家が手を染めています。そういう意味でみると、コミケで人気アニメをアマチュアが同人誌でパロディを描くという世界でなく、有名漫画家もそこに参加しまくりみたいな世界、その点で世界初の世界中でパロディされまくったエンタメといえるかもしれません。
ホームズはその世界では、宇宙にも出かける、未来にもやってくる、さまざまな有名人(フロイトだったり、ルイス・キャロルだったり、H.G.ウェルズだったり アインシュタインだったり、ルパンだったり、切り裂きジャックだったり、夏目漱石だったり、、、山ほど)と絡む、世界中を飛び回る、大活躍すぎます。
ホームズ譚を読んでいる人はご存知でしょうが、ホームズはライヘンバッハの滝でモリアーティと格闘して死んだと思われたあと、3年近く行方不明になるわけですが、戻ってきたときにアジア、チベット方面を探検してきたと語ります、そのために、失われた3年を埋めるようなパスティーシュもいくつか書かれています。
テッド・リカーディ「シャーロック・ホームズ東洋の冒険」は著者が東洋学者なのでチベット、インド、東南アジアを舞台にしていますし、加納一郎の「ホック氏、異郷の冒険」は明治の日本、「ホック氏、紫禁城の対決」「香港島の挑戦」は西太后のいる清朝中国が舞台です。
ということで、ホームズとアジアは遠いようで近い要素があります。
▶︎中国のシャーロック・ホームズ
「上海のシャーロック・ホームズ」は中国で書かれた、それも清朝末期1904〜1907年に発表されたホームズ・パロディ、パスティーシュ集です。
日本でのホームズパロディが1920年代以降だったことを思えば、中国の方がずっと先行していたんですね。ホームズ譚自体の翻訳も清朝の方が日本より早かったそうです。
この本には4つのパロディ掌編と3つのパスティーシュ中編が纏められています。
掌編は上海にやってきたホームズが、中国の風習、異文化に振り回されるという、少し笑い者にしたパロディです。この西洋とあまりに異なる文化のためにホームズの推理がうまくいかない、という主題は西洋以外を舞台にするときには大きな要素となりうることは、加納一郎のホック氏シリーズにも受け継がれます(こちらは真面目なパスティーシュですが)。
中編はホームズ譚をちゃんと踏襲しようとしたパスティーシュです。
ただ、ホームズの作品自体がまだ正確に理解されていなかったのか、舞台はヨーロッパなのになにか違和感がいっぱい、どこの世界なのかという奇妙さもいっぱいです。
言葉遣いが中国的比喩に満ちていたり、突然、泣きながら歌いだしたり、中国の伝統的連載物語の体裁だったり、と、異文化感がいっぱいです。でもホームズなんですよw
さらに、地理が変だったり、距離感や時間感覚が変だったりしますし、なぜかベーカー街に住んでるのにハドソン夫人はどの作品にもいないし、ワトソン博士がいなくてなぜか別の人がホームズの協力者で探偵業をしてたりするし、たくさんの部下がいたりもするし、と、ホームズ譚の骨格自体、あまり守ろうという意思がないのか、単にわかってないのか、、
**ここまで破格なものは珍しい。。。 **
そういう意味で、ホームズという探偵が出てきて、そのすごい探偵がなんだかどこの世界がよくわからないところの事件をなんか解決する物語、と思って読むしかないようなところがあります。(そのずれを楽しむのがこの作品集の楽しみ方ですね)
▶︎翻訳が認められない世界
さて、この本は不思議なホームズパロディやパスティーシュを楽しむだけでなく、編者による解題がとても興味深かったのです。
中国でどのようにホームズ譚が紹介、受容されたのかとか、なぜか中国ではシャーロック・ホームズものを「華生偵探案」(ワトソン探偵物語)と呼ばれていて、だれも不思議に思っていない、とか面白いことが書かれていますが、それ以上にショックだったのは、中国における翻訳小説の扱いです。
まず、驚いたのは、この作品集にも入っているパスティーシュの一部が、未だに中国の推理小説研究書やリファレンスにおいてドイル作の真作扱いされていて、誰も疑ってないという話です。ちょっと驚きません?
日本だったら何度もホームズ全集が出てるし、文庫でも手に入るので、どれだけの作品がホームズ譚なのかは自明ですよね。ところが、中国の人は、現代の研究者であっても、中国語でホームズ譚が書かれていたら、それは中国人が創作したのではなく、翻訳作品だと思い込むんだそうです。つまり、パロディやパスティーシュだと思わないというか、そんなことをするのは恥ずかしいことでありえないから存在しないはず、なのだそうです。。。。面白い思考回路ですね。
だから、それが翻訳なのか創作なのかをちゃんとオリジナルに当たって検証さえしない、、、って、**それって学術的研究が無理な姿勢ぢゃないかしらん。 **
そこには歴史的経緯もあります。清朝から中華民国に変わったころに「文学革命」が起き、そこでは自国小説を大事にし、翻訳という行為自体が批判され、西洋の娯楽小説(ホームズ譚に限らず)を翻訳するのは堕落行為として糾弾され、作品は捨てられたわけです。そして次に1960年代の文化大革命でも西洋文化は捨てられます。この2度の文化的災難によって、海外小説研究自体がボロボロにされて、研究自体がまた端緒についたのが21世紀の今、なんと中国の探偵小説の研究書を今まで出していたのは日本人研究者が過去にいるだけという悲惨さだそう。。。そしていまだに、研究者からみれば、**翻訳小説も創作パロディもどちらも無視の対象で誰もとりあげず、こうやって日本人が編訳して出るのが奇跡みたいなことに。。。なんか、やっぱり中国って大変ですね。。。 **
それにしても、中国人研究者にどうして翻訳小説を研究しないのか尋ねると、あれは中国文学ではない、と言われるってのはおそれいります。。。つまり、中国語で書かれていても元が海外のものは中国文学対象にしない、一方で外国文学研究者もオリジナルのテキストが研究対象であって翻訳されたものは対象ではない、というわけです。いやぁ、翻訳されたテキストだけで研究した顔をする人もいる日本人研究者に比べれば志は高いかもしれませんが、、、やっぱり翻訳者も翻訳作品もかわいそうですね。。。そんな不思議な文化的態度を知れて面白かったのです。
▶︎ホームズパロディに見られるお国柄
中国のホームズパロディの文章中には、けっこう中国の詩文や諺に絡むような表現が頻出するというのはけっこうお国柄というか、妙なミスマッチ感があって面白いのですが、おそらく英国外で書かれたパロディ、パスティーシュには少なからずそういう面があるのかもしれません。日本語で読んでいても、たとえば有名な延原謙氏の訳文のノリに近く、ホームズの立ち居振る舞い、言葉を近づけることが、日本のホームズ造形になってるのかもしれませんし、それを英語にもし翻訳したらそれを読んだ人はちょっと変、と思うのかもしれません。。。
まさに、それはホームズが依頼者が身分を隠そうとしても、少しのことから、出身地、国を見破ってたしまうように。。。
この本の出版元国書刊行会ではイタリア人作家やフランス人作家が書いたパロディ、パスティーシュも出していますが、この中国編にも続編としてインド編が予告されています。インドは英国植民地だったので英国文化が相当入り込んでいるにせよ、やはりエスニックなホームズパロディが書かれていたのでしょうか?
出るのが楽しみです。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
