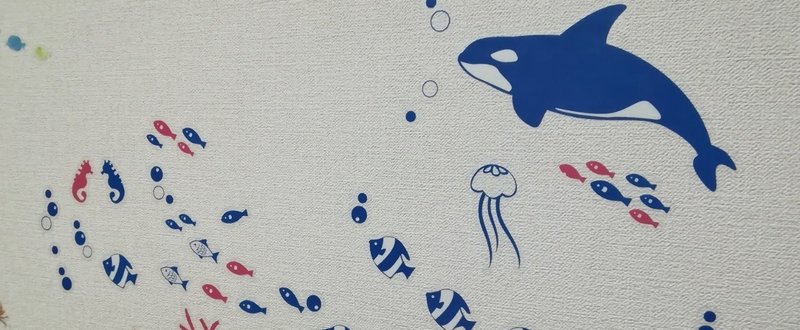
君は陸封型?降海型?
昨年末に家族で池袋のサンシャイン水族館に行って以来、2歳の双子に空前の魚ブームが来ています。
朝起きてから、壁に貼った魚のシールを指さして「マンボウ!シャチ!クラゲ!」と叫ぶことから始まり、魚の図鑑を引っ張り出してはページをめくれと急かしたり、それが飽きると、前に録画した水族館を紹介した番組や、ただただマンボウがゆったりと泳いでいるだけのyoutubeをスマホで見せろと迫ってきたりします。
そんななか、子どもたちと一緒に魚の図鑑を読んでいると結構面白い発見があったりします。
ヤマメとサクラマス
ヤマメは一生を同じ川で過ごす陸封型の魚。

サクラマスは生まれた川から海へ下り、そこで成長したのち、産卵期に今度はまた生まれた川へ遡上して戻ってくる降海型の魚(※写真は鮭です)。

30cmにも満たないヤマメと、その2倍以上の大きさがあるサクラマス。
稚魚の頃に、川に留まるか、海に向かうかの選択次第で、その後の成長に大きな変化があって、実は、この二匹の魚はもともと同じ魚だそうです!
生まれた川の酸素濃度や水温などの環境によって、陸封型のヤマメでいられるか、降海型のサクラマスになるか決まったりするそうです。
生き方の分かれ道
そういった環境が影響しなくても、稚魚のときの競争次第で、勝ってエサを多く取れた方はその川で大きくなり、競争に負けてエサが十分に取れなかった方は、小さい体のまま仕方なく海へエサを求めに向かうことになります。
ちなみに、この時点での体の大きさは、川に残る方が、海に向かう方に比べて10倍程度も大きいそうです。
小さいときに競争に勝った方は、ずっと同じ川に住み続け安定した環境で、エサも確保できるため陸封型の魚、ヤマメになります。
一方、競争に負けた体の小さな方は、天敵も多く危険な環境ではあるもののエサが豊富にあり、成長できる環境にある海を目指します。
春に川を出て、オホーツク海まで回遊し約1年間を海で過ごし、また春が訪れると、生まれた場所であり、かつて競争で負けた場所でもある元の川へと戻ります。ただ、危険が多い大海原で1年を過ごした結果、川に戻って来られるのはたった1割程度。
オホーツクの荒波に揉まれ、シャチやオットセイなど天敵の目をかいくぐって生き延び、そして今度は川の流れに逆らい、滝すらも飛び越えて遡上します。
その体は、生まれた場所を泣く泣く追いやられたかつての稚魚の姿とはかけ離れ、一回りも二回りも大きくなり、上あごは硬く曲がり、鋭い歯が生え、銀色に光る背中やお腹には天敵からの攻撃からか、遡上する間に岩にぶつかったのか、ところどころに傷が負っていたりします。
満身創痍、まさに死に物狂いで遡上し、どうにか元の川に戻ってくると、子孫を残すために産卵をします。
その傍らにいるのが、かつて競争に勝ったヤマメ。
そんなヤマメも、ボロボロになりながら帰ってきたサクラマスに比べて体長も半分以下で、重さも1/30と、大きく成長の差が開いています。
それでもこのヤマメ、なんと小さい体を逆に利用して、サクラマスの産卵にちゃっかり乗じて横から割り込み、自分も子孫を残そうとサクラマスのメスが産んだ卵に自分の精子をかけちゃうんだそう。
そして、サクラマスは産卵後に力尽きその生涯を終え、ヤマメは翌年の産卵期まで、また同じ川での生活が続きます。
狭い川と広い海
幅を利かせる奴がいるものの安全な狭い川に身を置くか、危険を冒してでも、成長と自由を望んで広い海に出るか。
さて、選べるとしたらあなたはどちらにしますか!?
・・・
・・・
狭い川に甘んじて、環境や人間関係に不満を抱えながら生きてるくらいだったら、広い海に出て自分の力で泳いでやるぜ!!
・・・
・・・
とはキッパリ言えず、川と海を自由に行ったり来たりできればいいなぁと、すぐ都合の良いことを考えてしまう今日この頃です(苦笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
