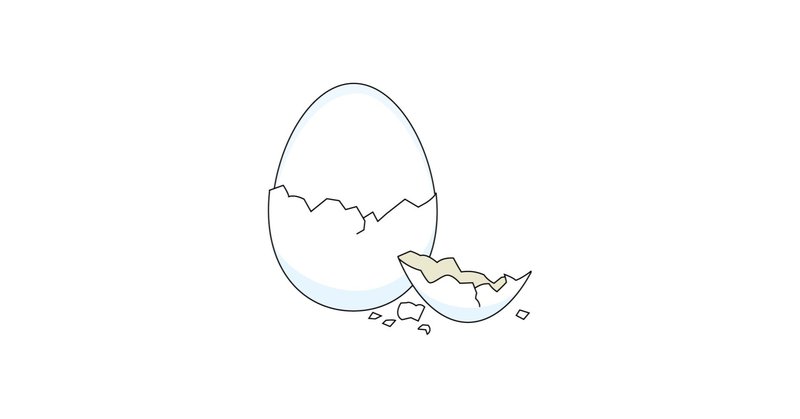
LINE交換しよ、と言えなかった~スクリプトドクターの脚本教室・初級編~
ハイ、LINE交換しよ、と女の子に言えないトホホな男です。
ゆうても、その女の子と言葉を交わせるのは、ほんの数分。
職場で顔を合わせるのは、一週間に一回あればいいほう。
その際も予期せぬ遭遇なので、いつもあいさつ程度のやりとり。
なので、LINE交換しよ、というゴールへの道のりの途中で会話は終了。
だって、会っていきなりLINE交換しよ、って唐突すぎでしょ!?
あらかじめ決めていたセリフを言っている感、ハンパねー
ハイ、言い訳です。
だから、LINE交換しよ、と毎回言えてません。
そして今、その後悔と自責の念でキーボードで入力しています。
ハイ、一体なんの話をしているんだ、と疑問に感じてるあなた。
これがまさに スクリプトドクターの脚本教室・初級編 で私が学んだことなんです。
この本の著者である 三宅隆太 さんは、脚本家・映画監督であり、スクリプトドクター=脚本を(大幅に)手直しする人。
そして、心理カウンセラーの肩書きを持った珍しい人です。
そんな三宅さんは、街場のカルチャースクールで脚本教室の講師もされています。
その講座に通う生徒で多いのが『窓辺系』と三宅さんが名付けた特徴を持つ生徒。
『窓辺系』とは、私の解釈でいうと自意識強い系。
また一見、物腰は柔らかで腰が低く穏やかな人に思えるが、実は内面に怒りをためていて、その怒りを表現することができないタイプ。
その『窓辺系』の問題点とは、
・企画やストーリーが保守的で、テーマが一般常識の域を出ていない。
・描写が繊細すぎて推進力に欠け、各シーンの意図や役割が不明瞭になる。
・個々のエピソードが点のままで、線を結ばず、物語の軌道が立ち上がらない。
・作者が主人公の内面に入り込むあまり、実際には描かれていない心情を描いたつもりになる。
・結果、主人公が孤立し、環境や登場人物たちのとの間に、外的葛藤が生じない。
・主人公の内的葛藤が相対化されないまま後半を迎えるため、明確で力強いクライマックス(葛藤の解消行動)が発生しない。
・にもかかわらず、ラストシーンではいつのまにか主人公が変化・成長したかのように描かれている。
まさに一昔前の私も、そんな『窓辺系』の一人でした。
そんな私が、なんやかんやあってどん底にいて、そろそろ起き上がろうかなというタイミングで、書棚のこの本を手にしました。
※購入したタイミングでは、脚本のテキストにしては変な本だなぁと、数年の積ん読状態でした。
読み進める中で、私はずっと「建て前の自分・理性的な自分」で生きてきて、べき論や常識に縛られてることに気づかされました。
そんな私が、「自分のホンネ、感情」の存在に気づき、認めて、受け入れることの大切さを、このスクリプトドクターの脚本教室・初級編で教えてもらいました。
この本は本来、脚本のテキストなのにおかしいですよね!?
しかし、心理カウンセラーでもある三宅さんは、良い脚本を書くためには、まず自分と向き合うことが大切である。なにより自分と向き合っていない人が書いた脚本は、面白くない。常識に縛られたうす〜い内容であり、その常識から解き放たれた人間の内面を描いた脚本こそ、面白い。と書かれていました。
その内容と、私という人間を重ね合わせました。
すると、私はモロに「窓辺系」にハマりました。
その自分の自意識の強さに気づき・認めて・受け入れることで、ちょっとずつ少しづつ、自分の殻を破ることができました。
しかし、今でもまだ残っています。
ゆで卵でいう、外側の堅いカラは取り除くことができましたが、薄皮が残っています。
薄皮を一枚めくっても、新たな薄皮の層に気づく。
その繰り返しです。
ハイ、ここで文頭の「LINE交換しよ、と言えなかった」へ。
ごちゃごちゃいわずに、LINE交換しよの一言でいいんです。
でも、自意識の壁がジャマするんです。
いきなり、LINE交換しよなんて言ったら引かれるじゃないか。
コミュニケーションを重ねて、徐々に距離を縮めることが大切なんだ。
そんな“常識”が、私を縛って一歩踏み出せません。
別に、LINE交換しよぐらいなら、そこまで慎重になる必要はない。
これまでずっと好きでした、結婚してください。
なんて言いたいわけじゃないんだし。
いやー まさかこんな形で、このスクリプトドクターの脚本教室・初級編を紹介するつもりはなかったんですけど。
今朝、LINE交換しよ、と言えなかった自分が悔しくて、情けなくて。
まぁ、その感情を表現することが、この本を通して私が伝えたいことに通じるかもと。
でも、恥ずかしいし、書き終わろうとしている今でも正解かどうか分かりまへん笑
トホホ。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
