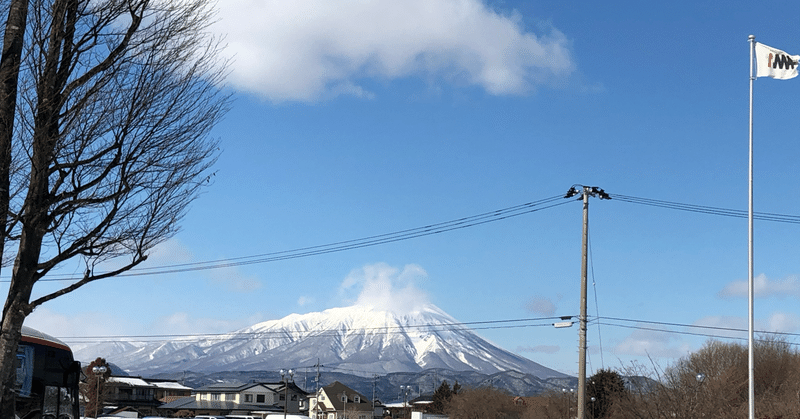
校則は「存在すべき学校」と「存在してはならない学校」があるという話
※私は高校教師をしている者です。
数日前、ツーブロックを禁止する校則の是非が激しく議論されていたことがあった。当該自治体の教育委員会の見解としては、ツーブロック等人目を引くような見た目をしていると、例えば公共交通機関等で犯罪に巻き込めれる可能性があり、その防止のために校則として定めているのだとのことであった。同じような議論が頭髪の染色、スカート丈にも当てはまると考えられる。これに対しSNS上では、「犯罪に巻き込まれることと生徒の外見には因果関係がない」「多様性が認められつつある現代で、生徒の外見を制限するのは好ましくない」など、教育委員会の回答に対して批判的な見方が多数挙がった。
校則そのものの存在意義、生徒の多様性の受容など様々な論点が錯綜しているので私としても意見しにくいのだが、一応私も教育に携わっている身なので言いたいことはある。結論から言うと、生徒の多様性は認められるべき(否定されてはいけない)が、それを校則として制限するべき生徒(学校)と、してはならない生徒(学校)の二種が存在すると思っている。
校則の存在意義から話をしたい。多くの学校には校則が存在し、その中身は学校によって異なる。校則が存在する場合、その存在意義とは「生徒自身でコントロールできない範囲を、学校と教員が代わりに規定することで、学校という集団生活を成立させる」ことであると考えている。(あくまで個人の見解)
皆さんの地元には、いわゆる進学校と偏差値が極めて低い底辺校があるはずだ。傾向として、前者は校則が存在しないか、あっても緩い場合が多い。一方で、後者では校則が細かく定められていることが多い。これは想像しやすいと思うのだが、底辺校には勉強以前の生活の仕方で困難を抱えている生徒が少なくない。例えば朝起きられない、授業中も集中して座っていられない、電車の中でも他人の視線お構いなしに騒いでしまうなど、とにかく勉強する以前の段階の指導が必要不可欠になるのだ。確かに学校は勉強する場ではあるが、それ以前に「その後社会に出ても生きていけるだけの生活力を身に着ける」ことも在学中に学んでおかなければならない。そのような視座に立った時、底辺校では勉強以外の指導の場面は非常に多い。だから、正しい制服の着方や(一般的に仕事をする上で)頭髪や装飾品の扱い、スマホの使い方などを校則で規定することで、学校側は生徒に対して指導する機会を効率的に確保することができるのである。ツーブロックの件(私は染色もないのである程度認めていいのではと思っている…)も、ツーブロックを超えた奇抜な髪形(モヒカンなど)を規定しなければならない場合を想定したとき、ある程度の頭髪の制限を設けるために生まれた校則なのだと捉えることができる。
一方で、進学校の生徒には底辺校で挙げたような困難を抱えている生徒は比較的少ない。なので学校側としてもそれらをわざわざ指導する必要がないので、校則として定める必然性もないのだ。かえって自分で自分のことを管理できている生徒に対して更に校則を課すのは、生徒自身が自律していることを盲目化する恐れがあるので、「校則は存在すべきではない」と私は思っている。
話をSNSの件に戻そう。ツーブロック問題に対する教育委員会の回答は、生徒が犯罪に巻き込まれないようにするため、という生徒の安全確保ということに由来するのもだった。犯罪に巻き込めれることと校則そのものの因果関係が希薄であることは置いておくとして、この回答は、上で述べた校則そのものの存在意義と全く違うところで無理やり理由付けしているので、私としても非常に違和感のあるものだった。安全云々の前に、そのような校則を定めなければならない「学校の現場」が存在している。この点に触れない限り、中身のない回答にならざるを得ないと思う。
SNSでの盛り上がりを受けて、テレビやネットのコメンテーターも様々な反応を見せていたが、彼らについても「現場の視点」がないと校則は適切に語れないと思っている。「このご時世で髪を規定するなんてありえない!人権侵害だ!」と言っている某氏がいた。確かにある程度の生徒の自由を奪っているのは事実なので、人権という大きなテーマでも語ることはできるかもしれない。ただ、もしかしたら当該の学校現場ではそのような規定を設けないと集団生活が成立しないなど、校則の策定の背景に何らかの現場独自の理由付けが存在する可能性がある。それを排して単にリベラルという理想形のみで校則を語るのは、やや短絡的に思えるのだ。
ただ、今回の問題は、ごく当然のように存在を認めていた「校則」を考え直すいい機会である。時代に合わせて校則や指導の在り方は変化していかなければならないので、ツーブロックにしても他の校則にしても、何を緩和・削除して何を新たに設けなければならないのか、現場の教員たちは常に考え続けなければならない。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
