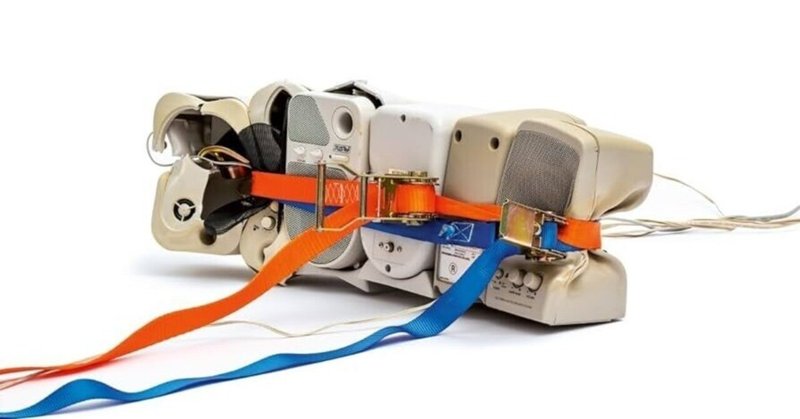
Oneohtrix Point Never - Again (2023)について
「なにかガラッと変わったんだよ。除菌されているのに近い。この都市ではもはや階級の分断によって、本来の意味におけるサブカルチャーの生存が不可能になっている……そして音楽シーンの発育不良があるということさ。ミレニアルのビルボードにどんどん近い見た目になっていってるし、その世代の人間に言わせれば、僕らがこの都市をこんな風にしたとは胸を張って言えない。」
“Its character has changed. It’s a little pasteurised. The class divide in the city makes it impossible for any real subculture to survive, and thus music scenes atrophy. It looks more and more like a millennial billboard, and being of that generation, I’m not proud to say we transformed the city in that way.”
(ダニエル・ロパティン、NYCについて)
この文章は書き殴りである。
0PNはポスト・ロックを、つまり「ジャンルの死」をジャンルとしてここで引用しているのだが、これは0PNの作品群においても初めての試みであり、また0PNが初めて未知の領域へ──参照可能な過去から追放され、現在へ、何も確定されていない荒野に放り出された瞬間である。その意味で、『サインフェルド』的な(典型的な)80'sの主流メディアのキメラである前作mOPNは、明らかに過去の断末魔を思わせるものであった。
とはいえ、かつて0PNが「現在」をサンプリングした作品を発表したことはある。BOTDF eccojam(2011)と、Chuck Person's Mixtape For Mark Fisher(2021)である。前者はフェイクエモ・バンドBlood on the Dance Floorの『Bewitched』を剽窃したもので、これは2011年に同バンドのリードシンガーが行っていた未成年のファンへのグルーミング及び性加害が露見し炎上、その上被害者の少女(当時11歳)が投稿した声明動画までも炎上し4chanを中心とした大規模なネットいじめへと発展したとある事件に対する直接の反応であり、ダニエルは後々にもこのエピソードを『Sticky Drama』(2015)のリリック及びテーマに据えている。('StickyDrama'はかつて存在した、ネット上のティーン・ゴシップを対象とするニュースサイト。この炎上に大きく加担した。)
そして、後者はサイモン・レイノルズ/マーク・フィッシャーという師弟の両方に敬礼を贈るものだ。トラップ・EDM・フェイクエモといったメインストリーム・ラジオを構成するジャンルの大量のサンプルから「Stuck in the past(過去に囚われて)」と言うリリックが出てくる数秒間のみを切り取り、執拗にかつ矢継ぎ早に強迫反復する。それはまさに想像しうる未来を失った認知世界と抗うつ剤と注意欠陥のためのサウンドトラックであり、マーク自身による加速主義のためのミックステープ『No Killing What Can't Be Killed』と併せて聴くことをおすすめしたい。この両者は法的にアウトであると言う点において真にプランダーフォニックなものであるため、新作『Again』の現在への向き合い方とは全く異なる。
ポスト・ロックは、ロックミュージック(確かレイノルズの定義によれば「白人のユースによる大音量での黒人音楽の模倣」)が、その歴史上で初めて社会文化的ムーブメントとしての無効性を自己認識したジャンルである。この一点から端的に書くならば、0PNは、参照可能な過去の貯蓄から追放されつつある。そこにはもはや「使える」過去がなくなってきている。彼のテーマは長らく、20世紀の消費文化とカウンターカルチャーの、つまり60年代以降の社会現象に関する集団記憶を──切り刻み、並び替え、しかもそれをアッサンブラージュにするのでなく、現在のトレンド現象に対してまるで攻撃を仕掛けるように、まるで過去の亡霊が現在のトレンドを「ただのサイクル」として告発しているかのように、ある種の過去→現在の間にある「不気味の谷」を称えたキメラを無邪気に解き放つことだった。それは、聴く者を前進的な時間、リニアに進行するポップミュージックの時間というロマン派以来の一般通念の領域から追放し、究極にシャッフル可能で、結果として永劫回帰的な(バフチンの言葉を借りれば歴史的感覚以前の)無時間の、階級を剥奪されてまどろむような深淵な覚醒状態へと強制的に移動させるものだった。それは「前進」していると主張し続ける社会とその市場が持つ現実認識とは全く異なる暴力的な現実を示唆していた。そして、それを構成しているのは日常の現実から強く異化された小さな時間たちの生き生きとしたモデュール群であり、それは失われるはずの印象、憶えているはずのない一瞬、音楽が音楽である所以にあたるあのアフェクトの強烈な一瞬、の丁寧に積み重ねられた断片群だった。彼はやはり、彼自身が何度となく言ってきたように、シネマの方法を自身のアイデンティティとしてきた人間なのだ。
デイヴィッド・レターマンショウに、ハーモニー・コリンは数えること3度にわたって出演している。最初は『Kids』の、2度目は『Gummo』の公開時で、3度目は『A Crack-up At The Race Riots』の出版時に。この中でも2度目の出演は興味深い。というのも、初出演時にまとっていた「奇妙なガキ」というペルソナと全く異なる態度の彼は、そこで明らかに憤っており、自身の芸術を弁護する準備のできた若き芸術家としてそこに座り、必死に言葉を選び、しかしオーディエンスに大いに笑われているのだ。
デイヴは『Gummo』について、ハーモニーにこう尋ねる。「こんな映像は生まれて初めて見たよ。この作品は一体なんのストーリーを伝えようとしているのかな?」それに対するハーモニーの返答は、「すべてのシネマは始まり、間、終わりを必要としてるけど別にその順番で無くてもいい、そうでしょう?僕はいつも映画を観たあと、あるキャラクターのこと、そこにあった何か特定の情景のことしか思いだせない。僕は、完全にその瞬間だけで構築されたフィルムを作りたかった。」冒頭の発言はゴダールの有名な引用句だが、これが特にそれを知らないオーディエンスの笑いを誘っていた。
ハーモニーは別のインタビューでこうも言っている。「(Gummoは)イメージの、映像の必ず来たる未来についての作品であり、またアメリカの近い未来の姿を描くサイエンスフィクションです。」数十年後に、われわれは15秒間隔で裁断されて全世界中を飛び交う、連邦議会議事堂に大挙したホワイト・トラッシュの暴徒たちの映像を「現実」のイメージとして見ることとなる。彼は自らの作品が根ざしている本質的な現実感覚を、誰もまだ気付いていない世界の本質的な姿を、完全に理解していた。ハーモニーはトリックスター(両面価値的存在者)なのだ。人々は彼の行いを、滑稽なトリックとして受け取り、馬鹿にして大いに笑う。しかしその時にはトリックスター本人は、全員が所属する世界の価値転換を済ませている。世界を反転させている。誰も彼を本気では受け取らない。そして彼は自身にもわからない理由でそれをせずにはいられない。彼はアートシネマにもハリウッドにも属せない。トリックスターは階級移動をし、それに縛られない。定住できない。
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーは、ポップミュージックの世界でそのような両面価値的な転倒を初めて実行した一人である。ハーモニーの方法に関する発言は、全て0PNの方法論に当てはめて受け取ることさえできる。異なるのは、ハーモニーが彼にとっての現実を強く示すイメージから直接に作品を構築してゆくのに対して、0PNのそれはもっと曖昧な記憶(Memory Vague)を、文化商品分類の中に発見する点だと言えるだろう。彼の過去の発言にもそうした意気込みを見て取れる。「音楽だけが他のアートと比べて旧態依然とした形に甘んじている。ジョイスがユリシーズで文学に与えたことを、僕は音楽に対してやってみせる。」
しかし、転倒できる価値が、もはやカテゴライズできるものではないとしたら?
ポスト・ロックとは、「トレンドから追い落とされた」初めてのロックである。それは祖先にあたるヴェルヴェッツのように選民的でヒップでもなければ先駆者であるUSハードコアのような政治的主張も持たない。もはや、そこには社会集団的な目的がない。レイノルズはそのタームを発案した時、「サイボーグ・ロック──人力のシーケンスとデジタル・エフェクト」とも説明してみせた。
かつてWilcoが「僕は、星条旗の灰に向かって敬礼をしたい」「高層建築群が揺れる、皆が逃げ惑う、悲しい悲しい歌を口ずさみながら──声が悲痛に歪み、摩天楼(スカイ・スクレーパー)が擦れ(スクレープ)あう、今きみの声は煙になる」と歌った時、彼らは完璧にアメリカの全てを予見し、描写しえていた。しかしそれは、かつてジギー・スターダストがしたような幻視的な予言や警告とは全く異なるものだった。それは必ずやってくることをもはや誰も止めることはできないという諦観に過ぎず、その時ロックミュージックは社会運動ですらなかったと言える。ウッドストック'99の悪夢的なヴィジョンは、アメリカという共同体が突入しつつある不安を先取りして象徴する負の祝祭であったし、当時ニューメタルが戯れていたモラル・パニックは、現在も増加している単独無差別射撃のケース・モデルを創出しさえしたから。ジム・オルークが、MAX/MSPやPure Dataによるラップトップ・ノイズの技術を駆使した先鋭的な電子音響を、錆び尽くしたカントリーとそこに歌われる絶望的なアメリカーナへと完璧に調和させて見せた時、それは完全な意味でポスト・ロックであり、アメリカ音楽の一つの最終形態だった。
しかし、現在はその時とも明らかに異なる。その時にはまだ文化の貯蓄がアメリカにもそのようにあったが、今はもうない。トレンドという概念が停止してから暫く経った。相対主義はもうポーズとしてすら機能しない。相対化する極など(かつての意味合いでは)もう存在しないからだ。「カウンター」する。一体何に対して?
0PNはその絶望的な問いをはっきり認識している。とても難しい問題と格闘している……と言うよりも、『Again』はそのあまりの辛さ、アメリカという終末的な政治状況の中で芸術を創ることのあまりに虚無的な感覚にもう耐えきれなくなったかのように聴こえる。その点でこのアルバムは、とても、とても悲しい作品だ。0PNのキャリアでも最も消滅主義的な響きがするとまで言えるだろう。
「Again」は、0PNのディスコグラフィに何度か登場するワードだ。特に『Problem Areas』(2013)と、『Music For Steamed Rocks』(2014)。どちらもttsMP3.comという音声読み上げサービスの、US English/Justinというキャラクターの声で。後者では、Spectrasonicsのボーイズ・クワイアがゆっくりとサスペンドしながら悲歌のステップを下降し、一気に収束してゆくインターヴァルが床にタッチする、そして鋭いホワイトノイズの破裂音と毒々しいデジタルな水音が合図となってストロボのごとき高周波のパルスが開放されるまさにその瞬間、悲嘆の感情を反復することの悦びを自ら独り確認するかのように、TTSが「Again」と不気味に幼い声で呟く。その感情を欠いた性別以前的な声はループ・フェイズに呑み込まれていって、低いくぐもった呻きとなり、切り刻まれて消えてゆく。あのモーメントには、説明できない、誰にも否定し難い、人間という経験についての勇敢な──遊び心溢れる真実があった。
あえてこう書きたい。ここからはもう、これからの未来はもう、我々の芸術はもう、ある種の知的操作では生き延びることが絶対にできない。これは誓ってもいい。いかに「間違えず」にどのジャンルを選ぶのか。そうした選択する行為が即時的にアーティスティックな営みとなる、そうした方法はもう通用しない。今年の’Rebuild’ツアーで披露されていた長尺の暴力的なアルペジエイター・ジャムは、0PNがもはやそんなものを必要とせずとも圧倒的に優れた、祝祭的なミュージシャンであることを証明していた。余談だが、サイモン・レイノルズの比較的流行らなかったタームにConceptronica(コンセプトロニカ)という言葉があり、これはDeconstructed Clubという醜いバズワードと同時に出現したのだが、2018年の段階でどちらも死語となっていた。そもそもDusterのStratosphereが、もしくはミッドウェスト・エモの自己憐憫に充ちた音楽的特徴(トロープ)が、平気でTikTokのミームとなってバズる2020年代である。そこには真新しいものがあるのではなく、ただ論理的な帰結があるだけだ。そうした死にゆく論理の帰結にわれわれが今から創り出してゆく芸術が折れることは決して許せない。それは、エッセイスト的な(ボクの体験は普遍的な共感要素だという)私見の単なる提示でもなければ、ポスト唯物史観的な無機物の操作でもないし、雑誌メディアが「存在する」と必死に主張するトレンドに目くばせすることでもなければ、テクノロジーと悠長に戯れることでも、テクニックの見せびらかしでもない。超越のある体験を、言語を超えることでのみ可能な高みを共有すること、それを惜しみなく贈与すること。それを、われわれは、必ずややるだろう。
P.S.
ふとジョイスとベケットのことが頭をよぎった。フィネガンズ・ウェイク。たしか、若きベケットはこの作品について「形式が内容であり、内容が形式そのもの」と高らかに言った。Finnegans Wake。Fin-again。また終わるために。Wakeは航跡、通夜、覚醒。それだけ意味を成さずに頭のなかをちらついて、そこで止まった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
