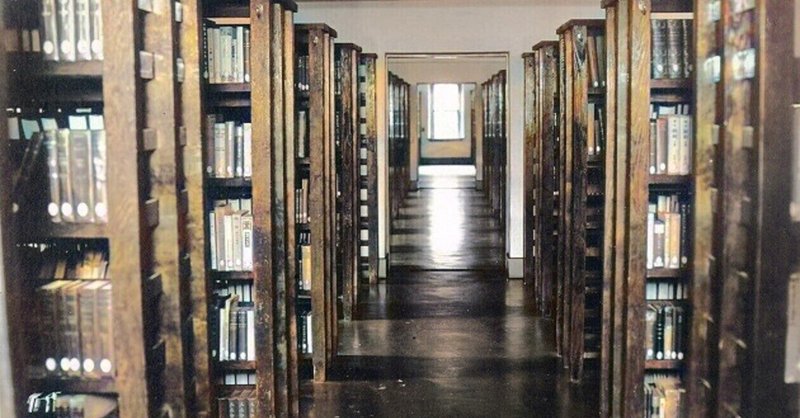
書評家に明日はない
書評って何なんでしょうね。
事の起こり
書評家の豊崎由美氏がTwitterに次の投稿を行い
正直な気持ちを書きます。わたしはTikTokみたいなもんで本を紹介して、そんな杜撰な紹介で本が売れたからって、だからどうしたとしか思いませんね。そんなのは一時の嵐。一時の嵐に翻弄されるのは馬鹿馬鹿しくないですか?
— 豊崎由美≒とよ婆 (@toyozakishatyou) December 9, 2021
あの人、書評書けるんですか?
これにTikTokerのけんご氏が引用リツイートで返答
書けません。僕はただの読書好きです。
— けんご📚小説紹介 (@kengo_book) December 10, 2021
書けないですが、多くの方にこの素敵な一冊を知ってもらいたいという気持ちは誰にも負けないくらい強いです。
読書をしたことない方が僕の紹介を観て「この作品、最高でした」「小説って面白いですね」と言ってくれることがどれだけ幸せなことか知ってますか? https://t.co/6Devv2V7QA
さらに書評家の大森望氏も反論し
TikTokで本を紹介するのだって書評でしょう。文字で書く書評より、リーチする潜在的読者の数がはるかに多いので、TikTokで影響力のある書評ができる人のことはたいへんうらやましく思います。才能と努力の賜物。自分でもやってみたいと思って検討したけど、とても無理だと思ってあきらめました。 https://t.co/pTALUcivPF
— 大森望 (@nzm) December 10, 2021
なんかめちゃくちゃに燃えてた。
Twitterではほぼ豊崎氏への批判一色であり、概ね内容としては「活字を読む習慣のない若者世代に強い影響力を持ち、実際に書籍の売り上げに貢献しているTikTokerを軽視すべきでない」「評論媒体に掲載された文章としての書評だけが書評なのではなく、TikTokでの紹介だって立派な書評だ」といったものが主立っている。また批判者の立場は立ち位置のよくわからない野次馬を覗けば大まかに次の3種類に分類できるように見受けられた。
①作家、ライター等本を「書く」人
②書店員、読書家等本を「買う」人
③出版編集者等本を「世に出す」人
経緯と批判の総括は次の記事に詳しい。
それから興味深いと思ったのが、音楽評論家の栗原裕一郎氏による次のような見解である。
原稿のネタにしようと虎視眈々と見守っていたのだが(笑)
— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) December 11, 2021
今回はトヨザキさんが失言気味だと思うが、行き違いは書評の二面性に起因しているでしょう。このコラムに書いたように、書評は出自的にも広告性を帯びている。一方で評論的性格も持っている。どっちに重きを置くか。https://t.co/CtSDS4w8zw
たとえば大森さんは、けんご氏の「リーチするポテンシャル」を指して「書評でしょう」といっていたが、これは広告性を評価しているわけですよね。糾弾している人たちもだいたい広告性に依拠して批判している。https://t.co/Q2TjgNKsl9
— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) December 11, 2021
一方、トヨザキさんの言い分は、評論的機能を重視したものである。そういう売り方をしていると、一時はいいかもしれないが、土が痩せ細って、しまいにゃぺんぺん草も生えなくなるぞ、といっているわけだ。
— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) December 11, 2021
現実的には、書評は広告的機能を失いつつある。もう書評じゃ本が動かないというのは前々から言われている。昨今、褒め書評すなわち広告的書評しか存在を許されなくなっているのは、その現状のネガでもあるでしょう。貧すれば鈍するというやつですな。https://t.co/NqKu8LR0bF
— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) December 11, 2021
だからTikTokの紹介レビューで本が売れることは、広告機能のオルタナティブとして出版業界にとって福音である。反面、欠落しがちな評論的機能をどう補完するかという問題が生じてくる。広告機能を失った書評がタッグを組んでそこを補うというのが良さげだけど、どうですかね。
— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) December 11, 2021
個人的には「売らんでもいい喧嘩をなんでわざわざ売るかなあ」くらいに思って傍観していたのだが、何故こんな炎上沙汰が起きたのかということを掘り下げていくうちに、この件の背景には随分とやるせない事情があるのではないか、と言う気がしてきた。
この記事は是非を決めるものではないし、誰の擁護をするものでもない。ただ少しばかり、この件は本当に「書評家の問題」なのか?という点について、思いを巡らせるのにお付き合いいただけたら幸いである。
書評書けるんですか?
そもそも「書評」って何ですか?
例えば私がこのnoteに、私の好きな小説について「この本はこんなに面白くてこんなに魅力的でこんなに画期的でこんなに優れていてこんなに面白いんだ!」といったような文章を5000字ほど書いたとしよう。皆さんにお尋ねしたいのだが、それは「書評」だろうか。
きっと「それも書評だよ!」と言ってくださる心優しい方は多いのではないかと思う。そんなにも熱意をもって、言葉を尽くして好きな本について語るなんて、それは立派な書評だよ、と。
だが私の意見はけんご氏のものと同じだ。私には書評は書けない。正確には私がnoteやTwitterやブログに書いたり、あるいはyoutubeやTikTokといった動画媒体で語ったりしたものは、どれだけ言葉を尽くしたものであってもそれは「紹介」や「宣伝」であって「書評」ではない。何故か。ここが書評の場ではないからだ。
書評とは何だろう。書を評することだ。評価し、評論し、批評することだ。では「評する」とは、評価し、評論し、批評するとは何だろう、どうやったらできるのだろう。これが一番の鬼門なのだ。つまり、私一人が言っているだけでは、私一人が言っているだけなのだ。私がいくら言葉を尽くしたところで、それは「私にとっての価値」を示すものでしかない。それは「私にとっての価値」以外のいかなる価値をも保証するものではないのだ。価値を保証するのは、ある価値基準によって築かれた「体系」だ。体系に組み込まれることによって価値は定められる。「書評」を「書評」たらしめるのはそれだ。書評とは、書を評価することだ。評価とは、価値を定めることだ。価値を定めるとは、体系の中に位置づけることだ。ここにはその「体系」がない。だから私には書評はできない。では「体系」はどこにあるのか。
文芸はどこから来るの?
文芸作品が世に出るプロセスを辿っていこう。本は最終的には読者が手にする。彼らが本を手に入れるのは書店だ。書店に納入する本を作るのは出版社で、出版社に作品を書くのは作家だ。では作家が文芸の出所なのか。否。文芸作品が最初に掲載されるのは文芸雑誌だ。
文芸出版というシステムすべての源流はここ、文芸雑誌にある。文芸雑誌に掲載された作品が、文芸雑誌をルーツに持つ文芸出版社によって書籍化され、世に出るのだ。文芸雑誌を経由しない書き下ろし作品や新聞連載の作品もあるが、それらの作品もいずれかの段階で文芸出版社の手を経て世に送られる。文芸作品を世に出す奔流を辿っていくと、結局は文芸雑誌という水源に行き着くのだ。
そして文芸批評が掲載される場所、文芸批評が属する体系もここだ。文芸体系、通称「文壇」と呼ばれる価値体系こそ、文芸批評が批評たり得る場だ。
そして一番肝心な事として、文壇の価値基準は市場価値ではない。ここが一番の誤謬ポイントだと思うのだが、ちょっと考えてみてほしい。文芸雑誌に連載されている小説が「読者の反応が悪い」といった理由で打ち切られるのを見たことがあるだろうか。あるいは「単行本の売れ行きが悪いと掲載が打ち切られてしまう」と文芸作家が読者に懇願しているのを見たことがあるだろうか。あくまでも文芸雑誌を発表の場とする文芸小説作品に限って言えば、原則として打ち切りはありえ無い。何故か。彼らは掲載された時点で価値を保証されているからである。……誰によって? 御待ちどう、文芸批評によって、である。文芸批評によって、文芸作品は文壇体系の中に価値を位置付けられ、既に評価されたものになる。これが文芸批評の本分である。
それって誰の仕事なんですか
ところがここでひとつ困ったことが起きる。文芸作品は文芸雑誌に掲載され、文芸批評によって価値を定められる。ここまではいい。その作品は出版社の手を経て書籍となり、書店の棚に並び、読者の手へ、そう、買われるのである。最終的に読者が本を購入する。そこで働くのは文壇価値ではなく、今度こそ市場価値だ。本当に二面性があるのはここだ。文芸出版と言う「文壇価値から市場価値へと作品を輸出する」仕組みにこそ、価値の二重性が内包されている。文芸出版というプロセスにおいて文芸作品は、まず文壇体系において価値を定められ、もう一度市場体系において改めて価値を問われるのである。
そして市場体系において価値を問われる時、つまり読者が本を買おうとする時、そこで基準となる価値は何だろう。文壇における価値だろうか。違う。読者が、あなたがその本に価値を感じるかどうかだ。それでちょっとお尋ねしたいのだが、ここに、書評が関与できる猶予が果たして僅かでもあるだろうか。「あなたにとっての価値」以外の何物をも保証しないあなたにとっての価値が、「あなたにとっての価値」以外の価値を保証する言葉によって、何か変わるということがあるだろうか。
今から、この件において最も重要なことを言うが、書評に本を売れさせる力なんかない。どうしてもこれだけは今日飲み込んで帰っていただきたい。これこそが全ての間違いのもとなのだ。書評に本を売れさせる力があると思うからこんな間違いを引き起こすのだ。そんなものはない。あるわけがないのだ。だって価値観が違うから。そして、何より、長いから。
長い文章なんか誰も読まんのだ。
正確には、長い文章であっても最初からその文章そのものに興味を抱いている人は読むだろう。例えば、小説とか。だがその文章に興味を抱かせるための文章が長ったらしかったら誰も読んじゃくれないのだ。もちろん書評家はいたずらに文を長くしているのではない。書評とは書を評することであり、評するとは理屈をつけることだ。理屈を語るには相応の分量の言葉が要る。だがたとえその書評がどれだけ言葉を尽くし、精緻な筆致で、丁寧な論理で、その作品がいかに素晴らしい文壇的価値を有するのかを物語っていたとしても、そんなことは読者に言わせれば、知ったこっちゃないのだ。市場価値という体系において彼らにとっての価値を決められるのは、唯一人彼ら自身だけなのだから。
文芸批評が働きかけられるのは、文芸批評体系の内側にのみだ。批評はそれが属する体系の内側にしか働きかけられない。そこが彼らの仕事場なのだから。書評を読むのは、最初から「書評を読みに来る人」、つまり最初から身内にいる人だけだ。彼らはそもそも外側に、つまり市場経済体系へとリーチする力を持っていないのである。そして批評体系の中には「売れさせる力」なんてものはどこを探してもない。では「売れさせる力」はどこにあるのか。外側にリーチする力は、読者の価値観に直接働きかける力は一体何なのか。
それは広告である。宣伝である。そして、紹介である。だからTikTokerの紹介で本が売れたのである。何故ならそれは、短いから。簡潔だから。そして個人の価値観以外の体系に属さない、「何物をも保証しない」ものだから。市場価値は誰にも保障できない。故に「保証しない」者だけがアプローチできる。彼らこそが真の「本を売れさせる力」を持つ人たちだ。そして彼らが「本を売れさせる力」を持っているのは当たり前のことだ。何故なら彼らは「保証する」書評家ではないから。
そろそろお気づきいただけるだろうか。この事件の歪さに。
本の紹介をするTikTokerと書評家、この二者はそもそも全く別のところで、全く別の仕事をする人たちなのだ。つまり両者の仕事や役割は絶対にバッティングしえないはずなのである。書評家は書評を、TikTokerは紹介を、それぞれの本分を全うしてさえいれば、絶対にパイの奪い合いにはならないはずなのである。
だが現にTikTokerと書評家は衝突し、炎上した。起こるはずのない事件が起きた。
何故か。
ケツを持つのは誰
ここで少し話を戻して、最初に引用した栗原氏の見解に触れてみよう。栗原氏は本件のすれ違いの原因を「書評の二面性」にあると見ている。書評には広告性と評論性の二つの性質があり、そのどちらを重視するかによって主張が分かれているのだという意見だ。
しかしここまで述べてきた私の見解としては、書評には広告性はないと言わざるを得ない。二面性を有しているのは書評ではなく文芸出版のシステムであって、書評は一貫して文芸体系の土壌に根差した評論性を有するものである。書評は広告的機能を失ってきたのではなく、その出自を考えれば最初から広告としての機能を有していなかったと見るのが自然であろうと思う。
ただ、栗原氏がこういった見解に立つのは理解できるところがある。というのも、栗原氏は評論は評論でも音楽評論家だという点である。これは全くもって作品の質とか文化的価値とかどっちがえらいとか高尚だとかそういう話ではなく、純粋に性質の違いの話なのだが文芸批評と音楽批評は性質が違う。音楽批評だけでなく映画批評や演劇批評とも、文芸批評は異なる性質を持つ。理由は文芸批評の出自だ。ここまで述べてきたように、文芸出版は文芸雑誌を出自とする。文芸雑誌、そこに根差す文芸体系と言う権威構造が文芸出版すべての源流なのである。そして文芸批評はその権威性を構成する一パーツだ。文芸出版のシステムそれ自体が、文壇と言う権威(価値)を地盤としているのである。映画や音楽にも権威性はあるがここまで「世に出るシステム」そのものが権威の上に丸ごと乗っかっているのは文芸を置いて他にない。
仮に音楽批評や映画批評に「広告性」があるのだとしても他ならぬ文芸批評に限ってそれはない。権威は権威の外では権威でなくなるからだ。体系の中にない批評に批評としての価値はない。そして書評がどれだけカジュアルになったとしても、それが文芸を扱うものである限りそのフィールドは文壇という帝国の統治下にある。その領土から出た瞬間にそれは書評ではなくなる。文芸批評が文壇に属しているということは、それは文壇の権威の外に出られない=広告たりえないということだ。広告が必要なら、批評家ではなくあらためて広告屋を雇わなければならない。
そしてそろそろこの権威構造の全体像が見えてきたのではないだろうか。出版と書評はグルである。同じ権威に属する、言うなれば「チーム文壇」のメンバーだ。そして書店や読者や広告屋は別のチームである。本を売ったり買ったりする「チーム市場」のメンバーだ。文芸出版業界というものは、全く異なる価値体系に属する二つのチームが同じ船に乗り合わせているような構造なのである。それを踏まえたうえで、もう一度豊崎氏のツイートを見てみよう。
正直な気持ちを書きます。わたしはTikTokみたいなもんで本を紹介して、そんな杜撰な紹介で本が売れたからって、だからどうしたとしか思いませんね。そんなのは一時の嵐。一時の嵐に翻弄されるのは馬鹿馬鹿しくないですか?
— 豊崎由美≒とよ婆 (@toyozakishatyou) December 9, 2021
あの人、書評書けるんですか?
TikTokでの紹介で本が売れたことを「一時の嵐」に過ぎないとくさし、馬鹿にしている。「本を売ること」と「書評すること」とを対立概念だと見做している。それから今回のとは別件で豊崎氏は本屋大賞にも長年懐疑的な立場をとっているが、その件を加えてみてもやはり論理に一貫性がある。豊崎氏の仮想敵は「本を売るためのムーブメント」そのものだ。「そんなこと」よりも書評のほうが意義があるのだと主張しているのだ(なぜなら文壇と言う権威がバックにあるから)。そして主張の正当性や喧嘩を売ったこと自体の是非はともかく豊崎氏の敵味方の判別は正確だ。明確にチーム文壇の立場からチーム市場に向けて喧嘩を売っている。そしてこれに対しTikTokerや書店員や読者ら「チーム市場」が反発するのも当然だろう。チーム市場の立場からすれば本を売ることこそ正義であり、それが彼らの本分だからだ。問題は書評家や出版関係者、あるいは出版社寄りの文芸ライターなど明らかに文壇サイドに属していながら「売り上げに貢献するTikTokerを馬鹿にするな」「TikTokだって立派な書評だ」というチーム市場の主張にそのまま乗っかった人々だ。彼らは自分の所属チームがどこなのかがわかっていない。スタジアムの中で迷子と化しているのだ。この件の真に根深い問題がここに如実に表れている。彼らは自分の仕事場をすっかり見失ってしまっているのだ。
もうそろ最後の種明かしをするが、TikTokerと書評家、絶対にバッティングしないはずの二人がなぜ共食いをしているのか。こんなにも大勢の職場迷子が発生しているということはもはや原因は明らかだろう。彼らは自分の仕事を「本を売ること」だと思い込み、根本的に向いていない仕事に取り組んで無能の烙印を押され、敵ではないものを敵だと見做している。彼らに本分ではない役割を割り振った者がいる。
これは明らかなキャスティングミスだ。では誰のキャスティングミスなのか。この話の登場人物の中にキャスティングを行う立場にある者は一人しかいない。それは文芸雑誌を発行している、文芸出版社だ。出版社が、執るべき指揮を執れていないのだ。
故にこの現状を生みだした要因は一つだ。文芸出版体系の老朽化による、致命的なまでの機能不全である。
書評、いる?
というわけで文芸出版が立ち直らない限りこういうわけのわからない喧嘩沙汰はこれからも増えるんじゃないかと思う。と言っても文芸を即座に元気にする魔法の使い方はちょっと分からない。そして今回の件で一番の被害者は好きな本を紹介していただけなのに急に殴り掛かられたTikTokerであることに異論の余地はないだろう(ほぼ八つ当たりで殴られたに近い)。
とりあえず当面の処置として、本が売れなきゃどのみちみんな死ぬわけだから本を売れさせるTikTokerさんには非礼を詫びてなんとか関係を修復するに越したことはないんじゃないでしょうか。
ただそうなってくると「書評いる?」みたいな話になってくるわけで。本売る役にたたないし、権威主義的でえらそうだし、わけのわからん喧嘩売るし、書評もういらなくね?ってなってくる。いい機会だからもう文壇なんか解体してしまえ、的な。ただそうなると、残るのは市場価値だけになるんですよね。売れる本だけが残る。売れる本を売る人だけが残る。そうなった文芸って、どう?
権威主義って嫌な言い方に聞こえるけど要するに「こいつには売れなくても価値がある」ってのを言い切れる力なんですよ。「売れないけど価値がある」ものが生きていくには市場価値から切り離された価値体系の構築と、その体系のバックにつくものすごく強い親玉が必要なんですよね。文芸雑誌という権威、出版社という親分はそうやって売れない連中を抱えてきたし、その仕組みを文芸批評は維持してきた。そういった一面は、文芸出版というものが文化の担い手として長年果たしてきた大切な役目でもあると、私は思っています。
でも御覧の通り文芸出版にもうそんな力はありません。売れないものを「俺が面倒みるから!」と背負っていくだけの体力はもうどこにもありません。そしてこれから先、文芸出版はますます「売れ」に舵を切っていくのだろうなという強い予感があります。本がなくなることは今後数世紀はないでしょう。でも文芸は近いうちになくなるかもしれない。その時には書評って、文芸の価値の中でしか生きられない書評って、どこにいるのでしょうね。
私には全部をうまいこといちどきに解決する妙案は思いつきません。なのでかわりに一つ、とても大切なほんとうのことを話して、この話を終わりにしようと思います。
もしあなたが、小説でも音楽でも漫画でも何でもいいのだけど、何か好きな作品があって、その作品に「売れてほしい」と思っているとしたら、長い文章を書く必要なんか一切ないということです。どんなにか言葉を尽くして言葉を凝らした丁寧な書評よりも、たった一言の「好き」とか「面白い」とかそういった率直なコメントのほうがずっと、本を売れさせる力があります。あなたの言葉にはそれだけの力があります。大切にしてください。
この話の教訓は結局のところ「売らなくていい喧嘩は売らないほうがいい」ということです。文学界が平和でありますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
