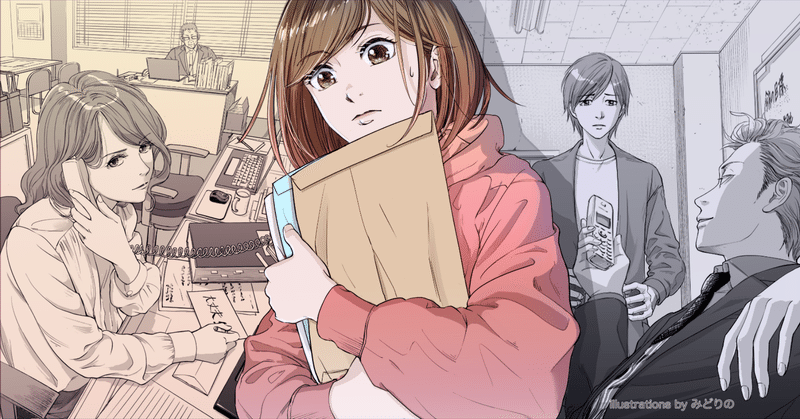
0497:小説『やくみん! お役所民族誌』[13]
第1話「香守茂乃は詐欺に遭い、香守みなもは卒論の題材を決める」[13]
<前回>
*
支社長室のドアがノックされた。どうぞ、と声を掛ける。ドアが向こう側に開いて、蘭が顔を覗かせた。
「お客さまがお見えです」
「通して」
蘭が引っ込み、代わりに押井が部屋の中に入ってきた。
「やあ、いらっしゃい。そちらへどうぞ」
ブッさんが促すと、押井ははっきりした声で「はい」と応え、合成皮革のソファに腰を下ろした。
ふうん。報告では挙動不審な小心者のイメージだったけどな。
ブッさんは書類を机上に置いてコンテッサから立ち上がり、応接セットへ向かいながら、押井から目を離さずに観察を続ける。
第一印象は、爽やかな好青年。細身で身長は170cm台半ばか。髪の毛はさらさらで服装を含め全体に清潔感がある。少し目に昏いものを湛えてはいるが、それが逆に異性には魅力的に映りそうだ。
どかりとソファに体重を預けた。半ば無意識のオーバーアクション。押井の表情に、さっ、と小さく陰が差すのを、ブッさんは見逃さなかった。やはりそうか。いじめられっ子はいじめっ子に逆らえない、それは本能のようなものだ。いざという時にマウントするのはチョロい、そう確認できれば今は十分。先ずは柔らかい当たりでいいだろう。
「で、持ってきた?」
ブッさんの明るい声音に、押井は固まったまま答えない。4秒、5秒、6秒。ブッさんは焦れて先を促す言葉を発した。
「ここに持ってくるように言われたもの、あるでしょ」
「……通帳ですか?」
「あれえ、通帳だけだっけ?」
少し声量を大きくして問うと、押井の表情に軽く怯えが浮かぶ。
「えと……通帳と、キャッシュカードですか? あ、あと、ハンコ」
「そうだよ、そう。わかってるじゃない」
押井はボディバッグから封筒を取り出し、中身を出してテーブルに置いた。異なる銀行の通帳三通、キャッシュカード三枚、印鑑が三本。ブッさんは通帳を手に取って確認した。どれも当初入金一万円の一行のみ記帳された新品だ。名義人は押井の本名。キャッシュカードには通帳と同じ口座番号と名義人がエンボス印字されている。
「確かに。で、これ、どうする? 持って帰る?」
押井は口の中で小さく「えっ」と呟き、意味を掴みかねているようにブッさんの顔を見た。
「お前が決めていいよ」
「あの、橋本さんからここに持って行けと言われたんですけど」
ブッさんはにこにこと笑顔を湛えたまま黙っている。
「えと、借金を返す代わりに……」
「借金の話は、俺は知らないよ」とかぶせ気味にいう。「それは橋本とお前の問題だ。俺は、この通帳とカードと印鑑を、お前の自由意思でどうするのかを聞いてんの」
「持って帰ってもいいんですか」
「いいよ、俺は。橋本とのことは知らないよ」
ブッさんは、決して通帳を渡せとは言わない。あくまで相手が自らの意思で通帳を渡すのを待つ。
一方で、押井は宝石商の橋本から、ネックレスの代金を払えないのであればその代わりにと今回の指示を受け、ここに出向いていた。持って帰ったら50万の借金がそのまま残る。
この人は素直に受け取ってくれなさそうな気配だ。話が違うじゃないか。どうすればいい。胸が苦しい。頭の中がグルグルする。息がうまく吸えない。呼吸ってどうするんだっけ。苦しい。
押井の顔が歪むのを、ブッさんはただ見ていた。
ダブルバインド(二重拘束)。強者から複数の矛盾する指令を受けて弱者が混乱し疲弊する状況。文化人類学者グレゴリー・ベイトソンが提唱した概念だが、勉強の嫌いなブッさんがそんなことを知る筈もない。ただ、相手をこうした状況に追い込むことで自分が圧倒的に優位に立てると、経験的に知っているだけだ。
追い込んだ先に、逃げ道を作る。そうすれば自然と相手はそちらに向かう。
「難しく考える必要はないよ。お前がこれを俺にくれるというなら、ありがとうといって受け取るよ。持って帰るというなら、それも止めない。どっち?」
初めて通帳をブッさんに渡す道筋が示された。押井はほっと表情を緩め、口を開いた。
「あげます」
言い方に幼稚なものを感じたが、ブッさんはそこはスルーした。
「わかった、お前の意思で俺にくれるというなら、受け取るよ。ありがとうな。橋本には受け取ったと言っとくから」
よし、ハマった。
ブッさんは一式を手元に引き寄せ、あらためて押井の顔をみた。気の進まないことをやり終えて、一刻も早くこの場を立ち去りたいという顔だ。けれども、今この瞬間にもう引き返せないところまで来てしまったのだと、こいつは気付いてない。
所詮は、無知で気弱なカモだ。「候補者」の器じゃあない。
*
龍神の忍ばせた罠が別班により発動したのは、押井がアンゴルモアから逃げるように帰ってきた二日後のことだ。
キャンパスに向かうため、茗荷谷のアパートから春日通りに出たところで、前から来た若い女性に呼び止められた。
「あのー、この住所を探してるんですけど、ご存知ですか」
目が大きく小柄で少女のようだが、スーツ姿を見ると二十代なのだろう。彼女の差し出したメモには、小石川の所番地とマンション名が書いてある。
「知らないですけど、たぶん、あっちですね」
と、押井は東の方角を指差した。
「こんなこと突然お願いして申し訳ないんですけど、案内してもらえませんか? 私、この辺りは初めてなので」
「スマホでナビすればいいと思います」
塩対応のようだが、押井に悪意はなく、これが彼の標準だ。しかし、女性の側もそれで引く様子はなかった。
「あの……恥ずかしいんですけど、私、地図の読めない女なんです。スマホの充電も切れそうだし。どうか助けると思って」
女性は両手で押井の右手を握り、真っ直ぐに押井を見つめる大きな瞳が少し潤んでいる。何か事情があるのだろうかという推測と、可愛らしい女性(ひと)だなという男心、他人に触れられていることの緊張と、それが異性であることの気恥ずかしさが、押井の一瞬の心の内に押し寄せた。
授業まで、あまり間がない。
「途中までなら」
「ありがとうございます!」
女性は顔を綻ばせた。誰かに喜んでもらえると、押井も嬉しくなる。彼の鋭敏な心は、他人の心の有様に簡単に左右される。
押井は自分のスマホでマンションを検索したが、ヒットしない。番地も同一のものは見当たらないが、播磨坂の下の辺りと見当をつけた。ひとまず真っ直ぐ坂上を目指そうと考えて、歩き出した。
道すがら、女性は饒舌だった。名前はサトミレイコということ。北海道の出身であること。就職のため上京して半年で心細いこと。あなたは? 素敵ですね。わあ、すごい。今度私にも教えてくださいよ。彼女いるんですか?
押井はいつもの調子で朴訥とした反応を返した。子供の頃から他人とリズムが噛み合わず、ごく一部の親友を除いて会話のキャッチボールが苦手だ。しかしサトミレイコは、まるで沈黙を恐れるかのように押井の言葉を全部拾って反応する。変な人だな、と押井は思った。
小石川5丁目交差点で押井は左方向を差し、サトミレイコに告げた。
「この坂の下辺りだと思うので、そこで誰かに尋いてみてください」
サトミレイコは、何かを言いかけて、口ごもった。押井はその様子を意に介さず「じゃあぼくはこれで」と元来た方向に5歩歩いたところで、背後に「きゃあっ」という棒読みの悲鳴を聴いた。振り向くと、サトミレイコが屈んで足首に手を当てていた。
「……大丈夫ですか?」
その場から動かず声だけ掛けた押井に、サトミレイコは捲し立てた。
「大丈夫じゃないです! 捻挫したみたい、困ったなあ、これじゃあ客先に行けない。会社で休みたいので、タクシー拾ってください。それから、心細いので、一緒に来てください!」
かけらもリアリティの感じられない、強引な台詞回し。
サトミレイコ──もちろん偽名だし路上で語っていた素性も嘘八百だったのだが──は、この時のことを後に押井にこう語っている。
「自分でも、大根だとわかっちゃいてんで? 役者志望やのに、客引きひとつうまくできひん。初めて引っかかった、ちゃうわ、ついて来てくれたんが、オッシィやってん。店まで連れてきたら歩合ゲット、うまいこと契約させたったら割り増しになるからここが踏ん張りどころや、て思た。つまり、逃すわけにいかへんカモやな。はは、ごめん、ごめんて。あの時は、まさかオッシィとこうなるなんて、思いもせなんだな」
*
デート商法は、異性を誘惑して商品を買うよう仕向ける手口だ。SNSや街頭アンケートなどをきっかけに近づき、数回デートを重ねてカモを感情移入させた後、プレゼントとして絵画やアクセサリーといった高額商品を買わせる。もちろん販売店はグルだ。これ以上は金を絞れないとみたら、その時点で誘惑者は姿を消す。販売店は表向き無関係を装っているから、文句の言いようもない。
押井は、高校卒業直前に配られた消費者トラブル防止パンフレットで、デート商法のことは知っていた。受験の終わった3年生が講堂に集められ、パンフレットを見ながら、消費生活センターの職員から1時間ほど話を聴いた。内容は若者に多い消費生活トラブルについて。その半分以上を悪質商法の話が占めていた。その時は「世の中は恐いことがあるものだな」と思ったくらいで、すぐに忘れてしまった。
自分が今まさにデート商法にはめられようとしていると気付いたのは、宝石店の応接室に軟禁状態で2時間ほど勧誘が続いた頃だった。
「これ、デート商法ですか?」
「デート商法? なんですか、それ。聴いたことないなあ」
社長を名乗る橋本はそう嘯(うそぶ)いた。優に体重100kgは越えているだろう、身長はそれほど高いようにも見えなかったが体躯は相当に太い。話の途中から上着を脱いで、薄青いカッターシャツに濃紺のサスペンダー姿。室温は快適だが顔の脂汗が天井のLED照明の白い光を反射している。
部屋の中には、ハシモトジュエルオフィスの男性社員3名がいた。橋本が押井の対面でソファに腰を下ろし、押井の背後に一人、もう一人はドアの前に仁王立ちで腕組みをしている。橋本以外はいかついタイプではないが、ただそこに居るだけで圧迫を感じさせる布陣だ。
サトミレイコは、お手洗いに行くといって15分前に席を立ったまま、戻ってこない。これは追い込みが終盤戦に入ったことを意味するが、その時の押井に知る術はなかった。
橋本は、ずい、と巨体を乗り出して、押井の目を真っ直ぐに見た。視線を受け止められずに押井の目が泳ぐ。その様子に、橋本はタメ口に切り替えるタイミングと踏んだ。
「お兄さんさあ、いちゃもんつけてもらっちゃ、困るよ。もう2時間も、こっちは説明してるんだよ? いや、まだ2時間、かな。先日のお客さん、何時間頑張ったっけ? ああ、そうそう10時間な。最後はうちの商品の素晴らしさを心から納得してくれて、契約書にサインしてくださったよ。うちもさ、品質に自信があるから、社員全員が熱心にお客様と向き合えるんだ。何時間でもね。まあ、早くにご決断いただいた方が、お互いに時間を有効に使える。で、お兄さん」
橋本はさらに顔を近づけた。呼吸が荒く、鼻息が押井の頬に吹き付ける勢いだ。その圧で、押井の呼吸は浅くなる。
「どうすんの」
押井は体を強ばらせたまま返事をしない。目の前の現実から切り離された意識に、ぐるぐると呪詛が渦を巻く。
クソだ。世の中、クソだ──。
その時、ドアが開いて前に立っていた男に当たり、男がよろめいた。
「あ、ごめんなさい!」
入ってきたのはサトミレイコだ。彼女は部屋の空気を読むことなく、明るい笑顔で押井の隣に腰を下ろす。二人掛けソファなので自然と上腕と腿が密着し、体温を感じる。同時に橋本も押井から離れ、上体を戻してソファに体を預けた。
押井の呼吸が、少し楽になる。
緊張と緩和。
追い込んだ先に、逃げ道を作る。そうすれば自然と相手はそちらに向かう。
「私、思いついたんですけど」
サトミレイコが橋本に言った。
「こういう時に、お金の代わりに買う方法があるって、友達に聞いたことが」
「ああ……アレね」橋本は思い当たることがある素振りを見せた。サトミレイコより演技は自然だ。
「じゃあ、お兄さん、こうしましょう。50万円で購入する代わりに、3万円+αで買える方法があります。普通のお客さんには言わないんですけど、お兄さんはお金に困ってらっしゃるようなので、特別にその方法をお知らせします。それなら大丈夫でしょう?」
「あの……αが47万円なら何も変わりません」
押井が真面目な顔でそう主張した。言っていることは正しい。でも今この流れで普通はそうは考えないし、言わない。対抗するなら、そこじゃないだろ。こいつ少しネジが足りないんじゃないか、と橋本は思った。
「大丈夫ですよ。少し手間がかかるのと、あとは印鑑を三本作ってもらう分の数千円ですね。それぞれ違う銀行、違う印鑑で口座を三つ作って、一万円ずつ入れておいてください。それからキャッシュカード。それを渡していただければ、ネックレスの代金は完済ということで」
押井に向けた橋本の言葉を、サトミレイコが代わりに引き取って反応した。
「えーっ、じゃあ3万数千円で50万円の価値あるネックレスが買えるんですか!? これはお得ですねえ」
お前はテレビショッピングの司会者の相方かっ、と橋本は内心で突っ込んだ。この試用期間の一ヶ月で確信した。サトミレイコは、この仕事に向いていない。
前任者が抜ける時に同じ劇団ということで紹介され、見た目が可愛いから適任と考え採用した。しかし訓練しても演技が全然ダメなのだ。全然客を捕まえられない。デート商法は見た目よりもコミュニケーション能力が重要だ。カモに惚れさせ、高額な物でも買おうと思わせるには、それだけの手管が必要になる。こいつにそれはない。セリフが全部浮ついている。役者にも向いてねえわ。
そもそも今日の展開も強引すぎる。普通は数回デートを重ねて体の関係を期待させてから、店に連れてくるもんだろ。それを当日いきなり連れてきた。ふらりと立ち寄ってプレゼントをねだっているのか、「私がデザインしたジュエリーなんですよ、助けると思って買ってください」という流れなのか、その辺りもグダグダのまま商談に突入されたら対応に困る。普通はここでカモを逃がしてしまう。
しかし──。
そんな状況でも橋本が強引な追い込みに入ったのには理由がある。深網社のネットワークで回ってきたカモリストの押井の報告書にはKK、つまり「「候補者」候補」を示す符牒が付いていた。優先的にカタにはめ、哲さんの面談を受ける「候補者」に相応しいかどうか、支社長クラスの査定に回す必要があることを意味していた。
橋本は余裕を装いながら、押井の反応を見守った。首を縦に振るまで、何時間でも追い込み続けることになる。手間を掛けさせるなよ。
「……分かりました。じゃあ、それで」
橋本の内心が伝わったわけではないだろうが、押井は屈した。
この時、今日に至るレールが敷かれた。
*
査定役のブッさんは、通帳の受け渡しの段階で、押井を早々と見切っていた。
世の中は、支配する強者と支配される弱者に分かれる。こいつは弱者だ。強者に喰われて世の中を呪いながら骨になる運命だ。支配する側、しかも幹部「候補者」には、決してなれない。
このまま通帳を取り上げて帰らせ、俺たちとはそれきりだ。通帳は後日然るべきタイミングで、振り込め詐欺の入金先に使う。金は全額即座に引き出すが、当局に察知された時点で口座凍結され、こいつは犯罪収益移転防止法違反で逮捕される。その頃にはこの拠点はもぬけの殻だ。
目の前にいる押井の顔を見ながら、恨むなら自分の弱さを恨め、とブッさんは胸の内でつぶやいた。
その時、支社長席の机上に置いていたスマホが鳴動した。
「ちょっとごめんよ」
押井にそう言い置いて立ち上がり、スマホを手にとる。
哲さんからだ。ブッさんは通話ボタンをタップした。
「はい」といって、続く言葉を言い淀む。目の前に押井がいるのに、社内通称ではあっても自分の名を口にすることは憚られた。
「そうです、すみません来客中で。はい。えっ?」
ブッさんはちらりと天井を見上げた。つられて押井も目線を上に向ける。クリーム色の天井には染みが浮き出て、築年数の古さを思わせた。
「分かりました、客対応が終わったらすぐうかがいます。……はい……あー、そいつは」
こんどはブッさんの目線が押井に向けられた。先ほどまでの威圧の色はなく、押井は視線を受け止めることができた。押井が怖いのは、害意を乗せた視線だ。相手の意識がよそを向いていれば、怖くない。
「今、目の前にいます。まあ、俺の査定はふごうか……はあ……そうなんですか?」
ブッさんは押井に背を向け、顔を伏せて話を続ける。
「俺は、お勧めはできませんけど。ええ、そうです。──分かりました、そうおっしゃるのであれば、今から連れて行きます。はい、では」
ブッさんは画面をタップし、再び天井を仰いで、ふう、と息をついた。こんな奴に、哲さんの時間を取らせる価値があるわけがないだろう。それでも哲さんの気の済むようにするしかない。
「じゃあ、これから面接いこか」
ブッさんは押井に告げた。
「ぼくは帰っていいですか」
「なあに言ってんだよ、お前の面接だよ」
苛立ちを隠せず、自然と語調が強くなる。押井の目に怯えが走る。
「まあ黙って付き合え。終わったらすぐ解放するから」
哲さんも、直接こいつと話をすれば、見込みがないとすぐ分かるだろう──。
この時ブッさんは、そう思い込んでいた。
【続く】
--------(以下noteの平常日記要素)
■本日の司法書士試験勉強ラーニングログ
【累積206h24m/合格目安3,000時間まであと2,794時間】
頑張った、やくみん今回分書き上げた! これで次のまとめが作れる。というわけでノー勉強デーに悔いなし。。
■本日摂取したオタク成分(オタキングログ)
『ODD TAXI』第11話、ミステリーキッスが物語の前景に躍り出た。『陰謀論のおしごと』第3話、トカゲ人間(レプトイド)はアメリカ陰謀論の中でも理解不能なもののひとつ。文化的背景を共有してないとわからん。『オイコノミア これで納得? 相続の経済学』オイコノミアはずっと興味を持ちながら録り溜めて全然観て無かった。データの中から取り敢えずこの回を視聴。法律論はもちろん試験勉強の中に含まれているのだが、この番組は行動経済学の視点なのでまた別の面白さがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
