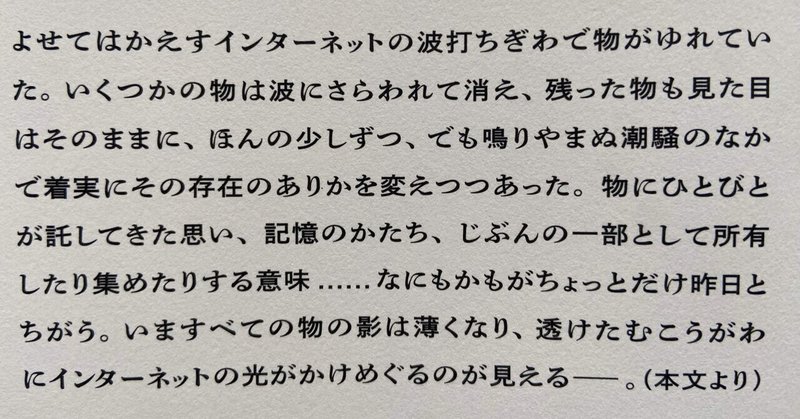
波打ちぎわの物を探しに
いつもの書店で、三品さんの新刊を見つけた。
わたしはいつも彼の雑貨店の並びの書店で本を見つけて買う。『波打ちぎわの物を探しに』には最近もやもやしていたことが、ゆっくり読みたい文体で綴られていたので2ヶ月半もかけて読んだ。この本はその間、東京と京都を二往復した。
この二十年間で、物はそれぞれ属していた古い文脈からいっきに解放されていった。物の抽象度はどこまでも上がっていき、入れかえ可能で、組みあわせ自由、ウェブに最適化した細かくてばらばらな商材となった。そして最終的には異常なまでの流通速度を獲得するにいたる。
やはりこの二十年余り、ネットの情報社会が世の中に変化を起こしたことによる、さまざまな影響と考察がかなりおもしろい。前著『雑貨の終わり』でそうか、と思ったことがこの本を読んでやはりそうだ、と確信された。
例えば今、「クリエイター」と称する(称された)人たちのこと。デザイナーやアーティスト、イラストレーターやライター、料理家や手芸作家など、どれほど多くのひとがその呼称を自分ごとと感じるだろうか、またはそのことによってなんらかの影響を受けているだろうか。
この言葉がインターネットにのっかって爆発的に広がり、市民権をえていったのと時をおなじくして、認定ルールのほうも自己申告制に変わっていった。いまではクリエイトするひとびとの増加に歯止めが効かなくなっていて、じぶんもふくめ、社会に自称クリエイターがこんなにいてもいいのだろうか、ってくらいいる。
時をおなじくして。その言葉でよみがえってきたのは前著『雑貨の終わり』で読んだことだった。
「パンブーム、パン好きといったナンセンスな言葉が巷で飛び交い、地元の人からすれば、なんでこんな裏道の小さなパン屋に人だかりが、という光景が全国にあらわれてきたのは、インターネットがパン界の情報を整理整頓していく過程と軌を一にしているはずだ」
ここをわたしはドキドキしながら読んだのだ。All Aboutでまさに二十年ほどその渦中にいたわけだから。確かパンブームなんてないという話を新聞メディアに書いた頃だった。『雑貨の終わり』にはすべての境目が消えつつあることが書かれていた。すべての物が雑貨化し、それはパンもそうで、雑貨店でパンが売られ、わたしは三品さんの店でパンを買ったことがあった。
その話は『月の本棚 under the new moon』に書いた。パン屋さん、Le petitmecの文化発信地としてかつてあったオウンドメディアで書いていた本の話に加筆して一冊にまとめたものだ。パン屋さんだけれどパンを売っていないサイトだった。わたしはパンのことを書かないブレッドジャーナリストとして連載をさせてもらっていた。
結局のところ、消費社会の大きな流れは不可抗力で、どんな人もその流れに漂いながら、自分を見失わないように生きようとしている。職業や名称は移り変わっても、自分は自分でしかないのだから。
デジタルに対して存在するリアルな物がその物である意味が問われたその先に残るのは何か、それを三品さんは「物に宿る古くて弱い力」と書いた。紙切れ一枚にも宿ることのある、お守り的なもの。
デジタルにできないことは、祈りかな、とわたしは思った。祈りをリアルな物に込めたのがお守りだ。
印象的な映画を観終わったあとのように、この本に書かれたことは自分のなかで再生され想像され続けている。
三品輝起の本で、雑貨や雑貨化の話よりも魅力に感じるのは、ノンフィクションがいつの間にかフィクションになっているような、やはり現実かもしれない、どちらかわからないけれど、どちらでもいい、と思えるその文章だとわたしは思う。例えばスティーヴン・ミルハウザーの小説や、ミランダ・ジュライの映画のように、現実がいつの間にか超現実にすり替わるような不思議な感覚を、わたしは、自分が読む本に求めているのだと思う。フィクションとノンフィクション、小説と日記、書店と雑貨店、パンと雑貨、現実と非現実、その境目がぼやけて溶けかかっている。それを目撃して体験している。ちょっと呆然としてしまう。果てしない気持ちになる。月を眺めているときみたいに脱力する。それは、悪くない感じだ。
サポートしていただいたら、noteに書く記事の取材経費にしたいと思います。よろしくお願いいたします。
