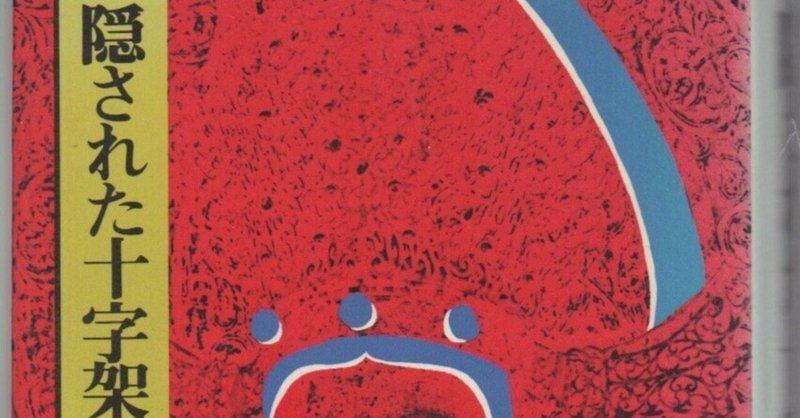
梅原猛(1925.3.20-2019.1.12)『隠された十字架 法隆寺論』新潮社 1972.5 『梅原猛著作集 第8巻 神々の流竄』集英社 1981.9 『梅原猛著作集 第9巻 塔』集英社 1982.3 梅原猛『葬られた王朝 古代出雲の謎を解く』新潮社 2010.4

梅原猛(1925.3.20-2019.1.12)
『隠された十字架 法隆寺論』
新潮社 1972年5月刊 456ページ
2009年8月再読
https://www.amazon.co.jp/dp/4103030011
https://www.amazon.co.jp/dp/4101244014
「法隆寺は怨霊鎮魂の寺!
大胆な仮説で学界の通説に挑戦し、法隆寺に秘められた謎を追い、古代国家の正史から隠された真実に迫る。
門の中央を閉ざす柱、一千二百年の秘仏・救世観音――古の息吹きを今に伝え、日本人の郷愁を呼ぶ美しき法隆寺に秘められた数々の謎。その奥に浮かび上がる、封じ込められた怨霊の影。
権謀術数渦巻く古代国家の勝者と敗者を追い、あくことを知らぬ真理への情熱と、通説を打破する大胆な仮説で、ときの権力により歪曲され抹殺された古代史の真実に華麗に挑戦する、「梅原日本学」白熱の論考。
【目次】
はじめに
第一部 謎の提起
法隆寺の七不思議/私の考える法隆寺七つの謎/再建論と非再建論の対決/若草伽藍址の発見と再建の時代
第二部 解決への手掛り
第一章 なぜ法隆寺は再建されたか
常識の盲点/たたりの条件/中門の謎をめぐって/偶数の原理に秘められた意味/死の影におおわれた寺/もう一つの偶数原理 出雲大社
第二章 誰が法隆寺を建てたか
法隆寺にさす橘三千代の影/『資材帳』の語る政略と恐怖/聖化された上宮太子の謎/『日本書紀』のもう一つの潤色/藤原―中臣氏の出身/『書紀』の主張する入鹿暗殺正当化の論理/山背大兄一族全滅の三様の記述/孝徳帝一派の悲喜劇/蘇我氏滅亡と氏族制崩壊の演出者 藤原鎌足/蔭の支配と血の粛清/権力の原理の貫徹 定慧の悲劇/因果律の偽造/怖るべき怨霊のための鎮魂の寺
第三章 法隆寺再建の政治的背景
思想の運命と担い手の運命/中臣・神道と藤原・仏教の使いわけ/天武による仏教の国家管理政策/日本のハムレット/母なる寺 川原寺の建立/蘇我一門の祟り鎮めの寺 橘寺の役割/仏教の日本定着 国家的要請と私的祈願/飛鳥四大寺と国家権力/『記紀』思想の仏教的表現 薬師寺建立の意思/権力と奈良四大寺の配置/遷都に秘めた仏教支配権略奪の狙い/藤原氏による大寺の権利買収/興福寺の建設と薬師寺の移転/道慈の理想と大官大寺の移転/二つの法興寺 飛鳥寺と元興寺/宗教政治の協力者・義淵僧正/神道政策と仏教政策の相関/伊勢の内宮・薬師寺・太上天皇をつらぬく発想/藤原氏の氏神による三笠山の略奪/土着神の抵抗を物語る二つの伝承/流竄と鎮魂の社寺
第三部 真実の開示
第一章 第一の答(『日本書紀』『続日本記』について)
権力は歴史を偽造する/官の意思の陰にひそむ吏の証言
第二章 第二の答(『法隆寺資財帳』について)
『縁起』は寺の権力に向けた自己主張である/聖徳太子の経典購読と『書紀』の試みた合理化/斉明四年の死霊による『勝鬘経』、『法華経』の講義
第三章 法隆寺の再建年代
根強い非再建論の亡霊/浄土思想の影響を示す法隆寺様式/法隆寺の再建は和銅年間まで下る
第四章 第三の答(中門について)
中門は怨霊を封じ込めるためにある
第五章 第四の答(金堂について)
金堂の形成する世界は何か 中心を見失った研究法/謎にみちた金堂とその仏たち/薬師光背の銘は『資財帳』をもとに偽造された/三人の死霊を背負った釈迦像/奈良遷都と鎮魂時の移転/仮説とその立証のための条件/両如来の異例の印相と帝王の服装/隠された太子一家と剣のイメージ/舎利と火焔のイメージの反復/金堂は死霊極楽往生の場所/オイディプス的悲劇の一家
第六章 第五の答(五重塔について)
塔の舎利と四面の塑像の謎/釈迦と太子のダブルイメージ/死・復活ドラマの造型/塔は血の呪いの鎮めのために建てられた/二乗された死のイメージ/玉虫厨子と橘夫人念持仏のもつ役割/再建時の法隆寺は人の住む場所ではなかった
第七章 第六の答(夢殿について)
東院伽藍を建立した意思は何か/政略から盲信へ 藤原氏の女性たちの恐怖/夢殿は怪僧・行信の造った聖徳太子の墓である/古墳の機能を継承する寺院/フェノロサの見た救世観音の微笑/和辻哲郎の素朴な誤解/亀井勝一郎を捉えた怨霊の影/高村光太郎の直観した異様な物凄さ/和を強制された太子の相貌/背面の空洞と頭に打ちつけた光背/金堂の釈迦如来脇侍・背面の木板と平城京跡の人形/救世観音は秘められた呪いの人形である/仏師を襲った異常なる恐怖と死
第八章 第七の答(聖霊会について)
怨霊の狂乱の舞に聖霊会の本質がある/骨・少年像のダブルイメージ/御輿はしばしば復活した怨霊のひそむ柩である/祭礼は過去からのメッセージである/舞楽・蘇莫者の秘密/死霊の幽閉を完成する聖霊会/鎮魂の舞楽に見る能の起源
年表
図版目録
梅原猛(1925.3.20-2019.1.12)
宮城県生まれ、哲学者。国際日本文化研究センター顧問。京都大学文学部哲学科卒業。立命館大学教授、京都市立芸術大学学長、国際日本文化研究センター所長などを歴任。縄文時代から近代までを視野におさめ、文学・歴史・宗教等を包括して日本文化の深層を解明する幾多の論考は〈梅原日本学〉と呼ばれる。著書に『隠された十字架一法隆寺論』、『葬られた王朝一古代出雲の謎を解く』、『親鸞「四つの謎」を解く』(以上すべて新潮社)など多数。」
2009年8月31日読了。
36年ぶりに再読しました。
高校三年生の頃(1972年)、日本史の教師から本書を教えてもらい、
翌年、大学一年生の夏休みに、本書を持って、法隆寺に行きました。
大阪で結婚していた姉の家に泊めてもらったなぁ。
今でも、その時、法隆寺でもらった、
横40cm・縦15cmの一枚、
法隆寺畧縁起・境内図
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺 電話斑鳩局(074575)-2555
聖徳宗総本山 法隆寺
が挟んであります。
著者、梅原猛は1925年生まれですから、まだ四十代の頃の作品です。
「雑誌『すばる』(集英社)に『隠された十字架』と題して連載[1971.2-8 三回]されたものに、少し手を加えた。この一連の研究はふとしたことから始まったのであるが、私は雑誌『芸術新潮』を、認識の最初の冒険の舞台としてえらんだ。山崎省三氏のすすめで、連載をはじめた『塔』において、私は古代にかんする自由な認識の冒険を行なった。この自由な冒険は、しばしば、私をとんでもない誤謬にみちびいたが、自らそこに一つの体系を生み出しつつあった。
『塔』では書き切れないものが、私の中にたまっていた。その時たまたま、雑誌『すばる』の発刊のために、かって、雑誌『展望』の編集者として私に『美と宗教の発見』(筑摩書房[1967.1])所収のいくつかの論文を書かせた安引宏氏が私をおとずれた。連載の依頼に、私は枚数制限なしに書かせてくれることを条件にして引きうけた。『すばる』は季刊であるが、そこに私は多いときは四百枚、少ないときでも百五十枚の論文を書いた。」
p.447「あとがき」
https://www.amazon.co.jp/dp/4480087230

「橘三千代の影が法隆寺には色濃くさしている。三千代の影が色濃くこの法隆寺にさしているとすれば、その夫、藤原不比等が法隆寺に何らかの関係をもたないはずはない。
不比等がかついだ女帝[元明天皇(天智天皇皇女)]と、孫の聖武帝、娘の光明皇后の寄付した品物が多いのを見るとき、藤原不比等が、この法隆寺建立に何らかの関係をもったのではないかということが推量される。
藤原不比等、私は、この人こそ、正に日本の国家というものをつくり出した、隠れたる大政治家だと思う。この隠れた大政治家は、日本の国家の基礎をつくり出すことにおいて、天才的であったが、また、自己の事蹟のあとかたを隠すことにおいても天才的であった。
日本を支配したさまざまな氏族がいる。蘇我氏、藤原氏、平氏、源氏、北条氏、足利氏、徳川氏など、そのうち平氏、源氏の支配の期間は、ほんのわずか、比較的支配期間の長い足利氏や徳川氏ですら、支配した期間は三百年に足らない。
しかるに、藤原氏は、鎌足以来、鎌倉幕府成立までの政治の実権をにぎった。その間、約五百年として、それ以後も他氏のように完全にほろびたわけではなく、尚且つ、天皇を擁して隠然たる力をもっていた。
明治維新に到るまで、正に千二百年の間、藤原氏は日本第一の、あるいは日本唯一の貴族であった。
その権力の基礎は、だいたい鎌足・不比等の親子によって、つくられた。よほど巧みに、彼等は、権力の基礎をつくったわけであるが、従来、このような権力の秘密について、ほとんど説明らしい説明はもちろん、それにたいする深い疑問も起こされなかった。
支配の跡を全く感じさせないかのような支配、それがもっとも巧みな支配の技術である。彼等は、正に、そういう巧みな支配者であった。
われわれが、今日、この時代を知るためには残された二つの歴史書である『古事記』と『日本書紀』によらざるを得ない。この二つの書は、従来、藤原氏と関係のないものと考えられてきたが、この二つの書が、藤原不比等の指導のもとにつくられたというのが、ここ二、三年来、私がひたすら考え続けてきた仮説であった。」
p.72「誰が法隆寺を建てたか」
「天武帝の死は朱鳥元年(686)九月であったが、それから一月もたたないうちに、持統帝は継子、大津皇子を死に追いやった。理由は大津皇子の謀反であったが、それは陰謀にすぎないだろう。それは、自分と天武帝との間の一人息子、草壁皇子を皇位につけようとして、競争相手を除くためであった。
この持統帝の強烈なる血の意思にもかかわらず、その後三年もたたないうちに草壁皇子は、安閇(あべ)皇女、後の元明帝との間に一人の息子と二人の娘を残して死んだ。息子は後の文武帝、娘の一人が後の元正女帝である。
己の血を引く子孫に皇統を伝えようとする持統帝の第一の計画は挫折したわけであるが、この沈着にして冷静なる女帝は、このような挫折くらいで、己の意思をあきらめるような女性ではなかった。
自ら帝位につき、己の孫、文武帝の成長を待とうとした。そしてついに、皇位をねらうもう一人の競争者であった高市(たけち)皇子の死と共に、彼女は無事、孫、文武帝を皇太子につけ、すぐに帝位をゆずった。
天智、天武帝の多くの皇子の中から、自分の血をうけているもののみが皇位につくことの出来る特権を確保することが、正に持統帝の最大の望みであった。このような意思がアマテラスが女帝とならねばならなかった最大の理由ではないかと私は思う」
p.163 「記紀」思想の仏教的表現
2009年3月に読んだ、
溝口睦子『アマテラスの誕生 古代王権の源流を探る』岩波新書 2009.1
https://www.amazon.co.jp/dp/4004311713
https://www.facebook.com/tetsujiro.yamamoto/posts/876756635732310
では、梅原猛説はまったく言及されていませんでした。
日本古代史や日本宗教史の学界からは否定・無視・黙殺されているのでしょう。
「明治以後の日本の思想に関する学問は決定的な欠陥をもつ。それは神仏分離の思想ゆえである。仏教を研究する人は仏教のみを研究し、神道を研究する人は神道のみを研究した。このような学問の仕方は、明治の神仏分離の政策にそったものであろう。
本居宣長、平田篤胤(あつたね)らが推進した国学は、神道から厳密に仏教の影響を除外しようとした。いわゆる神道と称せられるものの中に含まれる仏教的なものを不純と断じ、そういう仏教の影響のない純粋な日本の神道への復帰を主張したのである。
彼等が純粋な日本の神道としたのは古事記神道であったが、残念ながら『古事記』は、すでに日本に仏教が深く入ってきた時代に出来たものである。一見、仏教にかんして何も語っていないが、そのことが仏教から何も影響を受けず、また仏教にかんして無関心であることを意味するのではない。
私が考えるように、『古事記』が和銅五年[西暦713年]、藤原不比等を中心として撰述されたとすれば、その時すでに四大寺移転を中心とする藤原氏の仏教政策ははじまっていた。その神道政策は、まさしくもう一方の仏教政策と並行して行われた。
こうした歴史的状況下に成立した一つの古典、『古事記』を、宣長ははるか歴史の彼方にある永遠なる時間の中で聖化してしまった。この『古事記』の聖化によって、はじめて神仏分離の学問、純粋な神道学が可能であった。そして同時に、もう一方に純粋な仏教学が成立するのである。
このような学問の仕方がどれほど日本の思想の研究をさまたげているか、これについて私は再三論じてきたが、古代日本の研究に取り組んで以来、この信念はますます強まるばかりである。学問の神仏分離はまだ解消されてはいない。」
p.197「法隆寺再建の政治的背景 神道政策と仏教政策の相関」
大学一年生の時(1973年)に読んだ本書の奥付は、
昭和47[1972]年12月20日 12刷。
当時のベストセラーだったのでしょう。
36年ぶりに読み直してみると、読んだ覚えのないことが、たくさん書いてあります。ここに書き抜いている文章は、どれも記憶に残っていなかった部分です。まだ二十歳になっていなかった私は何に興味があって本書を読んでいたんだろう?
「阿弥陀仏はいかなる点においてこの時代の人間に必要であったのか。それを一言でいえば、死霊の恐怖からの解放のためであったと私は思う。
自分たちが殺した人間の死霊が再びここに現われ、生きている人間に復讐を試みる。その死霊を誰かがどこかへつれていき、二度と地上に現われて生者の生活を邪魔しないようにしてほしい。
そういう要求を人は仏教にもとめる。そして仏教側においては、そういう要求を満たすものとして阿弥陀仏の存在が認められはじめる。
古代日本人の生活を知るにつけ、彼等が死者にたいしてもっていた恐怖が、想像も出来ないほど大きなものであったのを私は知るのである。
それは、死に対する恐怖ではなく、死者に対する恐怖である。死者の霊魂が、いつ何時、生者の世界に現われて、生者の生活を乱すかもしれない。どうか死者よ、黄泉の国にいる死者よ、静かに眠っていてほしい。
おそらく、そういう願いを多分にこめてあの巨大な古墳が築かれたのであろう。あの巨大な古墳とそこにうずめられる巨大な石棺が、その恐怖をわれわれにはっきり見せてくれる。この重い石棺と大きな土山をこわして、まさか死者がこの世に現われようとは思えない。
特に偉大な人と恨みをのんで死んでいった人の霊は、よけい手厚く葬られる必要がある。なぜなら偉大な人間は偉大な力をもっているゆえに、死後もまた偉大な力をもっていると考えられるからである。
そしてまた、恨みをのんで死んでいった人間は怨恨ゆえに、しばしば人間の世界に現われやすいと考えられるからである。
私は古墳の大きさは、その人の偉大さとともに怨恨の深さにも正比例するのではないかと思うが、まさに聖徳太子の霊こそ、そういう偉大にして、しかも、もっとも深い怨恨をもつ霊なのである。
この霊は、もはや巨大な古墳によって鎮められる霊ではない。なぜなら太子自身が日本固有の神より異国の神(仏)を信じたからである。それゆえ太子の怨霊の出現にかんして、日本の神は無力なのである。そこで新しい神、すなわち仏が太子の鎮魂を引きうけねばならぬ。
その仏の中でも阿弥陀仏が鎮魂の主役となる。阿弥陀仏は、迷える霊をすべてまとめて極楽浄土へつれてゆく。死霊よ、どうぞ、阿弥陀仏の手によって極楽浄土へ行ってください。
私はこのとき、古墳時代の夜が明けたと思う。古墳時代において神道がはたした役割を、今や仏教が引きうけた。太子の霊、このもっとも厄介な死霊を引きうけるのは、もはや古代神道ではなく、仏教なのである。聖徳太子は、巨大な古墳に葬られるべきではなく、寺院に葬られるべきなのである。
四天王寺、橘寺、法起寺(ほっきじ)、広隆寺、法輪寺、法隆寺。それぞれ一つの時代の太子信仰、というより太子の霊にたいする恐怖のあとを残す寺が、続々と建てられてゆく。そしてそれらの寺の建造と共に、古墳時代の夜は完全に明けるのである。」
p.326「金堂は死霊の極楽往生の場所」
37年前、高校三年生の時(1972年)、一番好きだった教科は日本史でした。教室の最前列の机に教科書と参考書と年表を広げて、真面目に一生懸命に授業を聞いていました。その日本史の教師の名前をもう思い出せませんけど、彼が本書を紹介してくれたことは確かに記憶しています。36年ぶりの再読はとても楽しかったです。
追記 都立北多摩高校(現在は東京都立立川国際中等教育学校)の当時(1972年)の日本史担当教員は篠田先生という方だったような記憶もあります。

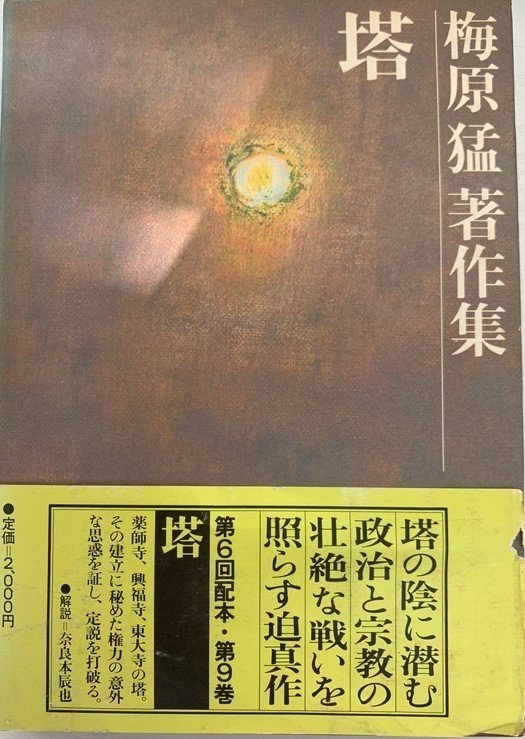
梅原猛 『梅原猛著作集 第9巻 塔』
集英社 1982年3月刊 556ページ
2009年10月31日読了
https://www.amazon.co.jp/dp/B000J7QM2E
https://www.amazon.co.jp/dp/B000J9F0XY
https://www.amazon.co.jp/dp/4087490033
https://www.amazon.co.jp/dp/4087490041
『芸術新潮』1970年1月号から1971年12月号に連載された「塔」という標題のエッセイと他5篇を収録。
塔
塔と日本文化 縦線文化と横線文化
大織冠の謎
石仏に秘められたもの
俗と聖の間の寺-西大寺
知恩院の二つの顔
年表 p.514~521
解説 奈良本辰也
解題 梅山秀幸
同じ1970年の『すばる』に連載が開始された「日本精神の系譜」とともに、「梅原古代学」と呼ばれるようになる最初の作品です。
「従来、すべての歴史家は日本書紀をもとにして古代を考える。この時代の歴史をさぐるには書紀がほとんど唯一の文献であることはたしかである。皇国史観も唯物史観も、書紀の上に事実を考える。
そこには歴史書というものにたいするあまりにも楽観的な信頼がある。歴史書は、本当のことを書くものであるはずだという信頼がある。
しかし、本当のことを書くために歴史書はつくられるのであろうか。本当のことであるならば、歴史書を書く必要はないのではないか。
歴史書を書かずに支配できる権力は、歴史書を書く必要がないのではないか。むしろ、歴史書が書かれるところ、そこに、大いなる欺瞞の意思が働くのではないか。
私は、古事記、日本書紀をそういう視点から見た。そして、その欺瞞の主体として、藤原氏、特に藤原不比等が大きく浮かび上がった。
この比べる人のないという意味の名を持った人間は、彼の子孫とともに、権力においても比べる人がない地位についたが、また欺瞞の知恵においても比べる人のないほど偉大であったらしい。古事記、日本書紀は、彼の指導のもとにつくられている。
そのように考えることによって、われわれははじめて、古代史の秘密をとく唯一の正しい視点を獲得することができる。そして藤原不比等は、消極的に己れの家に都合の悪い事実を書かせなかったばかりか、積極的に己れの祖先を、どうやら出身のあやしい自分の祖先を、様々な虚偽の神話の栄光によってつつまねばならなかった。
私はあえていう。日本の神話は、藤原氏の欺瞞への意思によってつくられたものであると。」
p.261「第四部 陰のヒーロー 第二章 若き中大兄皇子 何が中大兄を暗殺に駆り立てたか」
記紀の天孫降臨神話、アマテラス(祖母)からニニギノミコト(孫)への国譲りは、持統天皇(645-703 祖母)から文武天皇(683-707 孫)への、また元明天皇(661-721 祖母)から聖武天皇(701-756 孫)への譲位を神話化したもので、その作者は藤原不比等だと著者は主張します。
この主張の真偽は不明ですが、分かりやすい説明ではあります。
本当かな~。
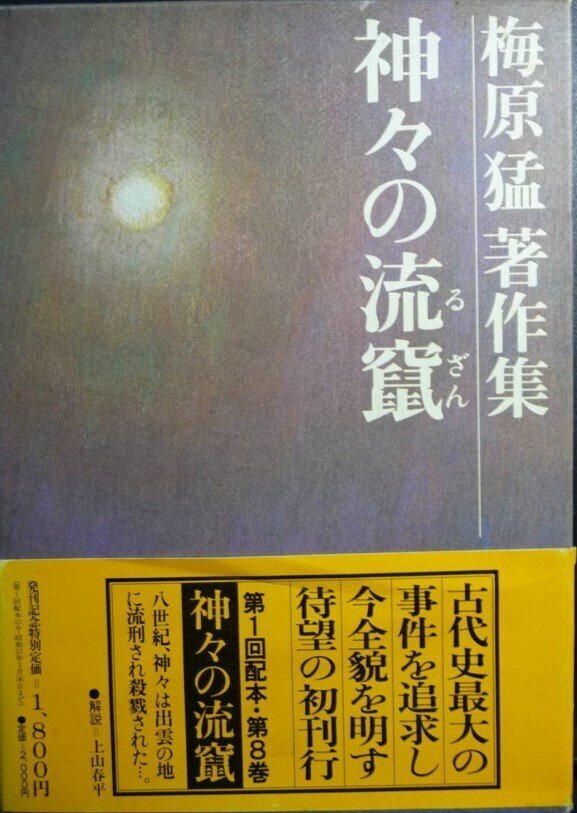
梅原猛 『梅原猛著作集 第8巻 神々の流竄』
集英社 1981年9月刊
2009年9月1日読了
梅原猛の日本古代学デビュー作
https://www.amazon.co.jp/dp/B000J7VNUA
https://www.amazon.co.jp/dp/4087490645
標題作は『すばる』1~2号(1970.6-9)に連載されましたが、単行本には収録されませんでした。
この集英社版『著作集』が出版された時、本書が第一回配本だったのを憶えています。
標題作の他に、
『文学』1980年5-7月号に連載された
「記紀覚書 稗田阿礼=藤原不比等の可能性」と
学習研究社から1980年10月に刊行された
『現代語訳日本の古典 1 古事記』
が収録されています。
「出雲神話と呼ばれるものの舞台は、出雲ではなかったのではないか。
スサノオやオオクヌシは、もし彼等が実在の人物の投影であったにしても、それは出雲を本拠にしていないのではないか。出雲を舞台にした「天の下造らしし大神」の話は、全くの虚構ではないのか。
こういう疑いは、日本神話の中心にかかわる根本的な疑いである。
『出雲国風土記』は、こういう疑いを生ぜしめるに十分な素材を提供したのである。」
p.45「大和と出雲」
「出雲神話は、出雲を舞台にしているものではない。
出雲は、じっさいは神々の流竄の場所である。
八世紀の政治的、思想的指導者によって追放された神々の、流罪の場所である。そしてその政治的、思想的指導者の中心に、藤原不比等がいるのではないか」
p.103「陰の部分 禊と祓の神話」
先月(2009年8月)上旬から梅原猛を五冊読みましたけど、そのほとんどは30年ぐらい前に一度読んでいたものの再読でした。本書は初めて読んでいます。
天武・持統・文武・元明・元正という天皇の頃に、『古事記』・『日本書紀』の神代の神話が、従来の神々の様々な神話をもとに新たに編纂された、というのが標題作の主張です。私には、その真偽は不明です。
「われわれは、天武・持統の宗教改革について論じてきた。つまり、彼等はもはや外来の仏教や儒教では、日本の国家統一のイデオロギーとして不適当であることを知っていた。そこで彼等のとった方向が、神道改革、新しい神道の創造である。
その第一歩は、伊勢神宮の建造であった。伊勢に天皇の祖先神を祭る。皇室の先祖の神をあらゆる神の中心におくことが、ここで必要であった。もしアマテラスが持統帝をモデルとしているとしたら、伊勢神道の完成こそ、持統帝の子孫たちにとってもっとも好都合ではないか。
……
天武・持統の神道、三輪神道や物部神道と全くちがった新しい神道を時代は必要としたが、こういう状勢に応じて新しい神道をつくり出したのが中臣氏であった。中臣大嶋によってつくられたこの神道を、[藤原]不比等は、[中臣]意美麻呂と協力して完成させていった」
p.220「中臣神道の確立 国家主義的な新神道の中心思想」
天孫降臨神話における祖母アマテラスから幼孫ニニギへの皇位継承は、祖母・持統天皇から孫の軽皇子(かるのみこ・文武天皇)への皇位譲位、および祖母・元明天皇から孫の首皇子(おびとのみこ・聖武天皇)への皇位譲位を望んだ女帝と女帝を支えて藤原氏の権力維持を願った不比等が作った物語だと著者は主張しています。
40年近く前に発表された、この梅原古代学第一弾は日本史学界では受け入れられていないのでしょう。
「古事記は、太安万侶(おおのやすまろ)の語るところに従えば、和銅4年(711)9月18日から和銅5年正月28日まで、わずか四カ月少しでできた。
この和銅5年(712)という年は、律令体制を完成させようとする藤原不比等が、はぼ独裁的な権力をもった時であり、この古事記も、藤原不比等と表裏一体をなして政治を行なった元明天皇の命令によってできたことを考えると、そのとき、当然彼らの政権を安定させるためのイデオロギーの改変が、行われたとものと思われる。
天照神話は、けっきょく、天孫邇邇芸命(ににぎのみこと)を葦原の中つ国に降ろして、その政治的支配者にするという話がその中心になっている。いってみれば、天照大神が、己の孫を高い所から低い所に行かしめて、その国王たらしめようとする思想なのである。
長い日本の歴史の中で、祖母から孫への譲位が行われたのは、わずかに一度、持統10年(696)だけである。ここにはじめて、天照大神から邇邇芸命への譲位のような、祖母から孫への譲位がおこなわれたわけであるが、文武天皇は在位十年で死んでしまう。
文武天皇の母元明天皇が、藤原不比等の助けによって帝位につくが、元明天皇の願望もまた、彼女の孫の首皇子(おびとのみこ・聖武天皇)に天皇位を譲ることであった。
……
古事記は元明天皇の和銅5年にできた。その神話の中心は天孫降臨である。これは、明らかに、当時の支配者の意思を物語っている。祖母から孫への天皇位の譲位は、古事記が書かれた十五年前にすでにあったのである。
ここで、はなはだ偶然的なこの歴史的事実を、一つの歴史法則にまで、高めようとしているのである。あの偶然的な歴史的事実よ、もう一度繰り返しておくれ。それが、元明の強い意志であったろう。」
p.550「古代国家を完成するためのイデオロギー革命」
小学生の頃、子供向けの「古事記物語」を読んだことはありますが、今日初めて、古事記を梅原猛による現代語訳で通読しました。
一度読んだだけでは登場人物の名前が憶えられないなぁ、というのが第一印象です。
「古代日本の精神史と私がいうと、人はおどろくにちがいない。なぜなら、人は仏教渡来以前の日本に、はたして思想らしい思想があったかどうかを疑うのである。
そして通説によれば、仏教をもまた、日本人は深い考えなく採用し、本当の教説は理解できず、ただそれを感覚的にのみ理解したという。このような考え方をとる限り、人はけっして、日本の思想の歴史をよく理解することは出来ないであろう。
六、七世紀という時代、私はそこに、日本においておそらく空前絶後のイデオロギーの戦いを見る。そしてイデオロギーの戦いは、当時にあっては宗教の戦いである。さまざまな宗教を奉じる氏族が、その文化的指導権と政治的指導権をめぐって、血で血を洗う争いをくりかえす、それが古代史の秘密である。
古い神道派があり、仏教派があり、儒教派があり、新しい神道派がある。そこでさまざまな神々が殺し合う。そしてそのような殺し合いの中から、ついに仏教が勝利を収める。
その仏教が勝利を収めた後では、もっぱら政治的争いは権力争いになるが、まだ国家の方向が定まらない時期は、ただ権力の争いがすべてではない。権力の争いの背後には、必ず、イデオロギーの、宗教の争いがある。
われわれは古事記と日本書紀を見るとき、まずそれを、イデオロギーの書と見なければならぬのである。」
p.79「古代日本の宗教改革 秘められた古代日本の宗教戦争」
古代からの神々の戦いを描いた
佐藤史生(さとうしお 1950.12.6-2010.4.4)のSFマンガ、
『ワン・ゼロ』全四巻
小学館PFビッグコミックス 1985-86
小学館文庫 1996.10
https://www.amazon.co.jp/dp/4835452534
を思い出して、再読したくなりました。
佐藤史生さんはきっと梅原猛を読んだのだろうなぁ。
山岸凉子さん(1947.9.24- )が、
『隠された十字架』を読んでから、
『日出処の天子』全11巻 を描かれたように。
https://www.amazon.co.jp/dp/459288051X
https://ja.wikipedia.org/wiki/日出処の天子

梅原猛 『葬られた王朝 古代出雲の謎を解く』
新潮社 2010年4月刊
2010年6月15日読了
https://www.amazon.co.jp/dp/4101244146
『芸術新潮』2009年10月号 特集「梅原猛が解き明かす古代出雲王朝」を大幅に加筆、写真・図版を追加。
私には著者の主張の真偽は判断できませんが、大和朝廷以前に出雲王朝が存在したとする本書は、読んでいる間、梅雨どきの蒸し暑さを忘れさせてくれました。たくさんのカラー写真がきれいで、出雲に行ってみたいなぁ。
「日本神話を解明するためには、本居宣長説、津田左右吉説と共に、私の旧説『神々の流竄』をも厳しく批判しなければならない。
率直にいうと、『神々の流竄』は「百の真理」と「百の誤謬」が混在した書物である。「百の真理」というのは、『古事記』『日本書紀』の実質上の著者として藤原不比等を発見し、不比等がどのように『古事記』『日本書紀』の編纂にかかわったかを明らかにしたことである。
藤原不比等は、藤原鎌足の嫡子であるが、その事跡はほとんど歴史の陰に隠れていた。しかし彼には、藤原鎌足によって獲得された藤原氏の権力をほぼ永久化したという大功績があった。
藤原氏は鎌倉幕府が成立する時まで天皇の陰にいて、ほぼ政治の実権を握っていた。そして以後も朝廷を抑え、実に約千二百年もの間、日本第一の名家として栄華を欲しいままにしていたのである。この千年以上の栄華の基礎を作ったのが謎の政治家、藤原不比等である。
私は、藤原不比等をこの日本歴史偽造の中心人物と考えた。この説をとるのは今のところ数少ないが、私はそれを間違いないと思っている。「百の真理」というのはいささか大げさであるが、このような不比等の権力の発見がなかったならば、『隠された十字架』の法隆寺論、『水底の歌』の柿本人麻呂論も書けなかったであろう。
その『神々の流竄』で、藤原不比等について語った後半部は正しいと考えているが、前半部は全くの誤りである。
それは、出雲神話は実は出雲に伝わる神話ではなく、ヤマトに伝わる神話を「神々の流竄」という藤原不比等の政策のために出雲に仮託したものであるという説である。」
p.227「第四章 記紀の謎」

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『世紀末そして忠臣蔵 丸谷才一対談集』
立風書房 1987.9
第11冊目の対談集
梅原猛(1925.3.20-2019.1.12)
「忠臣蔵と日本人」『現代』1984年11月号
「丸谷才一 私は以前から日本文学史を呪術的なものとしてとらえようとする傾向がありまして、『千載和歌集』は崇徳院の怨霊慰撫のために編まれた勅撰集だという評論
[平忠度 ささなみや志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな
『新潮』1975年8月号「読人しらず」
『新々百人一首』新潮社 1999年6月刊]
を書いたことがあるんです。
それは最近どうやら、学界の定説になりかけているらしいんです。
私の名前は出ないで……。
梅原猛 ま、だいたい出ません(笑)。
国文学者以外は出ないんです。
丸谷 梅原さんの場合もそうでしょ。
梅原 出ない。出ないけれども定説になっている。
丸谷 それがわれわれの光栄なんです。」
p.25「忠臣蔵と日本人」
https://www.amazon.co.jp/dp/4651710255
読書メーター 梅原猛の本棚(登録冊数25冊 刊行年月順)
https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091243

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
