
Blue植物化❺〜テッド的なものからは逃げねばならない。
ハルキムラカミの《海辺のカフカ》を
読み終わり、今は、
ジョン・アーヴィング
《未亡人の一年 上》を読んでいる。

葉月お盆のころのコメダ珈琲店
この本を初めて読んだとき、
物語の素晴らしさとは別に、
《読みづらさ》が、あった。
なぜなら、
登場する主人物の、ひとり、
美しいマリアン(39才)の夫、
女たらしで、酒飲みで
絵本作家の、ハンサムなテッド(45才)
が、絶えず、
《獲物》として
女たち、を、まなざすからだ。
テッドは、目の前に現れた
おんな、に、見惚れたり、は、しない。
恋に落ちて、《彼女》を欲するのではない。
ただただ、
《陥落》させるために
狙いを定め、
こころの深いところから
触手を伸ばし、
彼女の《心身》を
奪おうと、する。
好みの範疇か? とは、考える。
問題外なのは、彼の目には入らない。
しかし、多少の欠落は、
彼の、性的な興味をかきたてる。
例えば、書店で出会った
ふっくらとした十代の娘グローリーと
痩せ細った、その母親への《興味》は、
とても、グロテスクで残酷だ。
テッドは自分が、グローリーの母親に対しても、予想外の(性的な)興味を抱いたことに驚いた。グローリーが彼のいつもの好みより少し若すぎ、経験が足りなさすぎたーそれに体型は許容範囲ぎりぎりだったーとしたら、グローリーの母親はマリアンより年上で、ふつうならテッドの注意を引かないタイプだった。
「未亡人の一年 上』
新潮社 p201より

黒胡椒がきいた鶏ハム。
若かったわたしは、
本のなかでテッドに出会い、理解した。
世で出会う、
男のひとの半分、いや6割が
テッドのようなまなざしで、
おんなたちを視て、時に
近づいてくるのだ、と悟った。
彼は彼女の唇が気にいった。彼女の口は丸くて小さかった。そして胸は大きかった。ーほとんど大きすぎるほどだった。あと数年で自分の体重と闘わなければならないだろう。だが、今はいい感じにぽっちゃりしていたし、まだウェストもあった。テッドは女性を、体のタイプ別に分けるのが好きだった。自分はほとんどの女性について、将来どんな体型になるか思い浮かべることができるとテッドは信じていた。この子は、子供を一人産んで、ウェストがなくなるだろう。体のなかでも、圧倒的に尻が大きくなるかもしれない。
『未亡人の一年 上』
新潮社 p192
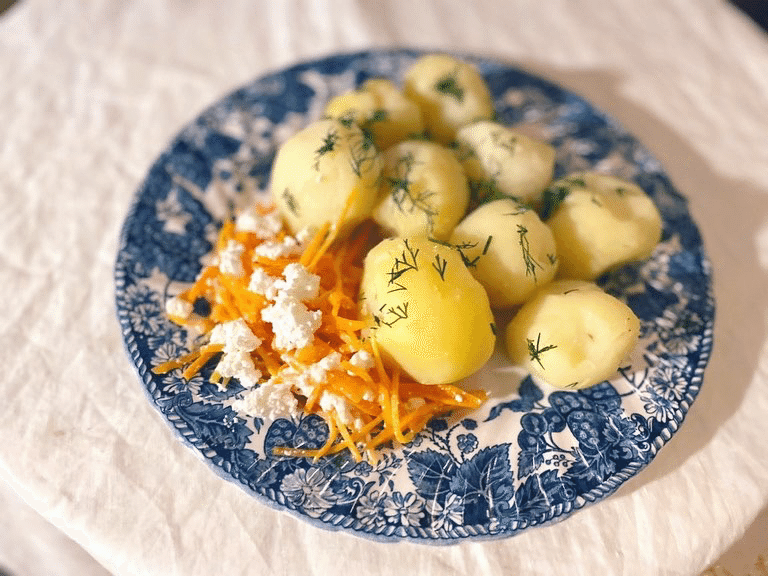
学生の頃、
アルバイト先で給仕した
見知らぬ40代の男性に
『痩せれば、有り』
と、囁かれたことがある。
そのひとは、汗で皺になった
ワイシャツを着て、
お腹はだぶついていて、
部下に、課長と呼ばれていた。
生ハムのサラダや
ピザを運びながら、
わたしは、傷ついていた。
なぜ、見知らぬ男が
わたしにそのようなことを言うのか?
理解できなかった。
たまたま、そのひとが
奇妙なひと、なのだろうと思い、
混乱を収めたが、
汚いもので触られたような
感触が、こころに残った。

しかし、そんなことは
度々、人生に起こった。
例えば、
町内の子ども会の役員になったとき
自治会のご老人との飲み会に出なければならず、
(それは、義務、であった)
彼らの数人が
『今年の子ども会のお母さんたちは
代替わりしたのか、若くて、良い。
去年のメンバーは、ひどかった。
あんなおばさんたちじゃ、つまらない』
『そうだ、そうだ』
『今年は酒がうまい』
と、ビールを注ぐ役目のわたしたちに
聞こえるのもお構無しに、喋っていた。
自治会のおじいさんたち、が
町内に住む、こどもを育てている母親たちを
テッドのように《まなざす》こと
は、トテモオソロシイコト、と
わたしには、思えた。
今も、ソンナコト、は
怒り続けている。

一枚ずつ、大事に食べる。
さて、Blue植物化を
志してから、
ダイエットとは
こういった、まなざし、から
逃れること、への手段として
ベクトルを向ければ
とても楽しい、と気づいた。
引き締まった腹部、
弓のような背すじ
重力にさからうヒップ
しなやかな太もも
すい、と、伸びた首
チカラを蓄えた、二の腕
それは、まなざされること、を
拒否するチカラを、持つ。
わたしの好きなように
わたしが思うように
と、生きるチカラになる。
テッドは、悲しみや不幸や
コンプレックスを表情や
カラダつきにたたえた、
おんなたちを、選んで
獲物にして、
がらんどう、に、した。
それは、彼の、《万能感》のタンクを
満タンにするため、必要なのだ。
突然、ものにしたい女性が二人現れた!似たような立場に置かれたら、たいていの男性はこう考えることだろう。まいったな、どうすればいいんだ!だがテッド・コールは可能性の観点からしか考えなかった。可能性が広がった!
『未亡人の一年 上』
新潮社 p202より
この万能感は、けっして
男からは得られないもの、らしい
と、わたしは、今更、知る。
(もしかしたら、パワハラ的なものは
それに代わるかもしれない)
テッド的なもの、からは、
逃げねばならない。
闘わなければならない。
(それは、昨今の政治にもある)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
