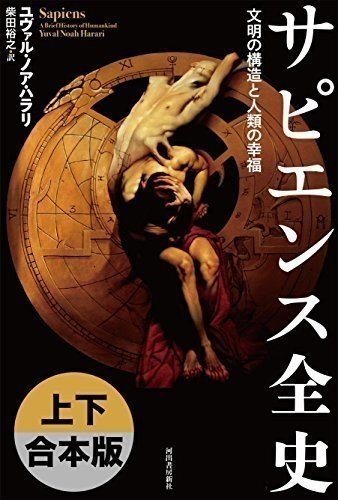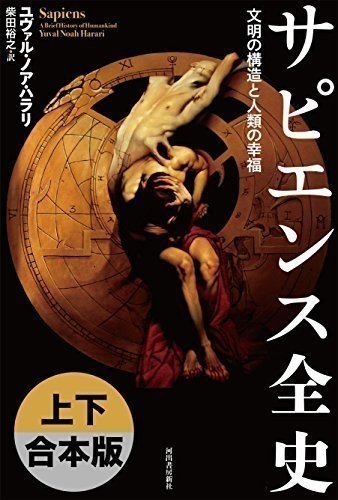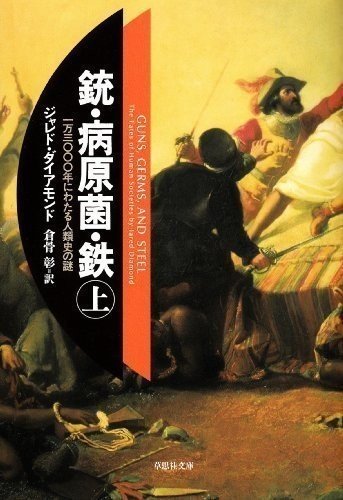書評 「サピエンス全史」
長らく積んであったサピエンス全史を、お正月休みを使って、ようやく読了。前評判通りの良作だった。一年最初の本として、かなりいいものを引き当てた感がある。
本書はホモ・サピエンスの出現から情報革命まで、あらゆる軌跡を1冊にまとめた超大作だ。タイトルに違わず、ホモ・サピエンスの歴史全てを俯瞰した本である。
本書は、ホモ・サピエンスとネアンデルタールの明暗を分けた、人類最初の革命、「認知革命」から語られる。
およそ7万年〜3万年の期間に、ホモ・サピエンスは高度な抽象思考の能力を獲得する。この瞬間、人類はDNAの奴隷から、後天的な学習により自らを大幅にリプログラミング可能な、特異な生物となった。抽象的な思考の獲得は、人類に「物語」(共同幻想)を与え、それはより巨大なコミュニティの運営を可能とすることとなる。
環境を改変しながら世界に拡散する人類は、1万年ほど前に農業という概念を発明する。しかし、古代人にとって農業は壮大なペテンであった。農耕民族は、狩猟民族以上の手間をかけ食料を生産した。しかし、手に入る食料は質も量も、狩猟民族に比べはるかに劣っていたのだ。食料の大量生産は、人口の増加で打ち消され、大量の貧しい民が増えただけだった。定住や家畜は衛生環境や疫病などの問題も引き起こした。
農業によって拡大した人口は、同時にコミュニティの統治に対する問題を生み出した。数千、数万人の人々を束ねるには、強い共同幻想が必要となった。結果、文字や階級の発明などを経ながら、強力な共同幻想として貨幣、宗教、帝国といった概念が生まれていく。
このような壮大な人類のサーガは、ルネッサンスの科学革命を経て、急速に加速していく。
「科学の発展」は「富の創出」をもたらし「帝国の拡大」を拡大する。この3者のトライアングルは、以後500年の発展の基軸となり、人類を大きく進歩させた。科学は力となり、力は帝国を成長させ富を生む。そして富は、さらなる富を生むために再び科学へと注ぎ込まれていく。急成長する帝国は世界を多いつくし、そのサイクルの中で資本主義や合理主義といった、神のいない宗教(イデオロギー)が生まれ、植民地が生まれ、奴隷貿易が生まれていく。
蒸気機関の発明は、農業人口を90%から数%以下へと引き下げ、余剰の人口は様々な職業に割り振られていく。生産性が向上を経て、エネルギー革命はついには原子爆弾を生み出す。ところが世界を終わらせるかに思えた核兵器は、予想外にも膠着状態を作り、グローバル経済と両輪で、意図せぬ平和の時代を生み出す。暴力で得られるものよりも、失うものが遥かに大きくなってしまったためだ。20世紀後半は、人類至上もっとも平和な時代となった。
一方で拡大する資本主義は、「成長し続けなければならない」という呪いを産み、科学と産業はパイの拡大を至上の命題とすることになる。このため、消費は善であるという幻想が発明される(「消費のための共同幻想」の発明に関しては、エイドリアン・フォーティの「欲望のオブジェ」が詳しい)。
このような、サピエンス全史の旅は、2つの課題を残して終わる。1つは「人類は幸せになったのか?」。そしてもう1つは「超人類の可能性」だ。
「幸せ」は、基準値からの相対的な変化であり、主観的なものである。このため現代人が、中世や石器時代の人類に比べて、幸せになったとは必ずしも言えない(このあたりのテーマはロバート・フランクの「幸せとお金の経済学」などが詳しい)。個人主義の発明と宗教やコミュニティの解体を勘案すれば、人類はむしろ不幸になっているのかもしれないと論じられる。
超人類は、これから未来について論じたテーマだ。人類のテクノロジは、遺伝子改良、不死化、サイバネティクスなど、超人類を生み出す方向に進んでいく。またAIなどの発展は、人類以外の新プレイヤーの台頭の暗示する。いずれにしろ、数百年後の人類は、現在と全く異なる価値観や、感情、生命となっている可能性が高い…その可能性を示しつつ、本書は幕を閉じる。
非常に駆け足であるが、本書はそのような内容を、俯瞰的に見つめた本である。個々の内容は、それをテーマとした名著があるが、それを包括した大著として大変な力作だと思う(ただし、それに見合う文章量だが)。
本書は、ジャレド・ダイアモンドの「鉄・病原菌・銃」と対比しながら読むと面白い。こちらは五大陸の地勢的な違いが、文明の進化や反映にどのような影響を与えたのかを論じる本。こちらも長いがよい本。
サピエンス全史 上下合本版
ユヴァル・ノア・ハラリ (著)
銃・病原菌・鉄
ジャレド・ダイアモンド (著)
いただいたサポートは、コロナでオフィスいけてないので、コロナあけにnoteチームにピザおごったり、サービス設計の参考書籍代にします。