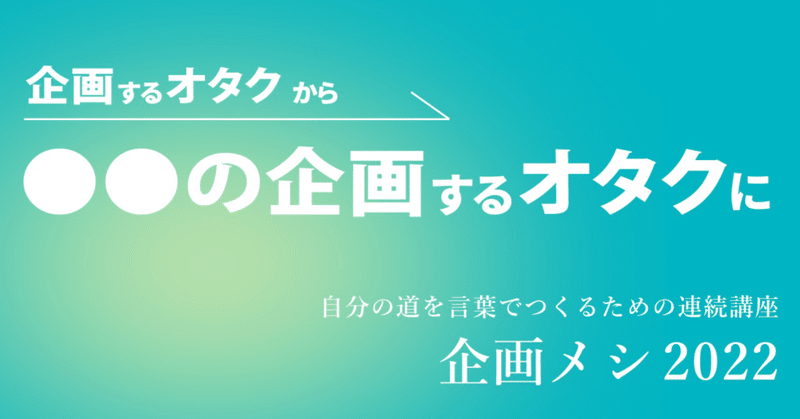
#企画メシ 第2回「感受性の筋トレ」
こんにちは、ふみです。
今日は「企画メシ2022」2回目の講義でした。
▼企画メシ2022マガジン
前回講義のようすなど、企画生の想いが詰まったnoteが読めます!
絶望、からの秒で開き直り
第二回は「放送の企画」。
放送作家の大井洋一さんがゲスト講師。
課題は「新しいドッキリを考えましょう」。
詰んだ〜〜〜〜〜〜〜〜〜と思いました。正直。
何を隠そう、私はTVを全く見ない。家にテレビがない。
Tverとかで見れるのは知ってるけれど、ほぼ見てない。
モニターと向き合うのはゲームか、PS4で見るネトフリ・アマプラのアニメと、時々リアリティショーを見る程度。
芸能人もうっすらしか知らない。
知識として人気な人の名前は把握してるけど、どれくらい知識がないかというと「千鳥がどんな芸風なのかわからない」レベル。
しかも、ドッキリ。
私の企画は、周りから超ロジカルと言われます。
アウトプットする時は右脳的な、感覚で感じられる良さも大事にしているけど、それに行き着く道にも論理がある。
だから、とにかく面白いこと考えるとか、ふざけてみるっていうのはちょっと弱い。
苦手な企画だ〜〜〜〜〜と崩れ落ちそうになったけど、
「あれ?苦手な企画って超チャンスじゃない?」と気づく。
普段仕事してて、ここまで強烈に「苦手」なんて感じたことない。
普段だったら縁のない企画。おもしろい。
むしろ、こういう経験をしに企画メシに来たんだった!
たぶん拙い企画になってしまうけど、全力でやってみよう!
秒で開き直ったのが、第一回で課題が発表されてすぐのことでした。
なんでも楽しめるのは自分の良いところだな、と再発見。
自分を使って実験する
企画メシの課題に取り組むにあたって、毎回取り組み方に関するテーマを設けることにしました。
「課題とどう向き合うか?」アプローチを毎回変えたり考えることで、何か殻を破れないかな、と思って。まさに自分を使った実験です。
今回は『とにかくインプット&ギリギリまで藻掻く』。
これは、阿部さんが第1回の講義で残してくれたヒントを、素直に実行してみようと思ったから。
誠実さを持って、相手のことを徹底的に調べる。
なんだ、当たり前のことではないか、あなたはそう思うかもしれない。
ただ、この当たり前のことをやり切ること、そこから自分なりの感動を見つけることで、いい企画は生まれる。
インプットが足りないのは分かってる。課題提出までの期間頑張ったところでずっと好きな人、ずっと続けている人には勝てないかも。
でも、その心に、頭に、少しでも近づきたい。
だから、良い企画ができるか自信はないけど、とにかくがむしゃらにやってみる。
大井さんの過去のインタビュー、ブログの過去記事全部、出演されているYoutube、Twitterを遡れるところまで、手掛けている番組やツイートしていた番組でYoutubeやTver、Abemaで見れるもの。そこから派生して、世の中で話題になったドッキリ、Youtuberのドッキリ、周りの人に好きなドッキリを聞いてみる…。
色々頑張ってみたけど、何もつかめない。
そもそもなんだけど、お笑いにやTVに対する感受性が死んでいるのをひしひしと感じました。。。
見て「面白い」と思ってもそこで止まってしまう。
面白くないからではなくて、私の感受性が足りていない。
感受性も筋肉みたいなものなんだなあ…。
脳ミソの筋肉痛になった気分でした。(ほんとに頭痛した)
とはいえ、この展開は若干予想していた。
だから、それでも粘ってみる。
締切前日、会社に残って企画を書きました。
提出後、即反省
TVを見ないオタクが企画を考える。
大井さんはきっと、TVを見てほしいと思っているはず。
じゃあ、普段TVを見ないオタクでも見たくなるドッキリってなんだろう?
大井さんはインタビューで「これどうなっちゃうの?」と思える企画がいい、と話していた。
ということで、オタクが好きで「これどうなっちゃうの?」とついつい続きを見てしまうネタ×ドッキリという掛け合わせに。
1つは「転生ドッキリ」。2つ目は「無限ループドッキリ」。
このネタが良いか悪いかは、自分でも正直分かりません。
けど、それ以外のところで提出後、即反省することになりました。
企画を見返して思ったのは「全然大井さんへのリスペクトを入れられてなかった!!!」ということ。
阿部さんがせっかくくれたヒントなのに、追いつめられた私は頭からすっぽ抜けていました。
自分なりに「面白いTVや放送の企画って、たくさん説明が無くても成り立つものだよな」というのはあったので、あえて企画意図は少なくしたり、工夫したところはありました。
でも、そことは別に、大井さんへのメッセージやインプットしての学びを書けばよかったな~!と、、ここは次回へ向けての反省です。
未知だったはずなのに、色が重なっていく
講義当日。
どんなお話をされるんだろう…と全く未知な状態で参加。
講義が始まると、課題に取り組んでいる間は死んでいた感受性が、生き返るようにたくさん動いていくのを感じました。
・人がやるより先にやらないと!という焦りにも似た原動力
・スキルをタダで提供するのはあんまりオススメできないけど、自分のことだとやっちゃうよね~という人の良さと好奇心
・どんな相手にも合わせに行く、ハマりにいく姿勢
・ハマりにいくけど、「こんなのどうですか?」と自分の思う面白さも大事にしてみること
・TVで放送するための「建前」と「出口」の考え方
・「こうだよな」からのほんの一ひねり、違和感づくり
・誘われたら断らない。忙しくても、迷惑をかけない限り受ける
大井さんはそうやって企画されているんだ!と感動することの中に、共感できるところもたくさんあったのが印象的でした。
やっと、「大井さんと自分の色が重なる部分」をたくさん見つけることができた。
今回は全然足りなかったけど、元来私もインプットすることは大好きだし、普段の仕事で「相手にハマりにいく」は結構やってる。「誘われたら断らない」も結構そう。
じゃあ、大井さんと私の違いってなんだろう?
一番に思いつくのは、「TVとお笑いへの愛」。
大井さんが話しているのを聞いていたら、なんだかTVが見たくなってきて。普段TVを見ない私がそこまで思うって、ものすごい。
愛がある人は強い。
まさに、好きこそものの上手なれ。
企画でメシを食っていくことを考えた時に、限られた時間でどこまで相手をインストールし、企画する対象に愛を持ち、感動できるか?
ここでまた、阿部さんからもらった「超言葉術」のヒントに戻ってきました。
言うは易し、行うは難しだなあ…。
それでも、これから普段自分が触れないジャンルに自ら飛び込んで、感動しにいってみたい!と思える講義でした。
息をするように企画する
息を吸うように企画していたい。
そして、「私はこういう企画をする人です」と、
周りに伝わるように宣言できる人になりたいからです。
企画メシのエントリーシートに書いた、参加理由。
大井さんはまさに、それを体現している人に見えました。
すごくフラットに、企画をする姿はまさに「ライフワーク」といった印象。
だけど、粛々と目の前の仕事と向き合っているようで、奥にはTVやお笑いへの情熱が灯っている。そんなふしぎな温かさを感じました。
そして、呼吸の仕方にも色々あるよなあ、と。
それが「自分の道」にも通ずるんだろうか。
前回「企画は山登りに似ている」とnoteに書いたけれど、どんな山を登るか?どんな人と登るか?どんな景色が見たいか?どんなペースで登るか?
そんな風に、自分なりの呼吸のしかたも、見えてくるのかな。
とにかく、今回も楽しかった!!!
講義後「企画メシの放課後」を開催して、企画生の距離がちょっとずつ縮まってるのも嬉しい。
エネルギーを使ったのでカロリーを求めてコンビニに行ったら、夏の夕暮れどきの空気がまさに放課後で、青春を感じたり。
話すこと、肌で感じることのインパクトって、やっぱり強い。
企画メシの放課後については、また別途note書きたいな~!と思ってます。
今回も大満足!!
おつかれさまでした!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
