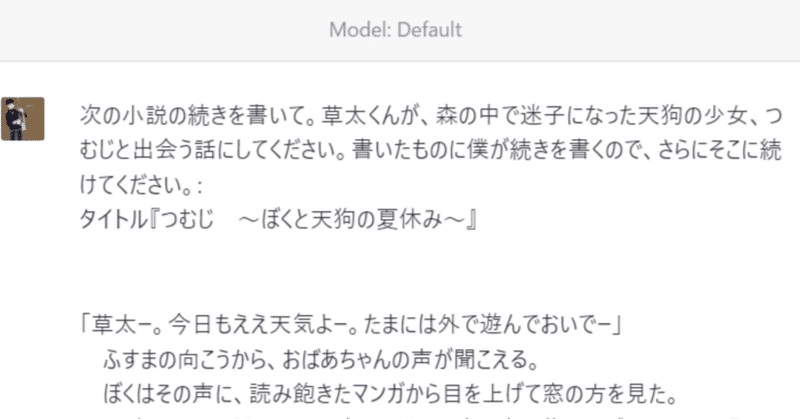
AIで書きかけの小説の続き書いてもらってみた。
すごすぎるAIとして話題のChatGPTで、小説を書いてみたらおもしろいな、と思っていろいろ試してみたところ、「この小説の続きを書いて」という形ならうまく行きそうなので、やってみた。
ちなみにChatGPTは、月20ドルの有料版に登録してみています。
やり方
1500字くらいの小説のプロローグ(約1500字)を用意する。僕の場合、ずっと前に書きかけて放置していた小説があったのでそれを使ってみた。
「次の小説の続きを書いて。書いたものにぼくが続きを書くので、さらにそこに続けてください。」と指示。
ChatGPTくんが書いてきた文章に対して、その都度3〜5行くらいの「続き」を書いて返す。
内容の矛盾点や、キャラクターの話し方のぶれなどを手動で校正して、完成。全体の文字数は7000字くらいになった。
実際の指示の文章はこれ。
次の小説の続きを書いて。草太くんが、森の中で迷子になった天狗の少女、つむじと出会う話にしてください。書いたものにぼくが続きを書くので、さらにそこに続けてください。:
プロローグ(最初に準備した文章)
タイトル『つむじ 〜ぼくと天狗の夏休み〜』
「草太ー。今日もええ天気よー。たまには外で遊んでおいでー」
ふすまの向こうから、おばあちゃんの声が聞こえる。
ぼくはその声に、読み飽きたマンガから目を上げて窓の方を見た。
おばあちゃんの言うとおり、窓から見える広い庭の芝生はバカみたいに明るい太陽の光に照らされてさんさんと輝いていた。
今日は確かにいい天気。いい天気過ぎる。
庭にたくさん植えられた木の幹にはたくさんのセミたちが張り付いて、快晴の空をよろこぶみたいに大きな声で大合唱してる。ミンミンゼミにアブラゼミ、それにシャアシャアと鳴くぼくの知らないセミも、この暑いのに一生懸命鳴きまくっていてうるさいことこの上ない。
そう、暑い。今日は——いや、この夏はずっとだけど、めちゃくちゃに暑すぎる。
部屋にいても噴き出した汗がぽたぽたと落ちてきて、ぼくは首に巻いたタオルで何度も汗をぬぐった。
そもそも、この部屋にクーラーがないのがおかしいんだ。いくらおばあちゃんちが古いからって、今時クーラーがない家なんて信じられない。おばあちゃんに文句を言っても、「夏は暑いもんよ」とか何とか言って取り合ってくれないんだ。
昔の人たちはみんなこんなに暑いのに耐えていたのだろうか。ぼくにはとても耐えられない。
それに、おばあちゃんちだけじゃない。この村の人たちの家にはほとんどクーラーがついてないらしい。村中にクーラーがないなんて田舎過ぎるにもほどがある。
だからぼくは、来たくなかったんだ。
こんな田舎のおばあちゃんちなんかに来ないで自分の家にいれば、今頃クーラーの効いた涼しい部屋で夏休みのはじめに発売されたばっかりの新作RPGをやれていたはずなんだ。
きっとクラスのみんなはもうあのゲーム、クリアしちゃってるんだろう。いつもは新作のゲームをクリアするのはぼくがクラスで一番早くて、それだけがぼくのちょっとした自慢だったのに。
それなのに。ぼくがここに来なきゃいけなくなったのは、お父さんの仕事の都合だった。仕事が忙しくて、夏休みにぼくのご飯を作ったりする暇がないから、ってお父さんはぼくをおばあちゃん(お父さんのお母さんだ)に預けることにしたんだ。
ぼくの家にはお母さんがいない。去年の夏、病気で死んじゃったんだ。ぼくには兄弟もいないから、ぼくはお父さんと二人で暮らしている。
お父さんは終業式の日の夜、つまりおとといの夜遅くに会社から帰ってくるなりぼくにこう言った。「草太、悪いけど明日からおばあちゃんのところに行っててくれないか? お前はもう六年生なんだから一人で行けるよな?」
こういう話し方をする時のお父さんには逆らえない。言葉は疑問形だけど、本当は命令なんだ。「一人で行けるよな?」ってのは「ひとりで行けよ、いいな?」って意味なんだ。
ぼくだって、お母さんが死んでからいつもいらいらしてるお父さんに口答えをして機嫌を損ねるのは得策じゃないって知っているから、黙ってうなずくしかなかった。
本当は嫌だったけどさ。夏休みの間中ずっと、テレビゲームもできないなんて。
クーラーさえないおばあちゃんちにテレビゲームなんてあるわけがなくて(それどころかおばあちゃんは、「テレビゲーム」ってのがなんなのかさえわかってないんだ)、ぼくはヒマをもて余していた。
来る前にお父さんにねだって買ってもらったマンガもとっくに読み終わっちゃって、何もやることがない。
「草太ー、聞いとるのー?」
ふすまの向こうから、またおばあちゃんの声がする。「今行くよー!」
ぼくはふすまのむこうに向かってそう叫んだ。
どうせ部屋にいたってやることない。おばあちゃんもうるさいし、しょうがない、外に行くか。
……別に外に行ったからって何があるってわけじゃないんだけど。
ぼくは畳の上に転がっていた白い野球帽を拾い上げると、頭にかぶった。
部屋を出て玄関でお気に入りの黒いスニーカーをはいて、ぼくはドアを開けた。
セミの声がもう一段階大きくなる。ドアの外には背の高い木が生い茂った森が広がっていて、その葉っぱの隙間から雲ひとつない真っ青な空が顔を出していた。
暑くってうるさくって、でも空がとってもきれいな、ひたすらいい天気な夏の日だった。
続き(AIが作成した文章を一部修正)
ぼくは庭を出て、しばらく森を歩いた。木々の陰に入ると、セミの騒音も少しは静かになる。そして、ぼくは一つの小川にたどり着いた。
小川のそばには、小さな岩がたくさんあって、水面に向かって積み上げられている。ぼくは小川に足を入れ、冷たい水に触れた。ぼくは水をすくって、手を洗った。
そのとき、ぼくは小さな声を聞いた。声は近くにいるように感じられたが、周りには誰もいなかった。ぼくは声の主を探すために、小川の上流に向かって歩き始めた。
しばらく歩いたあと、ぼくは小川の岸辺に座っている少女を見つけた。少女は、頭に巻かれた赤い布が風になびく、変わった格好をしていた。彼女はぼくに向かって微笑んだが、ぼくは彼女が誰なのかわからなかった。
「こんにちは、わたしはつむじ」
知らない名前だった。ぼくは彼女に近づいて尋ねる。
「ぼくは草太と言います。あなたは、この森で迷子になったの?」
「うん。でも、わたしは天狗なの。迷子になるのは珍しいことじゃないわ」
ぼくは彼女の話を聞いて驚いた。天狗が本当に存在するなんて、ぼくは今まで信じていなかった。
「天狗って、本当にいるの?」
「いるの。でも、人間にはなかなか見えないものなんだよ」
つむじは微笑んで言った。ぼくはつむじが天狗だと信じるようになった。そして、彼女と話すうちに、つむじが迷子になった理由を知った。
つむじは、ある日、天狗の里に行くことになった。天狗の里は、天狗たちが暮らす場所で、人間には見えないように隠されているという。つむじは、その里に行く途中で迷子になってしまったのだ。
「天狗の里に行くのは、大変なことなんですよ。でも、もしわたしが一人前の立派な天狗だったら、風に乗って空を飛び、高い空から簡単に里を見つけられるはずなの。でもわたしは落ちこぼれで、まだ空を飛べないから……」
つむじは泣きそうな顔になりながらそう言った。ぼくはなんだかつむじを助けてあげたくなって、急いでこう言った。
「じゃあさ、いっしょに、空を飛ぶ練習をしようよ。何をすればいいかわからないけど、ぼくも手伝うから」
その言葉につむじは、顔をぱっと明るくする。
「ほんと? 草太くんが、手伝ってくれるの?」
つむじが見せた笑顔のかわいらしさにちょっとだけドキッとしたのをごまかしながら、ぼくは、力強くうなずいた。
「当然だよ。迷子になってしまった仲間を見捨てるなんてできないからね。じゃあ、さっそく練習を始めようか」
ぼくは、つむじに手を差し伸べ、彼女もその手を取った。
「えっと……まずは、風を感じる練習からかな。この場所に来た理由は、自然の力を感じ取ることができるからでしょ?」
ぼくは、手を広げ、風を感じるように誘導すると、つむじも手を広げ、風を感じ始めた。
少しずつ、つむじは風を感じることができるようになってきた。そして、次は、一緒に走って風を味方にする練習を始めた。
最初は、吹き津ける風に合わせてつむじが走ることで、少しずつ浮いていくようにする練習をした。そして、しばらくすると、つむじ自身で風を起こして、体を浮かせることができるようになった。
数日後、つむじは自分で空を飛べるようになった。彼女は、ぼくに感謝の言葉を言い、天狗の里に戻ることにすると告げた。つむじはぼくに言った。
「草太くん、本当にありがとう。わたしは、帰った後もまた草太くんに会いたい。だから次は、草太くんにも、天狗の里に来てほしいな」
つむじはそう言うけど、空を飛べない人間には、天狗の里を見つけることは難しい。
「でもわたしは、もう草太くんに会えないなんて、さびしい……」
「ぼくだってさびしいよ! でも……」
一体何をどうすればいいのか、さっぱりわからなくて途方に暮れていると、つむじがハッと思い出したようにつぶやいた。
「そういえば、人間でも天狗の里に行ける方法があるって、お父様にきいたことがある」
「お父様って?」
「お父様は天狗の里の長の、大天狗なの」
つむじの言葉に、ぼくは目を丸くする。
「つむじって、お姫様だったんだ」
「そんなんじゃないよ……」
つむじは照れたようにはにかむ。
「それで、お父様の言うには、天狗が本当に愛した相手なら、一緒に天狗の里に入ることができるんだって」
「あ、愛した相手……」
思わずドキッとしたぼくに、つむじが続ける。
「必ずしも恋人とかってわけじゃなくて。家族や友達、大切な人なら誰でもいいって」
つむじはにっこりと微笑みながら、ぼくに言った。
「だから、草太くんと一緒に天狗の里に行けるはずだよ」
ぼくはつむじの言葉に安堵した。つむじと一緒に天狗の里に行けるなら、それ以上の幸せはないと思った。
「ありがとう、つむじ。じゃあ、ぼくを天狗の里に連れて行ってくれる?」
ぼくたちは、つむじが導く方角に向かって歩き始めた。どこか遠くで、セミの声が聞こえてきた。それは、ぼくたちが一歩一歩進む中で、ますます大きく響いてくる。
「里へは、歩いて行くの?」
ぼくがたずねると、つむじは首を横に振った。
「歩いてはいけないわ。風をつかまえて、一緒に飛ぶの。ほら、わたしにしっかりつかまって」
つむじの言葉に、うなずいて、ぼくは言われるままにつむじに抱きついた。やわらかい感触とあたたかなぬくもりが伝わってきて、顔が真っ赤になる。
つむじは、ぼくをしっかりと抱きしめ、そっと目を閉じた。そして、風を呼び起こすように、手を振り始めた。最初は、ほとんど風も感じなかったが、少しずつ風が強くなっていく。そして、つむじの手の動きも速くなり、ついには空中に浮かび上がった。
ぼくは、初めての空中散歩に興奮しながら、つむじにしがみついていた。風の音が耳に響き、周りの景色が一気に広がっていく。空気が身体を包み込むように流れ、心地よい感覚に包まれた。
つむじは、自由自在に空を舞い、空中での移動を巧みにこなしていた。そして、しばらくして、遠くに天狗の里の姿が見えてきた。
天狗の里は、緑豊かな山々に囲まれた静かな場所にあり、山中にある鍾乳洞を利用して作られた洞窟のような住居が建ち並んでいた。空から見ると、天狗の里はまるで別世界のように美しく見えた。
つむじは、しっかりとぼくの手を握りしめ、空から降りて天狗の里に入っていった。
ぼくは緊張しながら、つむじと手をつないで里の中に足を踏み入れた。里には、たくさんの天狗がいて、おどろいたように目を丸くしてつむじとぼくを見つめていた。つむじのように、ほとんど人間と変わらない天狗もいれば、顔がすっかり鳥のようになっている天狗もいる。昔話で聞いたような、赤い顔で鼻の長い天狗もいた。
里に入ったぼくらに気づいた天狗たちは、驚きと好奇心で視線を向けてくる。中には、つむじを見て鼻歌まじりに歌い始めたりするものもいる。その歌声に誘われるように、つむじは手を引いてぼくを連れて行き、天狗たちの中に入っていった。
「つむじ、どこへ行くの?」
「お父様の大天狗のところへ行くの。お父様に、草太くんを紹介したいから」
ぼくたちは人だかりをかき分けながら、大天狗の前までたどり着いた。
「お父様、草太くんを連れてきたわ」
つむじが言うと、大天狗は優しげな目をしてこちらを見た。そして、つむじに言葉をかけた。
「つむじ、お前が愛した相手を、このように連れて来るとは。草太くん、お前はつむじを大切に扱ってくれると約束するか?」
「は、はい、絶対に大切にします!」
ぼくは力強く言葉を返した。
「それならば、お前たちをこの里に迎え入れよう。天狗たちがお前たちをもてなすとしよう」
大天狗が言うと、周囲の天狗たちが歓声を上げた。色とりどりの食べ物が供えられ、音楽と踊りで祝福が始まった。
その後、ぼくとつむじは里の中を案内され、色々な場所を訪れた。大天狗は、ぼくたちに空を飛ぶ練習を見せてくれたり、天狗たちのダンスに参加させてくれたりした。
その日以来、ぼくは天狗の里に通うようになり、つむじと一緒に過ごす時間が増えた。里での暮らしが少しずつ慣れてくると、つむじと一緒に空を飛ぶ練習も頻繁に行うようになった。つむじは、天狗の里に来る前よりも、どんどん上達しているように思えた。
そしてある日、ぼくたちは、つむじがついに空を飛べるようになったことを、大天狗様に証明して見せようと思い立った。大天狗様に認めてもらえたら、つむじは一人前の天狗ということになる。そしてそうなればつむじは……結婚、することができるらしい。
そんなことを思いながら、ぼくたちは大天狗の前に立った。
「つむじは、一人前というにはまだまだ子供だな」
大天狗の厳しい言葉に、つむじは泣き出しそうになった。しかし、大天狗は少し考えた後、こう言った。
「しかし、つむじのその決意と、草太君との絆を見るにつけ、そう簡単に断るわけにはいかない。そこで、試練を与えよう。つむじがその試練をクリアできれば、一人前の天狗と認める」
試練の内容は、人間の世界に出て、あるアイテムを持ち帰るというものだった。アイテムの名前は「天狗の羽根」。それは、天狗が使うと風を操ることができると言われている特別な羽根だった。
「つむじ、君がその羽根を持ち帰ってくれたなら、君の力量を認め、一人前の天狗と認めよう」
大天狗の言葉に、つむじは立ち上がった。目を輝かせ、強い意志を感じさせた。そして、ぼくに向かってこう言った。
「草太くん、わたしたちで、そのアイテムを手に入れましょう!」
つむじと一緒に特別なアイテムを手に入れて、試練に合格する。まさに冒険と言えるそのことに、ぼくはわくわくした。
「でも、天狗の羽根っていったいどこにあるんだろう?」
ぼくが首をひねっていると、大天狗が口を開いた。
「草太くん、実は君なら、天狗の羽根を見つけられるかもしれないんだ。わたしが若い頃、天狗の羽根をある人間に託した。その人間とは草太くん、君の曾祖父に当たるはずなんだから」
ぼくは驚きを隠せなかった。「曾祖父って……ひいおじいちゃんってこと? そんなこと、聞いたこともなかった」
大天狗はうなずいた。
「それはあの頃、人間と天狗が混じり合うことは許されていなかったからだよ。でも、今はもう時代が変わった。君にはその力がある。さあ、天狗の羽根を見つけ出してみようじゃないか」
大天狗の言葉に、ぼくは気合を入れた。
「わかりました! ぼくは必ず、天狗の羽根を見つけてみせます!」
そう言ってぼくはつむじの手を取り、里を抜け出した。目指すのはもちろん、おばあちゃんの家だ。手がかりがそんな近くにあったなんて!
二人は手をつないで、おばあちゃんの家へと向かった。道中、つむじが「あのね、草太くん」と話しかけてきた。
「実は、ひとつ話しておきたいことがあるんだけど……」
「なんだい、何か悩みでもあるの?」
「ええ。わたしさ、大天狗様に許してもらえたら、結婚、できるんだよね?」
つむじは恥ずかしそうに言った。
「そうだよ、愛した相手と一緒に里に入ることができるんだから、結婚も可能さ。でも、なぜそれを聞くの?」
「だって、わたし……草太くんと一緒に里に入って、大天狗様に認めてもらいたいから」
つむじはにっこり笑って、ぼくの手を強く握った。
ぼくはクールに振る舞ったけれど、心臓がバクバクして、たいへんだった。それって、つ、つ、つ、まり、つむじが愛した相手って、結婚したい相手ってのは、ぼくってこと?
考えるだけで顔中が、耳まで真っ赤になる。嫌なんじゃない。むしろ……うれしくて、踊り出したいような気持ち。そう、いつの間にかぼくも、すっかりつむじのことが大好きになってしまっていたのだ。
「草太くん、ありがとう」
つむじが微笑みかけてくれた。その瞬間、ぼくは確信した。自分の気持ちを、つむじに打ち明ける時が来たんだ。
「つむじ、実は、君のことが好きなんだ」
つむじは驚いたように目を見開いた。しばらくして、彼女はにっこりと微笑んで言った。
「わたしも、草太くんのことが好きだよ」
心の底から嬉しくて、ぼくはつむじに抱きついた。彼女の暖かさが、全身を包み込むような感覚だった。
「つむじ、一緒に結婚しよう。そして、天狗の里で、ずっと一緒に暮らそう」
彼女の返事は、キスだった。心地よい甘さに、ぼくは完全に酔いしれてしまった。
「わたしも、あなたのことが好きです。もし、草太くんがわたしと結婚したいと思ってくれたら……わたしはとても幸せです」
つむじがそう言って微笑むと、ぼくの胸の奥が、ドキドキと高鳴った。その瞬間、ぼくは確信した。つむじのことを、これからずっと大切にしていくということを。
それから、つむじとぼくは、手をつないで、青空を見上げながら、未来を夢見たのだった。
(終わり)
感想など
さて、どんな感じだったでしょうか?
まぁ、とてもおもしろい物語になった、とは言えないけれど、なんというか、最低限小説の体は成している。
まだ一応、「僕が書いた方がおもしろいな」とは言えるんだけど、「はじめて小説というものを書いてみた人の作品」くらいにはなっているかも。
インターネットで学習しているせいか、わりとベタな展開というか、ありがちな話にまとめがちな傾向はあるみたいだけど、それはそれで、「ありそうな作品」にはしてくれているような。
これを生成するまでにはかなり何度も試行錯誤をしたけれど、それでもせいぜい片手間で2~3時間というところなので、僕が7000字近い文章を書くよりははるかに早いと思う。
ところでChatGPTは、まったく同じ命令でも毎回全然ちがう結果を出してくれるので、文字通り「試行錯誤」が大変かつ楽しいですね。
僕がもう少しこだわって何度も挑戦すれば、もっとおもしろい作品がつくれるかもしれない。
とは言え、今回は実験としてやってみました。
また挑戦しようっと!
文章を読んでなにかを感じていただけたら、100円くらい「投げ銭」感覚でサポートしていただけると、すごくうれしいです。
