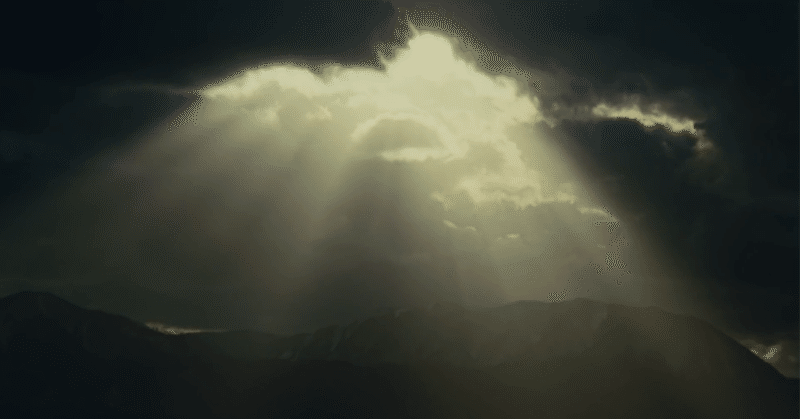
黒澤明監督作品案内
黒澤明は大谷翔平でした。スケールが大きすぎて、日本人はおろか、世界的にも十分には理解されなかったのです。黒澤は東京生まれですが、お父さんは秋田の人です。東北にはそういう人間を輩出する土壌があるのでしょう。晩年は「黒澤天皇」と呼ばれて、左翼映画人から忌み嫌われていました。もっとも左翼の本拠地ソヴィエト連邦で映画を作ったのは黒澤なんですが。
黒澤映画の特徴をあえて列挙すると
1、絵が綺麗(構図が良い)
2、時々素晴らしい音楽との結びつきがある
3、俳優をダイナミックに動かせる。動ける俳優を使う。画面の動作効率も非常に良い。
4、文豪の作品に果敢に挑戦する。ドストエフスキー(白痴)、トルストイ(生きる・原案は「イワン・イリイチの死)、シェイクスピア(乱のリア王、蜘蛛の巣城のマクベス)、ゴーリキー(どん底)
です。特に構図の綺麗さは細田守以外匹敵する才能を知りません。音楽との結びつきは、コッポラ、タルコフスキー、宮崎駿とかより、少々打率が落ちます。逆ばり路線で、あえて合わない音楽あわせたがりますが、時々はまります。ダイナミックな動きは宮崎駿に似ています。
逆に弱点列挙しますと、
1、セリフが聞き取りづらい。
2、内容に重層性がない。ここらへんが馬鹿にされるゆえんです。
3、ゆったりとしたアダルトな恋愛ものとかができない。よって女性陣から無視される。
となります。今日西洋で評価されているのは画面の動作効率なのですが、
私は綺麗な構図でダイナミックに動かせる、というのが最も優れた点だと思います。細田の構図で宮崎の動きができる。

「夢」の解説で書いたように、
もともと打率の低い監督です。そこらへんは大谷と共通です。2022年の大谷の打率は2割7分3厘。ホームラン34本。それでピッチャーで15勝。だいたい黒澤もそんな感じです。失敗作は多いです。現代の鑑賞者の立場から見れば、有名作品でもお勧めできないものが案外多いです。たとえば「生きる(1952)」、「影武者(1980)」など。見ないことをお勧めします。
映画の歴史は映像表現の歴史ですから、アニメを中心に鑑賞される方でも、少しは古い映画を見たほうがよいです。
でも古いから全て素晴らしい、というわけではないです。全般的には現在の作品のほうが優れているのです。特に最近の日本アニメは素晴らしいですね。だから無駄に見る必要はありません。本当に優れた数本をじっくり何度も鑑賞するのがよいです。人生は有限です。
ではお勧め順に、
一位「乱(1985)」
音楽の武満徹が素晴らしいです。オーケストレーションという意味では史上有数の天才です。特有の響きを作れます。黒澤にして最初で最後の互角の音楽、武満にして最初で最後の互角の映像、前半の三ノ城落城シーンで両者はぶつかり合います。奇跡的な瞬間です。この作品で両者は決別しますので、単発の奇跡に終わりました。両者は「どですかでん」でも共演してますが、これはあんまり視る価値ないです。バルファキスの印象には残ったようですが。
「乱」は後半ダレますので、最悪前半だけ見ればよいです。ラストシーンもよいですが。
画質悪いですが、落城シーンどうぞ。
武満の「乱」以外の映画作品では、「他人の顔」のワルツが一番有名です。
「波の盆」も人気がありますね。ドラマ用だったと思います。こんな気持ちで死ねたらいいですね。
映画音楽の主役は、武満死去の後は坂本龍一、その後久石譲と続きます。一方で西洋の映画からはどんどんメロディーが消失してゆきます。環境音楽的になる。音楽におけるメロディーとは物語におけるキャラですから、のっぺらぼうな映画になる。「アナと雪の女王」はメロディーありましたね。そして大きく当たりました。キャラが必要なように、メロディーは必要なのです。そして言いにくいですが、もしかして最近の日本アニメから、メロディーが失われつつあるのかもしれません。まどかマギカが頂点だった気もします。美術、演出、声優、ストーリー、全ての点で人類史上最高のレベルにあるこんにちの日本アニメですが、その点だけが少々心配です。印象的なメロディーないほうが映像作品作りやすい、というのはあります。整合性取りやすい。でもそこが欠けると、記憶に残る作品にはならない。
黒澤明は宮崎駿を早くから評価していまして、「実写が撮れる人だ。考証しっかりしている」。対談もしています。対談後つくられた作品には、


など強い影響が見られます。元は「乱」のこちらです。

二位、1960-1963年の4本のうちどれか
黒澤全盛期の4本です。本当にこれが最盛期なのかどうか定かではありませんが、偶然4本面白い作品が続いたので、世の人々は「ここが黒澤の最盛期だ」と言っています。それくらい当たり外れが激しい人です。この4本はどれを見ても面白いです。1本見て面白くなかったら「相性が悪い」と思ってください。ほかのは見る必要ありません。面白かったら4本ともどうぞ。
1960年 悪い奴ほどよく眠る
構図が素晴らしいです。少し長すぎるか?
料亭での三角形の構図など、ほれぼれします。
1961年 用心棒
この4本の中では一番内容薄いかも、しかしカメラワークは海外で一番有名です
「サシミにしてやる」のセリフとかいいですね。三船の納刀の上手いこと!
1962年 椿三十郎
三船の運動能力炸裂します。ストーリーの出来がよいです。
ご家老の奥方と娘のかけあいは絶妙です。
1963年 天国と地獄
列車シーン、警察での会議シーン、逮捕シーン、最後の面会シーンなどの視覚効果が素晴らしいです
逮捕シーンにハワイアン流していまして、ミスマッチの効果を上げています。深作「バトルロワイヤル」のG線上のアリアに似ていますね。
「悪い奴」の冒頭の結婚式シーンが、

「ゴッドファーザー」の冒頭の結婚式になりました。

三船敏郎は、映画史上ではオードリー・ヘップバーンと対になる存在だと思います。両者とも運動能力が非常に高い。アスリートなのです。
つまり黒澤は、どこまでも肉体を、生命を表現した作家なのです。肉体を殺し切る小津の対極ですね。肉体が前面に出るので、知的な印象はなくなります。だからインテリには嫌われました。でも人間は所詮は生物です。動物の一種です。動物の限界の中で精一杯生きなきゃいけない。と思ってる人には、いい監督なのです。
三位、「七人の侍(1954)」
こちらは「乱」の逆で、前半ダレます。最悪後半だけ見ればOKです。無茶苦茶危険な撮影しています。おそらく怪我人大量に出ています。
昔の日本映画界はブラックなんてレベルではなかったのです。戦後すぐは覚醒剤ジャンジャン使ってテンション上げて撮影していた時代もありました。「栄養注射をいたしますので、保健室に集合してください」とアナウンス流れていたそうです。無茶苦茶です。ある映画の中で歯を抜くシーンがあり、それをフェイクではなく本当に自分の歯を抜け、しかも(痛い感じが出ないから)麻酔ナシで抜け、と主張した女優も居ました。そして本当に麻酔ナシで抜歯して撮影しました。そんな痛々しいシーンは見たくない、と考えるのは現代人でして、昔はそれを良しとしていたのです。
黒澤もひどいもんでして、作中逃げる男性の背中に矢が刺さるシーンがありまして、撮影していると矢が刺さった男性が声を上げて倒れた。
「カット!」
とそこで止めたのは、人間は矢が刺さった時に声なんか出ないと判断したからです。リアリティーに欠けると。で、倒れた男性のところに行ってみると、クッションを外して、本当に背中の肉に矢が刺さっていた。
「なるほど私達の見解が間違っていた。人間は矢が刺さると声が出るのか!」
人体を損傷して学習したわけですが、そんな価値のある知識とも思えません。しかしそんな撮影していると、画面全体から正体不明の殺気がにじみ出ます。
特に最後の雨の戦闘シーンは必見です。西洋絵画を勉強してきた構図の美しい黒澤明が、美意識を全てを投げ捨てて縄文人の本性を露わにする瞬間です。むちゃくちゃにカメラが乱れるのです。仁義なき戦いよりひどい。戦闘の締めくくりは勝利の勝鬨ではなく、雨の中の馬の群れの疾走です。正義や美の向こう側にあるもの、生命そのものを表現できています。墨汁で壁に怒声を書き連ねたような、あえて言うなら黒澤明作品中もっとも汚い映画です。戦闘シーンでの俳優たちの熱演は、驚異的なレベルです。もっとも実際に生命の危険がありますので、ハイテンションにならざるをえないのですが、、いやはやブラックですね。
四位、「羅生門(1950)」
カメラがほとんど全てです。強い日差しの木漏れ日の表現を、完全にこなしているので評価されました。なんと日中におそらくミラーで役者の顔を照らしたりもしています。過剰に光の演出をしているのです。日本美術の最大の弱点はコントラスト表現の弱さです。しかしこの作品は、西洋美術以上の強烈なコントラスト表現を実現しています。
木漏れ日のコントラスト表現は、現代アニメにきっちり受け継がれています。




ちゃんと受け継ぐことのできるアニメ業界の人々は素晴らしいですね。しかし正直「羅生門」は、黒澤映画というより宮川一夫という天才カメラマンの映画です。宮川の名前を知らない人は、昔懐かしいCMですがご覧ください。撮影宮川一夫、世界のCM賞総なめにした名作です。
宮川に限らず、当時の日本映画のカメラマンの能力の高さは凄いですね。今日のアニメの美術的能力は本当に凄いですが、昔は映画でそうだったのです。
世界的には時系列倒置ストーリーに評価が高いのですが、これは黒澤の功績というより、原作の芥川龍之介の功績ですね。芥川は英文科卒業ですから、ドイルなどの推理小説の時系列倒置は視界に入っています。それを純文学にしたのは芥川の功績ですね。師匠の漱石も「彼岸過迄」という小説で時系列倒置使っています。そこらへんは時系列倒置の研究で今後扱ってゆきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
