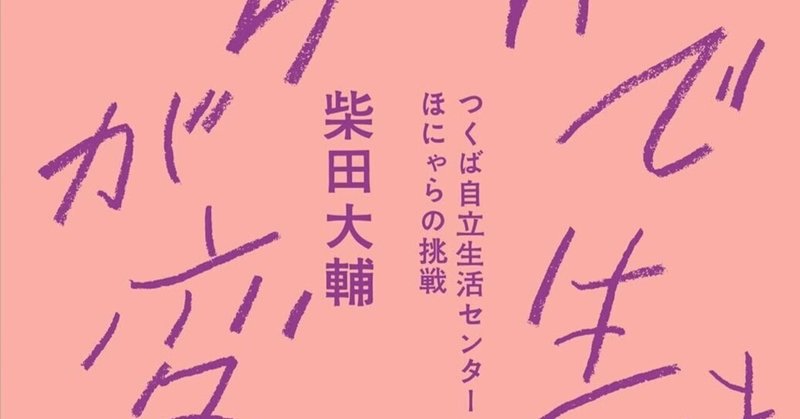
まちで生きる、まちが変わる つくば自立生活センターほにゃらの挑戦<柴田大輔>
たんなる「障害者福祉の本」ではない。自立生活に挑む障害者と、地域住民と、地域社会のダイナミックで感動的な成長物語だ。
かつて重度障害者は「就学免除」という名目で学校に通う権利を奪われていた。養護学校に行けるようになっても、卒業後は自宅や施設で隔離されてきた。「普通学級」に通っても、ほかの生徒に遠慮して小さくなっていることが多かった。
1980年代から、一人暮らしに挑む障害者がちらほらとあらわれる。最初は家族に反対され、行政の制度もないからボランティアを募るしかなかった。
そんな当事者が「自立生活センター」を組織して行政に制度改善を働きかけるようになった。一人ひとりに対するピアサポートなど、それまでボランティアでやってきたことを業務として取り組みはじめる。
「つくば自立生活センターほにゃら」はそんな自立生活センターのひとつとして2001年に結成された。
学習の権利を奪われていた重度障害者は、時計の読み方も簡単な計算もできない。計算ができないから無駄づかいをしてしまう。自分が具体的にどんな介助をしてほしいのか、介助者に伝えることも最初は困難だ。
でもひとり暮らしをはじめて、どんな料理を食べたいか、どうやって服を着替えたいか、自分がなにをしたいのかを介助者に伝える経験を積みかさねることで、生活能力を高め、自信をつけ、人間として成長していく。
そして彼らがまちにでることで、周囲の住民の「気づき」をうながし、商店や食堂がスロープをもうけ、行政も制度をつくる。地域そのものがだれもが住みやすいまちに成長していく。
そうした成長の背景には、人権をめぐる国際的枠組みの「成長」もあった。
隔離よりは普通学級での「統合教育」はましだとされたが、この段階では、障害者の側が努力して健常者に溶け込まなければならなかった。
2014年に批准された国連の「障害者権利条約」では、「障害」は個人の側にあるのではなく、社会の側の欠如がつくりだしているとし、障害者が排除されない「インクルーシブ社会」を実現しなければならないと定めた。
「ほにゃら」は、そんな世界の障害者の人権運動の先頭を走ってきた。
「障害のある自分たちにとって仕事とは、世の中でいわれる『働いてお金を稼ぐこと』ではなく……生きることそのものが仕事だ。自分たちの生きる姿をさらすことで、世間にインパクトを与え、社会を変えていく」
そんな言葉に「ほにゃら」の意志と意義が集約されている。
筆者は、中南米の人権問題にかかわるフォトジャーナリストだが、日本では定職についたことがなく、根無し草のような生活を送っていた。それが「ほにゃら」のメンバーの介助に入り、ともにすごすなかで、ともに生きる仲間と、自分のすむべき場を見出していく。
障害者と地域住民と地域社会の「成長物語」であるだけでなく、筆者自身の学びと成長のストーリーになっていて、親近感をおぼえた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
