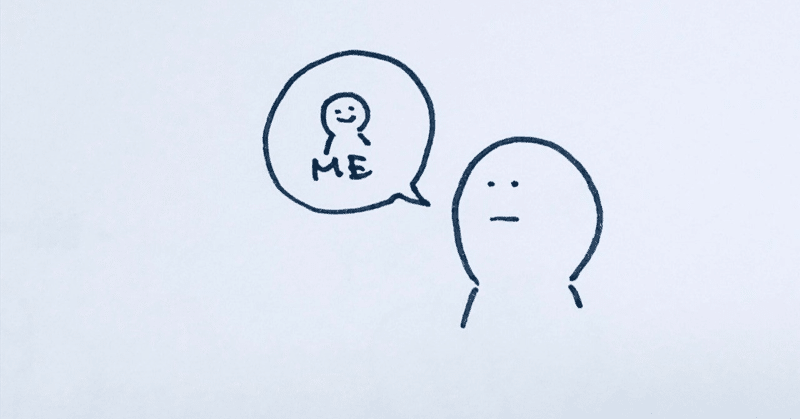
すばらしき新世界 (19)
カップ麺の空容器を片付け、ペットボトルのお茶を飲んで、二人は一息ついた。
「さっき買ったペットボトル、冷やしておきましょうか?」
「ありがとう。」
悟はミルクティーのペットボトルを登和に渡した。自分のメロンソーダと一緒に冷蔵庫に入れ、登和は悟の前に戻ってきた。
「さて。」
「うん。」
悟は言った。
「今から話すことは、他の人に話したりしないでくれる?他の誰にも話したことのない話だから。」
「はい。」
「ずいぶん簡単に『はい』って言うね。」
「だって、私、広瀬くん以外に話せる人はいませんよ。」
登和の目が潤んだのを見て、悟は胸が痛んだ。佐伯詩乃のことか?しかし佐伯さんは止めたほうがいい。吉井さんの手に負える相手じゃない。
何から話そうか。ええと、まずは自分の説明から。
自分は中学まで、私立の中高一貫校にいた。そのまま高校も通い続けていれば、東京の有名私大に行ける学校だった。うちの祖父はそこそこ大きな企業グループの会長で、今は伯父が代表取締役を務めている。伯父も父もその私大の卒業生だから、自分も当たり前のようにそこに行って、伯父の会社で働けばいいという空気が親戚内にあった。ガツガツやらなくても、勉強でも習い事でも、やりたいことは何でも最良の指導者・最良のサポートをしてもらえる環境が整っていた。
友人たちも似たような環境で育ってきた人が多かった。みんな性格がいいし、話も合った。自慢みたいにとられると嫌なんだけど、自分、けっこう女子から好かれるタイプらしくて、小学校高学年ぐらいからずっと彼女がいた。それも、みんながいいなと言うような女子が、向こうから告白してくるというパターンで。
「へー。今まで何人ぐらいいたんですか?」
「えっ、それ聞く?」
「あ、聞いたらダメでしたか。」
「いや、別に。……四人?五人かな?」
「そうですか。すごい。」
「いや、真顔やめてよ。すごくも何ともない。そりゃ、最初はうれしかったけど。後からだんだん、わからなくなった。俺、どうしてこんなことしてるのかなーって。」
「こんなこととは?」
「たとえば、デートとかね。」
彼女ができるたび、どこへ行って何がしたいか聞いた。答えはだいたい同じだった。当たり前だ、同じ雑誌やWEB検索で「中学生 デートコース 〇〇市」とか調べて言うんだから。五人とも同じコースを回った。で、同じスイーツを食べ、同じ店で昼ごはんを食べて、同じ映画館で映画を見て、同じ雑貨店でペアのアクセサリーを買った。みんなすごく喜んでくれた。
別にいいんだ。自分だって同じようなことしてるから。ただ、だんだんいろんなことが疑問に思えてきたんだ。これは、本当に自分でなければならないことなのか、って。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
