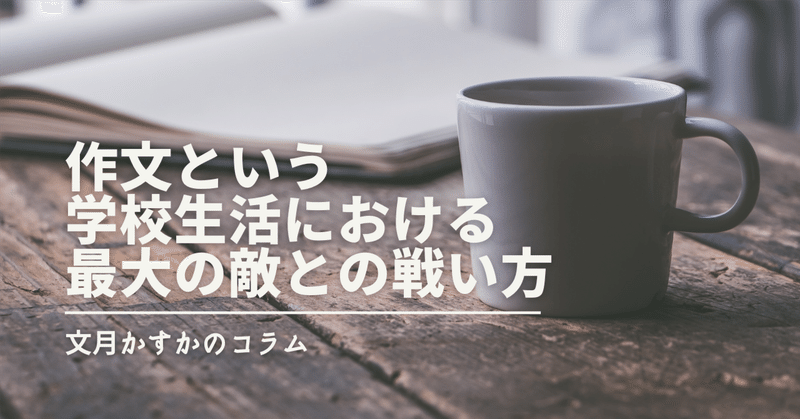
作文という学校生活における最大の敵との戦い方
※注意※
このコラムは半分以上はネタです。本当に実行してどんな結果になっても私は責任を負えません。
AIの使い方はその倫理面、法律面、情報保護などの多面的な意味で非常に難しいものです。未成年の方が使う場合は、保護者や教師などに相談の上で使用することをお勧めします。
そして、どこまでがネタでどこまでが本気か分からない場合も実行するのは止めたほうがよいと言っておきます。
作文と読書感想文。
嫌じゃありませんか?
中学生くらいまでは必ず書かされることになりますが、ほとんどの人にとって良い思い出ではないと思います。
私もその内の1人です。
中学3年生の時に書いた作文を国語教師が見て、「お前の作文は小学生みたいだな」と鼻で笑ってきたことは今でも忘れません。
仰げば憎し我が師の嘲笑。
30年近く前のそんなことまで鮮明に覚えているほどナイーブな中学生男子の心に傷をつける作文とやらですが、やはりここは先達としてその対策を書くべきではないかと思ったのです。
これ以上、小中学校の作文による被害者を増やしてはいけません。
そのため、その対策について次のように話を進めていきたいと思います。
・なぜ作文が嫌われるかの分析
・分析から導き出す対策案
・具体的な実現方法
それでは順番に見ていきましょう。
①なぜ作文が嫌われるのか
おそらくですが、この理由は大きく2つに集約されるのではないかと私は思っています。
それは、「書き方が分からない」と「正解が分からない」の2つです。
①-1 書き方が分からない
私に限った話なのかもしれませんが、私は学校で作文の書き方を教わった覚えがありません。
「授業を聞いてなかったんだろ」と言われそうですが、それは考えにくいです。
私は本を読むのが幼少期から好きで国語の授業も好きでした。
ですので、先生の話を聞き逃したとは思えません。
つまり、やり方が分からないのにいきなり原稿用紙を渡されて「作文を書け」となったとしか思えません。
算数や数学で例えるなら、四則演算が出来るようになったばかりの子どもに「はい、じゃあ連立方程式を解いてみましょう」といきなり言うようなものです。
不可能とまでは言いませんが、相当ハードルは高いことでしょう。
①-2 正解が分からない
学校のテストはほぼ必ず正解が決まっていますが、この作文というものについては正解が決まっていません。
そのヒントすら与えて貰えませんので、はっきり言って無理ゲーです。
書き方を教えてもらえないことも考えると、むしろ何でこれでまともな作文を生徒が書けると思えるのかが不思議です。
しかし、私も大人と呼ばれる年齢になって数十年が経ち、今では何が正解だったのか何となく分かります。
作文の正解とは、「大人である教師が気に入るような文章を書く」ことです。
当然ですが、教師が違えば正解も違うということになります。
そもそも子どもは教師の気に入る文章なんて分かりません。だって誰一人として大人になったことがあるわけではないんですから、その大人の気持ちなんて理解できません。
もし正解の文章が書けるとしたら、それは転生して人生をやり直しているチートキャラだけでしょう。書けるかこんなもん。
②分析から導き出す対策案
対策案は実に簡単に導き出せます。分析したことの逆を行うようにすれば良いからです。
すなわち、次のようになります。
・書き方を習得する
・正解を先に把握する
あとはこの2つを具体的にどのように実現すれば良いか考えれば、作文を書くというミッションはクリアできそうですね。
③具体的な実現方法
実現方法は2つ考えつきましたので、順番に見ていきましょう。
③-1 イマジナリーフレンドくんに書いてもらう
昔はイマジナリーフレンドと言うと、その人の心の中にしか存在しないものでした。
しかし現代では、このイマジナリーフレンドは電子の海の中に存在し、誰でも話をすることができるとても博識な存在です。
お名前はChat GPTくんって言うんですけどね。
それでは、Chat GPTくんもとい、イマジナリーフレンドくんに実際に書いてもらいましょう。
シチュエーションは、自分が小学生で牧場に遠足に行ったことを作文に書くということにしましょうか。
あなたは小学生男子であり、教師から「牧場へ遠足に行ったことを作文に書きなさい」と言われています。
次の条件を満たすように400文字以内で作文を書いてください。
もしこのタスクを最適化してクリアするための情報が足りない場合は私に質問してください。
下記の①から③が条件です。
①大人である教師が高い評価を付ける文章であること
②牧場には牛がいたことが分かる描写を入れること
③「牛は大きかった」という私の感想を文章中に盛り込むこと
そして、下記がイマジナリーフレンドくんが書いてくれた作文です。
遠足で牧場へ行った日
ある晴れた日、僕たちのクラスは遠足で牧場へ行きました。緑豊かな景色が広がり、新鮮な空気が心地よく感じました。教師の先生たちは、皆に自然の大切さを教えてくれました。
牧場に入ると、まず目に飛び込んできたのは、たくさんの牛たちでした。牛たちはのんびりと草を食べていました。牛の鳴き声が聞こえ、それが心地よいリズムになっていました。僕は牛がこんなに大きいとは思っていませんでした。その大きさに圧倒され、自然の力強さを感じることができました。
先生方は、僕たちに牛乳がどのように作られるかを説明してくれました。そして、牛乳が栄養豊富で健康に良いことも教えてくれました。僕たちは新鮮な牛乳を飲み、そのおいしさに感動しました。
この遠足で、僕は牧場の大切さと自然と共生することの素晴らしさを学びました。これからも、自然に感謝しながら生活していきたいと思います。
……え? 凄すぎない?
自分で言っておいてなんですが、あまりにも出来すぎですねこれ。
こんなものを提出してしまったら、「こいつAI使って丸パクリしたな」と確実にバレますのでやめましょう。これは普通の小学生が書ける文章ではありません。
ところで、ここまで読んで頂いた皆さんの中であることに気がついた方はいらっしゃいますでしょうか?
私はChat GPTへの入力文章をそれなりに工夫して書いています。
その工夫点というのは、AIに対して役割を明確に設定すること、インプットする情報とアウトプットの条件を明確化すること、分からないことは聞き返すこと、の3点です。
これは意識していないと書くことが出来ないと思いますし、もっと工夫すればさらに高度なアウトプットが出せるはずです。
つまり、普通の小学生は「どうすればAIからの回答をこちらが求めたとおりのものに出来るか」なんて知らないと思いますので、この方法はやっぱり無理ということです。
「じゃあどうすればいいんだよ」と言われそうですが、もう1つの方法があります。
次はそれを紹介しましょう。
③-2 教えてもらえないことを逆手に取る
作文の書き方や正解を教えてもらえないなら、それを逆手に取ってしまおうという考え方です。
つまり、「書き方を教えてくれないなら何を書いてもいいんですよね?」の精神です。
ただ、学校は世間のルールを教えてもらう場所でもありますから、そういったルールを破ったものは書くわけにはいきません。
あまりにも仰々しい誇張表現や、実際には思ってもいないような感想を書いてはいけないでしょう。つまり、嘘は駄目ということですね。
その条件を満たした作文を試しに私が書いてみました。条件はさきほどのAIに書かせたものと同じで、牧場へ遠足に行ったことを書くということにしましょう。
牧場へ遠足に行きました。
牛がいました。
大きかったです。
以上です。
完璧じゃないでしょうか。全く嘘は言っていません。
事実だけではなく自分の感想まで書いてますので120点です。いや、むしろ感想は嘘が入る余地があるので、無い方がいいかもしれませんね。
もしこれで教師が何か言ってきたらこう言い返しましょう。
「この作文の何がいけないのかを具体的に教えてください」
すると、教師は作文の書き方と教師自身が考えている正解を教えざるを得なくなります。
これで書き方が分かりますので、あとはその通りに書けばミッションコンプリートです。やったぜ。
③-3 ごめんなさい真面目にやります
さすがにこれで終わりにしてしまうと怒られそうなので真面目にやります。
まず、問題点としては書き方が分からない、正解が分からない、という2つです。
そして、この2つを同時に解決する方法としてはやはりChat GPTというかAIを使うのが最も簡単で正確です。
ただ、AIに書いてもらった文章をそのまま丸パクリするのではなく、AIに書いてもらった文章を自分で分析し、その分析結果を元にして全く新しい文章を作るのです。
どういうことかを説明するために、AIに書いてもらった文章を再掲します。
ある晴れた日、僕たちのクラスは遠足で牧場へ行きました。緑豊かな景色が広がり、新鮮な空気が心地よく感じました。教師の先生たちは、皆に自然の大切さを教えてくれました。
牧場に入ると、まず目に飛び込んできたのは、たくさんの牛たちでした。牛たちはのんびりと草を食べていました。牛の鳴き声が聞こえ、それが心地よいリズムになっていました。僕は牛がこんなに大きいとは思っていませんでした。その大きさに圧倒され、自然の力強さを感じることができました。
先生方は、僕たちに牛乳がどのように作られるかを説明してくれました。そして、牛乳が栄養豊富で健康に良いことも教えてくれました。僕たちは新鮮な牛乳を飲み、そのおいしさに感動しました。
この遠足で、僕は牧場の大切さと自然と共生することの素晴らしさを学びました。これからも、自然に感謝しながら生活していきたいと思います。
これを空行が入る部分で区切ってみてください。
全ての文に共通するパターンが見えないでしょうか?
共通するパターンとは、「事実とそれに対する感想が一文の中に書かれている」ことです。
つまり、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは遠足であった事実を書けるだけメモに書き出し、それに対応する感想をメモするのです。
そして、その中からいくつかをピックアップして、事実とそれに対する感想という形式で作文として書けばよいということですね。
私は大雑把にしかまだAIの文章を見ていないのでこの程度のパターン分析しか出来ていませんが、ちゃんと熟読すると他のパターンも見えるかもしれないので、そういったものを自分の作文へと反映させるのです。
余談ですが、この「パターンを読み取る」という力は色々な場面で役に立ちます。
こういう習慣を身に着けておくと、後々どこかで使える時が来ると思います。
そして、教師が求める正解が何かというのは、はっきり言ってAIではどうにもなりません。
シンプルな文章が好きな人もいれば、美辞麗句で飾られた文章が好きな人もいるなど千差万別だからです。
ですので、教師に対して直接「先生はどういう文章が好きなんですか」と聞いてしまえばいいと思います。
その際には手ぶらで聞くのではなく、上記の手段などを使って自分で書いた作文を持っていって聞くのです。
具体例があれば教師も教えやすくなるはずです。
つまり、最も大事なことは、「分からないことが何かを正確に把握して質問すること」と、「どうすればその質問に相手が回答しやすくなるかを想像すること」です。
これは作文以外のあらゆる場面で必要となる能力であり、大人になっても当たり前のように使う能力です。
学校というのはこの「質問をするための能力」を身につけるのにうってつけの場所だと私は思っています。
いきなりこれを実行するのは難しいと思いますが、試しに練習してみると面白い発見があるかもしれません。
「学校行くのだるいなー」といつも思っている方は、試してみると新しい発見があるかもしれませんよ。
それでは今回のコラムは以上です。
ご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
