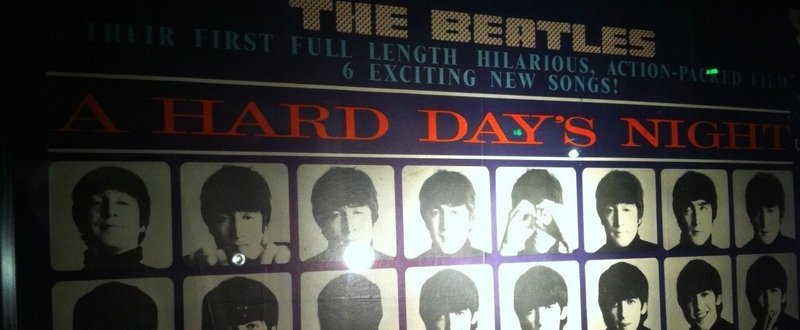
まったく、若さってやつは。
都会というところは、まったくおそろしいところだ。
年齢を重ねるにつれ、その思いは強くなっていく。若いころには感じることのなかった恐怖が、毎日のように襲いかかってくる。いったい、都会のなにがそんなに恐ろしいのか? ガラスである。ショーウィンドウである。そこにまざまざと映し出される、おっさん化した自分の姿である。
犬と散歩しているとき。通勤の駅に向かうとき。昼飯のため近所を放浪するとき。そして息抜きにコンビニへと逃げるとき。都会というジャングルのなかには、至るところにショーウィンドウ的なガラスが配置してあり、気を抜いた表情で歩く猫背のおっさん(つまりはわたし)を映し出す。「うわー、むさくるしいおっさんが歩いとるなあ」と思った相手がガラスに映る自分だった、という経験は、ひと月のうちに何度もある。
そんなおっさん化の激しい風体でありながら、ぼくはいまいち大人になりきれていないような、社会人として大事なことをスルーしたまま生きてしまったような、そんな申し訳なさを抱えて生きている。
サボってしまった大事なこと。それは受験と就活である。
ぼくは高校受験を最後に、受験勉強というものを経験していない。大学は芸術学部、しかも実技の必要ない学科だったので、なんら受験勉強することなく入学してしまった。そして就活も似たようなものだ。「メガネより重いものを持たなくていい」というだけの理由で、メガネ屋に就職した。受験や就活に直面する若者たちの苦しみに、なかなか寄り添うことができない。
といった心の空白地帯を思い出したのは、田中泰延さんのインタビューを読んだからだ。
メガネ屋さんの面接で、ぼくはひたすらアントニオ猪木最強説を語り、中学時代の尾崎豊的な青春を語った。転職先となった出版社&編プロの面接では自作の掌編小説を持ち込み、作品解説に終始した。
いまになって、強く思う。
なめていたのだ、ぼくは。
世のなかをなめていたし、おとなをなめていたし、自分をなめていた。
二十代の前半までぼくは、「自分はおもしろい」と思っていた。その自己認識は、容易に他者をなめさせる。いま、原稿を書きながら毎日のように「おれのつまらなさ」に直面しているぼくは、あのころの自分をぶん殴ってやりたい。その底の浅さとつまらなさを、こんこんと説教してやりたい。
でもね。「自分はおもしろい」という勘違いが、その世間知らずな思い上がりこそが、若造最大の特権であって、若造らしい無茶へと導くエンジンなんですよね。
たぶんぼくはこれからずっと「おれのつまらなさ」と向き合っていくんだろうけど、それは同時に無茶を避けながら生きるということでもあって、どこかでおおきくジャンプするためには、もう一度「自分はおもしろい」の暗示にかかる必要があるんですよ。
と、48歳の誕生日を無職で迎える青年失業家の大先輩に教えていただきました。いいインタビューなので、たくさんの人に読んでほしいです。
