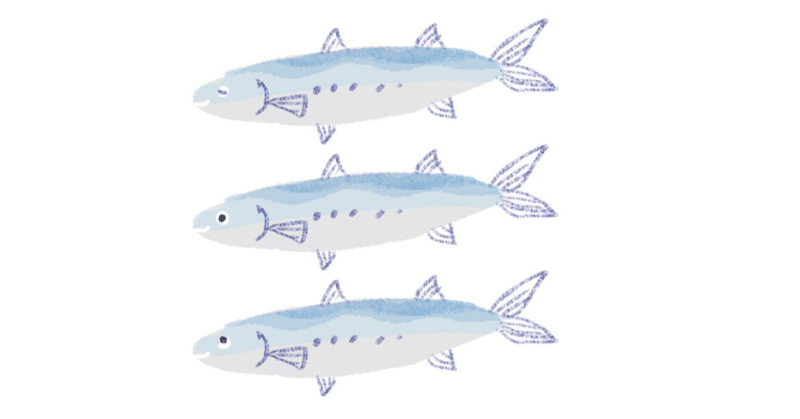
山田、古橋ちゃんは先に行くよ。#5
長い時間、山田を待ったことがある。待たせたことも。いつだって山田は、どんなに遠いところにいても見つけてくれる。まっすぐ、迷いなく古橋に向かってきてくれる。改札の向こうから、コーヒーショップから、ドン・キホーテのアダルトブースの奥から(?)。それはもういろいろなところから。
最初のうちは気づくのが遅くて、驚かされることが多かった。でも途中からは、ちゃんと山田のことを探すようにした。怒ったような顔をした、筋肉質の、いばっているようにも見える歩き方をするその男の一瞬を、見逃したくなかったから。
山田くん。山田。やまだ。ヤマダ。YAMADA。飴玉を転がすように口の中で反復した音。いうまでもなく、人生で一番好きだった男の子。山田に抱かれているときが、古橋のいちばんの幸せ。山田の太い腕の上に頭を乗せて、彼の息づかいや器用に動く指たちを身体いっぱいに感じるとき。浅瀬が満ちていくような、濡れた若い草花を踏むような、町の滅ぶのをぼうぜんと見ているような、そんな心持ちになれる。みんなはうんざりするほど知っていると思うけれど、古橋ちゃん、山田のこと、好きだったの。ちょう、ちょう、ちょう好きだったの。ほんとうに好きで、好きで好きで仕方なくて、いっときは、殺してしまおうって、思ったこともあったんだ。身体の大きな山田に敵うはずなんてないのに。ナイフを荷物の中にいれて、山田と落ち合ったときさえあったんだ。
山田から初めて連絡がきたのは、社会人になって一年目の夏。くたくたになって帰ってきて、とろとろと眠りかけていたところに、見覚えのあるユーザーネームのアカウントから、DMがきているのに気がついた。眠かったから夢かと思ったんだけど、自身の名前をもじったそのユーザーネームは、間違いなく山田のものだった。大学四年間、同じカリキュラムを勉強してきた山田のことは、前から気になってはいた。ちょっと意地悪ではあるけれど、誰にも媚を売ることのない、物おじしない、その堂々とした振る舞いに、憧れていた。山田は、男の集団のリーダーと言った感じだった。いつも講義では教室の一番後ろを占拠している、口の悪い、ちょっと怖い人だった。女の子も男の子も、いつも山田に揶揄われていた。古橋はあんまり話したことがなくて、ただ、古橋さんって、苗字で呼ばれていた。雑に呼び捨てをされて揶揄われる距離にいた女の子たちが、本当はちょっとだけ羨ましかった。当時、山田も私も十八歳。大学教授に連れられて、学科のメンバー全員でキャンプファイヤーをした時に、山田が隣に立っていた。大学に入ったはいいけれど、うまく馴染めていなかった古橋は、話す人もそんなにいなかった。それを見て、不憫に思って立ってくれたのかもしれない。歌を歌うときに、手を繋ぐんだけど、そっと手を差し伸べたら、大きな手でちゃんと握り返してくれた。山田のてのひらは少し湿っていた。嬉しかった。思えばその時からきっと特別だったんだろう。
好き、ほどはいかなかった。憧れていただけで、四年間を過ぎても、特別に会話したことはなかった。だからけっこう嬉しかった。彼のユーザーネームはすぐに古橋の宝物になって、仕事終わりにぽつりぽつりと言葉を返すのがとても楽しみになった。なんだって、私に連絡をくれたのだろう? それは山田にしかわからないけれど、古橋が山田を気にしていたみたいに、山田も古橋を気にしていたことが、何よりも嬉しかったのだ。
山田とセックスするようになって、すぐに山田はわたしの人生の核になった。山田の見た目はとってもタイプだった(古橋ちゃんは、細いイケメンとかは好きじゃないんだ。マッチョで顔が女受けしないゴリラみたいな方が好きなんだ)し、山田のちんぽも知っている中ではいちばん硬くて大きかったから(もしかしたら、好きだから大きく見えたのかもしれないけど)、セックスっていうのが、忍耐を試されるものだと思っていた古橋ちゃんにとって、山田とのあれこれほどエロティックで開放的なものはなかった。気持ちよかった。気持ちよくて、きっと許されるだろうと思って、行為の最中に、好きだと伝えた。最初のうちは、「おれも好きだ」と山田は返した。でも、途中から「ありがとう」って返すようになった。好きだと言われることを、山田は嫌がった。もちろん、直接嫌とは言わないけど、嫌がって、別の女の子たちとよく飲みに行っていることを、古橋に伝えた。連絡している子がいることも。高校時代に同じクラスだった女の子が可愛くなっていることも。ばかだから、その時は期待させない、山田の優しさだって、思うことにした。三回目のせっくすからは、好きだと伝えることをやめないとって、強く思った。
古橋ちゃん、ばかじゃない。卒業した高校はぜんぜん進学校じゃなかったけれど、その中ではいちばんの成績だったもん。ばかじゃない。だから、この気持ちも隠そうって決めた。山田のこと、山田の前では好きだって、全面に出さないようにしようって。そうじゃないと、きっと山田はわたしから離れていってしまうし、この身体を使ってもらえなくなっちゃうから。身体を使ってもらえないということは、山田との関係が白紙に戻るということ。関係が切れるということは、山田とのやり取りも無くなってしまうということ。それだけは、避けたかった。気持ちを隠すのと、会えなくなるのとでは、後者の方がずっとつらかった。山田が他の女の子の話をするとき。好きになりかけた女の子、付き合ってきた女の子の話をするとき、古橋はずっと唇を噛んでいた。少し泣きそうになっていたのを、山田は知っていたのかもしれないし、あるいはぜんぜん知らなかったのかもしれない。心がぐさぐさとナイフで刺されるみたいな鋭い痛みだったけど、そしてそれは丸一ヶ月続くような鈍い傷になってしまったけど、かわいいね、そうなんだね、いい子なんだねって、その女の子たちについて、何回も褒めてあげた。山田はまんざらでもなさそうに相槌を打った。ずたずただよ。本当に。ぼろぼろになりながら、セックスの帰り際に山田と歩いた。ラブホ街と言われる道はゴミだらけだったけど、死んでいても生きていてもどちらでも構わないような男と見たいつかの海の景色より、ずっとずっと綺麗だった。綺麗だったから、どうしてもこの一瞬を失くすわけにはいかなかった。
そのうち、山田は女の子のことを話さなくなった。飽きたのか、古橋ちゃんが動じないように見えたからなのかは、わからない。代わりに、自分の身体のことを卑下するようになった。男の人はどうしてあんなに自分のちんぽを気にするんだろう。山田も他の男の人と同じように、ちんぽの話しかしなくなった。言葉にするととてもおかしいけれど、ほんとうにそうだったのだ。そして、古橋ちゃんのセックス中の振るまいを、「演技だ」とか「他の男の方が良かったんだろう」とか、わけのわからないことで責める回数が増えた。そんなことない、山田がいちばんだよ。他の男の人にこんなふうに接したことはない。こんなにもちんぽがよかったことなんてない。そういうふうに慰めて、慰めて、でもなかなか山田は納得してくれなくて、だからもっと褒めて、褒めて、褒めまくって、山田が気分よくなるまで、古橋ちゃんはがんばった。そうしたら、山田は気分良く、古橋ちゃんに優しくしてくれた。嬉しかったし、愛しかった。ほんとうに、ほんとうに、繊細で、弱い人なんだと思えたから。
もっと不安定なとき。山田はいつでも古橋の気持ちを不健全な方法で確かめた。自信のないとき。メンタルがおちこんでいるとき。今度は自分のちんぽじゃなくて、古橋ちゃんに仕向けるように言うのだった。何度、山田しかいない、山田だけが頼りだと訴えても、山田は「他の男と寝てみればそうでもないよ」とか「他とやればもっと気持ちいいよ」とか「古橋ちゃんを満足させる男はたくさんいるよ」「前の男に連絡してみなよ」「ハプバーとか行ってみなよ」。職場のおじさんたちにプロレス観戦に連れて行ってもらった時には「そのおじさんとやってみなよ、ロエベのバッグ欲しいって言えば?」とか。わかっていたのだ。本当はそんなこと、思っていないこと。ただそんなことないよ、山田だけだよって、何回も、何百回も言ってほしくて。この人はぶつぶつと呟いているだけなのだ。でも古橋はたまに、かなしかった。こんなに好きなのに、それはもう殺したいくらい好きなのに、あなたの母親を恨んでしまうくらい愛しているのに、どうしてこの気持ちをわかってくれないんだろうって、思った。こんなに伝えているのに。あなたしかいないと伝えているのに。古橋の好意が、そんなに軽いものに見えるのか。他の男のちんぽが少し大きいくらいで乗り換えられると思うほど、古橋ちゃんの思いを軽んじているのか。
今回も、山田は、いつもみたいに古橋ちゃんと劇場を開きたかっただけだ。山田劇場。山田が落ち込んで、意地悪を言って、古橋ちゃんがそれを聞いて落ち込んで、怒って、山田の真意に気づいて、慰めて、仲直りして、いちゃいちゃする。ずっとやってきたこのサイクルを、ただ繰り返したかっただけだ。でも、なんだかわかんないけど、もうだめだった。山田がいつまでも受け止めてくれないことは、地味に古橋ちゃんに効いていたみたいだった。山田を捨てないといけないって思った。山田を捨てないと、わたしこのまま山田と落ちていってしまうと思った。もともとそれでよかった、いや、それ「が」よかったはずなのに。望んでいたはずなのに。だんだん職場の多忙と人間関係によるうつ病のような気持ちが回復してきて、哲学の勉強(を今はしているのだが)がまたできるようになってきて、久しぶりに大学の友人から連絡があって、小さいけれど、明るい兆しがぽつりぽつりと見えてきて、やっぱり今のままじゃだめなんじゃないかって思うようになった。
山田は神さまじゃなかったんじゃないか?
山田の苦しみを、自分の苦しみにしようと思っていた。山田に罪があるのなら、一緒に背負おうと思っていた。それが愛だと信じて疑わなかったから。今でもその気持ちは変わらない。山田の罪悪を背負って生きていきたい。でもそれは、山田がわたしのことを愛している場合、に限るのだ。山田がわたしのことを好きではないのなら、ていねいに扱えないのなら、わたしも山田をていねいに扱えないって、ようやく分かってしまったのだ。おんなじように、山田の喜びだってわたしの喜びではない。わたしに関する山田の喜びならば、わたしの喜びにもなりうるけれど。結局、山田の人生とわたしの人生は同じものではない。同じものを見ていても、山田のちんぽと繋がっていても、わたしたちが見ている景色、そこに見出す意味は違うんだって、分かっちゃった。ばかじゃないばっかりに、気づいてしまったのだった。
山田は神さまではなかった。
でもそれがなんだというのか?
山田の神さまは山田だし、古橋の神さまは古橋だ。こんなに単純なこと。誰にでもわかること。どうして今までわからなかったんだろうって思う。でも、山田は、たぶんだけど、古橋ちゃんのこと、ちょっと好きだったんじゃないだろうか。もちろんそれは軽々とまんこを使わせてもらえるからかもしれないけど、それだったら、山田くらいの格好の良さだったら古橋ちゃん以外のまんこもすぐに見つかるはず。ようはさ。ようは。自分が落ち込んだとき、立ち直れないとき、ずたずたになったとき、傷つけていいもの、けれども否応なく自分の魂を満たそうと立ち回ってくれるもの、それが古橋ちゃんだったんじゃないかな。小さなサンドバッグであり、小さな母親だったんじゃないかな。そういう彼のふるまいが、古橋ちゃんに「山田も多少は好きでいてくれてるんだろう」って期待させちゃったんじゃないかな。山田、最近では仰向けに横たわって、抱き枕を抱くみたいに古橋ちゃんを抱いて、左右に振って、これしてくれなきゃやだ、あれしてくれなきゃやだ、とねだった。かわいい。ほんとうにかわいい。大好きだ。でも、もう古橋ちゃん、山田に優しくできないよ。山田のお母さんは優しくしてくれたかもしれないけど、古橋ちゃんは山田のお母さんじゃないから、優しくできないんだよ。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
