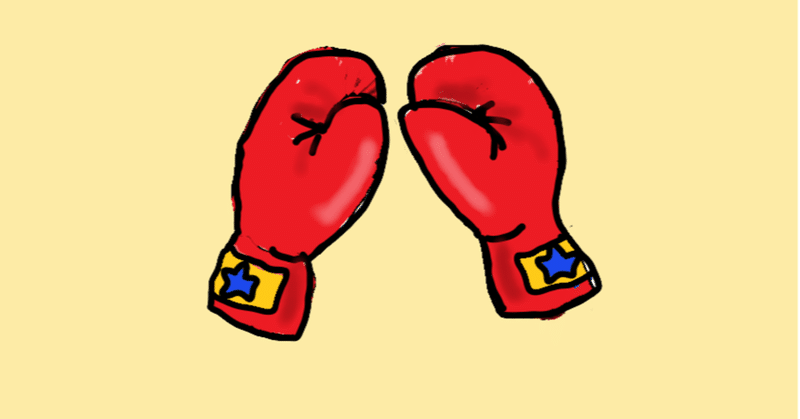
「怒り」という感情について
「最近プライベートで怒ったことがあるか」とこの前知り合いに訊ねられて、パッと怒った記憶が出てこなかった。
正直にそう答えると、「そんな気がした、あんま怒んなさそう(笑)」と相手からポジティブ(?)なリアクションが返ってきた。
でも、「その人が何に対して怒るかでその人が何を大切にしているかが分かる」という話を聞いたことがある。その説を踏まえるのであれば「自分が何を大切にしているのか」が、ふと分からなくなってくる。
--
前提として、怒りというのは体力や気力がいるし、なにより疲れる。
何か違和感のある言動や行動を耳にして「それは違うんじゃない?」と水を差す発言をするのはいわゆる”空気”を壊す行為であるし、それがどうして不快であるのかを論理的に説明できなければ相手に納得してもらえない。相手に納得してもらえるように説明できなければ、この今感じている怒りは自己中心的な感情に過ぎず、それを表出する意味はないのかもしれない、みたいなことを逡巡していると怒るべきタイミングを逸してしまうし、何よりも怒りのボルテージが下がってしまう。
さらに言うと、誰かや何かに不満や憤りがあっても、それをぶちまけて人間関係がぎくしゃくしたり、それを修復したりするのに掛かる労力よりも、(自分一人が心のうちに押し留めれば済む話…)と諦めてしまう方が、はるかに楽で”コスパ”が良いのだと、これまでの人生経験から判断してしまっている気がする。
でもこれは健全じゃないなと正直思う。
いつも怒ってばかりの人も嫌だけれど、「喜怒哀楽」が揃ってこその人間だと思う。何に対しても怒らないという人はそれはそれで怖い。
--
最近友人から『脱「いい子」のソーシャルワーク 反抑圧的な実践と理論』という本を借りて読んだ。
うまく要点を掴んで説明することができないけれど、「良くないことや怒るべきことを我慢していると、社会はもっと良くない状態になるよね」ということが書いてあった。(いや、このまとめはさすがに雑すぎるが
これは、教師のサービス残業の常態化や給特法の話にも通じる話だと思う。現状に不満を抱きつつもそれを当たり前だと受け入れてしまっていることが、自分だけでなく周囲や後世にも悪い慣習を押し付ける事態になってしまっている。
社会や個人からの抑圧を「そういうもの」だと割り切ってしまうのは、危険だし思考の放棄でもある。「それは違うんじゃない」「それっておかしいよね」の一言が出てこなかったことが今大陸で起こっていることに繋がっているのだと思う。対岸の火事ではない。
--
少し風呂敷を広げすぎたけれど、もう少し不満や憤りを素直に出してみてもいいのかもしれない、と最近思うようになってきた。それは自分の精神衛生の為でもあるし、運が良ければ他の誰かや当たり前だと思われていた決まりごとを変えるきっかけになるかもしれない。
その怒りを伝えられる信頼関係があることが前提にはなるかもしれないけれど、少しだけ勇気を出してみる機会が自分の今の生活にはまだまだ足りていない。
ただ、そうは言いつつも相手の意思に反することを言うのは、怖いししんどいし面倒くさい。怒ってしばらく経った後に(どうしてあんな風に言っちゃったんだろう)(もっと適切な伝え方があったんじゃなかろうか)と一人反省会を開いてしまうのが常である。
誰かに傷付けられることよりも不用意に誰かを傷つけてしまうことを恐れている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
