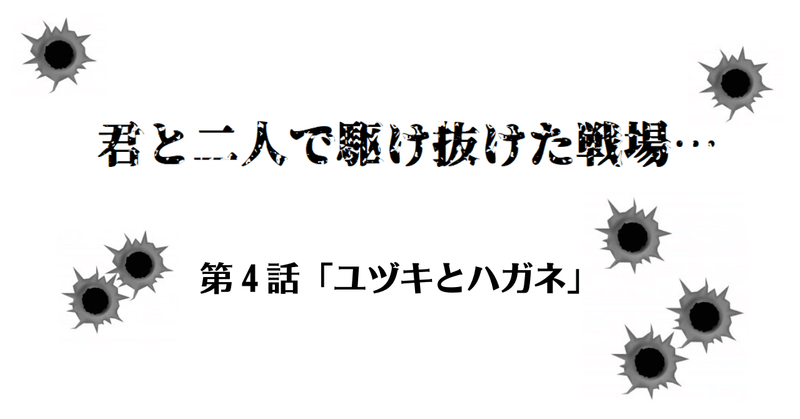
君と二人で駆け抜けた戦場… 第4話「ユヅキとハガネ」
俺はユヅキと行動を共にする事になった。
彼女はマクガイヴァー王国の第3王女で、れっきとした第7王位継承権者である。だが… 彼女自身が一兵卒の俺に、自分を王女ではなく一人の女性として扱えと言うのだ。
もう、俺はやけくそになってユヅキの言うとおりにする事にした。
しかし、ここはいったいどういう施設なんだ…?
入り口を含めた外観は大昔の遺跡そのものだったのに、この超近代的な内部はいったい…
古代文明の遺跡なのだろうか…?
俺は答えをユヅキに聞こうとした。王女の彼女なら知っているかもしれない。俺がユヅキに話しかけようとすると、彼女はスタスタと歩いていく。
俺は慌てて後を追った。
ユヅキがこの場所が初めてでは無い様なのは、最初にこの場所に入った時から分かってはいたが、やはり俺の様にキョロキョロとは見回さなかった。
彼女がある場所へ行くと、そこは手洗い設備なのかユヅキが手をかざすと水がほとばしり出てきた。俺は喉がゴクリと鳴った。今日は少ししか水を飲んでいなかったのだ。戦場では水は貴重だから、兵士一人に支給される水の量はわずかだった。
ユヅキを見ていると、どこからか取り出したタオルの様な布を水で湿らせて、それで自分の顔をゴシゴシとこすり出した。すると、顔の上半分をカモフラージュのために汚していた黒い汚れが落とされていく。
俺は喉の渇きも忘れて、ユヅキの様子をじっと見つめていた。顔の汚れを拭き取り終えた彼女は、また両手に水を救ってジャブジャブと顔を洗い出した。
そして、ようやく洗い終えたユヅキは顔をブルルンと振り水しぶきを飛ばした。
「ぷはーっ! はああ、スッキリしたあ…」
ユヅキが、ぽかんと口を開けて見つめていた俺の方を振り返った。
俺はさらに口をあんぐりと開いて呆けた様に彼女の顔に見とれていた。
『何て美しいんだ…』
俺は声にこそ出さなかったが、ユヅキの化粧もしていない素の顔を見て驚いてしまった。俺の周りに若い女がいなかった事は前に述べたが、それでも若い女を見た事ぐらいはいくらでもある。
学校でだって同級生の半分は女だったし、軍に入ってからも女兵士は結構な数がいた。街でも兵士以外の一般人の若い女なんて珍しくも無い。
だが… 俺は今までに目にした中でも、ユヅキの様な女には出会った事が無かった。もちろん、王女なのだから当たり前なのだろうが…
どう表現すればいいのか…
目の前にいる彼女は、何というのだろう…すごく透明な感じがするのだ。
身体つきは、ほっそりとして華奢で… でも不健康な感じは全くない。
汚れを落としたユヅキの肌の色は真っ白で、染みひとつ見当たらなかった。
まだ幼さも少し残したような美しい顔立ちは、深い緑色をした大きな瞳に小ぶりだが鼻筋がしゅっと通り、唇は薄いピンク色で薄すぎも厚すぎもしないぽってりとした愛らしく可愛い形をしていた。
俺は今まで女の顔に見とれた事など無かったが、生まれて初めて愛らしく美しいと言う表現しか思い浮かばない顔に出会った気がした。
化粧をしていなくてこうなのだから、化粧をすれば俺は彼女の顔をまともに見つめる事すら出来ないかもしれない。
しかし、なんと可憐で愛らしい姫君だろうか…
俺はユヅキの顔から目を逸らすだけでなく、そっぽを向いて何故かドギマギしてしまう自分の気を彼女から逸らせようとした。
「ん…? どうしたの、ハガネ? 」
ユヅキが俺の反応を見て不思議そうに首を傾げている。
「まだ、私の顔に汚れが付いてる…? いやだなあ… どこに?」
残念ながらこの手洗い場には鏡が付いていなかった。
俺はユヅキが可哀そうになったので、ちゃんと彼女の顔を見つめながら言ってやった。
「大丈夫… 綺麗に汚れは取れたよ。顔のどこにも残ってない。」
「ホント? 良かった… ハガネが私の顔をじっと見た後に目をそらすんだもん… てっきり、まだ汚れてるのかと思った…」
そう言って屈託なく笑う彼女の顔が俺には眩しかった。
「あのねえ、ハガネ… 私は今は王女だけど前はあなたと同じで、ただの平民だったのよ。」
ユヅキが微笑みながら俺に言った。
「何だって…?」
俺は耳にしたユヅキの言葉が信じられずに彼女の顔を見なおした。
「うん、そうなの。私は6歳までは普通の町娘だったの。
王都ヴァジーナの城下町ティーダで生まれたのよ。母はティーダの旅館で働いてたわ。」
ユヅキが遠くを見る目で語り出した。
「そして… わが父であるマクガイヴァー17世が、お忍びでティーダに来た際に母を見染めて二人は恋に落ちたと言うわけ…
二人が愛し合った結果、私が生まれたのよ。」
ユヅキが噛みしめる様にゆっくりと話を続けた。
「私は5歳までティーダの街で母と祖父と一緒に暮らしていたの。さっき死んでしまった爺やが私の実の祖父ケンゾウ・ラル・クリマ…
祖父は考古学を研究していたのよ。定年する前はティーダ大学の考古学の教授だったの。母が私を生んで間もなく死んでしまってからは、私を育ててくれたのは祖父だった…
そして6歳の誕生日前になって、城からの使者が私を正式なマクガイヴァー17世の第3王女として迎えに来るまでは祖父とずっと一緒だった。
そして…ついにその日が来たわ。
祖父は城で王家の人達に考古学を教えるためと、同時に私の世話係の一人として、幼かった私と一緒に城へと召し上げられたの。私を不憫に思った父マクガイヴァー17世の特別な計らいだったのね…
お祖父ちゃんは「城の膨大な量の書物を読む事が出来る」と言って、幼い私の手を握って喜んでたっけ…
私はお祖父ちゃんと一緒なら、どこで暮らす事になってもよかった。
そして… 城での王の娘としての私の生活は、三日前の王都陥落でマクガイヴァー城が落ちた事で11年間で終わっちゃった…」
そこまで話したユヅキの顔には寂しげではあるが、どこかホッとした様な安堵の表情が浮かんでいる様に俺には見えた。彼女の声の調子にもそれが表れていた。
だが… ユヅキの目が微かに潤んで光っているのを目にした時、俺は彼女の気持ちを想って少し切ない気持ちになった。
ユヅキは俺に後頭部を向けて涙を拭ったのか、少ししてから笑顔で振り向いて言った。
「私の身の上話はこれでおしまい…
じゃあ、ハガネ… 今度はあなたの事を教えて、お願い。」
「ああ… 分かった。」
俺も自分の身の上をユヅキに話そうとした。
その時だ…
「ドドーンッ!」
爆発音が聞こえるとともに俺達の足元の床が揺れた。
「何だ、今の爆発は? ここからそう遠くないぞ…」
俺は左肩に吊るしていた小銃に手をかけた。
「あいつらよ… 私を追ってきたんだわ。」
ユヅキが爆発音の方を振り返って言った。
「あいつらって?」
俺が聞くのに彼女が答えた。
「私を追っているグランバール帝国の兵士達だわ、きっと…」
ユヅキの顔を見ると、彼女は唇を噛みしめていた。
「グランバールの連中、建物の壁を爆破しやがったな! クソッ!」
俺は吊るしていた小銃を肩から外しながら、いつでも撃てるように薬室に弾を送り込んだ。
「はっ…! ハガネ、これを見て…」
俺はユヅキに肩を掴まれて振り返った。
「どうし… ⁉」
ユヅキを振り返った俺は目の前の光景に驚き息を呑んで、思わず小ぶりだが服越しにでも整った形をした彼女の胸のふくらみに見入った。
いや…正確に言うとユヅキの胸に吊り下げられたペンダントが、緑色の光を発していたのだ…
宝石だろうか…? 水晶の様にも見えるソレは彼女の胸のふくらみの上でで、まぶしいと言うほどでは無いが仄かに明るい緑色の輝きを発していた。
それは輝き続けているのではなく、まるで心臓の拍動の様にゆっくりと光を強めたり弱めたりする明滅を繰り返していた。
「ユヅキ… それは?」
俺は緑色の光の明滅を浴びるユヅキの顔を見つめて聞いた。
「これは…死んだ母の形見なの… 母はマクガイヴァー17世から贈られたのだと、お祖父ちゃんから聞いたわ…」
ユヅキは俺の目を見返しながらつぶやくように言った。
「驚いたな…」
俺は自分の胸の前のボタンを一つ二つと外した。ユヅキがハッと息を呑むのが感じられた。
そして俺がシャツの隙間から引っ張り出したソレは…
「まあ… それは…」
ユヅキが驚きの声を漏らしながら、手を口に当てて俺が取り出したモノに見入っていた。
それは、ユヅキの胸で明滅を繰り返している水晶(?)と同じ形をしていた。色こそ違って俺のは赤い石だったが…
そして俺の赤い石も驚いた事にユヅキの石と同じ様に、赤い光の明滅を繰り返していたのだ。
二つの石の明滅は、強さもリズムも全く同じだった…
俺達二人の胸で繰り返し明滅し続ける緑と赤の光…
光りは柔らかでとても美しく、こんな状況で無かったらずっと見つめていたくなる様な温かい光だった。だが…
「ドカーンッ!」「ガラガラガラッ!」
奴ら、また爆破しやがった。今度のは振動も音も大きいし、近い…
どうやら今度の爆破で壁が崩された様だ、奴らが入って来る…
「ユヅキっ! 逃げないと危険だ!」
俺はユヅキの右手を左手で引っぱって走り出した。
「待って、ハガネ! 見て、これ!」
振り返った俺はユヅキが左手で持った例のペンダントを見た。相変わらず 緑色の明滅を繰り返すそれは、さっきよりも明滅の間隔が短くなっていた。
俺は自分の胸元の赤いペンダントを見た。それは、ユヅキのものと全く同じ反応を示していた…
俺の頭に突然に閃くものがあった。
「分かった…ユヅキ! 俺達の二つのペンダントは、分からないが同じ何かに反応してるんだ! そして、それに近付くほど明滅が速くなるんだ!」
俺の怒鳴り声を聞いたユヅキは、大きく頷いて俺とペンダントを交互に見た。彼女も俺と同じ結論に至った様だった。
二つのペンダントの反応を見て、俺は自分達の進むべき方向をその明滅に賭けて見る事にした。
「どうやら、あっちの方角の様だ… 行こう、ユヅキ! どうせ、じきにグランバールの奴らが来る! 走るぞ!」
俺はペンダントを首から外して右手に握りしめ、ユヅキの手を引きながら彼女と共に走った。
もしよろしければ、サポートをよろしくお願いいたします。 あなたのサポートをいただければ、私は経済的及び意欲的にもご期待に応えるべく、たくさんの面白い記事を書くことが可能となります。
