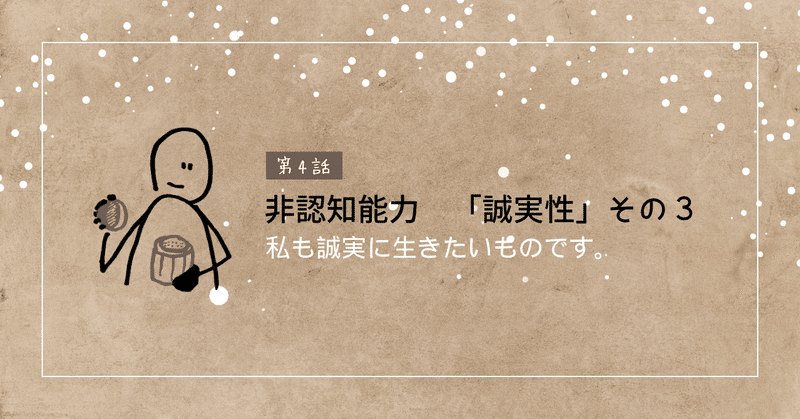
誠実性とどう向き合っていくのか
これまで,誠実性について考えてきましたが,では,私は実際にどう向き合っていくのか整理していきたいと思います。
ここは忘れないでおきたい
☆無理して伸ばそうとしない。でも,今しかできないことを。
誠実性に限らずですが,パーソナリティと大きくかかわってくるのが非認知能力です。高いのがいいのか低いのがダメなのかという前に,あるがままを受け入れることもまた大事なことだと考えます。
ですが,「あるがまま」がいいわけではないですね。
あるがままを受け入れ,それを踏まえてどうするか選択し,行動に移していく。そんな気概が大事だと思います。
しかも,そんな難しいことを小学生が個人で続けていくことは難しいうえに,大人になってからは身に着けることが難しいというなら,まわりにいる大人がいかに支え,導くのが大きく影響を与えます。
無理なく小学校のうちから継続的にコツコツと。
そんな意識は持っておきたいところです。
☆どの場面でも意識していく
では,どの場面で育てていくのか。私は場面にこだわらないことが必要であると思います。
前回の記事に,いくつか成果を上げるための要因をまとめさせてもらいました。これを押さえすれば,どの場面が意識しやすいのか,環境や先生のキャラによって見えてくる場面が見えてくるのではないでしょうか。
お掃除,委員会,学級での行事や係活動,日々の授業…
①どこで意識的に行うのかということ
②日常的に非認知能力を意識的に取り入れた指導を取り組もうとする気概
この2点を心にとめておきたいものです。
☆私は特に家庭学習で
葛原祥太さんをご存じですか?「けテぶれ」や「QNKS」を提唱なさっているすごい方です。
私も毎日お世話になっております。
実践の素晴らしさは言い尽くせないのですが,非認知能力の側面から見ても,非常に有効な手立てであると考えています。
「自分はどんな人間なのか。」
を日々の家庭学習で向き合い続けることは,よりよく生きることへとつながっていきます。
誠実性においては,他者とかかわる側面が大きいので,家庭学習は自己のために行うもので一見相性はよくないようにも見えますが,「なぜ学ぶのか」を考え続ける「けテぶれ」の実践は,誠実についての考え方もはらんでいます。
非認知能力の第2話にまとめたように,自己が課題とどう向き合うのかということを,学校だけでなく家庭でも,どこでもいつでもできるような態度を育てていけたらとても力が付きそうだと思いませんか?
最後に
さて,土台をそろえる。「よりどころ」をテーマに,今回は「誠実性」を取り上げました。
土台がそろわないまま,漠然と「誠実であることはいい。」「誠実でない行動は厳しくただしていくべきだ。」といった理解で話を進めていくと,
「あの子はいつも期限が切れてだらしがない。」
「あの子は話も聞かないし覚えてもいかない。仕方のない子だ。」
「大きな声を出して迷惑だし,勉強にもなっていない。」
などなど,その子が持っている本来の良さを見落としてしまうような話になってしまうかもしれません。
おさらいですが,誠実性はパーソナリティであり,小さいときは全体的に低い傾向にあります。ですが,大きくなるにつれて高まっていくこともわかっています。
そうです。みんなで育てていけばいいのです。
今だめだから,もう駄目な子だなんて思わないで,長い目でその子の成長に付き合っていけばいいんです。
ですが,いつでも担任でいられるわけでもないし,その子の人生を責任をもって見守り続けることも不可能だから,より多くの大人が土台をそろえて議論しあい,成長を見届けていくことで,教育のリレーが行われていけばいいんですよね。
こんな感じで,他の分野から見ても,いい教育のリレーが続いていくような「よりどころ」をこれからも探し続けたいと思います。
今回で「誠実性」は最後です。
お付き合いいただきありがとうございました。
誰かの「よりどころ」になりますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
