
素直なメロンクリームソーダ 前編
どうやら自分には、特殊能力が備わっているらしい。
それに気づいたのは、ごく最近のことだ。
やっかいなのは、それがいったいどういう能力で、どういう条件で発動されるのか、皆目わからないところである。
「喫茶店行きたい」
「また?俺は定食屋でいい」
「葉山と行くの」
昼になんの約束も入っていない日は、たいてい同僚の鹿嶋が誘ってくる。
のらりくらりとかわしたいところだが、なぜか彼女には通用しない。
***
会社の近くにある蔦に覆われたその店は、今風に言えばレトロ(矛盾した表現だが)あけすけもなく言ってしまえば、ひたすらボロイ。
駅前なのにわかりにくい場所に佇み、正直、葉山は最近までその存在に気づきもしなかった。
長年染みついた匂いや空気や時間。それらが全部、ドアを開けたときに一気に襲ってくる。
「はー落ち着くー」
この独特の空間に、鹿嶋ナツはいつからかハマりまくっている。
こうと決めたものには、とことん情熱を注ぐ。
あきれるくらいにまっすぐなヤツだという印象は、入社当時から変わっていない。
やたらと長いメニュー表に目を輝かせ年内にすべて制覇すると宣言し、ひとりではらちが明かないと同期を巻き込んできた。
***
「またイヤそうな顔する」
「現にだるいし。サバみそねーし」
やる気がないので、注文もほぼ鹿嶋まかせだ。
エビのリゾットとチキン南蛮というナゾの取り合わせを押しつけられ、渋々片づける。
鹿嶋のほうは、攻めたナポリタン、というネーミングのこの店の看板メニューだった。ありふれた見ためと味で、攻めているのは名前だけな気がしてしかたない。
「王道で真っ向勝負を挑みつづけてんだよ?何十年も。エモくない?」
そういうんもんか、とあっさり納得させられそうになる。
「それ絶対食っただろ。前に」
***
速いラリーが続くのが常なのに、そこで彼女がイレギュラーな反応をみせる。
「覚えてる?わたしがいつナポリタン食べたか」
少し考えてはみたが、思い出せない。
だが、客のほとんどが注文するのだから、それこそ初めて来店したときにでも食べているはず。
「なんかよどんだオーラ出てますよ、鹿嶋さん」
キッとにらみつけてきたあと、さっそうと手を挙げデザートを注文する。
「例のものを」
毎回思うのだが、メロンクリームソーダってデザートか…?
「アイスのってるもん」
ストローのしましまが今日は赤だと、うれしげに口に含む。
社内ではクールだのやり手だの妙に評判のいい鹿嶋だが、素の彼女はけっこう子供っぽい。
アイスが溶ける前に食すべきか、溶かしてクリーミーさを味わうべきかと、真剣に悩んでいる。
(つづく)
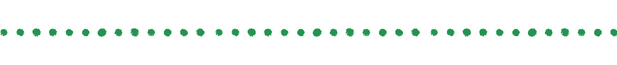
*23年7月に公開していた作品です
加筆・修正し、再掲します
最後までお読みくださり、ありがとうございました。 サポートしていただけたら、インプットのための書籍購入費にあてます。 また来ていただけるよう、更新がんばります。
