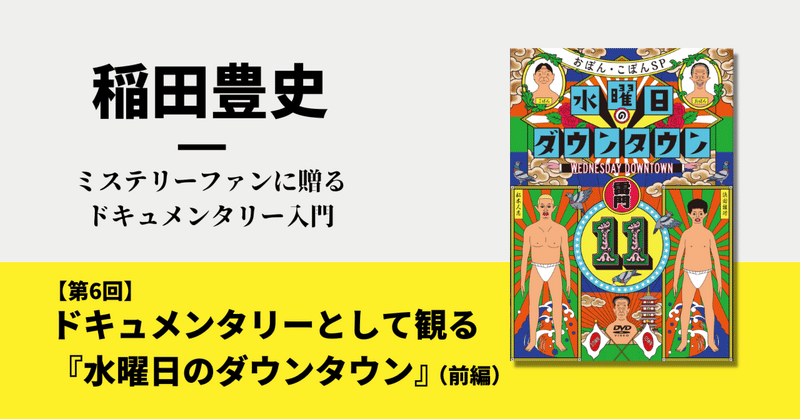
ドキュメンタリーとして観る『水曜日のダウンタウン』(前編)|稲田豊史・ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門【第6回】
文=稲田豊史
関与型ドキュメンタリーとしての『水ダウ』
『水曜日のダウンタウン(水ダウ)』というダウンタウンの冠番組をご存知だろうか。2014年4月からTBS系で放送中のバラエティ番組で、その基本フォーマットは、芸人を中心とした芸能人に仕掛けるハードめで凝ったドッキリ。ゆえにバラエティ番組の中でも、かなり〝作り込んだお笑い〟に寄った構造を特徴とする。
番組ホームページに書かれている内容はこうだ。
芸能人・有名人たちが自分だけが信じる〝説〟を
独自の目線と切り口でプレゼン
その〝説〟についてVTRで…
またはスタジオメンバーとのトークで…
検証を行っていく番組
ただし「〝説〟の検証」は形式的なフォーマットにすぎず、その実はなんでもあり。「芸人を強制拉致・監禁して過酷なチャレンジを強要する」「男性芸人の部屋に見知らぬ人間を潜ませ、帰宅した彼に恐怖を味わわせる」「先輩芸人が後輩芸人に理不尽にキレたらどういう反応を示すかを観察する」など。ターゲットを芸人あるいは少々失礼を働いても差し支えない芸能人に絞っているだけに、その鬼畜度は非常に高く、やりたい放題。サディスティック、と形容してもいいくらいだ。
とはいえ、ただ過激なだけではない。企画のオリジナリティは地上波バラエティ番組の中では群を抜いて高く、仕込みにかけているであろう準備や手間も尋常の範囲を越える。編集はキレキレで冗長さのかけらもなく、テロップもいちいち皮肉が利いている。要は、置きにいっていない、流していない、予定調和を許さない、実に誠実な作り込みを施されているのだ。当然ながらコアなお笑いファンの間では長年にわたって評価が高く、テレビ離れが叫ばれる若年層にもよく見られている。
今回は、「『水ダウ』の本質は、ほぼドキュメンタリーである」という話の前編だ。
やぶから棒に何を、とお思いだろうか。
ただ、『A』『FAKE』などで知られるドキュメンタリスト・森達也は、1998年にTV番組として制作した『職業欄はエスパー』について後年、同作が収録されたDVDに封入のブックレットで、被写体である自称エスパーと揉めたことを振り返りながら、ドキュメンタリーの撮影についてこんなことを言っている。
「被写体をフラスコの中に入れて、振ったり熱したり触媒を加えたりという作為によってどのように変化するのか、あるいはしないのか、その過程を作品にする。挑発したり誘導したり怒らせたり」【*1】
ドキュメンタリーには「関与型」と「非関与型」、大きく2つの種類がある。前者は被写体に働きかけることによって発生する状況や反応を記録するもの。後者は極力関与しない状態で観察・記録に徹するものだ。森は『職業欄はエスパー』について、すべてのシーンを〝仕掛けた〟と語っており、そこからしても圧倒的に前者、「関与型」のドキュメンタリストである【*2】。
被写体に積極的に関与し、仕掛け、その反応をカメラに収める――これは完全に、バラエティ番組の「ドッキリ」と同じアプローチだ。
「ドキュメンタリーとバラエティ番組の企画を一緒にするな」とお思いだろうか。しかし森は、’90年代に一世を風靡した『進め!電波少年』(日本テレビ系)のドキュメンタリーバラエティ(猿岩石の「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」など)を楽しんで見ていたと自著で述懐する。「あんなお笑いにドキュメンタリーのような呼称をつけられて腹が立たないのですか?」と聞かれることもあったそうだが、腹など立たないという【*3】。「ドキュメンタリーはそのテーマでカテゴライズされるジャンルではない」「土屋(敏男/『進め!電波少年』プロデューサー)の番組はドキュメンタリーとして面白い」【*4】という森は、「社会告発だろうが、お笑いだろうが、お涙頂戴だろうが、ドキュメンタリーの手法を使ったのならその瞬間に、その表現はすなわちドキュメンタリー」【*5】だと言い切る。筆者も、これには大きく同意したい。
ちなみに件のブックレットにおける森の対談相手は、ベテランお笑い芸人の東野幸治である。東野と言えば、トーク番組などでのぬるい予定調和的な展開を嫌い、絶妙な意地悪ワードをゲストにぶつけることで動揺させ、場をかき混ぜる腕に長けた芸人だ。まるで、ある種のドキュメンタリー監督のようではないか。
その東野はドキュメンタリーが大好きだという。
「ぼくは職業柄ツッコミをやることが多いから、(フィクションのような)作りものよりも、やっぱり生身のものに惹かれてしまう。つい『なに言うてんねん!』ってなるような……そんなとこもドキュメンタリーが好きな理由ですね」(カッコ内は筆者による追記)【*6】
ガチドキュメンタリーとしての強度
ドキュメンタリーバラエティの金字塔である『進め!電波少年』のヒッチハイク企画の面白さ――被写体に事情を知らせず連行し、途方もない目的を自力で達成させる――は、その後多くの番組に影響を与え、類似企画を生み出した。『水ダウ』も例外ではない。たとえば、芸人を無人島や辺鄙な場所に目隠しで連れていき、あるいは密室に監禁し、制約下での自力脱出を試みさせるものなどだ。「外界から隔絶した場所で新元号を当てるまで出られない」といった、現代的なサスペンススリラー映画さながらの名企画も多い。
ただ、むしろ、『水ダウ』が発揮するドキュメンタリー番組としての実力、そのガチ度を十全に見せつけた傑作といえば、「おぼん・こぼん和解ドキュメンタリー」をまず筆頭に挙げたい。
これは2019年から21年にかけて断続的に放映された連続企画で、芸歴50年以上の超ベテラン漫才コンビでありながら、どうしようもなく不仲のおぼん・こぼんに対し、番組が「和解」をアプローチするものだ。
番組はまずこぼんにコンタクトを取り、おぼんに対して解散ドッキリ(本当は解散する気はない)を仕掛けさせるが、バラエティ番組として笑えるオチがつけられないほどカメラの前でおぼんが激怒してしまい、その模様はそのまま放送された。
その後、ふたりに催眠術をかけて仲直りを試みるも失敗。最終的にはふたりがなぜ険悪になったのかを関係者の証言とともに明らかにし、こぼんの娘の結婚披露宴におぼんを招待して関係修復を図る――という壮大な展開に至る。しかも通常のお涙頂戴バラエティのような予定調和は一切なく、おぼんもこぼんも簡単には心を許さないため、VTRは常に緊張感に包まれていた。良い意味で、視聴者がまったく安心して見られないのだ。
もはやお笑い系バラエティ番組のいち企画を超えた、立派なドキュメンタリーコンテンツ。連載第1回で述べたドキュメンタリーの醍醐味であるミステリーの3要件、①発端の不可思議性、②中途のサスペンス、③結末の意外性をすべて満たす、図抜けて見応えのある〝作品〟に仕上がっていた。
2021年10月6日に放送された同企画の最終回『おぼん・こぼんTHE FINAL』は、すぐれたテレビ番組に与えられるギャラクシー賞の2021年10月度月間賞を受賞。2022年には放送文化基金賞において、テレビエンターテインメント番組部門の最優秀賞を受賞。それぞれの選評は「緊張感と説明し難い人間の複雑な感情に溢れた人間ドキュメンタリー」「出色の人間ドキュメント」と、いずれもお笑い番組ではなくドキュメンタリー作品としての高評価だった。
実は『水ダウ』は、同企画を含めてギャラクシー賞を4度も受賞している。そのひとつ、「徳川慶喜を生で見た事がある人 まだギリこの世にいる説」は、江戸幕府第15代将軍の徳川慶喜を実際に目撃した存命人物を探すという企画。スタッフが調査とインタビューを重ねた結果、「日本橋の髙島屋と白木屋の間くらいを、行列を従えて歩く慶喜を見た」という105歳の女性に行き着き、明治45年にその事実があったという専門家の言質まで取った。
地道なフィールドワークによって〝説〟を立証せしめる姿勢は、ほとんど調査報道の域。また、歴史とは決して「お勉強」や「教養」ではなく、現在の生活と地続きになっているという事実を、高齢者へのインタビュー(「子供のころ、村にちょんまげの人がいた」等)で視聴者に手触りとして体感させる点などは、硬派な問題提起型ドキュメンタリーが持つ「視聴者の認識を見る前と見た後で変える」機能そのものだ。
なにより、それを歴史ドキュメンタリーやノンフィクション教養番組ではなく、お笑い系バラエティ番組のフォーマット上でやってのけたところが粋ではないか。森達也の「社会告発だろうが、お笑いだろうが、お涙頂戴だろうが、ドキュメンタリーの手法を使ったのならその瞬間に、その表現はすなわちドキュメンタリー」が、再び頭をもたげる。
視点の設定によって批評的態度が目覚める
ドキュメンタリー制作のハウツーを網羅した翻訳本『ドキュメンタリー・ストーリーテリング』(シーラ・カーラン・バーナード著/フィルムアート社)は500ページ以上に及ぶ大著だが、その冒頭、イントロダクションの2ページ目には早くもこんな記述がある。
「(ドキュメンタリーとは)観客がその映画を見るまでは気にも留めなかったトピックについて、考えずにはいられなくさせてしまう」
秀逸なドキュメンタリーは、人々が普段から見慣れている事象や被写体にまったく新しい視点を設定し、今まで及びもつかなかった「見方」を提示してみせる。徳川慶喜を生で見た事がある人に語らせることで、この現代社会がシームレスに「徳川の治世とつながっている」事実を認識させたのも、そんな所業のひとつだ。
視聴者の認識が拡大する。世界の捉え方が一変する。さしずめ映画『マトリックス』の主人公、ネオの目覚め。そうして視聴者が獲得するのが「批評的態度」というやつだ。
その意味で『水ダウ』の批評性は高い。しかもその批評の矛先にあるのは、かなりの頻度で自分たちが身を置くテレビ業界だったりする。
たとえば、2022年4月27日に放映された「若手芸人コンプライアンスでがんじがらめにされても従わざるを得ない説」。これは街ロケに繰り出した若手芸人コンビ「そいつどいつ」に対して、現場スタッフが滑稽なほどに過剰な「コンプライアンス遵守」を求めるドッキリ企画だ。明らかに人畜無害な一般人の店員に対して「反社ではないですよね?」と確認するよう指示を出したり、番組のスポンサーと異なる飲み物の自動販売機を黒い布で不自然に覆わせたり。
極め付きは「鯛焼きを頭から食べると残酷に見えるからNG」というディレクターからの難色だ。度を超した理不尽だが、若手芸人だけにスタッフには逆らえないのではないか……と思いきや、そうはならなかった。コンビの片方である市川刺身が、その不快感と怒りをカメラの前で吐き出し、「俺ら芸人なんで、面白いっていうのをやりたいだけなんで。作っている側はわかんないですけど、なんかマジでつまんなくなってきたなって思いますね」と言ってのけたのだ。
極限状況下で絞り出された、笑いに身を投ずる者の良心。スタジオの松本人志も視聴者も、ここには笑いではなく感心と称賛を寄せた。本企画は明らかに、過剰なコンプラ規制と忖度で「TVがどんどんつまらなくなっている」ことへの、ドッキリに名を借りた批評的危惧の表明だった。
これは実に巧妙な状況設計だ。立場が弱いはずの若手芸人にここまで言わせてしまうくらいの深刻さを、状況を誇張しディフォルメしたうえで、白日の下に晒す。お見事、と言うしかない。
社会派ドキュメンタリーは「お笑い」に近づく
コンプラまわりではもう一企画ある。芸人たちに「罰ゲーム講習会」を受けさせ、そのライセンスを取得した者だけがバラエティ番組で罰ゲームを受けられる――として騙す企画だ。講習会には吉本興業の上層部まで登壇させる念の入れようだった。
罰ゲーム講習会など、馬鹿馬鹿しいことこの上ない。しかしバラエティ番組の罰ゲームに対する批判の声が年々大きくなっているのは、周知の事実。若手芸人にとっては派手なリアクションを披露することでカメラを向けてもらえる貴重な「おいしい」仕事だが、「芸人さんがかわいそう」「子どものいじめにつながる」という声に押され気味という現状がある。とはいえ、芸人や制作者たちが感じるその窮屈さは、時流的に決して声高に叫ぶわけにはいかない。
そのもどかしい状況を、ドッキリの体で問題の所在ごと可視化して俎上に載せ、本質的な馬鹿馬鹿しさを「嘘講習会」を隠れ蓑にして笑い飛ばしたというわけだ。
ここまで来ると、もはや社会派である。ある種の社会派ドキュメンタリーが担う役割と寸分たがわない。
実際、滑稽で馬鹿馬鹿しい状況を笑い飛ばすタイプの社会派ドキュメンタリーは少なくない。たとえば、保守王国・富山の地方政治腐敗を地方テレビ局が暴いていく『はりぼて』(’20、監督:五百旗頭幸男、砂沢智史)には、あまりにもトホホすぎる議員が多数登場するが、カメラの前で晒す醜態はほとんどコメディといってよかった。切れ味鋭い社会派ドキュメンタリーはしばしば「お笑い」に近づくのだ。
『水ダウ』の場合、暗喩的な笑いという高度なアプローチで社会を斬る。異議申し立てを唱える。しかも、あからさまで野暮ったい風刺や皮肉ではない、もっと気の利いた、もっとクールな、一級のエンタテインメントに昇華しつつ行う方法があることを、『水ダウ』は身をもって示し続けている。
「ドッキリ」の概念を解体する試み
『水ダウ』はまた、テレビ業界の悪習を告発もする。
たとえば、名の知られていない女性タレントに偽の番組オーディションを仕掛ける企画。オーディションに受かるためには「霊感が強い」「汚部屋アイドル」「おバカタレント」「不思議ちゃん」といったキャラが〝乗って〟いなければならないが、そもそも彼女たちにそんな属性はない。しかしテレビに出たい彼女たちは、そのキャラを強引に乗せてオーディションに出る。業界用語で言うところの「ヤリにいってる」というやつだ。
彼女たちのテレビ出演欲を利用した、あまりにも非道なドッキリではあるものの、その裏にあるのは、「そうやって、好きでもないのに何かのファンを公言したり、たいしてはまってないのにマニアですと言ってテレビに出ようと必死のタレントが多い」ことの内部告発だ。
つまりこの企画はドッキリではあるが、実際にそういう状況がTV界に存在し、そういうオーディションが開催されており、それに乗るタレントも普通にいる――ことの検証フィルムでもある。実際、はめられたタレントたちの必死さや切迫感は完全に本物だった。
陳腐で硬直化した既存のバラエティ番組フォーマットをあざやかな手付きでおちょくるのも『水ダウ』の十八番だが、そのひとつが「ドッキリという概念の解体」である。たとえば、雑な仕込みで明らかにドッキリとバレバレなのに芸人たちは「ひっかかったフリ」をし続けられるのか――という検証。過去にドッキリを受けた芸人に同じドッキリを仕掛けるとどうなるか。あるいは「これからドッキリを仕掛けるので、1週間後にどれがドッキリだったかの答えあわせをする」と芸人に宣言する「1週間予告ドッキリ」など。
ドッキリは『水ダウ』にとって欠けるべからざる、基本的な番組構成パーツのひとつ。にもかかわらず、そこにすら批評的視線を投げかける。テレビ局自身がテレビ局のニュース報道を徹底的に自己批判した東海テレビのドキュメンタリー問題作『さよならテレビ』(’18、監督:圡方宏史)に近いものがある。否、自己批判を自己批判としてストレートに口にせず、メタ化した笑いに昇華させている時点で、実は『さよならテレビ』より『水ダウ』のほうが高度かもしれない。
ドッキリ解体系企画でもっとも高度なのが「ホントドッキリ」シリーズだ。そのひとつ「CMホントドッキリ」では、複数の芸人たちに明らかに不自然なCM撮影をやってもらい、芸人が不審を抱いた時点で「ドッキリでした」と明かす。と、ここまでなら普通のドッキリだ。
ところが、実はCM自体は本当に制作されており、最後まで疑わなかった芸人を撮影したものだけが、本当に放映される。それを聞かされた芸人は二重に驚き、混乱する。騙されたことへのリアクションをきっちり取るべきなのか、CM撮影が本当だったことを喜ぶべきなのか。感情が渋滞を起こす。ドッキリ構造が複雑すぎて事態がすぐ飲み込めない者もいる。
「ドッキリとは何なのか」の定義ごと揺さぶる、実に哲学的な状況設定。高度すぎる。もはや単なるお笑い系バラエティとは呼びづらい。実験精神にあふれた関与型ドキュメンタリーの極みだ。
『MONSTER HOUSE』の批評性
『水ダウ』の常連ターゲットといえば、安田大サーカスのクロちゃんだが、2018年に7回ものシリーズで放送された『MONSTER HOUSE(モンスターハウス)』は論じがいのある労作企画だった。タイトルが示すとおり、他局であるフジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』のパロディだ。
『テラスハウス』は若い男女複数人をひとつ屋根の下〈テラスハウス〉で共同生活させてカメラを回し、そこで生まれる恋愛の行く末を観察するリアリティ番組(リアリティショー)。『MONSTER HOUSE』も同じだが、その男女(モデル、タレント、一般大学生など、20代)のなかにひとりだけ40代の中年男性であるクロちゃんが交じっている。
リアリティ番組とは、一般人もしくは名の知られていない芸能人を、ある空間・ある状況に集め、そこに番組側がなんらかの〝関与〟をほどこすことで彼ら・彼女らの反応を観察して楽しむもの――というのが一般的な説明である。日本では参加者同士の恋の鞘当てを観察するタイプのものがよく知られているが、どんなジャンルまでがリアリティ番組なのか、ドキュメンタリーとの境目はどこにあるのかといった議論は尽きないので、これは別の機会に譲ろう。
『MONSTER HOUSE』は――表面的には――若い美男美女の中にひとりだけ禿頭の中年男性が交じって恋愛ゲームに(厚かましくも)参加するという滑稽さを鑑賞する企画だ。その状況設定は、クロちゃんのゲスな恋愛観、嘘つきぶり、自分勝手ぶり、鬼畜ぶりなどを炙り出す装置としてうまく機能しており、それはそれでクロちゃんの人格のダメっぷりを存分に嗤うコンテンツとしてしっかり成立している(無論、クロちゃんの鬼畜ぶりが「ヤリにいったキャラ」ではないという保証はないが)。
ただ、同企画の真の面白み、言い換えるなら「悪意」はもっと他にある。そう、本家『テラスハウス』(という人気番組)に対する茶化しだ。
『MONSTER HOUSE』におけるクロちゃんの滑稽さを、もう少し因数分解してみよう。下心見え見えで女性たちに優しさを振りまき、恥ずかしげもなく甘い言葉でモーションをかけ、その裏で男性陣をネチネチと牽制する。カメラの前で恥ずかしげもなく披露される、芝居がかった発言や挙動。なにやら白々しく、背中がむず痒くなる。見えすいた茶番。
その茶番感をいっそう際立たせているのが、本家『テラスハウス』を完コピした画づくりだ。外観も内装も最高に洗練されたオーシャンビューのテラスハウス。インテリア、日中の自然光と夜の室内照明、テロップのフォントや選曲に至るまで、付け入る隙がないほど完璧な「オシャレ」然。今っぽい、洗練されたカメラワークと美しく整ったレイアウト。インサートされる人物紹介VTRやテラスハウス近隣の風景なども、すべてに隙がない。キメキメだ。
そんな見映えのいい空間で披露される、クロちゃんの汚いゲスさというギャップ。カメラの存在をものすごく意識した自意識過剰ぶり。我々はそこを笑う。嗤う。
しかし、ここで重大なことに気づく。もしこれがクロちゃんでなかったとしても、我々が感じる白々しさ、背中がむず痒くなるような感覚、見えすいた茶番感は、ほとんど変わらないということに。つまり『テラスハウス』という番組の作り自体が、じつに白々しく、背中がむず痒くなる、見えすいた茶番に満ちたコンテンツであるということを、『MONSTER HOUSE』はしれっと言い放っていた。
たとえるなら、悪意に満ちた著名人のモノマネだ。あるモノマネのある部分を笑うということは、それを持ち合わせているオリジナルの同じ部分を笑う行為に等しい。たとえモノマネが大きく誇張されたものであったとしても、オリジナルが持つ「おかしさ」や「違和感」の本質は、モノマネ芸として増幅はされても変質はしないからだ(ちなみに『水ダウ』はモノマネ芸人の起用が大好物だ)。
『水ダウ』が本当に弄りたかったのはクロちゃんではなく、『テラスハウス』という番組自体だったのではないか。であるからこそ、『MONSTER HOUSE』は、『テラスハウス』のカメラアングルからカット割り・編集のクセ、画面の色味に至るまで、恐ろしいほど精密にコピーした。ここまで完コピすれば、本家のシミュレーターとして十分機能するからだ。
つまり『MONSTER HOUSE』は、ドキュメンタリーバラエティ(リアリティ番組)として独立的な鑑賞に堪えられるようきっちり成立させながら(1)、クロちゃんの下劣な品性を最高の見世物エンタテインメントに仕立て(2)、『テラスハウス』という人気番組を丁寧に完コピすることで一見してリスペクトを示しながら(3)、実は同番組を悪意たっぷりに弄っている(4)――とも言える。
なんと複雑な構造のコンテンツだろう。しかもだ。(4)は番組側が明示していない。直接手を下していない。気づいた観客だけが勝手にそう感じた、というだけのことだ。本連載第2回で取り上げた『FAKE』同様、ターゲット(『FAKE』では佐村河内守)の嘘っぽさ、胡散臭さ、ニセモノ感、しょっぱさを、これでもかとばかりに記録して本編に組み込み、99%の道筋を作ったところで、最後の判定〝だけ〟を観客に委ねる、巧妙かつ悪質なフィクサーぶり。
製作者が観客に単一の解釈を押し付けない。意図まみれの誘導的な材料は存分に提示するが、判定の責任はまんまと視聴者に負わせる。『水ダウ』のそんな狡猾さも、秀逸なドキュメンタリー譲りである。
「台本はない」
『水ダウ』がここまで巧妙に『テラスハウス』を弄った理由を想像してみたい。
『テラスハウス』は番組冒頭で「台本は一切ございません」とアナウンスするのが通例だったが、それにしては展開がストーリーじみていた。
2020年、『テラスハウス』番組出演者のひとりが自死する事件が起こり、番組は打ち切りとなる。すると「台本はなかったが、ストーリーは制作側で作っていた」「スタッフから出演者への〝指示〟はあった」といった関係者の証言が報じられはじめた。
ドキュメンタリー、あるいはリアリティ番組における「仕込み」や「やらせ」の有無や是非は、常に議論の的となる。「関与型」と断りのついたドキュメンタリーであるにしても、作り手はどこまで前もって「展開」を想定することが許されるのか。それをどの程度被写体に伝えてもよいのか。「台本」の形ならNGだが、口頭の「指示」ならOKなのか。それは「仕込み」や「やらせ」と何が違うのか。線引きはどこにあるのか。
バラエティ番組でありながらドキュメンタリー的な性質を強く内包し、同時に強いお笑い志向ゆえVTRに確実な「オチ」をつけることが義務づけられている『水ダウ』が、その線引きに自覚的でないはずはない。
2018年、まだ何事も起きていなかった『テラスハウス』が、毎回「台本はない」と繰り返すことについて、当時の『水ダウ』の作り手たちは一体何を思ったのか。
次回後編は「やらせ」「仕込み」「台本の存在」やそこに介在する作り手の意図について、再びお笑い系バラエティとドキュメンタリーを横断しながら考察する。
*1 DVD『Tatsuya Mori TV Works~森達也テレビドキュメンタリー集』封入ブックレット
*2 一方で非関与型代表格が、自作を「観察映画」と称する想田和弘(『選挙』『精神』)である
*3 『ドキュメンタリーは嘘をつく』(森達也・著/草思社、2005年)
*4 同前
*5 「創」2002年7月号(創出版)
*6 DVD『Tatsuya Mori TV Works~森達也テレビドキュメンタリー集』封入ブックレット
「水曜日のダウンタウン」DVD第11巻 ©2022 TBS/吉本興業
《ジャーロ NO.85 2022 NOVEMBER 掲載》
▽ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門
▽稲田豊史さん最新刊
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
