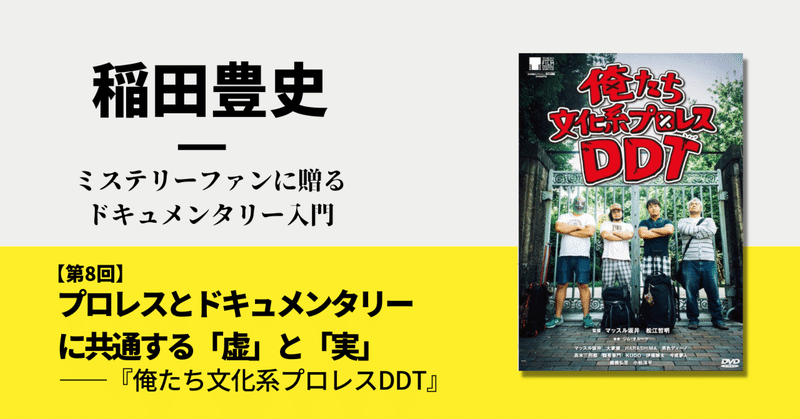
プロレスとドキュメンタリーに共通する「虚」と「実」~『俺たち文化系プロレスDDT』|稲田豊史・ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門【第8回】
文=稲田豊史
『ビヨンド・ザ・マット』の衝撃
プロレスラーたちの普段の顔を追った米国のドキュメンタリー『ビヨンド・ザ・マット』(99年製作)が2001年に日本で公開された際、多少なりともプロレスというものに触れていた者は大きな衝撃を受けた。プロレスが(正確にはWWF〈現・WWE〉を中心としたいくつかのプロレス団体が)筋書きのあるショーであると、〝証拠映像〟と共にはっきりと言い切っていたからだ。
同作は冒頭から「プロレスは基本的に芝居と同じ」「勝敗も暴力シーンもすべて演出されている」というナレーションで始まる。WWFにはドラマのように脚本家がついていてレスラー同士の「因縁」を創作していることや、撮影中に開催された往年の名レスラー、テリー・ファンクの引退試合(1997年、実際にはその後もレスラー活動を継続)の結果を監督が先に聞いていた(全盛期を過ぎたテリーが勝つとファンが疑うので、負けて有終の美を飾ることにしたらしい)ことまでも、作中で明かしていく。
もっとも衝撃的だったのは、当時トップクラスの人気を誇っていたレスラー、ザ・ロック(後にドウェイン・ジョンソンとしてハリウッド俳優デビュー)と、彼の宿敵であるマンカインド(ミック・フォーリー)が、試合前に打ち合わせをしているシーンだ。彼らは隠すこともなくカメラの前で、「スタンドの客席に行け」「ハシゴの下から殴る」「そして客席に上るんだ」「フラフラになってくれ」「俺はこの仕草からエルボーで一撃だ」などと会話する。しかもマンカインドは試合を心配する自分の子どもたちに、「ロックはパパの友達だ。だから本気じゃない。分かったかい? 心配しないで」などと安心させていた。
ミスター高橋のカミングアウト
2023年の今となっては、ある種のプロレス興行が「ショー」であることなど、良識ある大人の間では常識だ。無論、ショー要素と真剣勝負要素の配合比率は〝団体による〟が、「ロープに振ったらわざわざ帰ってくる」「ブレーンバスターなどの投げ技は、投げられる側の〝協力〟なしには成立しえない」ことを少しでも考えれば、オリンピックで披露されるアマチュアレスリング競技などとプロレスが根本的に違うものであるのは自明だろう。
しかし、2001年当時の日本で「プロレスはショーである」は、現在ほど定着した常識ではなかった。
1990年代には、大仁田厚が旗揚げしたフロンティア・マーシャルアーツ・レスリング(FMW)が、「ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ」といった過剰にショーアップされた興行で人気を得ていた。だが、当時二大メジャー団体だった全日本プロレスや新日本プロレスとは一線を画す、あくまで「飛び道具的別枠」の存在だった。
また、ドキュメンタリー監督の森達也が手掛けたTVドキュメンタリー「ミゼットプロレス伝説~小さな巨人たち~」(92年放送)には、小人レスラーたちが試合の「展開」「組み立て」「段取り」を前もって細部まで取り決め、何度も練習している姿が映っているが、同番組内に登場する元女子プロレスラーのマッハ文朱が、ミゼットプロレスを「自分たちのような真剣な試合の合間に、観客に気を緩めてもらう存在」として(好意的に)コメントしていたことからも、筋書きのあるミゼットプロレスはあくまで「特別枠」の余興という扱いだった。
ところが、『ビヨンド・ザ・マット』日本公開から4ヶ月後の2001年12月に、新日本プロレスの元レフェリー、ミスター高橋による書籍『流血の魔術 最強の演技 すべてのプロレスはショーである』が刊行されると、当時のプロレス業界はかなりざわついた。『ビヨンド・ザ・マット』でプロレスは作り物だとWWFが堂々と公言したことに衝撃を受けたという高橋は、新日本プロレスも同様だと同書で〝カミングアウト〟したのである。曰く、「プロレスは最初から勝負が決まっているショー」「映画のように細かくシナリオが決まっているわけではないが、勝ち負けとおおよその流れは決まっている」「一日の全試合について、マッチメイカーはカード編成と勝ち負けを決める」「プロレスは世界最強の芝居」等々。
同書は20万部近くのベストセラーとなり、「ウソだったなんてひどい」「その程度のことはプロレスファンなら薄々感づいていたが、はっきり暴露するのは野暮」「飯を食わせてもらっていた古巣に対する裏切り行為」など様々な反響が寄せられ、業界内外で議論が活発化した。ただし当の新日本プロレスは公式コメントを出さず沈黙を決め込んだ。
浮かび上がった論点は多いが、中でももっとも本質的だったのは「高橋の言う通りだとして、ではプロレスの面白さとは一体どこにあるのか?」であろう。
ここでふと気づく。プロレスの虚構性や価値を論じることと、ドキュメンタリーの虚構性や価値を論じることは、おおむね相似形にあるということに。
プロレスの「アングル」
プロレスの虚構性とドキュメンタリーの虚構性を考えるのにうってつけのドキュメンタリーが『俺たち文化系プロレスDDT』(16年)だ。あまたある国内プロレス団体の中でも特にショー要素、エンタテインメント要素が強い団体「DDTプロレスリング」に密着した作品で、監督は同団体所属のレスラー・マッスル坂井と松江哲明。松江は『あんにょんキムチ』(00)『童貞。をプロデュース』(07)『フラッシュバックメモリーズ 3D』(12)などで知られる、生粋のドキュメンタリー監督である。
本作の軸になっているのは、2015年11月17日に後楽園ホールで行われた試合だ。その試合とは、DDT所属のHARASHIMA&大家健vs新日本プロレス所属の棚橋弘至&小松洋平(現・YOH)のタッグマッチ。この試合が組まれるに至った経緯が、HARASHIMAや大家や坂井のリング外での姿や、これまでのレスラー人生を振り返りつつ描かれる。
冒頭、オープニングタイトルの後に流れるのは試合1ヶ月前の模様。マッスル坂井がマイクで、HARASHIMAと大家健にふさわしい対戦相手をブッキングしてほしいと会社(DDT)に要求する。その対戦相手とは棚橋だ。
実はタッグマッチの3ヶ月前、HARASHIMAは棚橋とのシングルマッチで負けていた。HARASHIMAはDDTのエース。団体のエースが他団体のスター選手に負けたままでは、HARASHIMA個人の想いだけでなく、DDTのプライド的にも収まりがつかない。
ちなみに当時、両団体の規模感や観客動員数には格差があった。現在よりもずっと「新日>DDT」だったのだ。また、棚橋はHARASHIMAに勝利した後、「全団体を横一列で見てもらったら困るんだよ!」と発言し、団体として格が違うと言わんばかりにDDTを挑発した。そういった意味でもDDTは新日に一矢報いたい。それが11月17日のタッグマッチなのだ。
このようなドラマチックな物語性は、プロレス用語で「アングル」と呼ばれる。アングルとは、レスラー同士の因縁やリングの外での抗争にまつわる筋書き、ストーリー展開のこと。ミスター高橋はアングルを「試合を盛り上げたり特定の選手を売り出したりするために、何らかの因縁や経歴などをでっち上げることを言う。でっち上げるというと聞こえが悪いが、つまりは芝居に不可欠な演出にほかならない」(*1)と説明した。
当たり前だが、アングルは自然発生的に出来上がるものではない。WWFに雇われ脚本家が存在したように、「誰か」が物語のシナリオを考えている。
棚橋の所属する新日本プロレスで展開された歴史的に有名なアングルと言えば、「新宿・伊勢丹前事件」であろう。1973年11月5日、アントニオ猪木が妻の倍賞美津子とともに新宿・伊勢丹のビルから出てきたところを、宿敵タイガー・ジェット・シンらが襲ったのだ。
ミスター高橋によれば、このアングルはアントニオ猪木自身がシンの売り出しのために考えたものだという。しかも猪木から協力を依頼されたミスター高橋は、シンとともに現場近くの車で待機していたそうだ(*2)。事件はスポーツ紙のみならず一般紙も書き立て、大きな話題となった。
これほどまでに派手ではないにしても、WWEやDDTに限らずプロレスにアングルはつきものだ。
「見え方」のコントロール
ドキュメンタリーを含む映像作品において「被写体に対するカメラの角度や位置」を表す撮影用語も「アングル」である。
本連載第5回で言及した『さようなら全てのエヴァンゲリオン』での庵野秀明監督は、まだ見たことのない、斬新で面白いアングルを見つけるべく膨大な時間と手間をかけていた。描かれる物語、描かれるシーンが同じでも、アングルが変われば印象はまるで変わる。その重要性を庵野はよくわかっているのだ。
ここでのアングルとは、文字通り対象物の視覚的な「見え方」をコントロールするものだが、プロレスにおけるアングルは印象面での「見え方」をコントロールするものと言えるだろう。
同じレスラー同士による同じ内容の試合だったとしても、その二人に過去の因縁というアングルが設定されているか、いないかで、観客が受ける試合の印象は大きく変わってくる。ちなみにWWEには男性プロレスラーと女性プロレスラーとの恋愛アングルも存在するから面白い。
『俺たち文化系プロレスDDT』のタッグマッチも「HARASHIMAと棚橋の因縁」というアングルがあるかないかで、観客の没入度はまるで違ってくるだろう。だからこそ同ドキュメンタリーは、タッグマッチの試合とHARASHIMAたちの過去が交互に描かれるというサンドイッチ型の構成を採用した。バックストーリーとしてのアングルと、目の前で行われている試合のダイナミズムを、観客のエモーションの部分でシンクロさせるためだ。高校野球の中継で言うなら、イニングの合間に事前収録した厳しい練習風景や家族からの激励の言葉をインサートするようなものである。
アングル解説としての「煽りパワポ」
ところで、DDTのエンタメ性が象徴的に現れているのが、マッスル坂井が覆面レスラー「スーパー・ササダンゴ・マシン」として登場する際、会場でノートPCをプロジェクターにつないで行う「煽りパワポ」と呼ばれるプレゼンテーションだ。「パワポ」とはもちろん、マイクロソフトのプレゼンテーションソフトウェア「パワーポイント」のことである。
一種のマイクパフォーマンスとして行われるこの〝余興〟は、お笑い芸人の「めくり芸」に近いノリ、と言ったら伝わるだろうか。リングコスチュームをまとったマスクの大男が、まるでビジネスマンのように流暢なしゃべりを披露するギャップも含め、「芸」としての完成度は非常に高い。DDTファンにはおなじみのパフォーマンスだ。
「煽りパワポ」では、試合に対する意気込みや今日に至るまでの流れ、論点、試合のポイントなどが冗談じみたスライドを駆使して語られるが、ある意味で「設定されたアングルを観客にわかりやすく言語化・可視化する」という役割も担っている点は興味深い。
『俺たち文化系プロレスDDT』のDVDには、映画の舞台挨拶初日に客前で披露された「煽りパワポ」が特典映像として収録されているが、ここでは本作が「2015年に起きたDDTと新日本プロレスの企業間抗争を軸に構成され」ており、「DDTと新日本プロレスは仲直り」できたかどうかが描かれていると説明される。これは一種の「アングル解説」だ。
世界はそんな単純にはできていない
「虚」か「実」で言えば、アングルという要素は「虚」に違いない。しかしプロレスラーの強靱な肉体や試合で生じる痛みや危険は、紛れもなく本物だ。つまり「実」である。
その虚と実が絶妙なバランスで拮抗し、かつ虚と実の配合比率が絶対に明かされないことから来るドキドキ感自体が、プロレスの魅力であり、かつドキュメンタリーの魅力でもある。
本連載では一貫して、ドキュメンタリーは虚実皮膜であると主張してきた。虚実皮膜とは近松門左衛門が唱えたと言われている芸術論で、事実と虚構の微妙な境界に芸術が成立するというものだ。多くのドキュメンタリストたちがそれに自覚的であることも、過去の連載回(第2回)で述べた。
ドキュメンタリーの虚実にも重なるプロレスの虚実、そこに惹かれたのが森達也だ。森はフリーランスのTVディレクターだった1996年、戦後のアメリカで〝卑怯な日本人レスラー〟として富を築いたグレート東郷についてのドキュメンタリーを企画。実現はしなかったが、その後『悪役レスラーは笑う ―「卑劣なジャップ」グレート東郷―』という本を書き上げている。〝卑怯な日本人レスラー〟という虚構性の高いキャラを演じた人物にドキュメンタリストの森が興味を抱いたのは、実に合点がいく。
森は「相反の共存は、明確な境界で分割されているわけではない。濃淡が入り交じる領域だ。プロレスの凄さは、この虚実の皮膜にある」(*3)と考える立場だが、この「プロレス」を「ドキュメンタリー」に置き換えても、文意に齟齬は生じないだろう。
虚と実の配合比率は、時として被写体(あるいはプロレスラー)自身もわからなくなってしまうらしい。元来は陰キャであるにもかかわらず、教室内での居心地がいいからという理由で全力で陽キャを演じた少年が、「本当の自分」の属性が陰なのか陽なのかわからなくなってしまうかのように。
森はそのあたりを、力道山を引き合いに出してこう言語化する。「力道山は本気でアドレナリンを放出する。ところがその怒りはあくまでも、暗黙のルールの内枠にある。演技であると同時に本気なのだ。明らかな矛盾じゃないかとこれを笑う人には、プロレスの魅力は永遠にわからない」(*4)。ここでも「プロレス」は「ドキュメンタリー」に置き換え可能だ。
さらに森は同書中、取材で会った往年のレスラー、グレート草津(取材当時63歳)に腕相撲を仕掛けて負けるが、草津より10歳以上歳下の森は「僕は本気で腕の力を入れたのだろうか」(*5)と自問する。草津に内心は勝ってほしいと願っていたから、わざと負けたのかもしれないと考えてみるものの、自分でもわからない。そしてこう綴る。
「本気なのかフェイクなのか。それは誰にもわからない。場合によっては本人にすらわからない。結末が決まっているから八百長などと、簡単に言えることじゃない。世界はそんな単純にはできていない」(*6)
そう、世界は単純ではない。だからこそドキュメンタリーは魅力的なのだ。複雑で、あやふやで、不定形なものを、白黒はっきりさせないまま、しかし監督がそこに抱いた割り切れなさもひとつ残らず込めることで、ドキュメンタリーは観客の胸を打つものに仕上がる。きっと、プロレスの試合も同じだ。
ほくそ笑むドキュメンタリストたち
『俺たち文化系プロレスDDT』の結末は、感心するほど「よくできた」代物だ。もしHARASHIMAが棚橋を負かしてしまえば、HARASHIMAのリベンジは成立するが、新日本プロレスを背負う棚橋のメンツが立たない。かといって再び棚橋がHARASHIMAを負かせば、HARASHIMA側の物語に大団円を描くことができない。
では、何が「正解」だったか。
HARASHIMAが、棚橋のタッグパートナーである小松をフォールしたのである。つまり団体としてのDDTは団体としての新日本プロレスに一矢報いた。HARASHIMAも「勝利」はした。しかし棚橋というプロレスラーに土はついていない。スター選手である棚橋個人のメンツは保たれたのだ。
しかも、その先には完璧なオチがついていた。
一旦は退場した棚橋が会場に戻り、なんと坂井のお家芸である「煽りパワポ」を披露したのだ。タイトルは「プロレス界をもっと盛り上げる方法」。団体同士手を取り合って頑張ろうという、前向きかつこれ以上ないプロレス愛に満ちたプレゼンテーション。DDTファンが多くを占める会場の心を宿敵・新日本プロレスの棚橋が一気につかんだのである。タッグチームとしては負けた棚橋だが、最後の最後に美味しいところを全部持って行くとともに、この団体間抗争に美しく終止符を打ったのだ。
その後、カメラは会場外の廊下へ。そこでDDTの社長・高木三四郎は坂井に言う。
「やっぱお前は天才だな」
完璧なアングルの考案者に対する、最大級の称賛だった。
エンドロールを挟み、エピローグ。DDTのレスラーたちは打ち上げの飲み屋へ移動する。高木は満面の笑みで「エゴサーチしながら……思い出しながら……食う飯は美味いね」。そして高木や坂井らが一心不乱にスマホをチェックする画で終わる。ドキュメンタリストたちの「しめしめ」が透けて見えるようなラストカット。仕掛けと恣意、作為の愉悦、会心の「してやったり」。何重もの虚構の上に成立している、超ハイコンテクストなリアル。それがプロレスの妙味なのだと言わんばかりの結びだ。
ところで、共同監督の松江哲明は本作と前後して、TVの深夜帯で『山田孝之の東京都北区赤羽』(15)『山田孝之のカンヌ映画祭』(17)といったシリーズ物のフェイクドキュメンタリー(モキュメンタリー)も手掛けている。
虚実皮膜の産物であるプロレスという題材を、これまた虚実皮膜の産物であるドキュメンタリーの手法で撮った松江は、その同じ手で、凝りに凝ったフェイクドキュメンタリー(これがまた傑作である)を創作した。そのことは、ドキュメンタリーをますます面白く、論じがいのあるものにしてやまない。
*1 『流血の魔術 最強の演技 すべてのプロレスはショーである』(ミスター高橋・著/講談社、2001年)
*2 前掲書
*3『悪役レスラーは笑う―「卑劣なジャップ」グレート東郷―』(森達也・著/岩波書店、2005年)
*4 前掲書
*5 前掲書
*6 前掲書
《ジャーロ NO.87 2023 MARCH 掲載》
俺たち文化系プロレスDDT
2016年/日本 監督:マッスル坂井、松江哲明
©DDTプロレスリング
▽過去の記事はこちらから
▽稲田豊史さん近著
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
