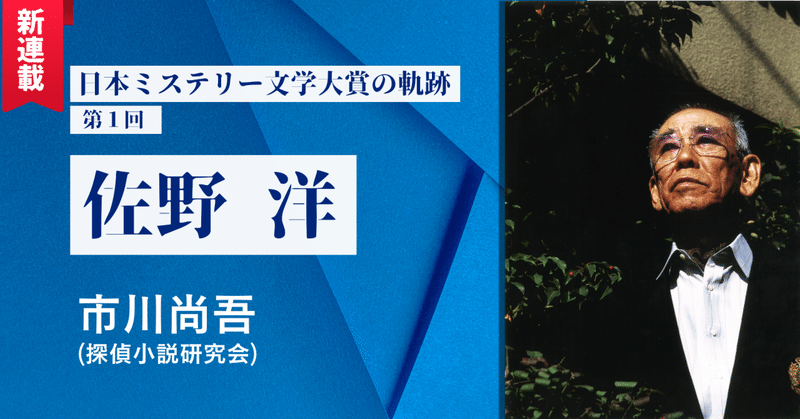
【新連載】日本ミステリー文学大賞の軌跡・第1回 佐野 洋|市川尚吾
日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。
その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、
戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても
過言ではない、錚々たる顔ぶれです。
そこで今回より、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集する新企画をスタートします。
回を追うとともに、日本ミステリー史を辿ることができる企画です!(編集部)
▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》
文=市川尚吾(探偵小説研究会)

日本ミステリー文学大賞は、ミステリー文学の発展のために顕著な功績のあった現役の作家・評論家を顕彰する文学賞として制定され、すでに四半世紀の歴史を持つ。二〇二二年八月の時点で二十五人の受賞者(特別賞も含めれば二十八人)を選出しているが、そのリストの先頭に名を残す、記念すべき第一回の受賞者が、佐野洋だったことは忘れてはならない。
土屋隆夫は選評(贈呈式で配られた小冊子に掲載)で「第一回受賞者に、どういう作家が選ばれるかによって、賞の持つ意義が分明になり、その将来が予見されることになろう」と、初回受賞者の人選の重要性を強調したが、都筑道夫の講評によると「多少の論議のあと、全員一致で、佐野洋氏をえらんだ」という。
土屋と都筑は、選ばれる側の候補に名を連ねていてもおかしくはない存在であったが(実際、第五回に土屋が、第六回に都筑が大賞に選ばれている)、第一回では選考する側に回った。あとの選考委員三氏はジャンルの外部から重鎮を招いている。といっても三氏ともミステリーへの理解があり(五木寛之は江戸川乱歩賞の、小松左京は日本推理作家協会賞の、田辺聖子はサントリーミステリー大賞の選考委員をそれぞれ務めた経験がある)、またジャンル外に身を置いていても仄聞するレベルの顕著な功績が、第一回の受賞者には求められていたと言うこともできよう。その五人が「全員一致で」佐野洋を選んだのだ。
実際、後世の目から見ても、第一回の受賞者には佐野洋ほど適した存在はいなかっただろうと思われる。都筑は受賞の理由として「千編にちかい短編を書いたことも、すごいけれども、作品の質、量だけではない」「日本推理作家協会という団体は、佐野氏が理事長だったときに、近代的なものになった。若い作家諸君は、その恩恵をこうむっている」という二点を挙げている。
ここで佐野洋の略歴を紹介しておこう。
一九二八年(昭和三年)五月二十二日生まれ。本名は丸山一郎。海軍経理学校一年時に終戦を迎えたあと、GHQによる軍関係学校出身者の受験制限のため一年半の浪人生活を強いられる。一九四七年に旧制一高文科丙類に入学。東大では文学部心理学科に進む大岡信、日野啓三らと出会い、同人誌《現代文学》を発行した。一九五三年に大学を卒業し読売新聞社に入社。四年間の札幌支局勤務を経て一九五七年に東京本社に復帰。一九五八年十月、雑誌《週刊朝日》と《宝石》が共催した探偵小説コンテストに応募した短編「銅婚式」が二席に入選。同作が《宝石》に掲載されてデビューを果たす。一九五九年に長編第一作『一本の鉛』を上梓。その他にも長短編を精力的に書き続け、同年十一月に新聞社を辞めて専業作家となった後は、さらに執筆ペースを上げる。一九六〇、六一年の二年だけで長編十一作、短編百編を発表。一九六四年に刊行した『華麗なる醜聞』で第十八回日本推理作家協会賞を受賞。一九七三年から日本推理作家協会理事長を三期六年間務める。一九九七年に第一回日本ミステリー文学大賞受賞。デビュー四十周年を迎えた一九九八年には著した短編の数が千編を超える。二〇〇九年に『推理日記』シリーズで第五十七回菊池寛賞を受賞。二〇一三年(平成二十五年)四月二十七日に肺炎のため死去。享年八十四。
筆名の由来は、勤務先の読売新聞社の知り合い三人から漢字を一字ずつ採ったという説が有力である。というか佐野自身が晩年のエッセイ『ミステリーとの半世紀』(二〇〇九年)で、そのときの奥さんとの会話まで再現しているので決定的に思えるが、ただし最後まで韜晦し続けた可能性は残されている。他に兼業作家としてデビューするにあたり「社の用」もしますという意味を込めた説や、「サノヨイヨイ」から採ったという説もある。後者はただの俗説と思っていたが、集英社文庫版『片翼飛行』の解説で、増田れい子が東大時代を振り返りつつ「私たちは、同人雑誌をはじめることになった。『現代文学』というのである。昭和二十五年の秋――ごろであったろうか。そこではじめて、佐野氏が小説を書くことを私は知った。(中略)筆名もすでに佐野洋といっていた。「サノヨイヨイ」からとったのだ、と彼は笑った。戯作者気取りだった」と証言している。もし増田のこの記憶が正しければ、時系列的に、実は「サノヨイヨイ」こそが本当の由来だったということになる。
佐野の作風は「都会的」「おしゃれ」といった形容をされることが多い。主人公のみならず登場人物の多くが理知的に行動し、品位を失うことが滅多にない点が、そういった清冽な印象に繋がるのだろう。旧来の探偵小説の怪奇性(松本清張言うところの「お化け屋敷の掛け小屋」性)とは正反対の方向を目指していたとも言える。田辺聖子も日本ミステリー文学大賞の選評で「まず第一に推理小説を一部の偏愛読者から解き放ち、汎く社会に浸透させられた点」「殊に女性読者を開拓することについて氏の功績はいちじるしい」と、その作風を評している。
実際に佐野作品を読んでみれば容易にわかるのだが、とにかく文章が簡潔で読みやすい。サスペンスの技巧に秀でていて、長編の場合は冒頭から読者を物語に惹き込んで離さない。初期の長編が軒並み原稿用紙換算で三百枚前後とコンパクトサイズであり、短時間で読めて満足感が残るというそのスタイルが、昭和三十年代の推理小説ブームの立役者の一人に佐野を押し上げたとも言えよう。断定を避け、語尾に「かもしれない」を多用している点が特徴的だと、佐野のデビュー三年目の時点で河上雄三(のちの三好徹)がすでに指摘しているが、そういった文体も、実はかなり理詰めで進む物語の読み心地を、柔らかくときほぐす役割を果たしていただろう。
ただし「都会的」「おしゃれ」といった形容を念頭に置いて、現代の読者が佐野作品を実際に読んでみた場合、作中の男女関係の乱れ具合にいささか驚くかもしれない(それも「進んでる」という意味でなら「都会的」とは言えるのだが)。登場する中年男性の多くは愛人を持ち、若くて魅力的な女性が作中に登場するとかなりの確率で男性主人公と関係を持つ(主人公が妻帯者であってもだ)。しかし書き方に清潔感があるせいか、そういった乱倫性もむしろ「女性読者を開拓」する要素になっていたりする。
郷原宏は終始佐野を「本格派」だと分類しているが、佐野自身は同派をヴァン・ダイン風の型にはまったものと狭く見た上で、初期作品で該当するのは『二人で殺人を』(一九六〇年)だけだと主張していた。一方で「社会派」は社会悪の告発を目的とした作品だから自作は該当しないとも言っている。佐野自身は自作の多くを「巻き込まれ型サスペンス」か「事件小説」のどちらかに分類している。後者は主人公を一人に絞らず、言わば「事件」が主役の小説である。言い換えれば普通の推理小説が「何が起こったか」を軸に話が進むのに対して、事件小説は「これからどうなる」という興味で読者を引っ張るタイプの小説だという。
佐野は大量の原稿を書くかたわら、内外の推理小説を読むこと疎かにしなかった。海外作家ではウィリアム・アイリッシュやアンドリュー・ガーブが自作に近い作風だと感じていた。江戸川乱歩はデビュー短編「銅婚式」をビーストン風と評した。多作でしゃれた作風からフレドリック・ブラウンになぞらえる人も多かった。《宝石》で海外作品レビューを担当していた小林信彦は、担当外であることを承知しつつ佐野の長編デビュー作に触れ「この作者は、ここ数年の間に出た新人の中では、ズバ抜けているようだね。『一本の鉛』が立派なのは、この作家が、探偵小説の面白さというものをよく知っていることだ。本格物の約束をよく承知の上で、わざと型を崩している」「こんな外国式にしゃれたミステリイは、ちょっと無いね」「書き方が凝っていてしかも本格的なのは、ブランドに似ているな」と、クリスチアナ・ブランドを引き合いに出してベタ褒めしていた。
佐野の作風のもうひとつの特徴は、現実性の重視である。佐野にとって推理小説の執筆は一種のゲームであり、作中現実の法律や制度を作家側が自由に設定できたら、執筆が簡単すぎて面白くなくなるので、法律の条文も運用ルールも、警察の捜査等も現実そのままを採用した上で、犯人になりきって費用対効果に見合う犯罪をまずは考えるという創作法が、その作品群からは読み取れる。殺人罪(最高刑は死刑)と過失致死罪(最高刑が罰金刑)の差の大きさは佐野にとっては重要だし、また公職選挙法第一一二条の規定(当選者の死亡が選挙から三ヵ月以内の場合は次点が繰り上がるが、それ以上が経過した場合は補欠選挙が行われる)が、充分に殺人の動機となり得ることを彼は見出している。婚姻届けや離婚届け、住民票から死亡診断書まで、さまざまな書類の現実世界での運用を調べた上で、佐野作品の犯罪者たちは法律の盲点をついて立ち回る。
そうした現実性重視の方針と「推理小説のおもしろさっていうのは、結局、こしらえものの美しさだと、ぼくは思うんです」といった発言は、しかし矛盾するものではない。佐野作品に登場するような犯罪者は、現実世界では滅多に現れない。そこに佐野自身が考える人工性(こしらえものの美しさ)があるのだ。ただし三億円事件やグリコ・森永事件の犯人たちは、佐野の分類では「こしらえもの」側に入るだろう。佐野作品は、一部の(頭のいい)犯罪者にヒントを与えかねない危うさを持っているのだ。だが『第一一二計画』(一九六一年)ではそれを逆手に取り、作中作として佐野洋作の短編をまるごと一編書いた上で、その作品に影響を受けた登場人物を作中で動かすという手法で、自身のそうした作風までをもしゃれのめしている。
プロ野球もので言えば、モデルは容易に想像がつくものの、あくまでも架空の球団名・選手を登場させた『完全試合』(一九六一年)では「こしらえもの」の楽しさが表現できていた一方で、巨人や南海、別所といった実名を使った『10番打者』(一九六二年)では、陰謀論的想像力の領域に足を踏み入れてしまっていた。現実からの距離感の取り方が難しい作風なのだ。
佐野作品には似たモチーフが頻出する。新聞記者を主人公とした作品が多く、扱われる題材も、プロ野球・ゴルフ・競馬・麻雀・折り紙など、自身の趣味と直結したものが多い。作中に現実性をより多く再現するためには、自分が熟知した世界を描くのが手っ取り早いのだ。逆の例をあげると『ひとり、そしてそれだけ』(一九八六年)には「ファミコンのテープ」というワードが出てくる。これはファミコンに詳しくない佐野が「ファミコンのカセット」という言葉を聞いて、カセットといえばテープのことだろうと勘違いした結果、そういった記述がなされたと想像される。その手のミスを防ぐのに、お定まりの舞台、お定まりの道具立てといったものは、佐野の場合、どうしても必要とされたのである。
一方佐野には数は少ないものの、SF設定の作品もある。現実には存在しない奇病などを設定に入れたぶん、いつも以上に面白い作品に仕上げなければならないという意気込みが、空回りする場合もあるが、初期短編「金属音病事件」はそれがうまく決まった作品と言えよう。佐野は短編の名手と言われているが、最終的に一二〇〇編を超える短編を残しており、何を読めばいいかわからないという場合には、とりあえず光文社文庫から出ている『尾行』『盗難車』『最後の夜』の三冊を薦めたい。これは三巻組の《短編一年に一つ×25》シリーズのそれぞれ上中下巻であり、日本推理作家協会が毎年出している「推理小説年鑑」の一九六〇年版から一九八四年版までに収録された二十五編を集めた、いわば他薦代表作集なのである。佐野が「年鑑」に二十五年間連続で選ばれるという、空前の記録を打ち立てたことを記念して刊行されたものだが、佐野はその数字をさらに増やし続け、一九九八年版で途絶えるまで、実に三十八年間連続掲載という、絶後が確実な記録を達成した(そのうち一九八五年版から一九九一年版までの七作を収録した『こわい伝言』も、光文社文庫から刊行されている)。
年鑑収録作から筆者の個人的なオススメを挙げておくと、『尾行』収録の「金属音病事件」と「尾行」、『盗難車』収録の「直線大外強襲」と「猿の証言」、そして『最後の夜』収録の「赤い点が光った」の五編である。
「金属音病事件」(一九六〇年)は主人公の知人が突然、過去の記憶を無限に遡って再生できるようになり、同時に推論力も高まって、いわば超人的名探偵の力を発揮できるようになるが、同時に特定の対象を目にすると脳内に金属音(警戒音)が鳴り響くという症状を呈するところから始まる。金属音の正体は過去の犯罪に由来するものらしく、また同様の症状を持つ女性が現れることにより、事態が紛糾してゆく様が描かれている。一種の特殊設定ミステリーとして、六十年以上経った現在でも通用する魅力に満ちている。
「尾行」(一九六一年)は『I・N・S探偵事務所』の第一話。依頼を受けて主人公たちが尾行していた女が、後日殺人容疑で逮捕される。主人公たちは女のアリバイを証言できるのだが、依頼人はそれを見合わせてほしいと言う。「年鑑」収録時には「読者への挑戦状」も付されていた(連作短編集ではカットされている)本格寄りの秀作。
「直線大外強襲」(一九七一年)は同題の連作短編集に収録された、佐野の競馬ミステリーの第一作。サラブレッドの血統に関する謎が扱われていて、岡嶋二人『焦茶色のパステル』(一九八二年)に先んじること十一年。主人公のベテランジョッキー桐元の人物造形も際立った名品である。
「猿の証言」(一九七二年)は殺人事件の被害者がペットとして猿を飼っていたため、その猿は確実に犯人を目撃しているはずであり、どうにかして証言させられないかと考えた警察がひねり出したアイデアに独創性がある。こうした思考実験の類を作中で重んじる傾向は、佐野が大学時代に心理学を専攻したことも関係しているのだろう。
「赤い点が光った」(一九七四年)は小説誌のグラビアで、作家が趣味に興じている姿を紹介しようということで、ある作家がラジコン飛行機の操縦をしている様を取材していたさなかに起きた事件を扱っている。佐野洋の目指していた「構築美」の完成形であり、個人的に佐野短編のベストだと思っている。
連作短編集では上記で名前の挙がった『I・N・S探偵事務所』(一九六三年)『直線大外強襲』(一九七一年)の他に、『密会の宿』(一九六四年)が意外と粒揃いでオススメである。長編第二作『高すぎた代償』(一九五九年)で一度使い切った基本設定を再利用して、連れ込み宿の女将とその情夫が、頼まれてもいないのに探偵気取りでいろいろ調べるという短編を、適度に変化をつけて並べたものである。八十年代に二時間サスペンス枠で映像化された際に、シリーズ続編が三冊分書き足されたが、初期に書かれたこの一巻がやはり飛びぬけて良い。サスペンスドラマの原作といって侮ることなかれである。
さて、先に紹介した都筑の講評にあった「作品の質、量だけではない」という言葉の重みを、ここで改めて噛みしめたい。その「質」(一九九七年の受賞時点で「年鑑」に三十八年連続で選ばれている)と「量」(同時点で約一〇〇〇編、最終的に一二〇〇編を超える短編が書かれたこと)の物凄さは、誰にも真似できないだろう。しかもそれ「だけではない」のだ。佐野が理事長を務めていたときに日本推理作家協会が「近代的なものになった」というのは、具体的には「年鑑」の文庫化という事業を起こしたことで、協会の財政が健全化したことが筆頭に挙げられよう。また協会賞が部門別に分けられ今日に至るのも、佐野が理事長時代に発案して制度化されたおかげである。そもそも佐野は一九六三年(デビューわずか五年目)に協会が社団法人化したタイミングで常任理事の一人になり、早期から内規作りなど会の運営に参加していた。その手腕が理事長となったのを契機に実を結んだのである。
都筑の挙げた二点に追加するとしたら、『推理日記』シリーズを通じて、作家や編集者たちの質的向上をもたらした点も、日本のミステリー文学に与えた大きな功績として認められるべきであろう。一九七三年から雑誌連載がスタートしたミステリー評論・時評(ときどきエッセイ)を書籍化したもので、日本ミステリー文学大賞を受賞した段階で単行本が八冊も刊行されていた(最終的に亡くなる前年、二〇一二年に全十二巻で完結)。ちなみに先行する評論活動として一九六三年に「ミステリー如是我聞」を雑誌に一年間連載していたことも、佐野の作家活動を振り返ったときには重要になる(「如是我聞」連載を経て作品の質が向上した)ので忘れずにいたい(その「如是我聞」は潮出版社版の『推理日記』第一巻に収録されていたが、講談社文庫版では残念ながら割愛された)。
『推理日記』では「名探偵論争」が有名である。名探偵(シリーズ探偵)を用いると作品がマンネリ化する点、思い付いたアイデアを常に既存のシリーズに当てはめるのが最適とは思えない点などを挙げ、都筑道夫を相手どって論争を仕掛けたのだが、これは都筑を信頼して(小説も評論も著している仲間として)互いの主張を明らかにすることでミステリー界を活性化しようという試みであった。論争は主に一九七八年に行われたが、当時は横溝正史ブームの真っただ中であり、金田一耕助という日本を代表するシリーズ探偵に若い読者が熱狂しているさなかであったこと、またTVドラマの「刑事コロンボ」が多くの視聴者を虜にしていたことは、特記しておくべきだろう。それらが佐野の目には、旧来型の探偵小説の復権に見えていただろうし、自分の作風や、あるいは初期の都筑の作風のような自由な創作を、もっと多くの推理作家に目指してほしいという願いも込められていただろう。佐野は都筑の初期の長編群(単発作品ばかりで、すべてが旧来の型を意識して避けた創意工夫に溢れたものだった)を高く評価していたのだ。
ちなみに『推理日記』の影響を受けたのは、同時代に活躍した作家だけではない。多くのミステリー読者が読むことによって、読者側の鑑賞眼までをも引き上げた結果、後世の作家にとっても『推理日記』で取り上げられた論点の一部は、地雷のような役割を果たすまでになった(視点のブレなどもそうだし、単純な例でいえば「嘔吐物」と「吐瀉物」の違いなどもそうである)。佐野洋が批評レベルを引き上げたミステリー読者の一部は、新人作家のそういったミスを見逃さない。結果、『推理日記』は(現在ではさすがにその効力は薄れているであろうが、少なくともある時期までは)ミステリー作家の卵にとって、必読の書とされていたのである。そこまで考えると、ミステリー界全体の質的向上に果たしたその役割は、想像以上に大きなものがあったはずなのだ。
最後に佐野洋の長編群からオススメの作品を、紙幅の許すかぎり挙げてゆきたい。現代読者へのオススメという視点からより現代に近い、千街晶之監修『本格ミステリ・フラッシュバック』(二〇〇八年)で取り上げられた作品を(本格寄りのセレクションになるが)まずは確認してみよう。
1『一本の鉛』(一九五九年)
2『二人で殺人を』(一九六〇年)
3『第六実験室』(一九六一年)
4『重要関係者』(一九六二年)の特に「密室の裏切り」
5『赤い熱い海』(一九六七年)
6『轢き逃げ』(一九七〇年)
7『七色の密室』(一九七七年)
8『ひとり、そしてそれだけ』(一九八六年)
妥当な選択と言えるのではないか。1と6は一九八五年版『東西ミステリーベスト100』に選出されており、昔から佐野洋の代表作として定評があった(雑誌《幻影城》一九七八年6・7月合併号掲載の「日本長編推理小説ベスト99」では1と6に加えて『透明受胎』が選ばれていた)。5も間違いのない傑作。3は個人的に同年(一九六一年)刊だと『秘密パーティ』のほうが好みなので差し替えても良いと思う。4と7は『大密室』(ハルキ文庫版限定。他の版元から出ている『大密室』は中身が別物なので要注意)に一本化できる。8はアイデアの一部が同じ『金色の喪章』(一九六四年)のほうを個人的には高く評価している。
『一本の鉛』は女性専用アパートで起きた殺人事件が扱われている。内側から施錠された密室内で被害者と一緒に発見された男子大学生がいたので、当然のように別件逮捕されて取り調べを受けている。しかし事件には多くの謎があった。先述したように小林信彦も絶賛した佐野の長編デビュー作。まずはこれを読むべき。
『轢き逃げ』は人身事故を起こした犯人側の偽装工作を倒叙形式で描く第一部と、殺人犯を突き止める第二部の二段構えの構成が何より秀逸。内容も分量も、佐野洋の初期作と比べて二冊分の厚みがある。
『秘密パーティ』は県会議員五人が休日の料亭の一室を借り切り、ホステス等女性五人を集めて、秘密のパーティを開いていたところ、飛び入り参加の女性が毒死するという事件が発生する。ビデオのない時代であり、個人撮影のいかがわしいフィルムを映写機で上映するために、部屋を暗くしていたので、誰がどこにいたかがわからない。すわクローズドサークルものの本格ミステリーかと勇み立つところだが、しかし誰が毒を入れたのかという展開にはならない。県会議員の一人が開業医だったので死亡診断書を作成して病死扱いにしてしまう。ホステスの一人が恐喝を思いつく。という感じで本格好きの読者ほど、その独自の展開に驚くだろう。
『金色の喪章』は羽田空港の駐車場に停められた車のトランクから女性の死体が転がり出る場面がまずは目を惹く。そのトランクが一種の密室となり、車のキーを持っていた主人公が容疑者扱いされる。神奈川県で監察医をしている主人公は警察とのコネを使って、辛くも疑いを晴らす。登場人物が少ないため真相の見当はつくだろうが、主人公に変わった属性を付与した効果なのか、最後の一ページまで異様な雰囲気を保持したまま話が進む点が面白い。鮮やかなトリックが印象に残る良作である。
ちなみに上記のあらすじを見て、某芸能人が起こした殺人事件をモデルにしたと勘違いされる読者がいるかもしれないが、羽田空港の駐車場に停めた車のトランクから女性の死体が発見された事件は、現実世界では一九七六年に発生している。つまり佐野は十年以上前にすでに同事件をモデルにしたかのような小説を書いていたのだ。それがなければ、芸能人が殺人を犯すというセンセーショナルな事件は彼の興味を惹き、その後の小説の中に何らかの形で取り込まれていた可能性がある。あるいは『美しい死刑』(一九七八年)の冒頭で、車のトランクから犬の死骸が発見される場面が出てくるのが、単に『金色の喪章』との関連だけではなく、その二作の間に現実世界で起きた事件が影響を及ぼしたという指摘は、できるのかもしれない。
キーラー嬢事件や草加次郎事件(ともに端緒となる事件は一九六二年に発生)と『華麗なる醜聞』(一九六四年)刊行までの期間や、三億円事件という世間の耳目を集めた事件が一九六八年に起きた後、同事件を題材にした短編を佐野が集中的に著して『小説三億円事件』(一九七〇年)としてまとめるまでに要した期間が、ともに約二年間である点が、傍証として挙げられよう。
ちなみに日本推理作家協会賞を受賞した『華麗なる醜聞』も代表作のひとつとされてきたが、個人的にはあまり評価していない。佐野洋作品がそれまで扱ってこなかった「巨悪」を作中に取り入れ、スケールの大きな話を書いたということで、一皮むけたという意味で評価された作品なのだろうが、現代の読者が読む積極的な意味が見いだせないのだ。佐野洋自身も、一九六四年に発表された塔晶夫『虚無への供物』を(自作とは正反対の指向性を持つのに、あるいはだからこそ)高く評価しており(受賞後に評判を聞いて読んだという)、同作が最終候補に残らなかった結果、自分が受賞したという点に割り切れない思いは抱いていたのだろう。佐野が札幌支局に在籍していた時に洞爺丸の沈没事故が起きており、佐野は取材のため函館に行っているのだ。自分が取材した事件がこういう形で扱われている、という意味でも『虚無』は特別な作品に思えただろう。一九七二年に刊行が開始された講談社の現代推理小説大系の作品選定には佐野洋も関わっていたはずだが、別巻1に『虚無への供物』(名義は塔晶夫から中井英夫に変わっていたが)を収録したのは、何よりも私利を嫌い公正でありたいという佐野の姿勢が反映しているように思う。
佐野が『虚無への供物』を読んだ翌年(一九六六年)、古巣の読売新聞社で松本清張監修による新本格推理小説全集の企画がスタートする。佐野は『赤い熱い海』を執筆した(刊行は一九六七年の一月になった)。同作では津軽海峡上空を飛行中の旅客機内で火事が起き、函館沖の海上に不時着した機はやがて沈没する。救命具をつけた乗客の多くは救助されるが、溺死する乗客も現れる。という冒頭から話が始まるのだが、船と飛行機の違いこそあれ、函館沖での遭難という点に洞爺丸の影を、つまり『虚無』からの反響を見出すことができる。古巣の企画だということのみならず、『虚無』を差し置いて日本推理作家協会賞を受賞したことの重荷を、この新作で下ろしたい(もし『華麗なる醜聞』で協会賞を受賞していなかったら、この作品で受賞していたであろうと言われるような作品を書きたい)という意思を、個人的に『赤い熱い海』からは感じるのだ。
『華麗なる醜聞』とは逆に『貞操試験』(一九六〇年)は、今だからこそ読む価値のある作品と言えよう。地方都市の富豪が二十代の男女五人を集めて、自分の財産の十分の九を贈与するという。税金などを差し引いても二億円(六十年前の貨幣価値で)は受け取ることになるだろう。条件は三つ。現在付き合っている恋人と一週間以内に別れること。その後一年間恋愛をしないこと。市内に居続けること。自分は恋愛をせず事業に専念して巨万の富を築いた。余生で使い切れないお金を同じ価値観を持つ若者に譲りたいのだ。条件をクリアした人物が二人以上いたら延長戦になるという。そこで彼らはお互いをライバルとして蹴落とそうとする。昔だったら遺産相続ものの変奏として読まれたのだろうが、現代の読者は浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』(二〇二一年)の(六十年以上前に書かれた)遠い祖先として読むことで、よりいっそう楽しめるのではないだろうか。
『光の肌』(一九六四年)はAとBの二つの筋が交互に描かれてゆく構成が特徴的である。Aでは晴海埠頭で海中に沈んでいた車が引き上げられ、その所有者の女性が行方不明になっていることが判明する。Bではその女性がある会社に雇われ、車を与えられるまでの過程を描く。現在と過去が交錯するような、B・S・バリンジャーの構成を真似した作品はいろいろな人が書いているが、これは最良の一作であろう。
そして『死んだ時間』(一九六三年)は、個人的に佐野洋の長編のベストだと思っている。無給医の主人公が付き合っている料亭の女中が、デートの約束をすっぽかし、その後殺人犯として逮捕される。無実だと信じる主人公が調べるうちに、アリバイを証言する男が現れる。だが彼女はなぜか自分が犯人だと言い張るのだった。佐野洋自身が『推理日記』でいろいろな男と寝る女を「万能接着剤」呼ばわりし、プロット作りが楽になるけど安易に使いすぎないほうがいいと批判的に取り扱っていたが、まさにそういう女性が出てくる作品である。でもそれが気にならない。二段構えの真相の、一段目がまずは鮮やかである。そして二段目の真相を経て、すべてが主人公の決断へとのしかかる幕切れが何より最高。作り込まれた逸品である。電子書籍でも出ているので、機会があれば読んでいただきたい。
あっと。光文社文庫の『尾行』『盗難車』『最後の夜』も電子書籍で出ています。よろしく。
(第1回 おわり)
《ジャーロ No.84 2022 SEPTEMBER 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
