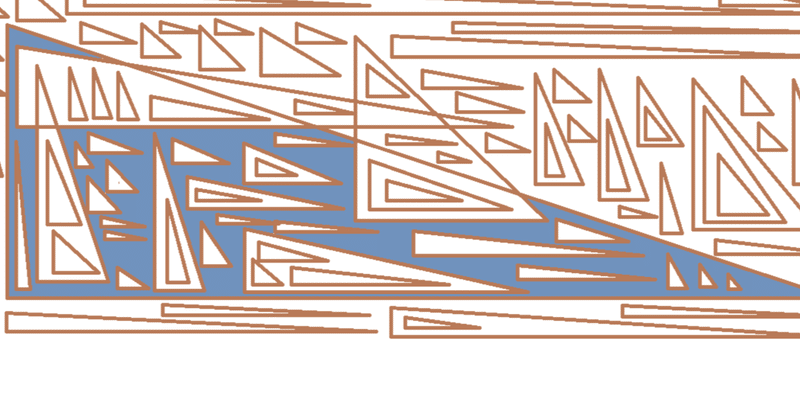
小説 「カポック」
ぼくとチチが、いま借りて住んでいる家には塀がない。どの温泉町でもそうなのだろうか、この別府では土地に余裕がある家が少ない。特に、細い路地に向かい合って建物が密集しているこのあたりでは、どこも狭い敷地いっぱいに建てられている。
小さいながらも造りのいい2階建て木造家屋なのだが、建物がそのまま外に向かって剥き出しな感じがするのは、ぼくにはとても気恥ずかしい。生活の場が、そのまま外の世界に続いていることに、ぼくは慣れていないのだ。これまでに住んだのはアパートで、それも、2階より上ばかりだった。
そして、ぼくの生きてきた18年間の100パーセントに近い時間を、ぼくは家の中ばかりで過ごしてきた。
ぼくはいまの家に越して来てすぐに、2鉢のカポックを、玄関の前に置いた。これを、ぼくと外界と隔てる境界線にしようと、自分で勝手に決めたのだ。
今年も今日、居間から、大きく育ったカポックを引っ張り出した。冬の間は、南に向いた屋内に避難させていたのだ。ここ数日、春の暖かさが続いている。これなら、ツヤツヤした葉っぱがやられることもないだろう。
この2鉢のカポックは、ぼくが大阪からこの町に持ってきたものだ。着の身着のままの出立だったが、チチは、カポックを両手にぶら下げたぼくにチラリと目をやっただけで、特にとがめることはしなかった。
カポックを家の前に置くということは、ぼくが住んでいることを示すマーキングでもある。こんな標(しるし)でも付けておかないと、自分がこの世の、この家で生きているということさえ、忘れてしまいそうになるからだ。
カポックを置いているのは、この家だけではない。挿し木をして殖えた分を、ぼくの気に入ったところに置いている。そこは、ぼくが緊張せずに身を置くことができる場所を意味する。ヨシエさんやミサコさんも、「カポックがドンドン増えて、マー君の生活の場が広がていくといいわねえ」と言ってくれている。
この5、6年のぼくの楽しみといったら、カポックを形よく育てることだった。葉っぱをきれいに水拭きしたり、剪定した枝をほかの植木鉢に挿したり。ぼくの心が一番安まるときだ。
何しろカポックに出合うまでは、ビデオで映画を観ることが、ぼくの自由な時間のほとんどだった。ぼくに、善いことと悪いこと、やってはならないことや、やらなければならないことを教えてくれたのは、映画の登場人物たちだった。ぼくは、価値観も倫理観も、親からも友だちからも教わらなかった。もちろん、学校からもだ。
家庭や学校の痕跡が薄い分、ぼくのことを、太陽の光が当たらないモヤシのように思われがちだが、生き抜くしたたかさは人一倍あると自負している。ただ、世の中の規範とぼくのそれには、かなりのズレがある。
ぼくが子どものころ、踏み台に乗って台所に立ち、料理本を片手に食事を作ったのは、料理が好きだとか、嫌いだとかではなく、チチに食べてもらいたかったからだ。何にしろ、チチはおいしいものが好きだから。
カポックと出合ったのは大阪だった。四天王寺に向かって右に左に、数え切れないほどのお寺が並ぶ道筋に、突如ラブホテルが群がっている一角があって、その一軒のホテルの入り口にそのカポックはあった。たった一本の鉢植えのカポックは、建物の中と外をさえぎってしまうほどに枝を茂らせて立っていた。
「チチが帰ってくる」、「チチは帰ってこない」
ぼくは呪文のように唱えながら、チチと女がいるはずのホテルの前で、カポックの葉の一枚を引っ張った。その葉がポロリと折れてしまえば、「帰ってこない」の方だった。葉は意外に強く、枝を傾げながらぼくの方に折れ曲がった。3日後に、チチは戻ってきた。
帰って来た夕飯に、12歳だったぼくは、チチの好物のビーフカツとチキンスープを作った。ポテトサラダも添えた。そして、翌日、ぼくはあのホテルからカポックの1枝を失敬し、冷蔵庫の上で育てた。
カポックの葉を使っての「あれか、これか占い」を、ぼくはときどきやる。もちろん、ぼくの指先は、ぼくの望む方を選ぶ。最近では、ミサコさんのことを占った。
この町に来て3年、カポックはぐんぐんと丈を伸ばし、ぼくの背の高さほどになった。そろそろ植え替えてやらなくてはかわいそうだ。鉢の中では、ウミヘビの冬眠のようにからまり合って、根をほぐすのにずいぶんと時間が掛かるにちがいない。
午後7時25分。ぼくは数日のうちに落ちてしまうかもしれない黄ばんだカポックの葉に目をやりながら、チチの帰りを待っている。シャンプーやボディーソープの入った洗面器を2つ重ねて両手で持ち、首にはふたり分のタオル類を巻き付けている。
チチは、よほどのことがないかぎり、ぼくが見当を付けた時間に帰ってくる。その誤差、10分程度。長年、チチの一挙手一投足を気にしながら暮らしてきたせいで、チチの行動を読み取るのがうまくなった。
その日、チチが職場の人たちとうまくやれたかどうかだって、顔を見ただけで、おおよその察しがつく。無表情で無口なチチを見て、「ニワさんって、喜怒哀楽があるのかね」などと評する人もいるが、チチはぼくの前では、ひょうきんだったり、おしゃべりだったりする。
ところが、ぼくはチチのことを、ほとんど知らない。どこで生まれ、どういう育ち方をしたのか、チチは一切口にしない。だから、ぼくが知っているのは、「ぼくが接してきた範囲の」という、限定されたチチだ。
それほどたいした金額ではないが、チチは毎月、ぼくに決まった額のお金を渡してくれる。ぼくはそれを家事に必要なものの購入に当てる。しかし、そのお金を、どこでどう稼いでいるのか、ぼくは尋ねたことがない。尋ねたとしても、せいぜい「そんなこと、どうだっていいことですよ」という返答が返ってくるだけだろう。
チチは風のような人だ、とぼくは思う。普通は吹いていることさえ気が付かないのだが、突然強風に変わってぼくを驚かせる。風の中心に、女がいたことが3度、競馬やパチンコの賭け事だったことは無数。
吹き荒れて何もかもをすっかり失ってしまうと、もうそこには住めなくて、どこかへ移って行く。そんなときでも、顔色ひとつ変えない。40歳の精神世界の一部は、太古の狩猟民族のころで停止しているところがある。どこかに居付いて、大過なく生活することをチチに求めるのは、絶対に無理なことかもしれない。
だから、息子のぼくは、チチの不始末による一方的な理由だけで、東京、岡山、高松、大阪、そしてここ別府と、五度の転居をした。
チチの車が、ノロノロと坂を登って来た。ぼくの前を通り過ぎて停車し、左いっぱいにハンドルを切りながら、ソロソロとバックする。普通車がやっと離合できる程度の道路と直角に、車一台ギリギリのスペース。チチは、切り返しなしのハンドル操作で車を納めると、その夜はとても機嫌がいい。何でも、男の美学だそうだ。
3分の1ほどしか開けられない運転席のドアから、187センチ、90キロの巨体をねじ曲げながら姿を現す。
「来てるのですね」
チチは明かりが灯っている2階を見やった後、ぼくにうなずいた。ぼくは、それに応えずに、「じゃあ、行きましょうか」と、道路に踏み出した。
「ヨシエさんがいるのじゃ、今日はマー君、2階の部屋から、暮れていく鶴見岳を見られなかったわけだ。この町で、一番好きな景色だと言ってたのにね。残念でした」
たしかに、、この家に越してきたばかりのころは、鶴見岳をオレンジ色に染めながら姿を消していく夕陽を眺めるのが大好きだった。
ぼくたちが借りているのはこの家の1階だけで、二階には近寄らないという約束が、家主であるミサコさんと交わされていた。だから仏壇のある2階の和室には、ミサコさんか、ミサコさんの母親であるヨシエさんが1週間に1度、雨戸を開けて空気を入れ換えるか、だれかの命日などでお坊さんを伴ってくるとき以外は、立ち入らないことになっている。ぼくがあの部屋から、顔ひとつ分に雨戸を開けて鶴見岳を眺めたのは、あくまでも内緒のことであった。
実を言うと、いまのぼくは、道の向かい側の荘園(そうえん)病院の屋上から、夜景に変わっていく別府湾を見る方が好きなのだ。ネオンの色が濃くなって、昼間の素顔から気取った夜の顔に移ろう街の風情は見飽きない。
ついでに言っておくと、ぼくは別府の人たちをとても気に入っている。だれもがよそ者に見えるところだ。喧(かまびす)しく天下国家を論じる割に、自分勝手に生きている。だれに対しても、ここに住む条件などを強要しない。
うちの玄関からぼくの歩幅で結構急な坂道をちょうど百歩下ると、県道に出る。この町では、ほとんどの道が山に向かう上り坂、逆にいえば海への下り坂になっているのだが、この県道は町を南北に横断するめずらしく平坦な道だ。
町の人たちが鉄輪(かんなわ)線とか旧道と呼ぶこの通りの風情は、ぼくがこれまで住んでいたどこの町にもあったような気がする。例えば坂を下って右に曲がると、刺身パックの横に白菜漬けが並んだ魚屋、手作りハンバーグがウリの肉屋、それにミサコさんの経営する洋食屋など、間口2間ほどの店が並ぶ。隣はガラス戸を黒く覆ったマッサージ店。その向こうはクリーニング店。
だからであろうか、ぼくは初めてこの通りに立ったとき、母の胸の中にいるような感触がしたのだ。
ぼくには、この温泉町は、後にそびえる休火山の鶴見岳が胡座(あぐら)をかき、別府湾の海水をすくい取っているように見える。そう考えると、海に添ってホテルや商業施設が並ぶ国道あたりは腹部で、このあたりはふくよかな胸のあたりということになる。ぼくの頭の中を一瞬、ミサコさんの形のよい胸のふくらみがよぎった。
「マー君。何かいいことでもありましたか。口許がほころんでますよ」
県道の縁に立って、右と左からやってくる車をやり過ごしていたぼくの顔を、巨体を傾けながら、人差し指をぼくの口許に当て、チチがのぞき込んできた。足許の巨大なチチの影が、160センチ、ウエスト68センチのぼくの影をたちまちのみ込んだ。
こういうひょうきんなチチを、ぼくは見たくない。風向きは定まらなくとも、ぼくを吹き抜けていくようなチチの方が好きだ。ぼくは素知らぬ顔を続けた。そして、チチから1、2歩離れると、去年の秋、カポックの葉を眺めていて気が付いたことを口にした。
「ぼくの家のカポックと、下の家のカポックの葉の痛み具合がずいぶんとちがうんですよね。この道を隔てて、こちら側とあちら側では、気温とか、空気の澄み具合とか、かなりちがうように思えるのですが、そんなことってありますかね」
チチは、ぼくの言っている意味が分からないらしい。怪訝な表情で道の向かい側を指差しているぼくを見返すと、「別府の冬は寒いですからねえ」とつぶやいた。
「境界ってやつかもしれません」と、ぼくはチチにかまわず、言った。「ほら、何にでもあるじゃないですか、境目というか、分かれ目というか、こちらから見ても、あちらから見ても端っこに当たるところ」
「そういえば、いまのマー君は、そんなところにいるのかな。おとなと子どものちょうど中間点だけど、ちょっとおとな寄り」
そうか、チチと話すとこういう展開になるのか、それにしても、ぼくの言いたいことを見透かしているのだろうかと、ぼくは睨み返そうとした。そういうぼくの前には、顔中のパーツを真ん中に集めた笑顔があった。
「でも、境界線なんて無理に引かない方が気楽ですよ。何か、あっちとこっちが一緒になって、混沌とした世界もいいじゃないですか。それに……」と、まだ言い足しそうになったが、それは口に出さず、話題を変えてきた。
「あっ。そうだ。今日は入試の合格発表の日だったんですね。帰ったら真っ先に聞こうと、朝には考えていたんですが、これじゃ父親の役目はつとまりませんね。で、高校から連絡がありましたか」
チチに父親の資格があるのか、ないのか。この人に父親であってほしいのか、ほしくないのか、そのあたりのことが、ぼくには分からない。
言えるのは、ぼくがチチに見捨てられると、面倒なことになるということだ。施設に入るのも億劫(おっくう)だし、役所の人に顛末(てんまつ)を説明するのも鬱陶(うっとう)しい。これまで、その寸前までいったことが2度、一時的にだが、施設に収容されたこともある。
「ネットで、高校のホームページに、昼ごろ」
ぼくたちは、車が途切れたところで道を渡った。荘園病院の横の、やっと車が通れるほどの路地を下って行く。
「で、受かりましたか」
「定時制ですから。落ちる人なんかいないのですから」「学力はともかく、マー君、中学二年の終わりから学校に行ってなかったからね、その辺をちょっと心配していたのですよ」
チチが知らないだけで、それまでだって、たいして学校に通っていたわけではない。特に、ぼくが炊事やら洗濯、掃除の家事ができるようになって、連続して学校に通ったという記憶がない。家事の合間に顔をのぞかせた、という程度だ。
学校は、時たま訪れる方がいい。どこの学校の先生もうれしそうな声で迎えてくれたし、ほとんど名前の知らないクラスメートだって歓迎してくれる。
それ以上付き合うと、ぼくがテレビも観ない、ゲームもしない、流行(はやり)の歌も知らない子で、家事にいそしみ、ビデオ映画ばかり観ている奇っ怪なヤツだってことがばれてしまう。フェリーニの『カリビアの夜』をボーボーと涙を落としながら観たなんてことが分かったら、彼らにいじめの口実を与えることになる。
「ぼく、決めましたよ。昼間は、『いおり』で働くことにします。今日、ミサコさんにお願いするつもりです」 チチには、ちょっと唐突すぎたかなとも思ったが、よどみなく言えたと、とりあえずホッとした。何にしろ、ぼくは自分の生き方を、初めてチチに表明するのだ。
「昼働いて、夜に勉強。これまでの生活が180度変わりますね」
それに加えて、家事までこなせますか、チチの言葉は言外にそう告げていた。
ぼくにとっては、今や、できるかどうか、ではなく、やるのだ、という決意が固かった。それは、もうひとつのクリアしなければならないことと関連があるのだ。このことは風呂に入りながらチチに話そう、と考えた。
県道から250歩下っていくと、ぼくたちが下の家と呼ぶ平屋のアパートに着く。この建物もほとんど敷地いっぱいに建てられている。不動産屋の張り紙風に表現すると、「1K・トイレ付き、風呂は共同(温泉)」ということになるのだろうか。そういう部屋が四室並んでいる。
この建物も所有者はミサコさん母子。ただし、こちらはヨシエさんの名義になっているらしい。
一番手前が、ぼくたちも毎晩利用させてもらっている風呂で、おとなが5、6人も入れるほどの湯船がある温泉だ。ぼくたちは、入り口に掛かっていた木札を「入浴中」にして、脱衣所に入った。
実は、ぼくはここの風呂はあまり好きではない。というのも、贅沢(ぜいたく)なことかもしれないが、こんこんとわき出る温泉で、いつも熱すぎるからだ。ぼくはざっと浸かると、「背中を流しますよ」と、心地よさげに首までどっぷりのチチを促した。
固太りの背中が、ぼくの目の前に現れた。ぼくは、ボディーソープを泡立てたタオルを背中に当て、いつものように首筋あたりから円を描くようにこすり始めた。日ごろから何事につけ、余計な手出しを嫌うチチが、自分からぼくに望んだただひとつのことが、背中を流すことだった。そのたびにチチは、「最高の贅沢です」と言った。
いまがチャンスだと、ぼくは思った。
「ミサコさんのことなんですが……」
ぼくの声は少し震えていた。ぼくからチチに願い事をすることなんて、これまでにほとんどなかったから、やむ得ないことかもしれない。
「ミサコさんが、どうかしましたか」
そのとき、アパートの住人のひとり、ヤスオカさんが勢いよく入ってきた。ヤスオカさんとはミサコさんの洋食屋『いおり』でもときどき顔を合わせるので、見知っている。そのほかのアパートの住人には、風呂でも会ったことがない。
「息子が親父の背中を流すなんて、いい絵だねえ」
ヤスオカさんは、湯船のお湯を豪快に頭からかぶると、
70歳を越えているとは思えないすばやい身のこなしで肋骨の浮き出た体を湯船に沈めた。
「聞いたかい。おいらっちの隣の男の話」
ヤスオカさんは江戸っ子だと、ぼくは勝手に推測している。わずかに残るぼくの東京の記憶からくる、勘だ。
「いきなりのことだよ、制服、私服の警察官がやって来てさ、隣の2号室のヤツの、出身地だとか、暮らしぶりだとかさ、訊いてくるじゃねえか。おいらが4年前に住みついたときには、ヤツはすでにここの住人だったが、何かさあ、ひっそりと身を隠してるって感じで、名前だって知らねえやな」
「はあ、そういえば、ぼくたちもお目に掛かったこと、一度もありませんねえ」
ヤスオカさんの話に、ぼくが応じた。チチは、手のゆるんだぼくに、もう少し強くこすれというふうに振り返った。チチは関心がないことには口を出さない。
「だろう。時たま『いおり』のおかあちゃんが声をかけていたことは、おいらも知ってるけどさ。ここじゃあ、住人同士はおたがいに不干渉、つまりおたがいの領分は侵さない、ってことでやってるんだ。だから、安穏、剣呑(けんのん)、観音様さ。いくらそう言っても、ケイサツのミナサンは聞くもんじゃねえ。まあ、変死かも知れねえってんだから、分からなくもないが……」
「変死って、亡くなったんですか、ヤスオカさんのお隣さん」
「らしいのさ。三号室の若い衆が昨夜(ゆうべ)うなり声を聞いてさ、気になって、朝になってのぞいてみたら、眼をひん剥いて、おっかねえ形相でおっちんでたというこった。こちとら、まったく知らずに、焼酎かっ食らっての白河夜船だわさ」
縁(ふち)に腰を軽く掛けると、ヤスオカさんは上目づかいになり声をおとした。
「詳しいことは教えちゃくれねえが、苦悶の表情、部屋の荒れ具合から、事件かも知れねえってことで、警察がヤツのことを調べ始めたわけよ。すると、どうやら、入居するときに、『いおり』のおかあちゃんに告げていた名前も偽名でさ。でもって、身元も何もまるっきり分からねえらしい。そこで、死んだのは一体誰なんじゃ、というややこしい話になった……」
ヤスオカさんはヨシエさんのことを、「おかあちゃん」と呼んだ。いつだったか、ぼくは、ヤスオカさんと深い仲だった女性が、ヨシエさんと生き写しに近いほど似ていると話していたの思い出した。
しかし、ヨシエさんの歳は、ヤスオカさんより1回りは若い。ついでのことだが、もうすぐ28回目の誕生日を迎えるミサコさんは、ヨシエさんが34歳で産んだ子だ。
「で、どうなったんですか、警察の調べは」
どこの誰かも分からないままに死んでいくというのも、それはそれで奥ゆかしい話じゃありませんか、と口にしたかったが、そういう話題は多分チチが嫌うだろうと思い、ぼくはありきたりのことを訊いた。
「いまんとこ、さっぱりらしい。でもって、さっきまで部屋ん中、ひっくり返しての大捜索よ。解剖して調べるんだってんで、遺体も持って行っちゃった。まあ、置いてかれても、みんな困っちゃうけどなあ」
家主と店子ということで、ミサコさんやヨシエさんも長時間にわたって事情聴取を受けたらしい。チチを洗い終えたぼくは、自分の体はそのままにして湯船に向かった。ミサコさんのことを、チチに話すのは、別の機会にしようと思った。
下の家からふたたび県道に上り、右に折れて五十メートルも行くと、目の前が『いおり』だ。チチとぼくは、ひと言もことばを交わさずに日ごろより歩調を早めて歩いた。
チチが、職場の同僚の妻と懇ろになって居づらくなり、大阪から別府にやって来たのは、三年前のことだった。 ぼくに、同僚の妻とのいきさつが分かったのは、その同僚がアパートにどなり込んで来たからだ。たいていは、何が起こったかまったく分からないままに、転居となる。
転がり込んだマツモトという友人の部屋は2間きりのアパートで、しかも同棲している女性がいて、ぼくたちは着いたその晩から、ふすま越しに睦言を聞いて寝る羽目になった。
その部屋には、湯を沸かすガスコンロとヤカン以外に食事を作れるような調理器具もなかった。居酒屋に勤めているマツモトとその彼女は、店の賄(まかな)いで済ませているらしい。
ぼくとチチは仕方なしに、近くの食堂に出かけた。それが『いおり』だった。一週間ほど通ううちに、ヨシエさんから自分のところに貸家があるから住まないかという話になり、とんとん拍子にまとまった。
大阪から身ひとつでやって来たぼくたちは、布団だとか、鍋や食器だとか、とりあえずの生活用品を購入しなければならなかった。たちまち、ぼくたちの所持金は底をついてしまった。スーパーでわずかな買い物をすることもままならなくなった。
そのとき、ミサコさんからありがたい話が持ち込まれたのだ。店をしまう9時ごろから、店の調理場で、夕食を作ったらどうかという提案だった。冷蔵庫、冷凍庫の食材も自由に使ってよい、と言う。
「そのかわり、あたしたち母子の分も作ってほしいのよ。あたしたちだって、他人(ひと)に作ってもらって食べたいじゃない」
最近になって聞いたことだが、ミサコさんがそれほどまでにぼくたちを親身になって世話をしてくれたのは、チチとぼくの身の上を知ったからだそうだ。
「何か、わけありの親子だなってことぐらい、長年客商売をやってりゃあ、すぐ分かるわよ。で、マツモトさんにね、あんたたちのことを、こそっと訊いたわけ」
マツモトさんは、ぼくたちのことをどう話したのだろうか。「若くして妻を亡くした父子が、苦労して……」という程度のことだろう。チチが自分の身の上を他人に語ることは、まず考えられない。一番に億劫がることだ。
「あたしもね、高校をやめてまでくっついた男とうまくいかなくなって、それでバツイチっていう過去があるからね。それに、あんたたちふたりとも、どこかさ、放っておけないってとこ、あるからから」
ぼくは、その話を聞きながら、ミサコさんをじっくりと眺めた。小柄で、顔が小さくて、頬がちょっと張っている。顎(あご)もしゃくれている。だから、どことはなしに骨っぽいが、目許に笑みがこぼれていて、見る人の視線を包み込むやさしさがある。
ぼくたちが借りた家は、結婚したミサコさんのためにヨシエさんが建ててやったものだという。しかし、離婚後、夫だった男の匂いが残ったところには住みたくないからと貸しに出し、ミサコさんは『いおり』の2階でヨシエさんと住むようになった。
ぼくは初めのうちは、言われたように閉店間際に『いおり』に行き、4人分の夕食を作るだけだったが、そのうちに少しずつ早く調理場に入るようになった。
食材の下ごしらえをミサコさんに教えてもらったり、皿洗いを手伝ったりするのも楽しかったが、3人で談笑しながら、という景色の中にぼくがいるのが新鮮だったのだ。ぼくのそれまでの18年間で、チチ以外の人と会話を交わすことは、ほとんどなかったからだ。
このころ、ぼくは自分が肉体を持った人間であるという奇妙な発見もした。骨が組み合わされ、筋肉と血液の上から皮膚で覆われたぼくが、ぼくの意思で働いたり、話したりしている。当たり前のことが、心地よかった。
半年ほどしてからのことだった。店じまいにかかろうかというあたりで、いつもなら世間話、といってもヨシエさんの話をふたりで聞くという構図になるのだが、ぼくはその日、無性に、ぼくたち、いやぼくのことを話したくなった。
「ぼくたちのこと、変な親子と思うでしょう」とぼくは問いかけた。
「変だわよ。どう見たって、変だわよ。第一、体型も顔立ちも似てないでしょう。他人行儀な話しぶりだって普通じゃないし。年齢も性格も、どこかあいまいだし。父親は無口。息子はろくに学校にも行かずにいたらしい。1日中、料理に、掃除に、洗濯。変だわよ」
コップを食器棚に戻していたヨシエさんは、「変」を強調した。
「で、あんたたちの関係って、どうなってるわけ?」
「実はチチとぼくは、血の繋がりはないんです」
「うん、うん」というふうにヨシエさんが手を休めて寄って来た。ぼくの隣にいたミサコさんが、「よその家のことを詮索するのはよくないわ」とヨシエさんをたしなめ、そして、ぼくに、「無理に話すことはないのよ」と付け加えた。
「いや。おふたりには聞いてもらいたいんです」と、ぼくは話し始めた。
とは言うものの、実は、ぼくのことで語れる材料は、ぼくにはほとんどないに等しいのだ。
5歳だったぼくを抱えて、東京でひとり暮らしをしていた母のところに、いまぼくが一緒にいるチチが転がり込んだ。そして、しばらくして、母がトラックにはねられて死んだ。チチと同い年、22歳だった。
チチがどれだけ熱心に探したかどうか、それも気になるところだが、母の身寄りを知る手立ては、部屋の内にも外にも、見当たらなかったらしい。母は、区役所に住民届も出していなかったし、健康保険証も育児手帳も持っていなかった。自分やぼくの過去を抹消してしまいたいという、母の覚悟のようなものが感じれられる生き方をしていたようだ。
死亡届や埋葬許可などがどう処理されたのかしらないが、チチには、母と数ヶ月の間同棲したという事実と、「マー君」というぼくが残された。婚姻届を出した訳ではなかったので、チチとぼくは法的に他人だった。
区役所の人たちがやって来て、チチの意向も訊かずに、ぼくを児童施設に入れる手続きを進めた。
明日には迎えが来るという日に、チチはぼくを連れて東京を出た。
「『どうして、ぼくを連れて出たのですか』と訊いたら、事故の賠償金が実子であるぼくに出るだろうから、ということでした」しかし、結局、賠償の金は受け取らなかった。
「受け取りに行けば、私たちの居場所が分かってしまうでしょ。そうなると、役所の人がマー君を連れて行ってしまいますからね」
ぼくたちは、誰にも知れないよう、どこにいてもひっそりと暮らした。
「いまどきの日本で、そんなことって、あるのかしら」
ミサコさんが不憫(ふびん)そうにぼくの顔を見た。ヨシエさんが、「そりゃあ、あるわよ、ねえ」とぼくを見ながら、確信ありげに言い切った。「お天道様の下で暮らしたくても、そうはできない人だっているのよ。だれにも迷惑をかけずに生きられるなら、それも人生よ」
「そういう薄い空気の中でも離れずに生きているという関係って、いいかもしれないわね。それにしても、どこから見ても頼りげない感じの人だけど、ニワさんて、偉いんだ。見直しちゃった」
世間の基準からすれば、チチがしたことはほめられるようなことだろうか。
「捨てる」という気はないらしいが、チチはぼくを何度もうっちゃらかしにした。
あるとき、ぼくはチチの布団の中で待っていた。温めておけば、チチが必ず帰って来ると思ったのだ。そうしているうちに、チチは自分のことを何ひとつ語らないけれど、チチも親の帰りをこうして待っていたことがあるのではないかと、ぼくは思い始めた。チチの枕を抱きしめていると、そうにちがいないと思えてきた。
ぼくは1度だけ、ぼくの母のことをチチに尋ねたことがある。表で卒園式を終えたらしい母子を見た日だった。
「ぼくのお母さんって、どんな人だったの」
「そうだなあ。白い肌がスベスベしていて、抱くと私の胸にも,腹にも、脚にもピッタリくっつく人」
その後、ぼくは母のことを話題にしたことはない。
しばらくして、チチはぼくを正座させると、言った。後にも先にも、チチの真剣な表情に接したのはそのときだけだった。
「マー君がよければ、君をぼくの子どもにしたいんだ。私はリョウコのことが大好きだったからね。マー君といると、リョウコのことを思い出すから……」
ぼくはそのとき初めて、母の名がリョウコだと知った。
ぼくがコクリとうなずくのを見て、チチは目を細めてうなずき返した。
そのときぼくは、ぼくが母の代わりをしなくては、と思った。
チチとぼくは、それから何度も裁判所に呼び出され、別々の部屋で質問を受けた。何度目だったか、建物を出るとき、「ここは人を幸せにするところじゃありませんね」と吐き捨てるように言ったのを覚えている。感情をあらわにしてしゃべるチチを見たのは初めてだった。
チチが我慢してくれたお陰で、ぼくは「ニワマサユキ」になった。どこでも、正々堂々と名乗れる名前がぼくにもできた。学校へも行けるようになった。
「それにしても、ニワさんって、一体、何者なんだろうねえ。生まれ故郷の話とか、子どものころのこととか、マー君にも一切言わないのかい」
ぼくはあらためて振り返ってみたが、思い当たらなかったので、ヨシエさんに「ええ」と短く答えた。
「あれだけ献身的に世話してあげれば、お父さんだって、ねえ……。まあ、持ちつ持たれつ、ってところなんだろうが、腐れ縁って、マー君たちのことを言うのかね」
ヨシエさんが、洗ったフキンをしぼりながら、ぼくにほほえみかけた。ぼくは、ちょっとちがうと思ったが、笑顔で応えた。
「最近じゃあ、チチの操縦法がだんだんに分かるようになりましたよ。チチはチチでも、女性のオッパイの操縦法の方がいいのですがね」
久しぶりに、後先を考えずに笑ったような気がした。
「去年の桜は早かったけど、今年はどうでしょうね」
ぼくたちが『いおり』の前に立ったとき、チチはこう言って、荘園病院の脇の道に沿って植えられた桜並木を見上げていた。ぼくは下の家を出てから、自分の息の弾み具合が気になっていた。早足のせいではなかった。胸騒ぎ収まらないのだ。ぼくが店の前に置いている鉢植えのカポックがやけに黒々としている。
引き戸の脇に、メニューと値段を表示した1メートルほどのボードがあって、それが『いおり』を照らす唯一の灯りだが、ぼくたちが店の前に立ったときにはすでに消されていた。
「誰!」戸に手を掛けると、ミサコさんの声が奥の調理場から鋭く届いた。ふだん聞き慣れない口調に、とまどったぼくは、思わず「ぼくです」と応えた。
「ああ、マー君ね。ニワさんも一緒?」
カウンター7席と4人掛けのテーブルが2つの店内はいつものように明かりが点いていたが、調理場のそれは消えていた。その暗闇から、ミサコさんが姿を現した。コックコートにコック帽で、上から下まで真っ白。この姿のミサコさんに、ぼくはてんで弱い。
「今日はね、ちょっと早めに閉めちゃた」
「あっ、聞きましたよ、今日のこと。いま、風呂でヤスオカさんから」
ぼくはそれ以上のことは言わなかったし、尋ねなかった。
「お母さん、上の家に行ってるよね」
上の家とは、ぼくたちが借りている家のことだ。
「ええ、2時間ぐらい前かなあ。2階にいますよ」
ミサコさんがカウンター席に座った。ぼくたちもミサコさんを真ん中にして、ひとつ飛びに腰掛けた。
「何かあると、決まってお仏壇の前だからね。で、どんな様子だった?」右側のぼくに尋ねた。
「奥にいるぼくに、『2階借りるよ』って、いつものように声を掛けて上がっちゃったから、これと言って……。ヨシエさんに、何かあったんですか」
「うん。とても他人(ひと)には言えないこと」ミサコさんは左側のチチをチラリと見た。
「ぼく、行って、見てきましょうか」
「ううん、あたしが行く。あっ、そうだ。試験、どうだった? もちろんよ、ね」ミサコは椅子から滑るように降りて、ぼくの方を振り返った。
ぼくが小さくうなずくのを見て、「乾杯しよう。マー君、ビールを出して。あたし、コップを用意するわ」とそれまでの鬱(ふさ)いだ空気を振り払うように言った。
「そんな、乾杯だなんて。別に、たいしたことじゃないし。それにミサコさん、今は、ヨシエさんのことが気になってるんでしょう」
ミサコさんはすでにカウンターの中に入り、後の食器棚のコップに手を伸ばしていた。
「マー君が、18年目にして、初めて世の中に漕ぎ出すのよ。こんなうれしいことないじゃない。ねえ、ニワさん」チチが口許をほころばせて応えた。お付き合いに笑顔を返すなんて、あり得ないことだ。
「それにさ、マー君にはすまないけど、きょう亡くなった人とのお別れのお酒ね」
ミサコさんは飲みたいのだ、とぼくは思った。ミサコさんがそれほど飲めもしない酒を口にするときは、ぼくを見つめる時間がほんのちょっぴり長くなるから、ぼくにはすぐ分かるのだ。そんなときは、飲みながら、ぼくの若者らしからぬ物言いを聞いているとスカッとしてくるらしい。
チチのことを話してから後、ミサコさんの酒のお相手をすることが多くなった。「マー君も愚痴のひとつぐらいこぼしなさいよ」とミサコさんに何回か言われたことがあったが、彼女の不平や不満を聞いている方がぼくは好きだった。
あるとき、ミサコさんの心がどっぷりとぼくに寄り掛かってきて、「うん」、「うん」とうなずくうちに、ミサコさんと同じ息づかいをしていることに気付いたことがある。ぼくの鼓動がだれかの鼓動と重なっているなんて……。ぼくはその晩、なかなか寝付けなかった。
ミサコさんの愚痴は、客足が減ったとか、ぎっくり腰以来ヨシエさんの動作が鈍くなったとか、取るに足りない内容が多かったが、決して口にしない話題があった。夫だった男のことだ。ミサコさんが酒を飲むのは、男の残滓を振り払おうとしているためだと、ぼくは思った。
「マー君は、あたしの心がどんなに荒れても、いつまでも、何にも言わずに、じっと収まるのを待っていてくれるのね」
ミサコさんの心がぼくと話をすることで癒されるなら、こんなうれしいことはない。
「ニワさんとマー君の共通点があるとすれば、そんな、人を包み込んで、安らかな気分にしてくれる力だわ」
ぼくはこの話を聞いているうちに、定時制高校を受験してみようかという気持ちになった。
ミサコさんはぼくからビールを受け取ると、3人に注いだ。カチカチとコップを合わせ、たがいの顔を見ながら飲み干した。ミサコさんは瓶に残ったビールを自分のコップに注ぎ、「もう1本」とぼくに命じた。2本目からは、ぼくが注ぎ役に回った。
ミサコさんはとても速いペースで、注ぐたびに一気にあおった。最初の乾杯では黙ったままだったのに、2杯目からは、飲むたびにぼくに向かって「おめでとう」と言った。
「入学祝いは、何がいい?」
お祝いだなんて……。ぼくはこれまでに、入学祝いはもちろん、誕生日のプレゼントなんて、もらったことがないです、と言いかけてぼくは口をつぐんだ。ぼくの過去を憐れに語ることは、チチにすまないことだと感じたからだ。チチはふたりのやりとりを聞きながら、ぼくの隣で手酌のビールを飲んでいた。
「じゃあ、お言葉に甘えるとして」
「ん? 何だろう。値段の高いものはだめよ」
「いつだったか、ヨシエさんとふたりで、ぼくにこの店を手伝ってくれないかって言ったの、覚えてます?」
「お母さんの腰がひどくなって、入院しようかって話のときでしょう。もちろん覚えているわ」
ぼくは強く息を吸い込んで、その勢いで言った。
「定時制に行くようになったら、手伝いっていうのじゃなくて、ちゃんと働かせてくれませんか」
そのときのぼくは、自分の生き方を自分で決めようとしていることに、身震いするほどの感動を味わっていた。
ミサコさんはじっとぼくを見つめながら、コップを脇に置いた。そして、カウンターの上にあったぼくの両の拳を握りしめた。
「あなた、本気で生きようとしているのね。飛び立とうとしているのね」
ミサコさんの瞳から大粒の涙があふれ出した。ぼくは、自分の感動がミサコさんに伝わっていることがうれしかった。
「もちろんよ。もちろん、即、採用」
ミサコさんはぼくを見つめながら、コックコートの袖で涙を拭いた。
「じゃあ、あたし、上の家に行ってみるわ。お母さんの涙もそろそろ涸(か)れるころだから」
ミサコさんの両手がぼくの拳を包んでいることに、ぼくはやっと気が付いた。ずいぶんな力が込められているような気がした。
ミサコさんとぼくが日ごろになく感情をたかぶらせているのに、チチは背を丸めて、時折ビールを口に運びながら正面の食器棚を見やっていた。多分、チチはこの場の雰囲気にはそぐわない、とてつもなく変わったことを考えているにちがいない、とぼくは思った。
「後で尾ひれが付いて耳にされるのはいやだから、今日あったことを話しておくわ」
ミサコさんは蛇口をひねると、自分のコップを洗った。
「無理して言うことはないですよ」
「あたし、あんたたちを身内だと思っているから」
ぼくたちに身内ができたなんて……。もう、今日はぼくには初体験のことばかりだ。
「下の家で亡くなった人ね、お母さんとは中学の同級生でね、初恋の人だったらしいの。といっても、お母さんの片思いだったらしいけど」
初恋がみのらなかったヨシエさんは、その後、この地で『いおり』を開いたばかりの男性と結婚した。浮き沈みはあったものの、店にも常連客がつき、そのうち、ミサコさんも生まれ、忙(せわ)しないが、ほどほどの生活が続いたという。ところが、ヨシエさんの夫は、ミサコさんの早すぎる結婚に最後まで反対した気苦労などが重なって急死した。
「あたしが悔しかったのは、お父さんが亡くなって、そのすぐ後なのよ、お母さんが下の家にその男を入居させたのは。会社の金を横領して、逃げて来たんだって」
ぼくには、ヨシエさんとミサコさんの諍(いさか)いの様子が、どうしても頭に浮かんでこない。ぼくには、親子で言い争う姿が想像できないのだ。
「それから10年あまり、あたしの目を盗んで、その男に会いに行ってたと言うじゃない。いろんなものも、買って届けたらしわ。もちろんお金もね」
「そのことを、警察には?」
「言わなかったみたい。あたしも話すつもりはないわ」
ミサコさんの目は、切なさだろうか、潤んでいた。 「お母さんがね、今夜だけ、泣きたいと言うの。でも」、ミサコさんはヘアピンで留めていたコック帽をはずしながら、少しさびしそうな顔をした。「あたしの前では泣いてほしくないって言ったら、上の家で思いっきり泣くって……」
「早く行ってあげた方がいいですよ」
ぼくは手を差し伸べて、ミサコさんから帽子をあずかった。
「ありがとう。お母さんを呼んでくる間に、夕飯の用意をお願いね。献立はまかせるわ」
ミサコさんは引き戸に手をかけて、ぼくの方を振り向いた。
「ゆくゆくは従業員じゃなくて、オーナーシェフになってね」
ぼくは調理場の灯りを点け、冷蔵庫の中をのぞき込んだ。いつもは食材を眺めていると、メニューが浮かんでくるのだが、さっきからのドキド感が高まるばかりで、頭の中が真っ白なままだった。ぼくは相変わらずカウンターでビールを飲んでいるチチに、少しばかり声を張り上げて尋ねた。
「夕飯、何がいいですかねえ」
「何でも」という答が返ってくると思っていたら、意外にもすばやい返事があった。
「ビーフカツ、できますか」
「はい! ビーフカツですね。かしこまりました。ポテトサラダを添えますね」
今の応対は、はしゃぎすぎだったかなあ、と反省しながら、ぼくは野菜や肉を取り出し始めた。
勢いよく水をシンクに溜めて、ジャガイモやキュウリを洗っているうちに、動悸が収まってきた。
ガスに火を点け、ジャガイモを茹でる。タマネギを晒す。キュウリを塩もみする。次に、牛肉を少し分厚くカットする。ぼくの頭の中は次の手順を描きながら、心地よく、クルクルと回転する。ぼくが料理が好きになったのは、こうやってひたすら五感を手許に集中するだけでいいからだ。
肉にパン粉をまぶしているところで、店の電話が鳴った。コールは3回、4回と続いている。
「お願いできますか。手が離せないんです」
ぼくは、店にいるチチに向かって叫んだ。呼び出し音がやみ、チチのボソボソと応対する声が聞こえてきた。ぼくはふたたび料理に戻った。
「マー君!」
突如、頭の上から、チチの声がした。ふだんの間延びした呼び声ではなかった。ぼくは顔を上げた。
「上の家で、ヨシエさんが倒れていたらしいです」
「どういうことです? で、ヨシエさんの具合は?」
「ミサコさんひとりでは、心細いでしょう。急いで行ってあげなさい」チチは声を荒げて、ぼくを急(せ)きたてた。
ぼくはガスの元栓を閉めた。「すぐに行きます。もちろん、一緒に行ってくれますね」
「私は後で行きます。駆けつけたら、ミサコさんをぎゅっと抱きしめてあげるんですよ。それがマー君の役目ですよ」
「えっ」
「プロポーズをする前に、OKをもらうなんて。マー君は果報者ですね」
「分かってたんですか」
チチの細い目が、さらに細くなった。ぼくはこの笑顔を思い出した。養子縁組の話をしたときの目だった。
「私は、マー君の父親ですよ」
「お父さん。ぼく、ミサコさんとちゃんとやっていけますかね」
チチは、ぼくの問いには答えずに、頭をかきながら照れ笑いをした。
「お父さんと呼ばれる気分も、いいものですね」
ぼくは表に飛び出した。勢い余ったぼくは倒れそうになり、思わず店の前のカポックにすがりついた。体は何とか転ばずにすんだが、カポックは、鉢ごと足下に倒れてしまった。
「それは私が片付けておきますから……」
チチの声を背に、ぼくは駆けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
