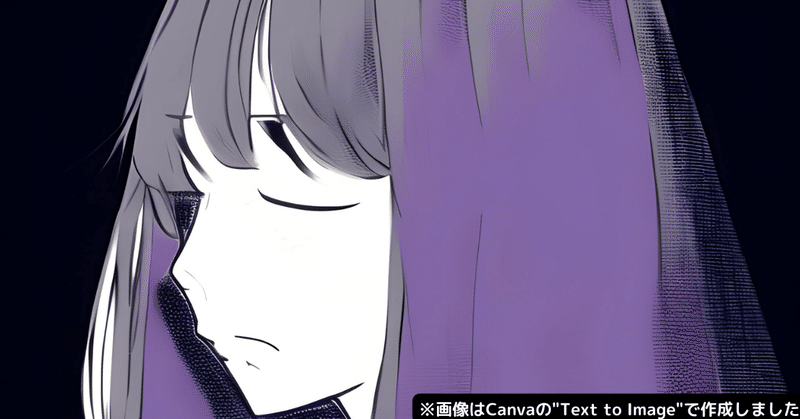
短編小説:蜘蛛姉(改稿)
旧版:v0.0.1
姉1
ほとんどの場合、思い出というものは自動的に消滅するものだ。あたしが自らの進路を決めあぐねている今この瞬間も、四月になってしまえばきっと忘れているだろう。
ボールペンの先を咥えて、ただ天井を眺めていた。唇の先で感じる揺れと重み。教科書に落書き中は、ペンの重さなんか決して意識しない。それをあたしに感じさせているのは、きっとテコの原理というやつだ。「こんなことも知らないの?」ってバカにされたから、言葉だけは覚えていた。椅子の後ろ足の二本だけで、自分の体重を支えてみる。どうしようもない事柄なんて、こうでもしなくちゃ考えていられない。
結局、進路希望の調査票には「市内で就職」とだけ書いた。第二志望、第三志望の欄も設けられているけど、一体何を書けというのだろう?あたしには、それ以外の道が存在しないのに?仕方なく思いついた職種を並べいていく。
- 第一志望 市内で就職(事務関連)
- 第二志望 市内で就職(販売員)
- 第三志望 市内で就職(福祉関係)
まあ、こんなものだろう。勉強は嫌いだけど、進学してみたい気持ちがないわけじゃない。本音を言えば、こんな田舎からおさらばして都会に出てみたい。だけど、もう子どもじゃないから、そんなワガママも言っていられない。
「矢口、具体的にはどれくらい考えている?」
進路希望調査の二者面談で、岩槻先生が心配そうに聞いてきた。
「具体的にって言われても、これ以上詳しく考えてません」
と正直に答える。心配して貰って悪いけど、あたしは自分の進路について深く考えていない。「まあ、何とかなるだろう」くらいにしか。ひとまず高校を卒業できるのなら、それでいい。
岩槻先生は大柄で、格闘技をやっていたらしく筋骨隆々としていた。
そんな体格にも関わらず物腰は柔らかいし、公民の授業で社会問題について説明しているときには、決まっていつも悲しい表情をする。岩槻先生がもし雨の日に道端に捨てられている子犬を見つけたら、きっと助けてしまうだろう。
そのせいか、あたしの仲間内で岩槻先生は「ダメ男に貢がされている」といつも噂されていた。本当は奥さんと子供を、とても大切にしている人なんだけどね。
けれど、そんな噂をされても仕方ないとも思う。現に、一年生のときに色々あったあたしの進路について、今こうして本気で心配してくれてるんだから。
なんで、そんなに心配して貰えるのかって?それはあたしが憂いをたたえた美少女だから、って訳じゃない。まあ、あたしの家庭には色々あってね。岩槻先生は、それを心配してくれているだけなんだよ。
あたしの家族は、父、母、あたし、弟の四人家族。他に兄も一人いるんだけど、結婚して家を出ていってからは一度も帰ってこない。連絡先も分からず、ほとんど絶縁状態だった。
あと、これを言うと微妙な反応がよく帰ってくるんだけど、あたしたちの家族には血の繋がりがない。つまり、あたしを育ててくれている人は、あたしの実の両親じゃない。あたしは六歳の時に施設から、この二人の元に引き取られてきた。そして養子縁組というものをして、あたしたちは親子になった。
あたしが施設から引き取られた、そのしばらく後にユイもあたしたちの家庭にやってきた。当時のあたしは、弟っていうものはこういう風にしてできるものだ、と本気で思っていたよ。まあ、実際はウチくらいなものだったんだけどね。コウノトリが赤ちゃんを運んでくるのは。
この話をすると、たまに「かわいそうに」とかいう見当違いな反応が返ってくる。あたしたちの家族を、血が繋がっていない他人同士の寄せ集めとでも思っているのかな?想像力が足りないのか、単なる無関心なのか、どっちにしろ良い気分はしない。両親はあたしたちの世話を焼き、困っていると助けてくれた。あたし自身も、体が小さく弱かったユイを、いじめっ子から守ったりした。血は繋がっていなくても、あたしたちは普通の家族と変わらなかった。
それにユイは、あたしにとって自慢の弟だ。ユイの名前は「結」と書いて「ひとし」と読ませる。だけど、あたしは弟のことをユイって呼んでいる。顔が女の子みたいで可愛いからだ。小さい頃は、
「ユイは可愛いから、守ってあげくなる」
と、よくからかったものだ。その度にユイはバツが悪そうに、こちらを見返してくる。はっきり言い返してこないところが、また可愛らしいかった。
ある時、そんなふうにユイをからかった後に、
「まんざらでもないんだろ?」
と言ってみたら、そっぽを向かれてしまったことがある。もう今では懐かしい思い出になってしまったけど。
「本当のお父さんやお母さんじゃなくてごめんね」
ありがちな話かも知れないけど、そんな風に両親から謝られたことが、あたしにも何回あった。だけど、あたしにはその理由が全く分からなかった。それがどうかしたの?と思っていた。
だけど、ユイの方はそうでもなかったみたい。
ユイは、アニメを見るのがとても好きだった。深夜に放送されているような、少しエッチなやつじゃないよ。人が血だらけになって死んでしまう残酷なやつでもない。ユイが好きだったは、平日の夕方や、土日の朝に放送されている子供向けの方。その手の番組が放送されている時間帯、居間にはだいたいユイがいて、一人でテレビに向かっていた。中学生になっても、幼稚園児や小学生の低学年が見るようなアニメばかり観ていた。
なんでそんなに熱心に見るのか、一度だけ理由を聞いてみたことがある。
「この子達には、本当のお母さんやお父さんがいるから」
そう言って、ユイは寂しそうに画面の中を見つめていた。
「小さくて弱いこの子達には、支えてくれる親がいるんだ」
アニメの中の子どもたちが羨ましくて仕方がない。そんな様子だった。たぶんユイは、実の両親が恋しいのだ。会うことすら叶わない本当の両親をアニメの中に求めていた。ユイにとって、実の両親のいる生活は画面の中の世界のことだった。
何度だって繰り返すけど、あたし達の家族が互いに血が繋がっていないことなんて、あたしは少しも気にしていない。
ちゃんと親としての役割を果たしてくれているから、それでいい。大人になって働いて自立できるまで、世話してくれるだけで十分なんだ。それなのに、お金がないのにも関わらず、あたしを私立の高校に入れてくれた。しかも、その高校に合格したときには、すごく喜んでくれた。お母さんなんて高い学費のことを忘れてしまったかのように「これで春からお嬢様高校に通えるね」って涙まで流していた。あたしには合格したことそのものよりも、そっちのほうが嬉しかった。だから、あたしは両親にとても感謝している。
ただ、お嬢様高校っていうのは、都会育ちの両親の感覚ってだけだった。この街では、私立高校のステータスはそんなに高くない。これが高校の同級生たちの感覚だった。二年生の夏休みくらいまで、それに気づかず浮かれていたのだから恥ずかしい話だ。
あたしを私立高校に通わせるためだけでも、両親は結構な無理をしていた。だから、弟思いのあたし(自分で言うもんじゃない?)は、ユイの進路が気になっていた。両親の話では、東京にいる知り合いが助けてくれるらしい。だからあたしが心配することはない、と父は言っていた。
「なんで、わざわざユイのことを?家族でもないのに」
あたしは不思議に思って、父にそう尋ねた。
「結には才能があるからな。期待されているんだ」
ふーん。ユイにそんな才能あったっけ?あやとりは、めちゃくちゃ上手だけど。ユイは、図書館から分厚いあやとりの本を借りてきて、すっごい複雑な形を平然と作ってしまう。あたしも挑戦してみたけど本の説明はチンプンカンプンで、手の中の糸はすぐに絡まってしまった。なんで、あれをスラスラ理解できるのか、不思議で仕方がない。
冗談はさておき、ユイは学校の成績もとても優秀だったから奇特な人が進学を手助けしてくれる。だから東京の高校に進学できる。そういうことだった。
東京いるというその知り合いに会ってから、ユイは机にばかり向かうようになって、その人が買ってくれたらしい本がユイの部屋には溢れた。ユイのあまりの変わりように心配になって両親に相談すると「弟の勉強の邪魔をするんじゃない」とあたしの方が怒られてしまう。
相変わらず夕方のアニメだけは見ていたけど、ユイがあたしたち家族と一緒に過ごす時間はほとんど消えて失くなってしまった。あたしにとっては可愛い弟でいてくれれば、それで十分なんだ。ユイをそんなふうに変えてしまった「東京の知り合い」とやらが、あたしは恨めしかった。
そんなユイだったが、今は車椅子で生活している。
原因は一年前の交通事故。父の出張ついでの家族旅行の帰り道、家族四人で車に乗っていた。そのとき、運転中だった父が突然苦しみだして、制御不能になった車はガードレールに激突した。
この事故でユイは重症を負って、一時はほぼ体を動かせなかった。リハビリを続けているおかげで、だいぶ元気になってきたけど、また歩けるようになるかどうかは微妙。東京行きの話も、うやむやになってしまった。
母とあたしは軽症で済んだけど、父はそのまま帰らぬ人となった。主たる家計の支持者を失って、一家のお財布が火の車になった。岩槻先生が授業料の免除や奨学金などの申請を手伝ってくれたので、あたしはなんとか高校を卒業できるのだ。
つまり岩槻先生があたしのことを心配してくれるのは、そういう理由。騙して貢がせている訳じゃないよ。実際、お金は一銭も貰ってないし。
リハビリから帰ってきたユイを出迎え、家の中まで連れて行く。
ユイが乗る車椅子を押しながら、
「小さい頃のユイはほんと可愛かった。守ってあげたくなるくらいに」
と耳元で囁いてみる。すると、ユイはチラッとこちらを見て、
「今は?」
とだけ聞いた。いつものやりとり。こいつも図太くなったものだね。昔の恥じらいは、どこに行ってしまったのだい?
いつもどおり、あたしは、
「守って上げたいのは変わらないよ」
とはぐらかした。ホントは、今も可愛いけどね。そして、これからも。
ユイの頭をくしゃくしゃに撫でながら、心の中で呟いた。ちょっと嫌そうにするところだけは、昔のままだ。
就職先を決めるのは、まだまだこれからだけど、あたしはこの街に残るつもりだ。
弟1
新しく購入した計算機にOSをインストールする。
計算機の電源を入れた直後にF2キーを押してUEFIを開く。起動デバイスをUSBメモリに指定、そこに保存したISOファイルを立ち上げる。あとはインストーラーの質問に答えていけば、道なりでインストールが完了する。
ユーザー名、パスワード、使用言語などなど。インストーラは分からないこと、管理者に確かめるべきことがある度に質問を投げかける。それらの一つ一つに答えてやる。
各種設定を終えて、様々なパッケージをダウンロード&インストールする段階に入った。圧縮されているとは言えパッケージのデータはギガバイト単位だから、もう画面の前を離れても構わない。インストーラが作業を終えるのを、ただ待つだけだからだ。少しの眠気。箱で買って廊下に置いてある缶コーヒーを取ってくるため、俺は車椅子のストッパーを外した。
缶コーヒーは、まるで冷蔵庫に入れてあったかのように良く冷えている。モニターの前に戻ってみると案の定、まだデータのダウンロード中だった。コーヒーが作業部屋の暖房でぬるくなってしまうのが不安になって、俺はタンブラーにコーヒーを注ぐ。
37%……58%……79%……
モニターに表示される数字を眺めながらコーヒーを舐める。最後に熱いコーヒーを飲んだのはいつだったろうか?少なくとも、あの事故の前だ。ちょうど今のように新しい計算機にOSをインストールしていた。その記憶と、コーヒーの湯気の香りが一組になっていた。その時はまだ足が不自由ではなかったから、配達されてきた計算機を玄関先で受け取れた。ダンボール箱の開封から設置、配線、全て俺一人だけで作業できた。しかしあの日以来、日常生活ですら一人で送れなくなった。あの事故さえなければ今頃は、この部屋にいなかっただろう。
そんな俺の悔しさを知ってか知らずか、事故の後から、やたらと姉さんが身の回りを手伝ってくれるようになった。この計算機だって、机の上に置いたのは姉さんだ。計算機が届いても俺は、姉さんの予定が空くのをただ待っているだけだった。その間ずっと、この計算機は玄関先に置かれていた。
パッケージのダウンロードがまだ終わらない。もしかしたら、無線LANも買い替えた方がいいのかも知れない。巨大なデータをやり取りする機会が最近なかったから気にしなかった。
ただ待っているのは苦痛だった。いつだって喉の奥から不快な思いが込み上げてくる。俺は何の味も感じなくなったコーヒーと一緒に、その思いを飲み込んだ。冷たさが喉を通り過ぎる。そう言えば、このタンブラーも姉さんが誕生日プレゼントに送ってくれたものだ。やっとパッケージのデータのダウンロードが終了した。パッケージのインストールが完了するまで、まだ待たなければならなかった。
「ゴメンねー、待たせちゃって」
昨日の夕方のことだった。新しい計算機の設置をほぼ諦めて、別の作業のためにキーボードを叩いている時、姉さんが現れた。
「突然、後ろから声を掛けないでよ。それにまた勝手に入ってきて」
「まーまー、いいじゃない?」
姉さんはマイペースだから細かいことなど気にしてくれない。このやり取りだって、何度繰り返しただろう?忘れっぽいのか、わざとなのか、似たようなことを繰り返し言ってくる。
「そんな格好で寒くないの?」
「さっきまで歩いてたから、むしろ暑いくらいだよ」
しかし半袖のシャツにジーンズだけでは、すぐに寒くなってしまう。机の上に畳んであったブランケットを羽織るように姉さんに勧めた。
「ありがと。だけどまだ要らない。あとで使うね」
ブランケットを机の上に戻す。
「それでこのパソコンだけど、どこに置けばいいの?」
僕は黙って机の下を指さした。
「古い方のパソコン、どかさなきゃじゃない?」
「うん」
そこでは、いま使っている計算機が動いていた。
「こっちの方をずらしてできた場所に、新しい計算機を置いて」
「人使いが荒い」
「まだ何もやってないよ」
僕が車椅子をバックさせると、入れ替わりに姉さんが机の下に頭を入れる。僕は、背中にプリントされたイラストを見て、新しいシャツを買ったのだと気づいた。服なんて、二ヶ月に一度、市役所のロビーで開かれるバザーで古着を買えば十分なのに。そのイラストは、知らないアニメのキャラクターだった。少し不気味なデザインで、おそらく悪役だろう。
「なにこれ、蜘蛛の巣?」
「え?」
姉さんは机の下を覗き込んだままだった。少しの間、沈黙が流れる。
「ねえ、ここ凄く汚いよ。ホコリだらけ」
元の体勢に戻ると、姉さんはその方向を指さした。しかし、暗くてよく見えない。それに車椅子に乗ったままでは体を上手く屈められなかった。
「そのさ、いろいろ繋がっているコード、外しちゃっていい?」
「この計算機、いま動かしているとこ何だけど」
「ダメ?」
「駄目」
データを移す必要があるから、この計算機も使える状態にしておく必要があった。
「この部屋、掃除したい」
「掃除なんて後でいいから、早く計算機を運んできて」
今日中に終わらなければ、次はいつになるか見当がつかなかった。だから、ボーッとしてないで早く作業を進めて欲しい。
すると姉さんは、まじまじと僕の机の上を見た。そこには筆記用具と書類が乱雑に散らばっている。だんだんと嫌な予感がしてきた。案の定、姉さんは机の上をスーッと指でなぞって、それから指先を見る。あ、これ、テレビで見たことあるシーンだ。
「汚い」
「知ってる」
姉さんはエコバックからウェットティッシュを取り出すと、机を拭き始める。
「ここなんてホラ、擦ると色が変わるよ」
確かに拭かれた箇所は、明るく輝いていた。
「いいから早く廊下から箱を持ってきて、計算機をそこに出してよ」
「できる範囲でいいからさ、身の回りのことはちゃんとやりなよ。ユイは事故の前からずっと、自分のダメなところを少しも直そうとしてない」
確かに姉さんの方は事故の後から、僕をよく手助けしてくれるようになった。しかし、それは姉さんの気が向いたときだけだ。計算機の設置だって、やろうと思えば前の土日にできたはずだった。高校の同級生との約束が入っていた日曜日はまだいいとして、土曜日の方は映画を見に行くから無理と断られた。それも一人で。「それ今じゃなきゃ駄目?」と聞いたら「一刻も早く観たい」と真顔で返事をされた。仮に「僕と映画とどっちが大事?」と質問したら、「そんなの決められない」とか「どっちも同じくらい大切」と答えていただろう。
「ユイはパソコンのことしかできないくせに、偉そうにして」
計算機を使った作業以外しないし、愛想も悪いほうだから否定はできない。実際、ケアワーカーの人からも似たようなことを指摘されていた。だから何も言い返せない。僕は仕方なく話題を逸らした。
「とにかく今は新しい計算機をダンボール箱から出して配線までやって欲しいんだ」
床に視線を落として静かに説得する。僕が顔を上げたら、姉さんはわざとらしく方をすくめてみせた。
「モニターの裏もホコリでいっぱい」
これみよがしに覗き込みながら言う。流石にこんなシーンはテレビでは見ない。
「手が届かないんだから仕方ないだろ」
「これ、一ヶ月前に買ってあげたやつだよ」
姉さんは柄の長いモップを僕に向かって突きつける。押し入れに放り込んで置いたのが見つかってしまったのだ。もう形だけでも掃除する振りをするしかなかった。僕はモップを受け取り、机の上に書け始める。姉さんはこの姿を見て納得したらしく、ダンボール箱を持ってきて中身を床に並べ始めた。
姉さんの説得が済んでしまってからは、作業は順調に進んだ。分からないことがあるたびに姉さんは尋ねてくる。まるでOSのインストーラのようだった。机や本棚のホコリ取りが終わると、モップの代わりに濡れ布巾を渡された。これで机の上を拭けという。力を入れて何度も擦ると、どんどん机の色が変わり、コーヒーのシミも消えていった。替わりに布巾が真っ黒になった。
最後にHDMI端子を差し込んだところで、姉さんの作業は全て完了した。本人はダンボールの空き箱も片付けたいと言っている。その間に計算機の電源を入れて、モニター、キーボード、マウスの動作に問題がないかを確かめる。そして僕は、キレイになった机の上に突っ伏した。
気がついたら柔らかな布団の中に沈んでいた。長い間そのままだった作業が片付いて緊張が解け、限界を迎えたのだ。睡眠不足で作業中だった僕の前に、何の連絡もなく突然現れた姉さんに全ての問題がある。しかも、僕の意識がなかったのをいいことに、古く汚くなっていた布団一式まで勝手に取り替えていった。
背筋に寒気が走って、慌てて着ているものを確かめる。大丈夫だ。これは中学校のときのジャージ。十四歳の時からほとんど背が伸びなかったので、今でもこれを着て過ごしている。これを着ていたおかげで、姉さんに着替えさせられずに済んだ。
ベッドの脇に置いていかれた車椅子に乗り作業台に向かう。ブロックタイプの完全栄養食が入っている引き出しを開けると、その中から空き箱や空の包装が消えていて整理整頓されていた。
また余計なことを。
ブロックをかじりながら、本棚へ資料を取りに行く。違和感を覚えて、本棚の縁を指でなぞるとホコリが全くない。僕が意識を失ってから、いったいどれくらい姉さんはこの部屋にいたのだろう?事故の後、入院の期間が終わってこの部屋に戻ってから、僕の警戒対象は母から姉さんに変わっていった。
後日そのことで文句を言ったが、
「全然掃除できてなかったじゃない。やっぱりユイはあたしがいないとダメなんだよ」
と姉さんは胸を張るばかりだ。
姉2
窓を開けると一面の雪景色だった。板張りの床が白くなった。
「それと、これは返しておく」
「きっと読み返すだろう。まだ持っていてくれて構わない」
「読み返さないから返す」
雪が纏っていた空気と入れ替わりに、体温が去って行く。
「気にされることはない。わたくしは電子書籍でも持っているのだ」
「ひどい話だった」
「そうだろう?とても悲しく、それでいて美しい物語だ」
そして、ついに声が波であることをやめる。
「いいから持って帰れ。この本が家の中にあるだけで胸糞悪くなる」
「は?」
「ちょっと、ユイ!」
どんどん険悪になっていく二人の会話に、慌てて割って入る。
「申し訳ありません。あたしはとても気にって何度も読み返したんです。だけどユイにはちょっと、合わなかったみたいで」
「最初の数ページ以外、読んでいない」
まったく悪びれないユイに代わって、あたしは頭を下げた。
「ふん、文学について、お前はサル程度の知能ということだ」
「ええと、美術とか音楽とか、芸術関係はユイには解らないみたいです」
そんなやり取りをしている間に、部屋の中の気温がどんどん下がっている。ユイもお客さんも、何でクソ寒いのに窓を開けているのか考えて欲しい。
「それで、あの、頂いた壺には、何を飾るのが良いでしょうか?」
テーブルの上には、お客さんがユイに持ってきた手土産が置いてある。なんでも、茶道で使うお高い品物らしい。
「なに、大したものでなくても良いのだ。庭や道端に、自然に生えている草花で構わない。むしろ、その方が季節の移ろいが感じられるというもの」
ユイの視線は相変わらず凍りついたままだった。あたしの愛想笑いの方も凍りつきそうだった。この人は、小説の中の雪景色については暑苦しく語るのに、目の前の雪景色には気が付かないらしい。
「それで、いったい何をこの壺に飾れと言うんだ?生えている植物もあるだろうが、見ての通り雪に埋もれている」
ユイが言ってくれたので、お客さんもやっと窓の外の景色に気づいてくれた。あたしは二人の様子を窺いながらそーっと窓を閉めると、すぐに灯油ファンヒーターの近くに移動した。
「それに四季の移ろいなら、部屋の中だけで嫌というほど感じている」
この時期、二重窓には一面にびっしり霜が降りる。昼間になっても氷点下なので、霜が溶けることはない。
「おお、なんと美しい模様か!」
お客さんは、純粋に窓の霜に感動しているみたいだ。あたしにとっては、ただ寒くて冷たくて、学校に行くのが嫌になるだけの模様だった。
このお客さんは、ちょっとアレなところがあるけど、悪い人ではないのだ。この様子なら、窓なんか開けないで、最初からこれで良かったのかも知れない。
「ごめん姉さん、そこの窓を全開にしてくれる?」
と言ったユイを少しだけ恨む。
まだカリカリしているユイを遮って、あたしはお客さんに質問した。
「そういえば、お母さん、じゃなくて、母の様子はどうでしょうか?あたしたち二人への連絡では元気でやっているって言うんですけど、強がりなんじゃないかって心配で」
「強がりか……」
お客さんは少し上を向いて顎をさする。
「ここに来る直前に会って話したが、少し疲れた様子だった。だが心配はない。仕事場の仲間に頼られているから、それも仕方ない」
やっとユイもしおらしくなり、
「姉さんと俺はずっと帰りを待っていると、よろしく伝えてくれ」
とお客さんにお願いした。そんなユイの様子を見て、あたしの胸も痛む。母さんは父が死んでから東京に出稼ぎに行って、一度もここに帰ってこないからだ。
この一件があって少ししてから、ユイが変なことを言い出した。
「姉さんは東京に行った方がいいよ」
例のお客さんが置いていった壺には、金魚草が突き刺してあった。
稲くらいの大きさで、それほど背は高くない。壺に飾るには丁度いい大きさだ。青々と真っ直ぐに伸びた茎の先には、いくつもの小さく可愛らしい色とりどりの金魚がぶら下がっている。それなりに人気のあるキャラグッズだった。スーパーの福引でユイが当てたものなんだけど、小さかったユイは、草にぶら下がっている金魚が「気持ち悪くて怖い」と泣いた。
その壺を持って屋根裏部屋に入ったとき、ついでに色々な箱を開けて眺めていたら、偶然その金魚草が見つかったのだ。金魚草を生けた壺をユイに見せると
「あの阿呆が置いていった壺には、このくらい不気味な金魚がよく似合う」
と満足そうだった。例のお客さんに金魚草と壺の写真を送ってみても、まんざらでもない返事だった。
「金魚草というのは、このぬいぐるみの事ではない。だがコレはコレでいい」
ユイが最近、同じキャラグッズのシリーズで鯛釣草を手に入れたらしいから、それを飾った写真も送ってあげよう。
それで、もう四月だと言うのに、相変わらずユイはあたしに東京に行った方がいいと話してくる。
「母さんのことを心配してるの?えっと……例の壺の人が、疲れた様子だったって言ってたものね」
「いや、母さんのことは心配していない。奴が大丈夫だと言ったのだから、大丈夫だ」
「まさか自分が東京に行けなかったから、代わりにあたしに夢を託そうなんて思ってないよね?」
あたしは真剣な気持ちでユイに詰め寄った。
「……」
口を半開きにしたまま動かないでいるユイ。
「ねえ、ちょっと」
このプログラムは応答していません。ポカンとして固まっているユイを見て、そんな言葉を思い浮かべた。
「あ、ごめん、そうだよね。うん、そうだよ。僕の代わりに東京に行って見て欲しいんだ。ちなみに、母さんは引っ越してもう東京にはいないから、この話と母さんは全然関係ないんだ。純粋に、東京に行きたかったっていう僕の夢を、代わりに叶えて欲しいんだ」
え、なに?この違和感しかない反応は?
「ちょっと待って、ユイが上京したかったのは大学に行って、ユイの実力に見合った仕事に就くためだったよね?」
「うん。姉さんが東京に行ってオシャレな仕事をすれば、僕が託した夢を叶えたことになるよ」
あたしの中のユイのイメージって頭脳系の悪役……悪役かどうかはともかく頭脳系だった。
「ユイが憧れていた仕事はあたしには絶対に無理だよ。スマホとイヤホンのBluetooth接続ができなくて弟を頼る人には、絶対に不可能。そう思わない?」
「えっと、具体的な仕事の内容は、もうどうでもいいんだ。こだわっているのはイメージで、都会的なキラキラした感じが重要なんだ」
悲しくなるほどにバレバレな嘘だった。ずっと前から、あたしはこの街を離れないって決めてる。それなのに付け焼き刃の嘘で誤魔化そうとするなんて。
「そんなつまらない理由でユイは東京に行きたかったんじゃないでしょ。自分に比べて両親がとても頼りなったから、だから、ユイは六辻さんに憧れて東京に出ようとしたんじゃない!」
すると、ユイは押し黙ってパソコンに向かってしまった。
「ちょっと待ってよ。じゃあなんで今頃になってそんな話?時期外れもいいところじゃない?」
嘘を見破られてバツが悪いのかも知れない。
「ねえ、何か言ったら?」
キーボードを叩いていた指が一瞬だけ止まる。
「本当はね、一人でも大丈夫だって分かったからだよ」
「なに?」
ユイは車椅子のストッパーを外して、あたしの方に向き直った。
「この間、直に聞いて確かめたんだ。今まで姉さんがやっていた事は全部、ケアワーカーの人にも頼めるんだよ」
見え透いた嘘、そんなのデタラメだ。訪問介護でやってくる事業者なんて、決められた仕事をすぐに終わらせて帰ってしまう。あたしのように手の込んだ料理や、ユイの生活面に気の利いたアドバイスなんてやってくれない。そういうことは全て業務外なんだ。
「現にホラ、ここに置いてあった古い計算機が片付いているよね。困ってたけど、ケアワーカーに相談したら解決できた。本当は、新しい計算機の配線だって相談できた。姉さんに気を使って黙っていただけなんだ」
つまりユイにとっては、パソコンのことさえ何とかなればそれでいいのだ。ユイの髪の毛は何日も洗っていないので、油っぽく、フケも浮いていた。あたしの使っているシャンプーはそんな高級品じゃないけれど、それで洗ってあげればサラサラで、ちょうどいい感じでフワッとうねる髪なのに。服だって中学校のときのジャージじゃなくて、ちゃんとしたものを着てほしかった。
「ケアワーカーはね、仕事で来るだけなんだよ?」
「僕にはそれで十分」
そんな、それじゃあ、あたしが東京に行ってしまったら、ユイはどうなるの?
「あたしがいなくなったら、ユイはこの家にひとりぼっちじゃない」
薄暗い部屋で一人パソコンを叩くユイの姿が目に浮かんだ。
「ひとりぼっちになるのが嫌なのは姉さんの方だろ?」
「は?なに言ってんの、バカじゃないの?」
あたしにはちゃんとした人間関係がある。家に引きこもったままのユイとは違うんだ。このことはユイだって知っているはず。だってあたしの身の回りで起きたことを毎日のように話して聞かせて上げてるんだから。
「行かない。あたしは東京に行かないよ。何があってもユイが住むこの町から離れない」
ユイはこれ以上あたしの言葉を聞くつもりはないと言わんばかりに、パソコンに向かって再びキーボード叩き始めた。
「ねえ、ユイ?何か言ってよ、あたしの何処が悪かったの?今まで十分、助けて上げてたじゃない?」
あからさまな舌打ちの後に、ユイは静かに言った。
「分かった。なら、今から本当のことを全て説明する」
再び向き直ったユイは、あの日、たった一度だけ見たのと同じ表情をしていた。
今だからこそ分かる。これはユイが本気で怒っているときの表情だった。
弟2
風の音が室内まで響いてきて、低く落としていたテレビの音を邪魔してくる。さっきブラウザで見た気象情報では、家の外は暗闇の吹雪だ。アニメの登場人物の台詞がかき消されるので、僕はテーブルの上のリモコンを取ろうかどうか迷っていた。
だから、リビングルームの電話が鳴ったのは良いことだった。受話器まで行って、戻るついでにリモコンを回収しよう。
回線の向こう側でのんびりと構えているのは、姉さん以外にいない。車椅子の向きを変える間、屋外の何かがカタカタと音を立てていて、今にも飛ばされそうだった。これじゃこの家に来れなくても仕方のないのに、姉さんは電話で伝えないと気が済まない。
「どちら様ですか?」
そんなの、あたしに決まってるじゃない。繰り返されるいつものやり取り。それを期待していた。しかし聞こえてきたのは、まったく違う回答だった。
「矢口結様のお宅で、お間違いないでしょうか?」
質問に質問で返すな、学校でそう習ったのか?ことある毎に姉さんは、僕にそう言ってきた。質問の意味が分からないから聞き返しているのに、なんでそんなことを言われなければならないのか。それに姉さんだって、僕の質問に対して質問で返すことはままあった。だが、この声の主は違う。
「どちら様ですか?」
慇懃無礼な女の口調に対して、俺は一字一句なにも変えないで繰り返した。まず名乗れ。どこの誰かも分からない人間にプライバシーを明かすなど、間抜けな素人だってそんなミスは犯さない。
「申し遅れました。私は谷川紫陽(しはる)という者です」
俺はただ黙っていた。本日は、どういったご要件ですか?ごく単純な決まり文句を飲み込んだ。息の音が相手に聞こえないように、細心の注意を払う。
「私は貴方のお姉さまの知り合いの妹です。本日は、矢口様にお尋ねしたいことがございまして、お電話を差し上げました。電話口でお話されているのは、矢口結様ご本人でお間違いないでしょうか?」
「あの、たいへん申し上げにくいのですが間違いです。その人はきっと前の住人です」
今度は女の方がただ黙っていた。息を殺して耳を済ませると微かに管弦楽が聞こえてくる。背後からは吹雪と、とぎれとぎれのテレビの音声。
「間違い電話なので、もう一度よく確かめてみて下さい。切りますね」
嘘を吐くのは泥棒の始まりですよ。
まだ施設にいたときの事だろうか?それとも、この家に引き取られた後のことだろうか?とにかく俺は、子供の二人組がそう怒られているのをただ眺めていた。その光景が不思議で仕方がなかった。嘘を言ったら泥棒になってしまう。泥棒は悪者。だから嘘を言ってはダメ。
じゃあ何故、大人はみんな嘘を吐く?
私が怒っているのは、あなた達が大切だから。違う。その大人は自分が騙されたことに単に苛立っているだけだった。じっと顔を見れば、それだけで分かる。何故そんなに分かりきった嘘を言うんだ?聞いた瞬間に嘘と分かるのに、なんでそんなに堂々と言ってしまえるんだ?
しかし俺の周りはそんな嘘で満たされていた。全員が全員で嘘を信じていた。嘘が嘘だと分かるのが俺だけしかいなくて、いつの間にか俺は誰とも話さなくなっていた。
「もう一度、言いますね。矢口様、嘘を吐くのは悪いことですよ」
「いきなり電話がかかってきた上、嘘つき呼ばわりされて非常に腹立たしい。同窓会の名簿か何かで調べたんだろうが、そのデータはもう古いんだ。もっとも俺がこの家に引っ越してきたのも、つい最近だから、それも仕方ないんだろうがな」
「いいえ、ちゃんと確認した上でお電話を差し上げています。矢口様は六歳のときに児童養護施設から引き取られて以来、ずっと今の家にお住まいです。私、仕事柄こういう地味な情報を確かめるのは得意なんですよ」
「探偵か?」
「警察に勤めています」
同時に、谷川楓(かえで)の名前を思い出した。十三年前の忌々しい記憶が蘇ってくる。
「突然のお電話で大変失礼いたしました。警戒して嘘を言ってしまうのも無理はないですね。さっきのことは水に流しますから、本当のことを話してもらえますか、矢口さん?」
「いったい何の用だ?」
「あなたのお姉さまが高校一年生のとき、ちょっとした事件がありました。その事件についてお聞きしたく思います。日を改めてこちらからお伺いするので、焦らなくて結構です。できれば、お姉さまにも同席いただきたいので、日程調整をお願いします」
姉3
ユイが車椅子になったのも、父親が死んだのも、全部あたしのミスのせいだった。
あたしの家族は、血が繋がっていない他人同士の寄せ集めだ。
裏仕事を熟すために作られた偽りの家族。あたしとユイは、家族として取り繕うための飾りに過ぎなかった。
その絆は、だけど、普通の家族よりも遥かに強い。どこからか命令される裏仕事。弱みを握り、お互いを縛り付ける。家族の秘密を外に漏らすことは絶対に許されない。些細なミスを犯すことも同様だ。この絆を裏切った場合、どうなるか?それは、あたしの兄が身をもって示してくれていた。表向き、兄は結婚して家を出ていったことになっている。しかし、彼があたしたち家族に会うことは、もう二度とない。あたしたちの絆は、世界中のどんな家族よりも強かった。
小さな綻びを取り繕う毎日が崩れた切っ掛けは、ユイがあの男に出会ったことだった。それまでのユイは、あやとりとアニメが好きな、少しだけ内気な普通の子どもだった。だけどユイは、その出会いの後から一人で部屋に籠もるようになった。両親は学校の勉強を頑張っているんだと言っていたけど、絶対にそれだけじゃない。学校の勉強とは関係ない、大人が読むような難しい本もユイの部屋には積まれていた。
いつの頃だったか、父とユイが居間で知らない男の人と話していたことがあった。父の会社の同僚であると紹介された男の人の顔はその日、痣だらけで唇も切れていた。「大丈夫ですか?」と声を掛けようとして止めたのは、ユイがその人に注いでいた視線が凍てつくように冷たかったからだ。あたしは何も言わずに、ペコリとお辞儀をしてその場を去った。
おそらく、ユイは知ってしまったのだろう。自分の父親の仕事について、家族以外の人間が知ってはならない部分まで。そして今や、ユイ自身もその部分に手を染めている。
その日の深夜、両親が台所で何か話しているのを偶然聞いてしまった。
「あいつがこれだけの仕事を熟せるなんて思っても見なかったよ。それも、あの年で。あのお方が結のことを気に入る理由が、やっと俺にも分かった」
母さんに向かって、父が愚痴っている。心なしか、怯えの交じる声だった。その頃からあたし達の家族は、段々とユイに逆らえなくなっていった。
そんなとき、あの事件が起きた。原因はあたしのミス。迂闊だった。もっと注意するべきだったんだ。
今から振り返れば、避けられる不注意だった。
そのせいでクリスマスツリーの飾りの購入費について、谷川楓とかいう生徒に問い質されたのだ。
そして、そいつは全てを明らかにするよう、あたしに言ってきた。
彼女が話したことは今でも、思い出すだけで腹が立ってくる。あの時あたしは、机の上に置かれている証拠書類を凝視しながら震えていた。体中から嫌な汗が吹き出てきた。
「全てのことをみんなに話しましょう。きっと、分かってくれるはずです」
そう言いながら、「証拠書類」を持ってきた谷川は、あたしの手を握ってきた。
「触るなっ!」
彼女の手を振り払い、椅子から立ち上がった。
窓を背にして、その正義の味方ぶった生徒を睨めつける。
毅然とした態度、校則通りに着こなされた制服、目には哀れみと静かな怒りが宿っている。
ふざけやがって!
全て白状?馬鹿じゃないの?いま、そんなことをしたら退学は必至。
自分がすんなりとお嬢様高校に入れる身分だから、そんなことが言えるのだ。あたしがどれだけ苦労して、この高校に入学したと思っている?それを手放せと?ふざけるな。
退学なんてしたら、残るのは何だ?借金、そして、中退という不名誉な学歴だけ。この田舎町で小さな企業に就職して、そこそこな男と結婚する。そして、平凡なつまらない家庭を築く。こんな慎ましやかな夢が全て自動的に消滅する。絶対に白状するわけにはいかない。
「一週間したら、またお尋ねします。どうか勇気を持って決断して下さい」
彼女は、持ってきた資料を鞄の中にしまって、教室を出ていった。忌々しい生徒が去ってゆく足音が完全に消えた後、あたしはその場にへたりこんだ。足に力が入らない、でも、帰宅しなければならない。ユイなら、きっと解決してくれるだろう。でも、……。躊躇いで、その先に考えを進められなくなる。
家に帰ったとき、ユイはテレビを見ている最中だった。いつもの子供向けのアニメ番組。
きっと、おとぎ話の中では、あたしはシンデレラに出てくる意地悪な姉のような存在なんだ。実際、ユイの前でもあたしは、そんな風に振る舞っていた。無力な弟を虐げる意地悪な姉として振る舞っても、ユイは怒らなかった。多少のわがままも言っても、あいつは黙って引き下がる。風呂やトイレの掃除を押し付けたり、アイツの分のお菓子を黙って食べたりしても、「お姉ちゃん、ひどい」と言うだけで終わりだった。
数日後、あたしは岩槻先生に呼び出され、応接室に案内された。そこには何故か、あたしの母の姿があった。あたしを母の隣に座らせると、クリスマスツリーの費用に関して疑いの声があることを、岩槻先生は静かに話し始めた。
岩槻先生と母の二人に囲まれる中で、あたしはうつむき震えていた。あたしのやったことが知られてしまうことに。この学校の生徒たちに?それもある。しかし、何よりもユイに知られることが恐ろしかった。あたしは、つまらないミスをした。些細なことで失敗し、家族に、ユイに迷惑をかけた。
無能、役立たず、出来損ない。
罵倒するユイの声が思い浮かび、顔から血の気が引いていく。
「今日は、ここまでにしましょう。」
重苦しい空気の中、岩槻先生が口を開いた。
「一度、ご家族で話し合われることをお勧めします。この件については、まだ、私の他に数人しか知りません。私としては、できるだけ穏便に対処したいと思っています。」
帰り道の途中、あたしは母に懇願した。
「ねぇ、このことは絶対にユイには黙っていて。岩槻先生も穏便に対処してくれるって言ったでしょ?きっと、何事もなく有耶無耶になるだけだよ」
あたしが必死になって訴える中、母はずっと押し黙ったまま。怯えた様子であたしと視線を合わせることはなかった。
家に帰ると、あたしの部屋がグチャグチャに荒らされていた。空き巣か強盗にでも入られたのかと思って、部屋の中を確認したが、現金やお金になりそうなものは盗られてはいなかった。
部屋の中を片していると、物音を聞きつけたユイが何の断りもなく入ってきて、乱暴にあたしの胸ぐらを掴んで詰問した。
「帳簿は何処に隠してある?隅から隅まで探したのに、この部屋からは見つからなかった」
部屋を荒らした犯人は、ユイだった。
「ちょっと、人の部屋をメチャクチャにしておいて何、その態度は?」
あたしはいつもの調子でユイを睨め返す。
「チッ」
小さく舌打ちをしたユイ。次の瞬間あたしは力任せに投げ飛ばされ、床の上に崩れ落ちた。
「ぎゃっ」
そしてユイは何の躊躇いもなく、あたしに目掛けて椅子を投げつけてくる。激痛のあまり、その場であたしは蹲った。ユイの目は血走り、冷たい表情であたしを睨め付けている。
「僕が知らないとでも思ってるの?とっくにバレてるんだよ。生徒会のカネに手をしたことが、谷川楓という生徒に嗅ぎつけられたんだろ」
ユイの言葉を聞いて、あたしの目の前は真っ暗になった。痛みで切れぎれになる声で、あたしは必死で訴える。
「違うの。本当はあたし、生徒の誰かにハメられただけなんだ。お願いだから、兄さんのようにはしないで」
突然、髪の毛を乱暴に掴まれて、恐怖で全身が硬直した。掴んだ髪の毛を無理やり引っ張ってあたしの体を起こすと、ユイは言った。
「立ち上がって帳簿を持ってこい。すぐにだ」
何も言わず、半ば這うようにして、あたしは部屋を出る。こんなことになったのも、全部あの女のせいだ。違和感に気づいて、全てを白状しろと言ってきた生徒。あたしは急いで帳簿を隠している物置に向かった。
一週間後、あたしは岩槻先生と話していた。岩槻先生の隣には、谷川も座っている。これはあたしが希望したことだった。
「これを見て下さい。」
と言いながら、あたしは一つのファイルを差し出した。岩槻先生は「わかった」というと、ファイルを受け取り、中身を確認する。谷川が、ファイルとあたしの顔とを交互に見比べながら、
「これは……」
と何やら言いかけたので、
「書類を整理するのに少し手間取っていただけなんです。」
とあたしは彼女の言葉を遮った。
「慣れない作業だったし、細かい資料も沢山あったから。時間がかかったために誤解を招いてしまい、申し訳なく思っています。」
ユイに教えられた通りの言い訳を二人に説明した。すると、岩槻先生は
「そうか、そういうことだったのか。私の方こそ、疑ってしまって本当に申し訳なかった。どうか許して欲しい。」
と深々と頭を下げた。その様子を、谷川が驚きと困惑が混ざった表情で見つめている。
「私もファイルを見て構いませんか?」
「どうぞ」
ファイルの内容を確かめる谷川を注視する。案の定、谷川は
「まさか、そんなはずはない。なんで、こんなレシートがあるの?」
とかなんとかブツブツと呟いている。その様子を見ながら、あたしはユイに指示されたことを反芻する。何か言ってきたとしても「資料は本物だ」と、そこだけは決して譲らないこと。余計なことは言うなと、強く釘を刺されていた。
「矢口さん、この領収書は本物なのですか?」
「本物です」
「ですが、私の日記には……」
「谷川、もう止めろ」
納得できないという調子の谷川の言葉を、岩槻先生が怒気を含んだ声で制止する。それに気圧された谷川は黙って引き下がった。これで決着はほとんど付いたが、あと一つだけユイから指示が残っている。
「そのファイルはまだ整理している途中なので、返して頂いてもよろしいですか?」
「ああ、もちろんだ」
岩槻先生が了承すると、谷川はしぶしぶといった感じでファイルをあたしに返した。谷川からファイルを受け取り、鞄にしまうとジッパーを閉めた。もう一度、谷川の方を見て、彼女が何か盗ってないか確かめる。問題はないみたいだったので、「それでは失礼します」と言って教室を後にした。
家に帰ると、直ぐにあたしはベッドの上で仰向けになった。本当にひどい数日間だった。ふふ、と自然に笑いが込み上がる。
「よくも濡れ衣を着せやがって。だけど、証明してやったぞ。あたしの身は潔白なんだってな。これであたしの勝ちだ!ざまあみろ!」
いつしか、それは哄笑へと変わり、顔を覆う両手は冷たく濡れていった。
あとがき
第55回NEMURENU(企画テーマ:自動的に消滅する)への参加作品です。今回が初参加です。
2万字くらい書きたかったのですが、約18'000字で挫折しました。江口夏実『出禁のモグラ』の人魚島編、呪いのゲーム編では、勧善懲悪の物語が破綻し自動的に消滅することで、まったく別の物語が浮き上がります。そんな作品を目指して書きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
