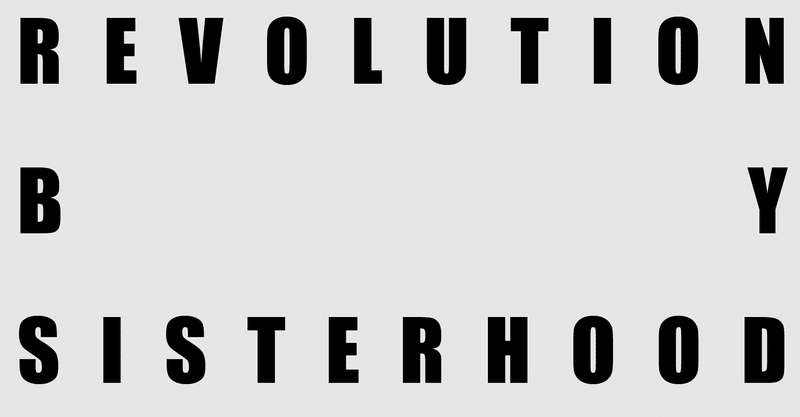
反『美術館女子』女性の主体性と連帯の可能性、それを無視するな
0. 前提 これは論文ではない、アジテーションである
前提としてあなたは『美術館女子』をめぐる議論における要点をある程度知っているものとする(例えば「女性というものを外部の客体として、無知の存在と見なすことへの批判」「芸術を感動という非知的に鑑賞することを推奨する点に対する批判」「女性が美術の中の深く関わっているのに、美術館女子としてそうした女性を無視することへの批判」「美術におけるジェンダーバランスの問題からこれは重大な問題である」などなど)。
私は今からそれとは少し違う話をする。違う話には要点が二つある。
一つは「インスタグラマーという主体をきちんと考える」。これを通して映えの主体性を考え『美術館女子』が持つ客体性を批判する。自撮りと場所を組み合わせて写真を撮影するインスタグラマーたちは─それが現代美術のジャンルに入るかはともかく─間違いなく行為主体である。しかし『美術館女子』の企画において彼女は客体として表されその主導性が乏しく、またこの議論も乏しい。ここでは女性の視線と、女性が見られること、そして女性の視線とされるもの、それへの嫌悪などが複雑に絡み合っている。画中画の歴史を踏まえつつ、インスタグラマーを巡る議論における女性嫌悪を考える。
もう一点は「美術館に関わる複数形の女性たちがどう連携していけるか」である。当然ながら美術館に関わる女性は多様である。まず学芸員にはとても女性が多い(一方で館長では女性が極端に少ない。これは「ガラスの天井」そのものだ)。また東京国立近代美術館の発表によれば来場者においても、男女数はやや女性の方が多いことがわかる。何故こうした既にある美術館にいる女性が、不可視化され、外部の女性だけが『美術館女子』として表象され、結果的に断絶を生むのか?この両者の間に連帯は可能なのか?なぜ女性は周縁化されその地位が著しく低いのか?それを考える。
1. インスタ、女性、主体、知性、それらを周縁化するな
言うまでもなく、「映え」と言う基準に従って場所を選び構図を決め、写真を撮るその行為は一つの表現手法だ。
しかし『美術館女子』企画ではその主体性は曖昧にされる。記事冒頭では「AKB48チーム8のメンバーが各地の美術館を訪れ、写真を通じて、アートの力を発信していく。」とあり記事内には「柔らかい光が差し込む館内で。「アート作品と共演するということで、今日のコーデは、作品のパワーに負けず、且つ、うまくなじむ色を意識してみました。映え写真、いっぱい撮れるかな?」」という本人のセリフを表す箇所もあるが、この記事における写真を誰が撮ったのかは曖昧にされている。
記事で見ることのできる写真は全て、女性と美術館が同じフレームに収まったものであり、三脚や雲台を想定しない限りにおいてこれが彼女自身が撮影したものであると判断することは難しい。実際末尾にはカメラマン大村克己の名前が記されており、この写真は彼によって撮影されたものであることがわかる。写真の撮影の指示は誰から出されたのだろうか?このような手法が美術の企画としてインスタに画像をアップする女性を表象するのに適切とは思えない。
テキストもまたこの曖昧さを補強する。写真に付記されたキャプションは本人がその時に見た感想と思しき文章を「」で区切り、それに解説を付与するが、ではこのテキストの書き手は誰なのか?
写真数枚ごとに、モノクロの東京都現代美術館を背景に本人の手のナルと思われる長文が挿入される。しかし冒頭と末尾の同じ形式で付された文書は、企画者側が書いたと思われるものになっている。
長文の書き手である小栗は「私の作品はどんな形でしあがるのか?」とし「新しい小栗有以がいる」さらに「アイドルではなく"作品"としての小栗有以」とさえする。
「私」は「私の作品」であるというアンビバレンツなこの宣言は、アイドル的なものであるのかもしれない。そもそも女性アーティストというものが、作者であり客としての作品であるという状況に長い間置かれてきた。そして現代美術とはそれに対する反抗の歴史であり、いかに女性という眺める主体を確立するか?という問いに支えられたものでもあった。
しかしこの記事においてはその作者性というものは、写真やテキストの提示の仕方によって曖昧にされ、本人の主体的な選択は「コーデ」のみしか読み取れないようにされている。この作品であり作者であるという性質が、徹底的に客体化され美術館女子として提示されるとき、この記事は小栗というアイドルから女性というジェンダー全般に至るまで、主体的な女性全般を毀損する。歴史を無化する。
文中では「私を含め、いま若い女性は「インスタ映え」に夢中だ」などとして「インスタ」「映え」との接続が図られる。しかし無論、こうした記事の持つ性格はそれとは大きく異なる。
小栗のインスタグラムには自身で撮影した風景写真や食事の写真が自撮りと共に多数アップロードされている。インスタグラム的な景色だが、選択された風景と自身の写真が並置されることで、作者としての主体性が極めて強く押し出されている。
シンディシャーマンは自身でもって女性のパロディを示すことで、客体と主体を打破しようとした。企画記事にも出てくる草間彌生はハプニングを通して女性の身体を主体化した。クロウドカウンら多くのレズビアンたちは写真を用いて客体ではない身体を示しジェンダーを越境する表現を用い、女性と女性の関係を示そうとした。近年でもUlamnやToledanoはインスタグラムを用いて女性の自己充足的な主体的欲望を自身の身体を用いて示している。それをポジティブなものとして無条件に肯定するわけではないが、女性アーティストがこうした主体の問題に取り組んできたことは尊重されなければならない。これらのアーティストが示した主体的な姿をも、『美術館女子』企画はインスタの写真を撮る女性から主体性を剥ぎ取ることで侮辱している。
インスタグラムで最も多くのユーザがいる20-30代の層では6割が女性を占める(ここでいう女性はむろん幅広い意味の女性だと私は理解している)。インスタ女子と言われる所以でもある。
撮影されるということがメインだった女性たちが積極的に自身を含めて撮影し、それに共感を示すことで、女性間の関わりを深める。友達同士の写真もそうした機能を持つ。この主体性と社会構築は、より広範な形で評価されるべきだ。そこで生まれる女性間の関係性のあり方は、従来の写真のあり方ともまた異なる。インスタや映えを雑駁な議論で片付けるのは、ある一面において女性嫌悪的な可能性を持ち得る。それをどのように捉えるににせよ、主体的な知性を私たちは前提にしないといけない。
そもそも作品の礼拝的価値が議論されたベンヤミを持ち出すまでもなく、芸術作品は所有と旅行との間に共犯関係を持ち続けていた。画中画やギャラリー画のような作品は、作品の中に作品を背景として肖像と共に書き込んだ。あるいはグランドツアーのような旅行のムーブメントと共に、ピクチャレスクな絵画は風景への欲求を掻き立てた。
もちろん「映え」の美学はこれとは異なる基準を持ち、これとは異なる社会的装置の役割を持つ。しかし、なぜこうしたインスタ的な文化が等閑視され、初めから否定されるのか?男性もホモソーシャルに対する女性のホモソーシャルのようなこうした文化を初手で切り捨てる事は可能なのか?
視覚の快楽と共犯してきた美術が「映え」をこうした議論を前提とせず直感的に否定するのであれば、それは『美術館女子』が行った主体性の隠蔽と同じ隘路に入り込むことになる。
否定されるのべきなのはまず、女性から主体性を奪い、インスタを周縁化し、その知的な可能性を拒絶する『美術館女子』の企画の態度であり、映えの文化それ自体ではない。アイドルも含め、それの対するミソジニックでマッチョな否定はあってはならないし、それでは何も変わらない 。無条件で肯定すべきものでもないが、無条件に否定されるべきでもない。
またインスタグラムは全体としては男女半々から男性の方がユーザー層が多く、このインスタ男性に目が向けられない理由についても私たちは考えるべきだ。むろん女子という言葉が持つ含みも考えねばならない。
特に対象が言説の蓄積が少ない場合には批評は正しく慎重に行われてほしい。
2. 美術館に携わる女性たちの個別性と、そのジェンダー不平等、そして連帯の可能性、それらを無視するな、そして可能性の話をしよう
ではどうすればそうした「インスタ映え」の知的な主体の可能性を考えられるだろうか?その発展の可能性に女性どうしの連帯は可能なのか?女性を無知に置こうとするジェンダー不平等にどう抗えばいいのか?そのことを考えるために美術館と女性についてを考えていく。
当然であるが、現代において女性は美術の周縁ではなく、ほかの種々の性と同じく中心にいる存在である。たとえ差別構造があるにしても。
美術館に関わる女性は圧倒的に多い。学芸員の7割は女性である。しかし、館長になるとこの数は大幅に減り、2割に満たなくなる。間違いなくこれはジェンダーの不平等を示す。
中世古貴彦氏による東京国立近代美術館の来館者の分析では、美術館来場者の男女比は半々でありむしろ女性の方が多いことが示される。中世古氏はこれ「美術館初心者」「東近美初心者」「リピーター」の三つの層に分けるが、この男女比は美術館初心者から、リピーターのようなコア層まで変わらない傾向である。また全体として20-30代の層が厚い(あとこういうデータがあるからここと層が被って見えるインスタを狙った企画が出されたのかもれない)。
私が所属する東京芸術大学においても学生の多数は女性であり、研究室の助手も多数が女性でありながら、教授の9割は男性である。
美術や美術館に関わるプレイヤーの多数が女性であるにも関わらず、その地位が上がっていくにつれ女性がむしろ少数になっていく。こうした傾向は決して今に始まったことではなく数十年以上も続いている現状だ。
美術館女子という単語は当然、こうした女性を含む広範囲な美術館を指す女性を指し示さなければならない(また女子という言葉の含むニュアンスがの差別性も検討すべきだった)。しかし前項で論じたように『美術館女子』企画はこうした現状を無視して「芸術をほとんど知らない」女性を客体化して商品として提示する。
この仕草により、美術館に関わる女性の多様性は隠匿され、各女性たちはそれぞれのセグメントの中で分断され、何よりこの圧倒的な差別性が無視される。
『美術館女子』企画は「女性目線で再発見」するというが本質主義的な意味においての女性目線とは架空のものでしかない。ただ、女性という経験をしたことによる視線は存在するかも知れず、数多くの女性作家と共にGuerrillaGirlsなどの明示的なフェミニズムアーティストを私は思い出す。
ある面において女性目線とは、この世界における女性差別を見返す視線でもあるはずだが、ここではそうした視線は無視され単に美術外部の無知である主体性のない存在として貶められる。なんならそれは、眺められる女性としての提示でさえあり、GuerrillaGirlsが作品で指摘した「女性は裸にならないと美術館には入れないのか?」というヌード作品の多さに対する女性作家の少なさを皮肉ったスローガンよりも後退したやり方でもある。女性が美術館に入るには女性が眺められないといけなないのか?
仮に、映えを求める女性の中に美術に無知な存在がいたとしても、それは全般において無知であり学習の機会を持たないわけではない。ましてや眺められる客体であるわけがない。むしろ美術館の生涯学習装置としての機能を思い出すのなら、そこにおいては知的な交流が図られ、学びが行われることが想定されなくてはならない。なぜそこでより積極的な女性同士の交流の可能性が閉ざされてしまうのか。
女性目線からの知性の剥奪は、結果として美術館と美術自体からも知性を剥奪し、感情という感性だけで作品を示すことになってしまう。記事内ではオノヨーコによる作品と小栗の共作も撮影されているが、オノヨーコこそまさにフェミニストのアーティストではなかったのか?女性目線から知と主体を奪うことで、作品が無化され、さらに女性同士の社会への反抗としての連帯の可能性さえ剥奪する、最悪でグロテスクな画面だ。それはまさに、美術と社会における女性のジェンダー不平等性をそのまま示したかのようでさえもある。
オノヨーコのようなアーティストであったり、来場者であったり、学芸員であったり、美術館に関わる女性は実に多様な主体が存在する。しかしこうした企画はそれぞれの女性たちの姿を覆い隠すことで明確に区別し、それぞれの場所の中で分断させ、学びの忘却により連携の可能性を消し去り、規範にとって無害なものへと変える。
なぜこのような企画でそうした複数形の女性が分断されねばならないのか?企画に見られる操作と仕草がまさに、美術界の中で女性を差別している根源の一端であることがより一層、暗澹とさせる。
そもそもインスタグラムはSNSであり、共感をベースにした相互関係性を育む。それがどのようなものであれ、そこには一定の女性同士の関係性が生まれている。時に危ういものであるが、このような回路をもって、美術に関わる様々な女性の多様な姿をつないでいく事はできないのだろうか?よりポリフォニックな女性同士のあり方を。
単一化され、眺められる対象としての「女子」ではなく、主体としての女性たち、美術館に関わる女性たちの、女性目線の美術の可能性は、知的な存在としての女性同士の交流による学習を、私は激しい怒りと共に今、望んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
