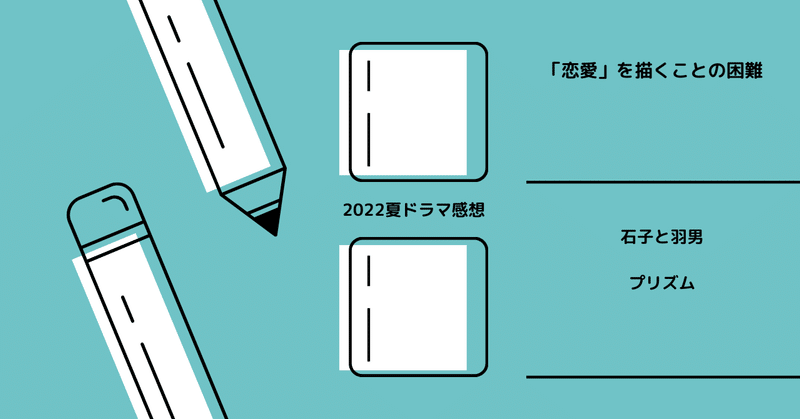
「恋愛」を描くことの困難——「石子と羽男」「プリズム」から考える
「プリズム」「羽男と石子」、今期のドラマでは、群を抜いて面白かった二作品。ともに現代社会におけるジェンダーや多様性の問題、そしてそれをドラマで表現することの困難について考えるうえで、きわめて示唆的な論点が含まれていた。それは、ドラマにおけるいわゆる「恋愛」要素の「取り扱い」に関係している。
「羽男と石子」は軽妙な台詞のやりとりにカタルシスがあり、毎回楽しみに観ていた。しかし観終わって、何かすっきりしない「もやっと感」が残った。まずこの「もやっと感」の在りかを明らかにしておきたい。
一昔前のトレンディドラマなどは、主として若者向けに作られ、誰と誰が「くっつく」か、誰が「ライバル」で誰が「当て馬」かは最初から(キャスティングをみれば)大体わかっていた。見え透いた行き違いやありえない誤解や余計な邪魔だてなどをふんだんに散りばめて、最終回にようやく結ばれる・・・、初回にお互い「好きっ!」って思っているのに、それを言ってしまうと「ドラマ」にはならないので、無理やり話しを引き延ばしているとしか思えない・・・、そんな「恋愛ドラマあるある」に気づきながらも、結局それを王道の恋愛ドラマとしてみんな楽しんでいたのだ。しかしそんな時代はとうに過ぎ去った。九十年代一世を風靡したいわゆる若者向け「恋愛ドラマ」はすっかり影をひそめ、今ではあまり作られなくなった=観られなくなった。視聴者はもはや「恋愛ドラマ」を求めていない、いやむしろ「主要キャスト——要するに主役と相手役——が男女だからといって安易に恋愛関係にするな」といった感覚のほうが主流になっている。つまり、すでに現代社会において進行中だったロマンティック・ラヴ・イデオロギー(恋愛至上主義)の衰退がドラマ事情にも如実に現れるようになった、ということだ。そしてこの作品にはこうした傾向が過剰に反映されていて、それが「もやっと感」に繋がっているのではないか、と思うのだ。
「石子と羽男」では、主要キャストの二人(有村架純と中村倫也)をただの「同僚」として描こうとする意志があまりに強く、そのために大庭(赤楚衛二)を登場させ石子との恋愛エピソードを入れたのでは?と思わせるほど、二人(石子と大庭)の関係には無理繰り感があった。逆にいえばそれくらい、石子と羽男の関係性のほうに「萌え」があったのだ。二人の軽妙な台詞のやりとりに、心に何か事情を抱えていることをまったく見えないようにお互い振る舞いながらもそれとなくわかってしまう・・・そうした微妙な関係性が反映されていた。つまり二人は、いつとも知れず自然に、お互い「弱み」を見せることができる唯一無二の相手になっていたのだ。そこには、単なる同僚や仕事仲間にはない、ある種の「親密さ」が漂っている。二人は、誰が見ても、妙にしっくりくる、相性がいいな、と思う関係を、会って軽口を叩き合ううちに、あっという間に築いていたのだ。それだけに、いったい石子は大庭のどこが好きでつきあうことにしたのか、どうして大庭とは恋愛で、羽男とはそうではないのか、がよくわからない。さらにいえば、「主要キャストを安易な恋愛関係にはしない」うえに「第三の男(あるいは女)が出てきても単なる当て馬にはしない」という強い意識が働いていたのかどうか、羽男と大庭の間にも——嫉妬や羨望といった感情とは無縁のどこかあたたかい——友人関係が展開して、最後には恋愛も友情も「超えた」三人の——おそらくまだ「名前」はない——新しい関係性を呈示しているかのようにも思えた。もしそうなら、それは果敢な挑戦的な試みとして評価されるべきなのかもしれない。しかし、そうだとしても——いやそうであればなおさら——ことさら二人の関係を「これは恋愛じゃない!」と強調するより、「石子と羽男」というタイトルどおりの、二人だけの「特別な関係」の繊細で丁寧な描写に撤すべきだったのではないか。そのほうが、制作者の意図はストレートに伝わったのではないか。たとえそれが視聴者の側で素直な「恋愛」関係に回収されてしまう可能性(危険性?)があったにしても。
「プリズム」は、ゲイの男性とストレートの女性と、(おそらく)バイセクシュアルの男性三人の「人間」関係を軸に、いわゆる「普通」の恋愛や結婚や家族のあり方を改めて問い直し、現代社会における「多様な」関係性の在りかを探る意欲的な作品である。セクシュアル・マイノリティを扱ったドラマとして「女子的生活」、「腐女子、うっかりゲイに告る」、「恋せぬ二人」など、NHKにはこれまで地道に積み上げてきた実績がある。「プリズム」もまたその期待に違わず、素晴らしいドラマだった。
園芸店でアルバイトをしていた主人公前島皐月(杉咲花)は、ガーデンデザイナーの森下陸(藤原季節)と知り合い、やがて陸が友人と立ち上げた会社で見習いとして働き始めた。二人は恋に落ちるというよりは、戸惑いながらお互いの距離を確かめつつ、手さぐりでどこかぎこちない関係を続けていく。皐月には、ゲイの父が母と離婚し今はパートナーと暮らしているという事情があり、「普通」の恋愛や結婚というものに積極的になれないでいた。また陸は、七年前突然理由も告げず自分のもとから去っていった恋人のことが忘れられずにいた。物語は皐月と陸、そして陸の勤める会社にガーデナーとして偶然やってきた陸のかつての恋人、大学時代の教師として陸を園芸の世界へと導いた白石悠磨(森山未来)の三人の関係を軸に展開する。
クライマックスは最終回直前の第8回。三人がそれぞれ心に蓋をして、相手を気遣いながら懸命にバランスを保ってきた「関係性」を一気に打ち破るかのように、本音をぶつけ合うシーンは圧巻だった。息詰まる台詞の応酬には、人を好きになることの苦悩と理不尽が溢れていて胸が痛くなった。しかしそれでも三人がそれぞれ、相手を深く思いやり自分自身と向き合うことで、「三人の関係」を「ここ」ではなくどこか未来の別の場所へと開いていこうともがいているようにも見えて、そこに微かな、希望の温もりのようなものを感じた。
皐月に背中を押された(いや、最後通牒を突きつけられた)二人は、もう一度ちゃんと向き合う時間をもつ。バーで語り合い、思い出の大学構内を巡り、まっすぐに思いを伝えあう。しかし、二人は時間を巻き戻す選択はしなかった。三人が作り上げたガーデンを前に、悠磨は皐月と、そして陸とハグをして去っていく。陸は「俺たち戻らなかったよ」と皐月に告げる。
最初観たときには、この結末にしばらく納得することができなかった。皐月が陸と悠磨の「まだ終わってはいない思い」の深さに気づき、傷つきながらも、必死で二人に自分の気持ちとちゃんと向き合うべきだと訴え、陸から離れる決意を口にしたことで、あぁこれでやっと二人の恋愛が成就するのか、と思ってしまった。このときの杉咲、森山の演技があまりにも素晴らしく、その後の展開(最終回)が蛇足のようにも思えたのだ。しかしそうした「期待」は見事に裏切られた。考えてみれば、7年間のブランクを「乗り越えて愛が成就する」という「期待」には異性愛におけるロマンティック・ラヴ・イデオロギー(恋愛至上主義)の心性が色濃く反映されている。結局もとにもどることなどない、時間を巻き戻すことなどできない、おそらくそれが現実なのだ。
そして最終回、三人のそれぞれの道が陸と皐月の家族を含めて淡々と描かれ、おそらくそこにこそこのドラマの描きたかったことの核心があらわれているのだと納得した。
皐月の本音の爆発は、三人が三人とも苦しくて身動きとれなくなっていた状況を、陸と悠磨の二人の関係に閉じるのではなく、三人がそれぞれの未来へと一歩を踏み出す方向へと解き放った。皐月は「陸と過ごせたから、私は前に進むよ」と言う。陸は、皐月と別れ悠磨とも離れた気持ちを「離れていても相手の存在を感じるだけで十分じゃないか」と表現する。皐月は、パートナーシップ制度を利用して新しい一歩を踏み出した父耕太郎と信爾、そして長い時間をかけて二人の関係を受け入れた母梨沙子が穏やかに談笑する姿を目にして、「こんな景色を見られるとは思っていなかった、まだまだ当たり前じゃないんだね」と言う、「少しずつだね」と返す陸。「世間」の「普通」の価値観に縛られる典型的な人物として、頑なに陸と悠磨の前に立ちはだかっていた陸の父親も、最後には息子への態度を和らげるような気配を見せる。彼もまた苦しみながら変わろうとしているのだ。
人間は「変わっていく」ということ、それがおそらくこのドラマの根底にある「希望」の在りかなのだと思う。「三人でこのガーデンつくれてよかった」と悠磨は去り際に二人に告げる。そして一年後、一人のガーデナーとして初めて仕事を任された皐月は、悠磨と陸に協力を申し出て、再び三人で一つの庭を完成させ、またそれぞれの道に戻っていく。バラバラになってもまたどこかで会える気がすると言う皐月に、悠磨は深く頷き「お互い変わりながらね」と返す。三人の関係性は、ガーデニングという共通の「大切なもの」=価値を核にして、おそらくどこにもない——まだ「名前」をもたない——新しいかたちを得たのだと思う。
このドラマは、こうした共通の価値やセクシュアリティの設定に工夫をしたうえではあるが、ジェンダーや年齢やセクシュアリティの違いを超えた——現在の支配的な家族観やジェンダー観に縛られないもう一つの——関係性がありうるということを、けっして絵空事ではなく説得的に示すことに成功した。「恋愛の成就」にカタルシスを求めるような心性を慎重にかわしつつ見事なソフト・ランディングを果たしたこのドラマは、主題歌「ヤバイね愛って奴は」の原由子の歌声のやさしい響きとともに、「傑作」として長く記憶されことになるだろう。
ただし、それでも一点だけ付け加えておこう。こうした評価はあくまで、異性愛の制度が支配的である社会において恋愛や結婚、家族に対する価値観が少しずつ変化し、セクシュアリティの多様性が受け入れられつつある、まさにその途上にある「いまここ」においてのみ成り立つものかもしれない、ということだ。「いまここ」においてもし悠磨を「ストレートの女性」と入れ換えてみると、おそらく三人の関係は「普通」の単純な「三角関係」に回収されてしまうだろう。そしてもしSOGIの理念通りに、百人いれば百通りの性自認とセクシュアリティのあり方が存在するという「現実」が当たり前となった社会においては、三人の関係は、多くの個性的で唯一無二の多様な関係性のなかの一つとして数えられるにすぎず、何ら特別のものではなくなっているだろう。このドラマは、そんな未来を志向する微かな「希望」のうえに、絶妙なバランスで成立した「傑作」である、ということだ。
amanatsu20230326
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
