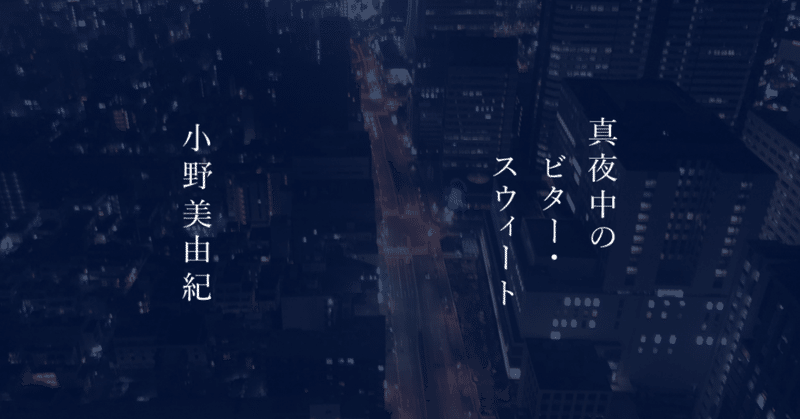
真夜中のビター・スウィート
バレンタインの夜、絶対にかけてはいけない人に電話をかけた。
「もしもし」
聞き慣れた低い声が聞こえたとき、驚いて思わずスマホを落としそうになった。
夢にまで出てきた愛しい人の声が、はっきりと耳奥に響く。
唇の動きまで、想像できそうなほどに。
「……絶対、出ないと思った」
声が震える。言葉をつなぎたくても、脳の奥がじんとしびれて舌が回らない。
「君と話したくて、待ってたんだ」
時計の針はもうすぐ12時をさす。バレンタインが終わる。
テーブルの上には、綺麗にラッピングされたチョコレートの箱が投げ出されている。
「ご家族は?」
奥さんは、と聞きたいのを、かろうじて言い換える。
毎年、渡せない、渡せるはずもないものを、会社に持っていき、鞄から出さずに家まで持ち帰っては、次の日のゴミに出す。
叶うことのない思いは、どんな食べ物よりも苦い。
やがて、淡い笑いを含んだ声が受話器の奥から響いた。
「君と、話がしたいから、電話を取ったんだよ」
電話の向こうは静まり返っている。まるで月の裏側の”静かの海”とつながっているみたいに。
「お久しぶり、です」
緊張して、変な挨拶が出てしまった。電話の向こうの彼の姿を、うまく想像することができない。オフィスで見慣れた笑顔や、うっかりデスクでうたた寝した時の、間抜けな寝顔はすぐに思い出せるのに。
「どう、元気?」
何でもない、みたいな声で彼は続ける。それが悔しくて、平静を装う。
「少し痩せました」
「仕事、忙しいのか?」
「理由、それだけじゃないです。知ってるでしょ」
「出張土産を渡してくる奴がいなくなって、ダイエット成功したんじゃないのか」
かすれた笑い声。笑うと鼻筋に浮かぶシワ。少し下がる目尻。
あれだけ叩き合ってた軽口が、オフィスで聞こえなくなってどれぐらい経つだろう。
「渡すって言ってたベルギー土産のチョコ、渡せなくてごめんな」
「太るからいらない、って言ったじゃないですか」
「太ったって可愛いよ」
限界だった。涙が溢れ出るのと、口を開くのがほぼ同時だった。
「なんで」
塩っぱい涙が、口元を濡らしてゆく。
ダメだ、と止めるように。
「なんで今なんですか……今までなんで黙ってたんですか。もっと早く、こうしてくれたって良かったじゃないですか。ずるいですよ」
「こんな立場で、慰めるも何もないと思ってたんだよ。早く忘れてくれたらいい、とも思ったし。……でも、毎年俺のためにチョコレート買い続けてる君を見てたら、いたたまれなくなってさ」
うちの会社はバレンタインは禁止だ。そうじゃなくたって、渡すのはおかしい。そんなことは分かってる。だからこれは儀式だ。叶わない、叶えちゃいけない、ということを確認するための。自分の気持ちを確認し、押しとどめるためだけの。
「知ってたんですか」
「知ってたよ」
体温が感じられそうなほど近くで、彼の吐息が響いた。
「生きてた時からね」
呼吸が浅くなる。
彼はもういない。その事実が、深く深く、胸に突き刺さる。
「君、俺が生きていた時も、毎年この日になるとすごく落ち込んでいただろう。俺と目を合わせようともしない。次の日はクマがすごいし」
「そんなことまで見てたんですか」
「メンターだからなあ」
「あの年はホッとしてたんですよ。あなた出張だったから、当日は顔を合わさなくていいって。……なのに、あんなことになるなんて」
繰り返されるニュース映像。上がる白煙。画面に映し出された、永遠に帰ってこない人の名前。
「先輩、好きです」
これまで絶対に口に出せなかった言葉を、私は口にした。
「うん」
「ずっと好きです」
「うん」
「ダメだって、いけないって、分かってたけど、好きでした」
溢れる気持ちだけ、止める堰を無くしてぽろぽろとこぼれてゆく。
沈黙。1秒、2秒。
やがて少し掠れた声が、耳の直ぐ近くで響いた。
「俺もだよ」
「ずるい」
私はそのセリフをかき消すように叫んだ。
「死んでから言われたって、どうにもならないじゃないですか」
彼の命日となった、3年前の今日。
4年続いた片思いは、あっけなく終わった。
出張中の事故で。
「なんで、生きてるうちに、一度でも言ってくれなかったんですか。
せめて一度でいいから、抱きしめてくれたら良かったのに」
一度でいいから、なりふり構わずチョコを渡せばよかった。
たとえ駄目でも、伝えればよかった。
「好きだよって、言ってくれたら良かったのに」
時間はもう、戻っては来ないのに。
「君を幸せにしたかったからだよ」
「は?」
「あのね、俺は、先輩として、男として、一人の大人として、君を幸せにしたかった。俺は君が好きだった。けど、それ以上に、君に幸せになって欲しかった。いつか、他の誰かと結ばれてくれたら良いと思ってた。俺は上司としてそばにいて、せめて仕事の面では誰よりも力になろうと思ってた……死んで、それもできなくなっちゃったけど」
「……あなたのおかげで、誰よりも強くなれました」
「頼もしいなぁ」
涙は後から後から出てきて、受話器から、胸元を濡らす。まるで部屋中を海にしてしまうみたいに。
「ごめんな」彼は言った。
「最後まで面倒見てやれなかった、ダメな上司でごめん。俺のせいで、時間を無駄にさせてごめん。死んでごめん」
どれだけ涙を流したら、この部屋はいっぱいになるだろう。私を沈めて、苦しい気持ちも、後悔も、呼吸も、止めて楽にしてくれるだろう。
「……ずっと願っててください」
鼻をすすり、むせながら、なんとか言葉を絞り出した。
「私が幸せになれるようにって。世界一、幸せになれ、って。願ってください。『初志貫徹』ってあなた、新年会の書き初めで書いてたでしょ、バカみたいに」
「バカみたい、かなあ」
くぐもった声が、耳奥で潮のように行ったり来たりする。
「うん、ずっと、ずうっと願ってる。誰よりも願ってるよ。だから、忘れろ。生きてる奴のために、チョコレート買えよ、来年は」
電話はそこで切れた。机の上の箱を開け、中身を取り出す。綺麗に並んだチョコレートの粒を、乱暴に全部、手のひらに開ける。いくつかがこぼれ落ち、床に転がった。彼の好きな苺のチョコ。口の中に、いっぺんに全部放り込む。
何よりも甘いはずのそれは、海の水を全部集めたぐらいに塩っぱくて、苦くて、私は後から後から出てくる涙と一緒に、それを飲み込むことも吐き出すこともできず、いつまでもいつまでも味わい続けていた。
執筆: 作家・小野 美由紀 (2019.02.10更新)
1985年東京生まれ。著書に、銭湯を舞台にした青春群像小説『メゾン刻の湯』(2018年2月)「人生に疲れたらスペイン巡礼 飲み食べ歩く800kmの旅」(2015)「傷口から人生」(2015)絵本「ひかりのりゅう」(2014)など。月に1回、創作文章ワークショップ「身体を使って書くクリエイティブ・ライティング講座」を開催している。
Twitter: @Miyki_Ono
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
