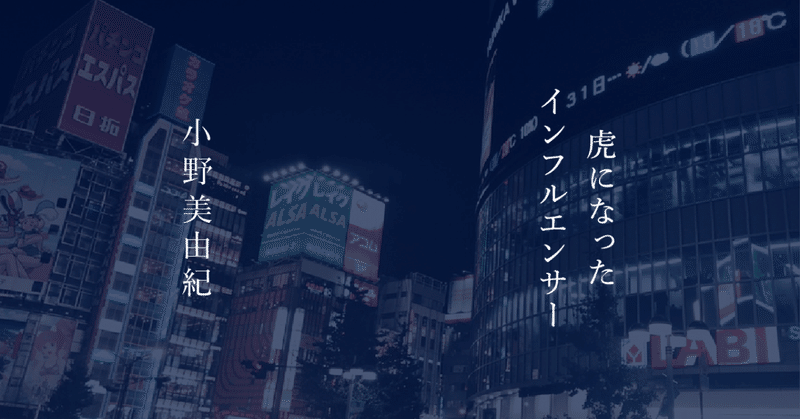
虎になったインフルエンサー
李徴がまじすげえカッコで薮の中から現れたから、おれはびっくりしてとりあえず写真を撮りまくった。
「ちょちょちょ、おまえやめろって。ツイッターにアップすんなよ」
「わり。だってお前、新しい服買ったときにはいつも写真撮れって俺に言うじゃん」
アップしようにもここは電波の届かない深い山の中だ。人里の明かりが山の辺の向こうにちらちらと燃えている。
「何、お前、そのカッコ。とりあえず配信した?」
「してない。お前にしか言ってない。肉球ツルツルして、スマホもうまく掴めないし」
そう言いながら李徴は地面にあぐらをかこうとするが、うまくかけないのでだらんと足を前に放り出して座る。その姿は狭いアパートの部屋で商品紹介動画を撮るときの、いつもの彼のままだ。
「どうすんの、お前。来週一緒にLINE LIVEやるって言ってたじゃん」
「わりい、無理だわ」
李徴は猫座りのまま、深いため息を吐いた。
「一体どうしたんだよ」
俺の友人、「りちょー」こと李徴はインフルエンサー志望だ。
25歳の誕生日に彼は「もうこれが最後のチャンスだ」と言って会社を辞めた。Twitterに Youtube、InstagramにTikTok、あらゆるメディアを駆使して日々自己発信し続けている。組織の力を借りずに自分の発信力でみんなを楽しませる人間になる、と豪語する彼のフォロワー数は6000人。俺としてはそこそこじゃん、と思うが、李徴にとってはまだまだらしい。
そんな彼から突然LINEで呼び出され、二人でよく遊んだ実家の裏の山に行ってみると、李徴は白い一匹の大きな虎に変身していた。
「昨日、◯◯さんがザイ・ゲームスの製品発表会に呼ばれたんだよ。あいつ、俺と同じくらいのフォロワー数のくせして許せねえ」
李徴は急に吠え始めた。鋭い牙をむき出し、地が震えるような唸り声を喉奥から漏らす。
「俺なんか毎回新商品が出るたびに自腹切ってレビューしてるんだぜ。なのにあいつ、ちょっとツイートがバズったくらいで調子に乗りやがって。俺よりも不細工だし、喋りだって下手なくせに、ただブランディングがうまいだけじゃねえか」
インフルエンサーの実力を決めるのは美醜でも喋りの面白さでもなく、今持っている武器や長所をどれだけ大きく見せられるかである、と先週李徴は得意げに話していたのだが……。
「で、なんでそんな風になっちゃったんだよ」
俺は慌てて話題を変えた。
「どうやったら人気が出るか、ずっと考えてたんだ」
ぐるぐるという喉の音に紛れて、李徴の声は聞き取りづらい。
「俺には何にもねえ。スペックがめちゃくちゃ高いわけでもねえし、ツイッターで面白いこと言えるわけでもねえ。Tiktokもイマイチ使いこなせてねえし」
あんがい自己分析できてるんだなぁ、と俺は感心した。
小学生の頃からずっと仲の良かったこいつの挑戦を俺は応援していたが、同時に心配でもあった。プライドが高く、ちょっとのことですぐに傷つくくせに、内省が足りずにすぐに新しいことに手を出しては失敗する。しばらくすると「あれは俺には向いてない」などと言い出しまた別のものに手を出す。李徴は俺からすると、典型的な「イキオイはあるけど、ちょっと足りない」やつだった。
「だからさ、俺、思ったんだよ。俺の人気がないのは、ひょっとしたら俺が俺だからじゃねえのかって。……だってさ、もし俺が可愛い子だったら、顔出しして乳見せれば一発だろ」
「……」
「だから、俺、神様にお願いしたんだ。お願いします。俺を猫にしてくださいって。SNSでどうしても影響力が欲しいんですって」
「なんで猫なんだよ」
「だってさ、SNSで”映え”る動物って言ったらやっぱ猫だろ」
俺は頭を抱えた。
「それなのに、何で虎になっちゃったんだよおお」
李徴は咆哮した。月明かりの下、白い毛並みが震えている。
「なあ、虎ってどう? 人気出るかな?」
「……一般受けは、しないんじゃねーの」
「引きで撮ったら、猫に見えるかなぁ!?」
「……お前さあ」
俺は言った。
「なんでそんなに有名になりたいんだ。別に今のままだっていいじゃねえか」
SNSの運用は一朝一夕ではいかない。一つのアカウントを時間をかけてじっくり育ててゆく。コツコツフォロワーを増やし、自分の関心のある記事を書いて反応を見ながら改良を重ねる。その繰り返しだ。ということを、大学時代に趣味で始めた音楽レビューサイトにそこそこのPVがつき、副業としてまずまずの額を稼ぎつつそのままフリーの音楽ライターとして業界の隅っこで活動している俺は知っている。だが、李徴はそういう努力が苦手だった。
「お前はうまくいってるからそう言えるんだ」李徴は虎の目できっと俺を睨んだ。さすがに迫力がある。
「お前には才能がある。けど、俺には何にもないんだよ」
俺が食えているのは地道な更新とファンに刺さる話題選びのおかげだと思うが、彼の目にはどうやら特殊なフィルターがあり、他人の努力や工夫といったものは一切、そこを通過しないようなのだ。
「あのな。会社っていうのは、個人の声なんか封殺されちまうんだよ。組織の倫理や理屈が第一で、何を言ったかじゃなくて、権力持ってるやつの意見だけが全てなわけ」
「まあ、そうだろうな」
「俺はそういう社会を変えたいわけ。誰もが自由に発信して、個として輝く社会を作りたいのよ。けど、無名のサラリーマンである俺がそんなこと言ったって、何の意味もない。……あのな、発言ってのは、誰が言うかが重要なんだよ」
李徴の瞳がぎらりと輝いた。飲み屋で夜も更けた頃、毎度繰り返される「夢」の話をする時と同じ、つんのめったような目。
「いいか。フォロワー数の少ない奴が何言ったって、誰も聞かねーの。有名なアイツやあいつが言ったからってことでみんなウンウンうなずくんだよ。人に話聞いてもらおうと思ったら、まずは俺自身がフォロワー増やして、有名になって成功しなきゃダメなんだよ。人気者になる方が先なの。そうしないと、誰も俺の言うことなんて聞いてくんねーんだよ」
「俺がいるじゃん」
李徴の丸い耳がピク、と動く。
「俺じゃダメなのかよ」
李徴は黙り込んだ。そのまましばらく張り子の虎のように首を左右に振っていたが、そのうち、藪に鳴く鈴虫のようなかすかな声でこう答えた。
「……あと、俺は女にモテたい」
はあ、と俺は溜息をついた。
「おまえさあ、焦りすぎだよ。いいじゃん、今だって。おまえのこと好きな奴はたくさんいるし、友達だっているだろ。そりゃ、まあ、誰かに比べたら、おまえにとっては十分じゃないかもしれねーけど、そんなすぐに人気なんか出ねーよ。焦ったってしょーがねーだろ」
「怖いんだ」不意に、人間だった時の李徴の声がした。
「俺、他には何にもねーし。社会的な影響力つけないと、足元から崩れていきそうで」
夜の闇が、俺と彼の間を遮っている。俺は李徴に手を差し伸べようとした。
「ああ~っ!」
急に、李徴はまた吠え始めた。
「忘れてた!これじゃ来週のYoutuber交流会いけねーじゃん、あの広告案件、××に取られる!……ああ、ちくしょう、なんであいつが有名なグラドルと付き合ってんだよーっ! 俺の方が、ずっと、ずっと面白いのに~っ!!」
「……李徴、とりあえず、2人で配信やろう」
俺はもう一度、はあ、と大きく溜息をついた。
「コンビYoutuberとして頑張ろうぜ。人間が喋るより、トラが喋る方が面白いと思うし」
「マジ?」
李徴はぐるりとこちらに振り向く。
「うん、マジマジ……俺たちさ、こっからだろ」
彼はベロンと大きな舌で顔を舐めて言った。
「超リアルなVTuberだと思ってもらえるかな?」
こうして俺たちは2人で活動を始めた。
さすがに珍しかったのか、最初の3日間はトレンド入りするほどの再生数で、李徴の喋りが絶望的につまらないことを除けばそこそこの滑り出しである。
李徴には「まだ企業からのタイアップ案件は来ていない」と伝えてあるが、先日、俺のメールボックスにペットフード会社からの広告案件の依頼メールが届いていた。
そのことを、俺はまだ彼に言いあぐねている。
執筆: 作家・小野 美由紀 (2019.01.06更新)
1985年東京生まれ。著書に、銭湯を舞台にした青春群像小説『メゾン刻の湯』(2018年2月)「人生に疲れたらスペイン巡礼 飲み食べ歩く800kmの旅」(2015)「傷口から人生」(2015)絵本「ひかりのりゅう」(2014)など。月に1回、創作文章ワークショップ「身体を使って書くクリエイティブ・ライティング講座」を開催している。
Twitter: @Miyki_Ono
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
