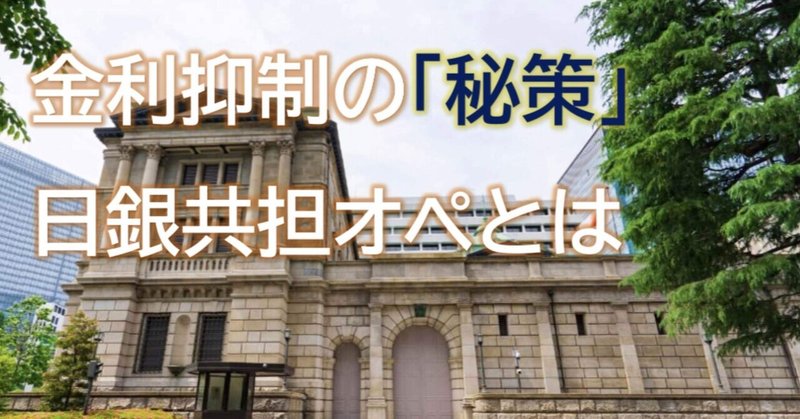
金利抑制の「秘策」日銀共担オペとは
足元の日本の長期金利は0.4%を下回る水準となっており、前回の日銀会合前の0.5%を上回る水準からみると、やや落ち着いた金利動向となっています。
日本の金利低下圧力に一役買いそうな「秘策」として注目されているのが”共担オペ”と言われるものになります。
共担オペとは、「共通担保資金供給オペレーション」のことで、日本銀行の金融政策手段の一つとなっています。
共担オペは、民間金融機関が日銀に国債などを担保として差し入れる代わりに、日銀から資金調達をする仕組みとなっています。
この制度自体は以前からありましたが、返済までの期間が短いなどの制約があり、主に短期金利を押し下げるための政策でした。
共担オペには「固定金利方式」と「金利入札方式」の2種類が存在し、前者は固定金利で貸し出す方法で、後者は入札で決まった金利で資金を供給する方法となっています。
日銀はこの共担オペの仕組みを前回の会合で変更しました。
具体的には固定金利方式での資金供給を0%から、貸付ごとに金利を決定する仕組みに変更されました。
また、金利入札方式は貸出期間の上限が1年から10年に拡大されました。
これにより、民間金融機関が従来よりも共担オペを利用しやすくなり、日銀から調達した資金をもとに利回りの高くなった日本国債を買いことで、利ざやを稼ぎやすくなると言われています。
日銀はこれまで、市中から国債の買付けを際限なく行うことで金利低下圧力を維持してきましたが、買付けが常態化するとともに市中に出回る国債の在庫が枯渇してしまう懸念がありました。
そこでこの共担オペの仕組みを変更することにより、民間部門で金利低下圧力を生み出そうとしています。
この制度変更に対して市場がどれほど反応を示すか注目されている中、23日に初となる5年物の共通担保資金供給オペの入札が行われました。
結果は5年物の共通担保資金供給オペ1兆円分(金利入札方式)のアナウンスに対して、応札額が3兆1290億円、落札額が1兆3億円となりました。
結果としては初回にしてはそれほど旺盛な需要があったとは言えない内容となっており、足元の長期金利水準が0.375付近と金利はやや抑制水準となっているものの、今後の制度運営には懐疑的な見方が残る結果となりました。
2月中の国会にて、岸田首相は次期日銀総裁人事案を提出するものとみられており、その後政府日銀の共同声明が変更されるのか、日銀は大規模緩和路線から明確に脱却するのかが注目されています。
前回日銀会合前の金利動向からも、海外勢は特に日銀の政策修正は不可避と見ている投資家は多いと思われ、日本の金利上昇圧力とそれに伴う円高圧力が今後も強まっていく可能性は高いままと思われます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
