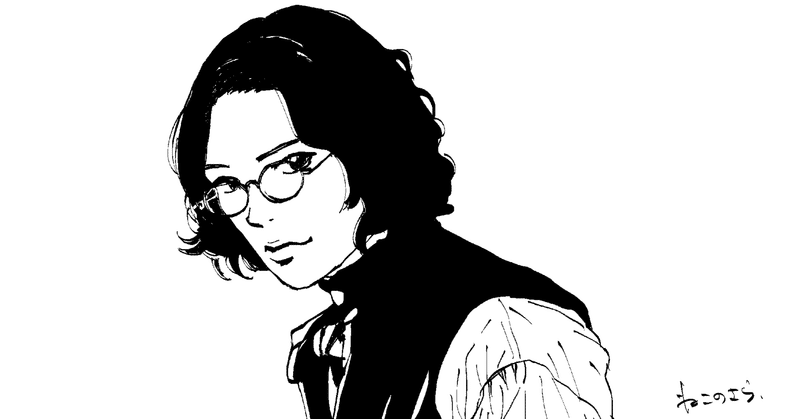
DON'T JUDGE A BOOK BY ITS COVER
何か難解な横文字をつらつら並べて
流暢に自信ありげに話している人を見て
まったく理解できていないのに
わからないことが恥ずかしくて
知ったかぶりをして頷いてしまう
そういうもう一周まわって恥ずかしいやつ
わからないことは素直に聞いた方が絶対良い
無知の知って遥か昔ソクラテスも云ってた
馬鹿でもわかるように話すのは本当に難しい
だから本当に頭の良い人は
すごくわかりやすい話し方をする
逆に頭を良く見せようとする人ほど
小難しい言葉を使いたがる
偶にレアケースで頭の良い人たちが
言葉遊びで使って遊んでいるケースもあるけど
言葉選びは知識とセンスが必要で
聞き手に合わせる器量も大事
そもそも
人と人のコミュニケーションは不完全なもので
お互いに見えている景色が違うことを
完全に説明は出来得ない
話し手も聞き手も
お互いに近い所を模索しながら合わせる作業だ
デジタル比喩するなら
相手の解像度に合わせる
どうやらオンラインサロンとやらには
言っている側も聞いている側も
相手のことを理解しないまま
都合の良い解釈をしているだけということが多いみたいだ
まさに蒟蒻問答
蒟蒻和尚と旅僧のやり取りのようだ
以下概要
上州安中に六兵衛という蒟蒻屋がいた
江戸のやくざ者であったが、今は堅気となって田舎暮らしをしている
面倒見の良い親分肌で、江戸から逃げてきた銭の無い若い衆が
六兵衛を頼って訪ねてくるとしばらく世話をしてやり
いくばくかの銭を渡して江戸に帰らせてやっていた
八公もその一人だが、いつまで経っても江戸に帰りたがらず
仕事もしたがらない
困った六兵衛は近所の禅寺がしばらく無住だったことを思い出し
八公にそこの坊主になることを勧める
渋々その寺の坊主になった八公であったが
田舎寺のためそうそう弔いなどもなく、怪しいお経を読み
寺男を相手に酒を呑んではだらだらと過ごしていた
ある日、越前永平寺の沙弥托善と名乗る旅僧が訪ねてきて
この寺の大和尚と問答をしたいと願い出る
禅問答などしたこともない八公は
「和尚は今出掛けているから」
と嘘をついて旅僧を追い返そうとするが
旅僧のほうは和尚の帰りをいつまでも待つ、と一歩も引かない
どこかへ逃げようかと考えた八公だったが
そこに現れた六兵衛が話を聞き
「俺が和尚のふりをして何とか追い返してやる」と申し出る
旅僧が本堂に踏み入れると袈裟を着て
和尚になりすました六兵衛が待ち構えている
しかし、当然ながら六兵衛に禅問答の知識などないため
旅僧から何を問われても無視してしびれを切らせようという作戦に出る
話かけても何も答えない相手を見て
旅僧はこれは禅家荒行の無言の行であると勝手に勘違いし
ならばと身振り手振りで問いかける
旅僧が両手の指を付けて小さな輪を作ると
六兵衛は腕も使って大きな輪を作り
それを見た旅僧は平伏する
しからばと僧侶が10本の指を示すと
六兵衛は片手を突き出して5本の指を示し、再び僧侶は平伏する
最後に僧侶が指を3本立てる様子を見せると
六兵衛は片目の下に指を置いた
そこで僧侶は恐れ入ったと逃げ出すように本堂を出る
陰から様子を見ていて驚いた八公は僧侶に負けた理由を訪ねた
旅僧曰く
「途中から無言の行と気付き、こちらも無言でおたずねした
『和尚の胸中は』と問えば『大海のごとし』
では、『十方世界は』と問えば『五戒で保つ』と
最後に『三尊の弥陀は』と問うたところ
『眼の下にあり』とのお答えでありました
とても拙僧がおよぶ相手ではなかった」と語り、悄然と寺を立ち去った
とにかく六兵衛が禅問答に勝ったことに関心した八公が本堂に行くと
六兵衛が激怒している
聞けば「あの坊主はふざけた奴だ
途中で俺が偽者でただの蒟蒻屋だと気付きやがった
『お前ん所の蒟蒻は小さいだろう』とバカにしやがるんで
『こんなに大きいぞ』と返してやった
野郎、『十丁でいくらだ』と聞くから『五百文』と答えたら
『三百文にまけろ』とぬかしやがったんで『あかんべぇ』をしてやった」
日々感じたことをジャンル問わず つらつら書いてます おもしろいなと思ったら フォローおねがいします
