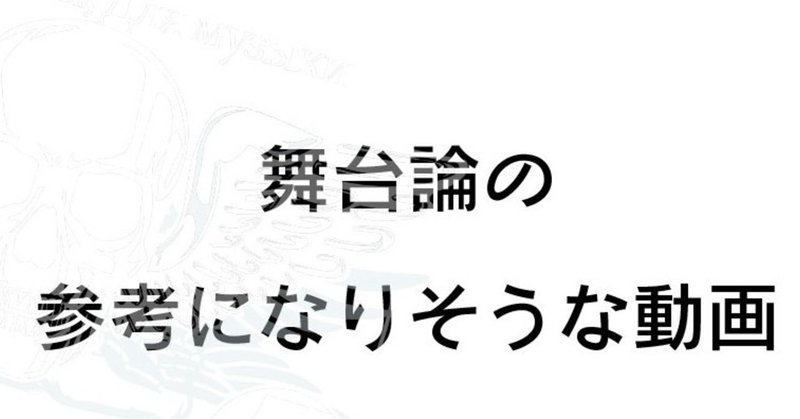
ヒッチコックのサスペンスと舞台論
先日777の反省会の際に舞台論の手本になるような動画は無いかという話題になりました。各バンドさんによって具体的な部分は変わってくるためこれというものは提示が難しいのですが、エンタメの基礎になるようなものは先日見た猫の動画が適切だと思いますので紹介と解説を入れて見たいなと思います。
まずは動画をご覧ください。
Leave no buddy behind pic.twitter.com/iT504ACTwp
— Life on Earth (@planetpng) September 11, 2020
(以下は動画をご視聴後に読んでもらった方が伝わりやすいと思います。っていうか可愛いから見て)
ヒッチコックのサスペンス
最近、ヒッチコックの映画術を読んでいますが、彼の言う所のサスペンスと自分がまとめようとしている舞台論は近いものが有るような気がしています。
この動画もサスペンスが存在している訳ですが、こういう時最も参考になるのは「自分自身がどう感じていたかを適切に思い出す事」のように思います。この動画の場合どうだったでしょうか。自分が感じた流れをまとめていきたいと思います。
なるべくピュアな反応を記憶しておいてもらいたかったため、字数を稼ぎましたが、この動画は簡単に言えば子猫を母猫が救出する動画です。
おおよその流れは以下の通りです。
1.最初に3匹の猫が目に入って何か下の方を見ている。
2.一匹の猫が飛び降りるとそこには子猫が居て、救出しようとしている。
3.ジャンプするが失敗する。
4.もう一回飛び降りて再度挑戦しようとする。
5.無事着地して4匹はその場から立ち去る。
自分自身の心の流れを振り返る
心の流れを思い出してもらいたいのですが、恐らく皆さんもこんな感じだったんじゃないかなと思います。
かわいい
1.3匹の猫がいる。下を見てる。かわいい。
2.子猫がいる。かわいい。
びっくりする
3.ジャンプしようとして失敗する。大変だと思う。転がり落ちる猫が目に入る。
応援する
4.もう一回救出に向かう猫。そこで大丈夫? もっと上じゃなくていい? あるいは、その高さならいける!
おめでとう!
5.無事着地して立ち去る猫。何とも言えない達成感がある。
動画としてはとても単純で、簡単な中身なんです。重要なのは一回失敗していること。だからこそもう一回挑戦しようとする猫に感情移入が出来る訳です。
失敗したことによって、その階段の高さが子猫を連れたままでは難しい壁である事、敵である事、そしてもう一度のジャンプがそれなりの挑戦である事が映像で理解が出来ます。ヒッチコックはこれをサスペンスと呼びました。カイジの鉄骨渡りが舞台論の基本だと以前言いましたがそれと全く同じで、挑戦するものがどういう物かが伝われば応援を呼び寄せる事が出来ます。
それと同時に、多くのバンドさんの取り組みの間違い。モノサシの狂いがここにあると言う点に注目してもらいたいんです。
バンドに置き換えてみてみる
バンドマンさんが告知などに良く使う要素。これをこの動画に例えてみるとそれぞれどのようになるでしょうか? まずは洗い出してみたいと思います。
新しい機材の購入。速弾き。ライブ告知。衣装。演奏の上手さ。楽曲のよさ。その日のライブの良さ。メンバーの紹介。スタジオ入った。新曲作った。音源作った。対バンがこの人。
それぞれこの動画内ではどの要素になるでしょうか?
例えば機材は猫の健康状態。速弾きはジャンプのスピード。告知はジャンプするポイントの予告。衣装は毛の柄。演奏の上手さはジャンプの上手さ。楽曲の良さはジャンプ時の姿勢。その日のライブの良さは放物線の良さ。メンバーの紹介はその場にいた猫。スタジオはジャンプの予備動作。新曲は新しいジャンプの姿勢。音源もジャンプの姿勢。対バンはジャンプする猫の品種です。
全て例外なくジャンプ時の話です。皆さんはこの動画を見ていたとき、ジャンプ時の猫の品種がだとかジャンプの高さだとかそんなものを評価の対象にしましたか? してませんよね。要すれば多くのバンドさんの取り組みと評価のモノサシが狂ってるんです。
この中で引きつける要素があるとしたら衣装などの見た目だけです。動画を見てもらうためのフックになりうるものですが、それも本質的なものではありません。代用が効きます。この動画でハラハラドキドキを生み出し、次のジャンプまで視線を引き付けたものは、この中には無いんです。つまりお客さんの目を引き付ける力はこの中の要素にはほぼ無いんです。
一回目のジャンプの失敗。そして転がり落ちた猫。これが次回の挑戦に対して応援をしようとする、その高さからジャンプしたらまた子猫が転げ落ちるんじゃないか、いや、きっと行けるっていう失敗して欲しくない、成功して欲しいっていう応援です。これがヒッチコックの言うサスペンス、引き付ける要素で、自分の言う舞台論の中身と重なる部分です。
お客さんが一体何にお金を出すのか。お金を出したいと思う要素は何なのか。本当に重要な要素は、階段と、高さと、挑戦(失敗した時のリスク。例えば777なら会場費等の経費全額)であって、これを応援したいと思う気持ちを生み出すことでお客さんの財布からお金が動きやすくなります。もっと言えば、バンドさんが普段告知に使う内容は動員を産む力に乏しいものです。
バンド、興行が挑戦しようとしている物はなにか
ここはもう少し抽象度を上げると、バンドさんが挑戦しようとしている物は何か、という話になります。
殆どのバンドさんがライブ告知、つまり「ジャンプします」、「ジャンプします」だけ告知するんです。そして「ジャンプしました」、「ジャンプしました」だけの告知になり、ライブとライブの間にエンタメ性が有りません。お客さん側も、バンドや興行の何を応援したらいいのか一切伝わってないんです。
ライブとライブの間にお客さんをつなぎとめる「間」がない。間が抜けている。つまり文字通り「間抜け」の活動になってしまっていて、多くの場合、単純にバンド側に挑戦している物が無いためにここを埋められていません。この挑戦を作るのはバンド側の仕事でもあり、興行を作る人の仕事でもあります。
次回のライブで何かしら挑戦した結果を叩きつけられることが明確であれば、多くのお客さんがその結果を見るために応援する動機を得る事が出来ますが、間を抜いたただ何となくぽんぽんと乱発的に発生したライブでは訴求力を得る事はまず無理です。
ですのでまずはバンド側が何を挑戦しているのかを解りやすく明確にすることが第一歩。そして、毎回出るライブに対して主催者側が趣旨を明確に持っているかをバンド側もしっかりと吟味する事。この2点がクリアできるバンドさんが増えれば応援してくれる人は増えるでしょうし、自然とライブハウスも盛り上がってくるのではないかなと思います。
作品作りの概念を、楽曲作り、ステージ作りにとどまらず、ライブが終わってから次のライブが終わるまでの期間も作品にする、を意識し実践できる人が増えてくれる日を願っています。
長文へのお付き合い有難うございました。
主催イベント
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
