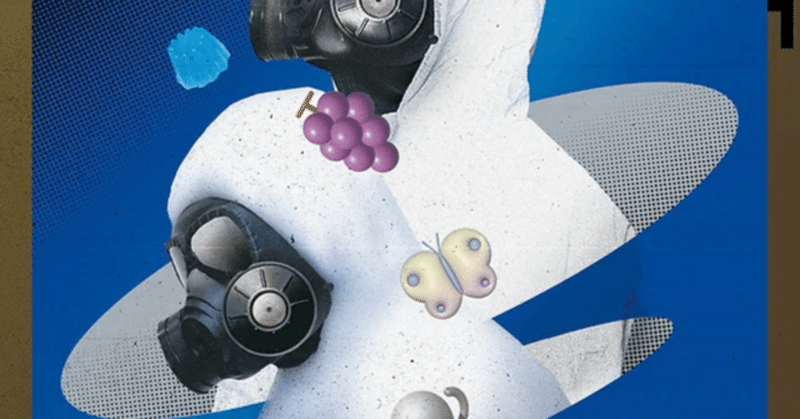
劇団壱劇屋「空間スペース3D」
劇評をしてみる
はじめまして。
私を見つけてくれてありがとうございます。
私が壱劇屋さんのファンになって、まもなく5年が経とうとしています。
初めて観劇した壱劇屋さんの作品は「劇の劇」でした。
まだ私が演劇とか舞台芸術とか、「芸術」に興味を持ってから半年の時に、初めて「お金を払って観劇する」という行為に触れた機会でした。
高校一年生の冬、金曜日の夜。
父にわがままを言って、大阪まで連れて行ってもらいました。
心斎橋まで車で1時間半。どうしてこんな無茶ぶり、父は承諾してくれたんでしょうか。
大阪へ引っ越してきてから、かなり観劇に赴きやすくなった気がします。
やはり演劇は都会のほうで催されがち。観客も集まりやすいもんね。
この度、「空間スペース3D」を観劇してきました。
観劇?
なんて言うんだろう。演劇・・・ではあったんだけど、よくあるあのステージと客席が向かい合った形式を想像していくと驚愕します。
オールスタンディング形式。名前の通り、ステージは目と鼻の先、周囲360°どこを見渡しても演劇が散らばっていました。
イメージはライブです。
クラブです。行ったことないけど。
そして最も特徴的だったのは、この作品に明確なストーリーがないということです。
物販には戯曲も販売されていて、もちろん細かなストーリーで構成されてはいるんですが、どっちかと言えば観察に近い感じ。水族館に行くときれいなお魚たちが泳いでいて、その無垢さになにか感じることがあったり、新たな発見があることでしょう。けれども、そのお魚たちが何かを創造しているわけではなく、私たちはあくまで魚の本能が築く自然の摂理に感銘を受けているはずです。空スぺもそんな感じ。
大熊さんの脳内にある端切れを縫い合わせたような、喜怒哀楽の要素満載なイベントでした。もはや演劇ではなくイベント。
誰にも相手されなくなってしまった廃墟な空間に重なるたくさんの物語
そもそもこの作品はリクリエーションなんですね。
最初はというと・・・2019年。なんと「劇の劇」の一作前!私が壱劇屋さんと出会う直前のお話ですね。
初作、観たかったなあ。時代は目まぐるしく廻るもので、やっぱり流行りが移り変わると、演出家の意識にかかわらず、取り入れるものって変わると思うんですよね。そのとき社会で評価されていたものが、時代の変化に伴ってタブー視されることってあると思うんです。「イクメン」みたいにね。
どの空間にも同じことが言えます。
あの時爆発的に流行って、人の姿は絶えずいろんなことが催されて、必ず賑わっていたあの場所は、いつしか埃っぽく薄暗くなってしまう。なんだかさみしいけれど、そんなのよくある話です。
もう使わなくなってしまったその空間の現在を誰も知らないし、わざわざ自分から知りに行こうと思うわけでもない。
どうせ何もないからでしょうか。いいえ、空スぺでは、その空間で確かに生命は活動していて、死んでいてもなお生きようとしたり、愛する人や会う必要がある人に会いたがったりして、しっかり生命としての本能を果たします。
身近にいそうなキャラクターもいました。郵便配達屋さん。新婚さん。複数のエンターテイナー。受験生。
3次元ではありえないキャラクターもいました。点Pの擬人化(数学的に言うと存在しますが、今回はもっと現実的に)。内臓がメジャーの宇宙人。
多種多様なキャラクターたちが最終的に目的を果たすと、観客は達成感で満たされます。観客である私たちは、ものすごくキャラクターに感情移入してしまうんです。きっと私たちはあの空間で、ただの観客ではなく、「観客役」だったんだと思います。
今度こちらも書くんですが、リプレイ公演シリーズの「6人の悩める観客」でも私たちは観客役をした記憶があります。このへん、言わずもがな大熊さん節ですね。バチバチに。
「どうだった?」と訊かないでほしい
世間話をしていて、「前の休みに、舞台観劇に行ったんです」と言うと必ずと言っていいほど「そうなんだ。どうだった?」と訊かれます。
普段から舞台観劇をする習慣がない人にとっては、「壱劇屋さん」とか「空スぺ」とか言ってもピンとこないはずですから、空スぺ以前に、演劇という未知のジャンルに対してがんばって話題を広げてくれているんですよね。私は演劇を観たことがない人にこそもっともっと観てほしいと思っているので、語るのをやめるつもりはないんですが、今回ばかりはどんな風に評価していいのかわからないというのが正直なレビューです。劇評をしてみるとか言っといてですけど。
空スぺにはあらすじが存在しないと感じたんですが、いかがでしょうか。いろんなSNSで、空スぺを観劇した人の感想をリサーチしてみましたが、あらすじをまとめられている方は見つかりませんでした。そもそも、フライヤーにも記載されていないし。
登場人物一人一人に存在意義はあるんだけれども、あくまで大衆というか、世間というか。とにかく雑多で、キャラクターの存在に共通点はないです。
ただひとつ確信をもって言えるのは、空スぺを観劇すると、もれなく推しができる。そんな気がしました。キャラクターとしての共感に苛まれることはもちろん、俳優さんの人間性とか、大熊さんの脳内とか、現実的な部分にも沼っていく気がします。それくらい距離が近いんだもん。
アフターイベントもとにかく距離が近くて、役者さんとのツーショット、何枚も何枚も増えていきました。ちなみに写ってくださった役者さんは皆さん初めましてです。
唯一できなかったこと
そうそう。今回、すごくむず痒い点がひとつだけありました。
作中に登場した「あっぱれヒゲ丸」というYouTuberを演じていた方が、リアルタイムで現実世界のYouTubeに生配信していたんです。
非常に前衛的な策略に驚きました。だって観客は今、自分が観ている世界に枝が生えて、ネットというもう一つの世界が派生しているという事実に思いを馳せてしまうし、都合が合わず行くことができなかった人が雰囲気だけでも楽しめたり、それが宣伝となって当日券を買うきっかけになったりするんですよね。実際に「空スぺを観に行った」と話をしたら、「知ってる。あんた映ってた」という会話もしました。
だけど、私は逆に、ほんのちょっとだけ悔しかったです。
やっぱり演劇は映像よりもリアルのほうが臨場感が増してのめりこみやすいことは大前提ですが、「今その場で空気を楽しんでいる人だけは、その映像を楽しむことができない」という点だけがすごく気になっちゃいました。
あっぱれヒゲ丸さん、YouTubeの撮影では、基本的に自分は映らず声だけ出演するスタンスでした。きっとその声は台本ではなく完全アドリブで、今画面越しに映っていることに対して言葉巧みにツッコミを入れていきます。
だからヒゲ丸さんが近くに来た時、必ずなんだかブツブツ仰っていたんですよね。そのツッコミが的確ですごくおもしろいだけあって、ヒゲ丸さんの作品を観ることができないということだけが心残りです。参戦しなかった回の放送を観る、そういうことでもないんですよね。わかってくれるでしょうか。
空想を可視化する
舞台芸術の醍醐味ですよね。私たちが一度はあこがれたこと・・・世界一周とか、魔法とか、非現実なことでも、なんとかできちゃうんですよね。そして人の条理を過大に美しくしたり、醜いものをやけに色褪せて見せてしまったり、ある意味ではマインドコントロールさえもできてしまう。そんな無限の可能性を最大限に駆使して、舞台を創る。こんな唯一無二な作品を肌で感じてしまうと、なんだかインスパイアされてしまいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
