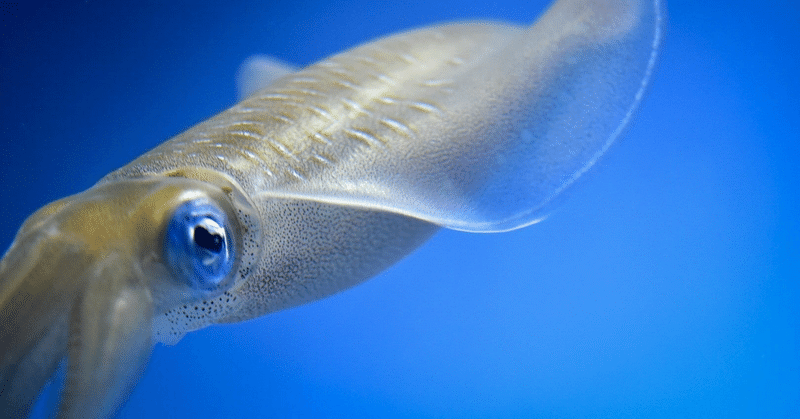
リーガルリリーの歌詞についてのノート——『東京』にみるロックのクリシェからの逸脱
リーガルリリー、いいよね。
特に、たかはしほのかの書く歌詞がいい。彼女の歌詞は、借り物の言葉じゃなく、自身のなかから発見した言葉だと思う。それは単にボキャブラリーが豊富であるということではない。それは、いまこの世の中にあふれている言葉が、つねに誰かがどこかで言っていたことを別の場所で繰り返しているかもしれないという不安の裏返しなのである。だから、彼女はロックソングの歌詞には到底使いそうもないような言葉をあえて使っているのではないか。
ホタルイカの素干し ライターの火であぶったら
君はどこから来たんだ
ホタルイカの素干し ライターの火を消すほどの
大海原にいたんだね
こうした語彙が突然曲のなかに出でくるわけだが、これはひとまずリスナーの興味を引くためのフックとして機能していると言えるだろう。しかしこの歌詞から筆者が感じるのは、歌詞を書こうとするときに出てくる言葉が、どれもこれも使い古された「キラーフレーズ」のように、既視感にまみれたものに思えてしまってならないアーティストの苦悩である。
「愛」「夢」「希望」「未来」「情熱」みたいな言葉を入れると、歌詞はすごく書きやすくなる。また、それらを「そんなことばかり歌いたくない!」みたいに書くのもロックソングのクリシェになってしまっている。リーガルリリーの歌詞は、そうした「綺麗ごと」と「それ以外」の二項対立から逃れようとしているように思えるのだ。そして、「ホタルイカの素干し」からは、そうした逃避、あるいは逸脱の試みが読み取れる。
歌詞を分析しながら考えていこう。
わたしたちはホタルイカの素干しを食べようとする。なんとなく味気ない。もっていたライターで炙ってみる。そうすると、芳醇な、というよりいっそ強烈な香りがただよう。それは、ホタルイカが住んでいたであろう、大海原の持つ生き物たちの豊かさや、なまなましさ、食物連鎖の厳しさの証左である。
このように、この歌詞は「ホタルイカの素干し」に備わっている圧倒的なマテリアリティから、多くのイメージを引き出している。
そこからさらに歩を進めて、「歌詞」じたいの比喩としても考えてみたい。
「ホタルイカの素干し」は味気ない。こうした言葉はロックで叫んでもカッコよくない。でも、カッコいいものは使い古されていて、何を書いても「パクリ」とか「インスパイア」と言われる。それはよく言えば文脈に位置づけられることで、わるく言えばオリジナリティを否定されることだ。だから問いかける。「ホタルイカの素干し」へ、「どこからきたのか」と。そして、「炙る」という新たなアプローチを経ることで、芳醇な「香り」という別の豊かさへと到達するのである。
音楽は特定の文脈に強く依存して聴かれる/作られるが、その他の文脈は強く意識されない傾向にある。例えば、いま作られ聴かれている邦ロックは、同時代の邦ロックとその近接ジャンルとの関係性のなかでのみジャッジされる。そのなかで、「異物」の文脈に寄り添っていくことで、そうしたゲームのルールから降りようとしているのだと言えないだろうか。
こんな感じでリーガルリリー、とりわけ、たかはしほのかに感じる繊細さや敏感さを説明しようとして色々考えてみている。筆者の言いたいことを歌詞に乗っけて言っているだけであるといえばそうです。
以上。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
