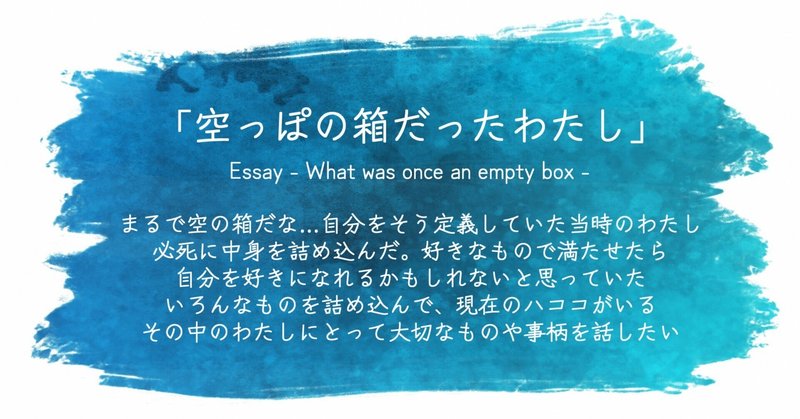
わたしの「ともだち」
「大丈夫だよ」あなたのそれはとても強い
To my dear friend ”President.”
And I dedicate it to my two ”friends”: her and her husband.
I wanted to convey this clumsy feeling to you someday.
I know it's very late, but I just wanted to say, ”You're going to be okay, too.'”
わたしは二十歳の頃に出会った女性のことを一生忘れないと思う。
彼女は「解離性同一性障害」を患っていた。
出会ったのは、精神病院の閉鎖病棟だった。
わたしが「解離」というものの存在を知るきっかけになって、その入院でわたしは「解離性障害」と診断された。
それまでも何度も閉鎖病棟に入院をしていたけれど、病名は「統合失調症」で、ゆえに前主治医の診断では説明のつかない現象が起きていて、当時の主治医がようやく診断を変えることとなった頃のこと。
彼氏に連れられて入院にくる女性をはじめてみた。
入院の手続きをしているのが「恋人」であるという違和感を覚えたけれど、どうしてなのかを当時は分からなかった。
家族が付き添わないで精神科にくる。
それそのものが違和感だったのだと思う。
どんなに迷惑に思われていたって、入院するほどの精神状態であるなら、家族が連れてくるものだ。
そうじゃないひとって、どういうことなんだろう?
夫でなくて、彼氏だとその女性は説明したのだ。
なんだかよくわからない。
彼女に対する第一印象は、それだった。
彼女は「社長」という愛称で呼ばれることになった。
わたしは「社長」という愛称が便利であることに気づく。
彼女はそのときそのときで、違う名前があるのだから。
彼女と言う存在に「社長」なんて愛称があるのは、わたしにとってとても心地よかった。
それぞれの名前を呼びたいなんて思うわたしにとっては。
彼女のことをわたしは何にも知らない。
過去について、彼女はほとんど話してくれなかった。
親から物差しで殴られていた。
結婚した相手がモラだった。
働いていた工場で指がなくなることだった。皮一枚で繋がっていて、見た目が痛かったなあ。くっつけたんだけど、動きは全然。
彼女には彼氏さんがいた。
冴えない感じの男性で、でもやさしくておもしろいってわたしは感じた。
家族しか会えないっていわれたから、旦那ですってしてきた。と笑ってた。
彼女には兄妹の子供がいて、すごくかわいがっていた。
彼氏さんにも懐いてる?感じで。
娘ちゃんは、小児がんで、骨髄に転移しての車いすになってしまっていて。
わたしが見る夢のことを話したとき、彼女は「それが解離なんだよ!」と興奮した様子で話していた。
そういうもの?わたしにはよくわからなかった。
ハココちゃんにはさ、きっと何か忘れてしまっていることがあるんだよ。
ピンと来なかった。でもそうなんだろうな、といまは思っている。
彼女は明るくていつも笑顔で、泣いているひとを励ましてばかりいた。
彼女がいると、その空間が明るくなる。
たくさんの友人に囲まれて。いつも楽しそうにしていて。
わたしは、いまとっても聞きたい。
ねえ、幸せだった?
彼女彼氏さんが結婚したそのお祝いの会には、多くの友人が呼ばれていた。
他のひとたちにはつながりがあって、でもわたしには彼女と旦那さんとなった彼氏さん、それとひとり共通の友人がいるだけで、その友人と雰囲気にうまく混ざれなくてふたりで話しているだけだった。
それでも、少し酔ってしまっての「乾杯」を歌う旦那さんを見ていて、不思議な感じがした。
新郎はそんなに飲むもんじゃないの!と窘める彼女。ほんわかとした気持ちでいた。
折を見て、彼女にはメールをしていた。
辛いことがあったとき。悲しいとき。とてもうれしいことがあったとき。
わたしが、人生で一番つらいと感じた、言ってしまえば「監禁」されての「性被害」とその前に起きた別件での「レイプ」と、監禁場所から逃げてきて、どうしてこうなってしまったのか、彼女に電話して泣いた。
あー、やっちゃったねえ。大丈夫だって。あたしもよく失踪したもん。大丈夫、ほら、泣くな泣くな。死なないって。あたしも生きてるし。大丈夫だって。泣かないの。大丈夫。生きてるんだからね。
まるで楽しい話をしているかのように。いつもの明るい声で、彼女は励ましてくれた。なんでもないことだって、そんな風に。
全然大丈夫じゃない状況で、でも、彼女に言われる「大丈夫」にはいつだって頷けた。
他のひとに言われたら、絶対に言い返したくなることや、むしろ絶望的な気分になったり、二度と話しかけないと決意する言葉もあったように思う。
でも彼女の言葉には「説得力」しかなかった。
それをいま、強く感じる。
彼女は、この世界に、もういない。
いのちは、彼女も思いもしないところで、消えてしまった。
虫垂炎の術後に敗血症。
彼女がなくなったことを聞いたのは、旦那さんからのメールだった。
突然すぎた。
一番に浮かんだことは、旦那さんは、この先を生きて行けるだろうか?
とてもとても怖かった。ふたりが並んでいる姿をもう見られないの?
わたしは電話が大嫌いだった。
それでも、電話をしなければ!って、かけたのだけれども、わたしは結局電話が下手くそで、上手く話すこともできなくて。
ごはん食べてる?眠れてる?食べられなくても、できれば少し食べて。眠れなくても、それは仕方ないんだけどね…。
わたしは彼女が亡くなったと聞いた日の夜、不思議な夢を見た。
立食パーティーで、彼女のお別れ会。
彼女の友達がたくさん集まって、思い出を楽しそうに話している。
彼女は髪をきれいに編みおろしにして、花かんむりをして、素敵なワンピースを着て、中央の寝台の上に横たわって、微笑んでいるかのように目を閉じていて。
花畑のようなあたたかい空間。わたしは彼女に「ありがとう」と言う。
当時、わたしは、めまいと吐き気で、動けなくて、彼女のお別れにいくことができなかった。
お墓に参ったのは一年越しになった。
娘ちゃんと名前が並んでいるのを見て。ああ、本当に亡くなったんだ。
はじめて実感した。
旦那さんは、こんなに年をとってしまったよ、なんて笑っていた。
どんなに泣いただろう。どんなに悲しかっただろう。どんなに、どんなに。
わたしの気遣う言葉をかける、旦那さん。わたしの「ともだち」が、なんだかとても遠くに感じた。
同じ空間に、隣にいるのに、彼とわたしの生きている空間は違うんじゃないか、そう感じた。
彼とはLINEで連絡を取るようになっていた。以前よりうんと多く。
この前は、カラオケに行った。奢るって言われたのを断った。
割り勘がいい。せめて、お互いの収入から割り出した、相対的な割り勘にしてほしい。
対等でいたい。君とは対等でいたいんだ。
たとえば、君が経済強者で億を稼いでるなら、奢ってもらう。反対にわたしが億を稼いでたら、奢らせてほしい。
その話に、ええやつやな。彼はそういった。
どこがだろうか? よくわからない。
とてもとても楽しかった。元気そうな彼を見られた。
元気そうで良かった、彼もわたしに言った。
でも、わたしはいま、かつてないほどに、精神状態が悪いと感じている。
ダメなことを自覚していられる状態は、自覚しないよりマシなのかもしれない。
けれども、かつてないほどに悪い。
だからこそ、「ともだち」をカラオケに誘ったりした。
衝動的にいなくなってしまいたいけれど、自制していられて。
それは、ほんの少しの跳躍で越えてしまえるハードルを越えないでいられていることで。
でも、その跳躍で越えたハードルの先、そこで立ち止まることもできるって、そんな自信がある。
きっと死んだりしない。たぶん。
それでも、過去一の悪い状態だ。
わたしに、尊厳なんてものは無縁であることを理解してしまって、戻っては来ないものであろうと感じている。
自分のことが大切だなんて思えないし、わたしにとって大切なひと、もの、こと、はたくさんあるのに、わたしだけは大切でもなんでもない。
わたしの身体、わたしの心、そんなものどうでもいい。けれど、わたしの大切を否定されることだけは絶対に許せない。
わたしを否定されること、わたしの人格を否定されることは、当然だとも感じる。
でも、わたしにとっての大切で、だれかにとっても大切でもあるそれは、何が何でも、わたしがどんなにも酷い目に遭ってでも、守りたいものなのだ。
そのためになら、どんな誹謗中傷をされてもどうだっていい。どんな酷い目に遭わされたっていいって思う。
わたしの大切にそんなことをするのなら、わたしにしてほしいって思う。
たとえば「ともだち」をわたしの犠牲で救えるのなら、
「ともだち」がそれを望むことも、幸福に思う。
あなたの未来の一部になれる。そう幸せな気持ちでわたしはおわれる。
わたしは自分のメンタルが不安定になっているのを良いことに、
「ともだち」に聞きたかったことを聞いた。
どうやって、そのぽっかりを埋めたの?
いまも空いたままなの?
こころの中のぽっかりを空いた穴。
彼は、涙が枯れるほど泣いた。と教えてくれた。
惰性で生きてるだけって。
それはそうだろうと思っていた。当たり前にそうなるよなって。
わかっていたけれど、そうだと言われるとやっぱり、なんだか、苦しかった。
どうして笑っているの?どうしてやさしいの?
彼女に思っていたことを、いま、彼に思っている。
あのひとの人生は辛すぎだ。彼は言う
彼女がわたしに話していないととを、わたしが勝手に彼から聞いていいものではないだろう。
でも、笑っていないと生きて行けもしない。
彼女はそうだったんじゃないかな、と思う。
彼女はいつも励ます側にいた。
泣いているひとに、「大丈夫だよ」って言い続けて。
彼女が励まされているところなんてただの一度も見たことがない。
きっと、彼女を励ませるようなひとは、いなかったのだ。
わたしは、彼女に掛けていい言葉があると思ってもいなくて、なんにの言えなくて、いつだって励ましてもらって「ありがとう」を言うばかりで。
彼女はわかってしまっていたのかもしれない。
自分を励ますことは誰にもできないんだって。
話したたとしても、誰も彼女のこころも経験も理解しないだろうことで、でも、聞かされたことに、ひとは共感や優しさを示すだろう。
その虚しさを、知ってしまって、知り尽くしてしまって。
共感を示したとして、どうせ理解していない事柄を、共感したと勘違いしたひとから押し付けられる共感なんて、本当に虚しい。
何ひとつ、共感できていない共感を見せつけられることへ感じる怒りは、虚しさになり、それを見すぎたのかもしれない。
だから、自分のことは一切話さないで、泣いているひとに「大丈夫だよ」と笑顔で励ますだけになったのかな。
彼女は、誰かに言ってもらいたかったのかもしれない。
「大丈夫だよ」
彼女が、ひとに渡す、その「大丈夫」を、彼女自身が誰よりも欲しかったのかもしれない。
彼女の「大丈夫」には、説得力しかなかった。
溢れんばかりの根拠が彼女にはあったのだろう。
彼女の人生が、その根拠で、確信をもって「大丈夫」であると彼女は言った。
あたしの人生でも生きていられているあたしがいる。
だからあなたは「大丈夫」でしかない。
あなた程度の悲しみなんて、その程度の辛さなんて、大丈夫だよ。
本当に、なんてことないよ。大したことないよ。
そんな気持ちもあったのかもしれない。
これは、わたしの勝手な想像でしかない。
わたしは彼女の過去を知らない。
でもそう思うくらいのものを抱えて生きてきただろうこと、なんとなく、感じる。
彼女はいつも確信を持って励ましていた。
彼女の確信は彼女の経験と人生、抱えたものがあまりにも大きかった、そこからくるものだったように感じるから。
それとも、誰かに言ってもらえることがどんなに幸せと感じるのかを知っているから、確信なんかなくても「大丈夫」と言っていたのだろうか。
欲しくてほしくてたまらないもの。
みんな「あなたは大丈夫よ」と言われたいのだから。
彼女は誰かに言ってもらえただろうか?
わたしは言ったことがない。言えなかった。
無責任だって思って、大丈夫だよなんて、保証を口に出来なかった。
わたしにそんな言葉を言う資格なんて無いと思っていた。
彼女はとてもきれいなひとだった。
その気配が好きだった。
容姿とかどうって、そんなことどうでもいい。
容姿だってもちろんきれいだけれど、それ以上に、彼女という存在そのものが、あまりにもきれいだった。
わたしは彼女に「きっと大丈夫だよ」と言われた。
監禁されたことすら、笑って聞いていた彼女。なんてことない。大丈夫。
わたしをとても弱っちいと感じていただろう。
自分と似た道(全く違うものだけれど)を辿って困り事にいちいち直面しているわたしを、どう見ていたのだろう。
もう聞くこともできない。彼女はもう、話すことができない。
彼女の声はいまも、聞くことができる。脳裏に鮮やかによみがえる。
彼女との思い出は、ほんの少ししかないけれども、わたしの中に鮮明に残っている。
笑顔が、たった一度の涙が、いままで出会った誰より、強く残っている。
彼女に聞きたいことがいろいろある。
一番聞きたいのは「幸せってなんだと思う?」だ。
彼女は「家族」と答えるかもしれない。
二度目の結婚の旦那さん、最初の結婚での兄妹。
その娘は小児癌で亡くなって。
そして、もしかしたら。わからないけれど。
いや、これは、彼女と出会ったことでわたしが考える、わたしの言葉でしかないけれど。
わたしは、いま、こう思っているんだ。
幸せなんてものはないんだよ。
そんなものは、ただの勘違いでしかないんだ。
でもね、その勘違いをできることこそが「幸せ」なんだよ。
どうかどうか、
安らかに、わたしの「ともだち」。
どうかどうか、
いつかわたしは「ともだち」に、なりたい。
あなたの「ともだち」になりたい。
あなたに「大丈夫だよ」と、言いたい。
わたしの大丈夫には根拠もない。あなたがくれるものとは違う。
ただの無責任な「だいじょうぶ」でしかないけれど。
それでも言いたいって、
本当に、なんてなんて、遅いんだろうね。
わたしは、生きてゆくんだと、
彼女に誓ってしまったら、生きてゆくことしかできなくなる。
臆病なわたしは、彼女に、生きてゆくことを約束できない。
それでも、生きてゆこうと思っていることを、
それはあなたたち「ともだち」のおかげなのだよ、と言いたいのです。
わたしが手首を切って、腱が泣き別れをして、縫合手術をしたその傷跡を、彼女は「見せて!」とはしゃいで、彼女は楽しそうに見てくれた。
おお、なかなか派手にやったね、これは。
にこにこしていた彼女。
こんなこといたらダメだよ!なんて言わないで、ただ、
「なかなかの傷だよ!すごい縫い跡じゃん!」
そう誉めてくれたんだ。
大好きだよ。言われたって、うれしくもないのかな。
それでも「大好き」なんだ。いまも、これからもずっと「だいすき」。
To Mr. and Mrs. I, a well-matched couple with similar personalities.
With love from the bottom of my heart, I would like to express my gratitude to my two friends, M’s. And I'm really sorry.
See you again... for sure !
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
