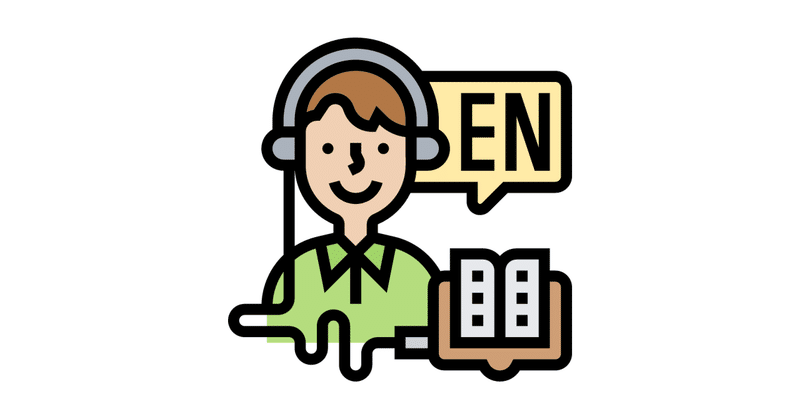
リピーティングとシャドーイング、どちらの方がスピーキング力向上に効果があるのか?
“Repeat after me!”
中学生の時の英語の授業で毎回教室で響いていた一文。
英語の先生の発話のあとに、同じように繰り返す「リピーティング(repeating)」をした経験はありませんか?
先生がお手本のネイティブ音声をカセット(レトロ!)やCDで流し、一旦ポーズを置いてから繰り返していた経験は?
筆者は両方あります。今も中学校の英語授業の現場では、「シャドーイング」より「リピーティング」が主流なのでしょうか?
筆者のクラスでシャドーイング中に「リピーティング」をしてしまう人が時々現れます。シャドーイングはちょっと遅れてひたすら音声についていかないといけないので、初めのうちは誰でもうまくできません。そこで諦めてしまい、「リピーティング」に切り替えてしまう人達です。「リピーティング」できてから「シャドーイング」しようと思っているのです。
「ちょっと待った~!」をかけます。
流暢に話したいんですよね?
だったら「発話スピード」を上げないと。
コテコテ日本語英語から脱出したいんですよね?
だったら「発音」も相手にわかりやすい発音に変えていかないと。
リピーティングしていていいのですか?
この記事ではシャドーイングとリピーティングで「発話スピード」と「発音」の観点からどちらの方が効果的かについてお話しします。
発話スピードはどちらが向上するのか?
そういう学生さん達の為に、シャドーイングとリピーティングで「発話スピード」の向上に差があるかを調べた研究¹を紹介しています。
実験の概要は、以下のとおりです。
日本人大学生を対象に、モデル音声を使い、以下の3群に分けました。
A群:シャドーイング
B群:ある句ごとにポーズしたものをリピーティング
C群:ある文ごとにポーズしたものをリピーティング
それぞれのグループが同じ英文を10回ずつ発話し、発話スピードがどのように変化したかを調べています。
B群の「句ごとにポーズしてリピーティング」したものの方が、C群「一文ごとにリピーティング」するよりも当然ながら発話速度は速くなります。そこで、A群「リピーティング」とB群「句ごとにリピーティング」の2群を比較しました。その結果が以下の図です。

縦軸が「発話時間」です。短いほど「速い」ということになります。横軸は「発話回数」です。10回発話する途中で3回発話時間を測っています。紫の棒が「シャドーイング群」、オレンジが「句ごとのリピーティング群」の発話時間です。
シャドーイング群は、繰り返していくうちに、どんどん発話スピードが速くなっているのがわかりますね。一方、リピーティングは.........あれ? どんどん遅くなっています。リピーティングは一度自分の脳の中の引き出しを開けて文法知識を引っ張り出し句や文を作っていきます。その分おそくなっていくと考えられます。
この研究を見る限り、リピーティングと比較して「シャドーイングの方がリピーティングよりも発話速度が上がる」と言えるでしょう。
発音はどちらの方が向上するのか?
私たちの記憶には、「感覚記憶」、「短期記憶」、「長期記憶」の3段階があります。
「感覚記憶」は見聞きした情報を何も処理しないでそのまま数秒だけ保持する記憶ですぐに忘れてしまいます。
「短期記憶」は、意識的に忘れないようにとどめておく20秒程度の記憶です。忘れないように心の中で反復しますが、反復には以下のような2種類あります。
① 維持リハーサル:情報を「機械的に反復」
② 精緻化リハーサル:「既存の知識に関連づけて反復」
「長期記憶」は、「短期記憶」で反復された結果、「半永久的」に脳に保持される情報=知識です。
「リピーティング」では、ポーズをおくことで、聞いたお手本の音声を一旦「短期記憶」として保持します。その際、「精緻化リハーサル」によって長期記憶内にある既存の知識(コテコテ日本人特有の発音やリズムなど)にアクセスしてしまい、無意識のうちにそれを反復してしまう可能性があります。そうすると、発音の上達がすぐには望めません。シャドーイングのように既存の知識にアクセスする暇もなく、機械的に反復する方が発音習得には効果的というのも頷けます。
筆者のクラスではシャドーイングの時、最初のうちはできるだけ自分の声を聞かないように指導しています。CALLシステムで行う場合は自分の声をミュート設定に、Windows Media Player使用の場合はイヤホンがっちり耳に入れお手本音声に集中させています。そうすることで、既に脳の中に保持しているニホンゴ英語の発音記憶にできるだけアクセスしない環境をつくっています。
「発話スピード」と「発音」、この2点に関しては、リピーティングよりもシャドーイングの方が効果がありそうです。
―――――――――
(参考文献)
¹ 三宅滋(2009)日本人英語学習者の復唱における再生率と発話速度の変化の考察、『ことばの科学研究』10:51-69.ことばの科学会
² 門田修平(2018) 『外国語はなせるようになるしくみ:シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム』東京:SBクリエイティブ
³ 門田修平・玉井健(2017)『決定版英語シャドーイング』東京:コスモピア)
いただいたサポートはクリエイター活動に活用させていただきます。
