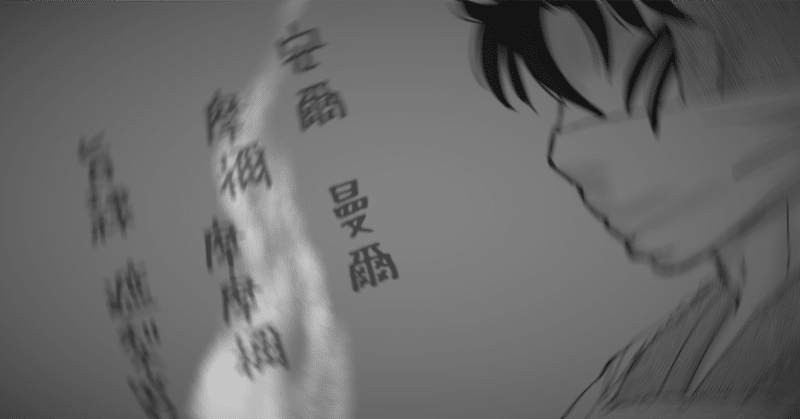
落乱元ネタ探し その5 善法寺伊作の陀羅尼呪
『落第忍者乱太郎』を読んでいて、これアレじゃないかなと思ったもの、他の本を読んでいてたまたま見つけたものなど、元ネタっぽい色々をメモする記事です。
今回は、ありがたいことにご質問をいただきましたので、第50巻に出てきた伊作の陀羅尼呪の元ネタっぽい資料について書いてみました。
※公式にこれだという発表がない以上、単なる個人の感想ですので、疑いながらお読みください。
【修正履歴】
2022.03.31 余談・雑談 3. 離縛の法の元ネタ?の内容を修正・加筆
ご質問の内容
記事にする時、お名前はナイショでとのことでしたので、いただいたTwitterのDMから、ご質問の部分のみ引用します。
50巻で伊作がとなえていた「あに・まに・まね・ままね」の陀羅尼呪の出典はわかりますか?忍者が唱えると新野先生が言っているので忍術書に書いてあるのでしょうか。
この件については過去にざくっと調査済みで、忍術書までは行き着いていないのですが、同内容の出てくる本は確認できました。
落乱の陀羅尼呪まとめ
質問者の方も書いてくださいましたが、陀羅尼呪は『落第忍者乱太郎』第50巻に出て来ます。
《伊作》
よーしッじゃあショウガを取り除いてその残ったショウガ汁で粉末にした材料を練る!!
あに・まに・まね・ままね・しれい・しゃりて・
しゃみゃ・しゃびたい・せんて・もくたび・しゃび
《白南風丸》
あれは何です?
《新野先生》
『陀羅尼呪』です
この呪文を唱えながら忍者は薬を調合したりするのです
兵庫水軍の身隠しの盾の役オーディションに参加する白南風丸が船酔い体質であるため、保健委員たちが協力して船に酔わざる薬を作るシーンです。アニメのほうでは、第20シリーズ第81話「誰がやった?の段」になります。
忍者は「あに・まに……」という陀羅尼呪を唱えながら薬を調合する、ということですね。これが出てくる資料について、次で書きます。忍術書や、忍者について書かれた史料というわけではなく、昭和の時代に出た本なのですが、ちょっと見てやってください。
『忍者の系譜 漂泊流民滅亡の叙事詩』
『忍者の系譜 漂泊流民滅亡の叙事詩』(創元社)は、杜山悠 著、手元にあるものの奥付には昭和47年7月20日 第一版第一刷発行とあります。忍者の研究をまとめられたものですが、テレビの歴史番組でところどころ挟まる再現ドラマのように、小説仕立ての文章を入れ込む形で書かれています。
私が普段どうやって元ネタ探しをしているのかについては、離行の術の記事の最初のほうで説明させていただきましたが、そこで主に参照すると書いた、藤田西湖、奥瀬平七郎、山口正之、名和弓雄、各先生方の忍術研究本と、この杜山悠先生の本はあまりリンクしません。
ちゃんと解析したわけではないですし、私自身の忍者についての知識がものすごく浅いので感覚の話でしかないのですが、杜山先生のご著書には先生独自の内容が多いように思います。
前置きが長くなりました。この本の「野臥と山臥」部の中、「将門反乱と風魔小二郎」という章に以下のような文章があります。
また、かれらは「陀羅尼呪」を唱えながら薬草を調剤した。
「あに、まに、まね、ままね、しれい、しゃりて、しゃみゃ、しゃびたい、せんて、もくて、もくたび、しゃび、あいしゃび……」
これは薬王菩薩(梵名バイシャジャラーヤ)が説法者に与えた陀羅尼神呪だと経義にある。
したがって、この陀羅尼呪も忍術とは無縁なのだが、ただ、これを唱えて調剤したという医薬剤は忍術の実法において大いに活用されたし、「陀羅尼品」の経文にある藍婆(梵名ラムバー)と毗藍婆(梵名ビラムバー)はラムバーが〝結縛〟の意で、ビラムバーが〝離縛〟の意であって、この語の転用も忍法の中に活かされている。
ちょっと補足しますと、「かれら」というのは風魔小二郎たち、真ん中あたりの「この陀羅尼呪も忍術とは無縁なのだが」は、この前の部分に出てくる小二郎たちも使った九字(臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前)、これは忍者のもののように言われるがそうではないよという内容を受けてのものです(※ 風魔小二郎は風魔一族の祖として書かれていて、時代は平将門の乱のあとくらいなので10世紀なかばの平安時代になると思います)。
九字と同じく、「あに、まに」の陀羅尼呪は忍者だけが用いたり忍者が発祥であったりはしないけれども、これを唱えて調合した薬は実際に忍者に大いに使われた、ということですね。呪文の中に落乱のほうにはない「もくて」が入っていますが、そこの違いは重要視していません。
ということで、質問くださった方には、とりあえずの出典(かも)として、この本の内容を返信させていただきました。
本当はこのあと、忍者がこの呪文を唱えながら薬の調合をしていたという記述の根拠になる史料を見つけたいのですが、どう探していいかわからなくて停止している状態です。今のところはここまででご勘弁ください。
-----
補足としまして、「陀羅尼品」というのは『妙法蓮華経(法華経)』の中の「陀羅尼品第二十六」のことで、例の陀羅尼呪は薬王菩薩が関係しているからお薬がらみかなー、くらいしか私にはわかりませんが、下の画像のような感じで出て来ます。結構長いので、写っているのは最初の部分のみです。


漢字だと、また違った印象ですよね。
余談・雑談
1.風魔関係の元ネタ?
最初にこの本を読んだのは十何年か前になると思うのですが、その時見つけたのは、落乱の風魔関係の内容でした。だいたい以下の内容の出典が集まっている気がします。※( )内は落乱内の出現箇所です。
・「昔むかし… 甲賀流の開祖が風魔流の開祖を裏切った…」(第28巻p.219)
・「風神魔障降伏」(第28巻p.229)
・「風の空中において一切障碍無きがごとし!!」「三毒を滅し三界を出でて網魔を破する」(第45巻p.81)
・「風魔は平安時代に山伏…山岳行者から大きく転換し『戦い』を第一の目的とした専門家の兵力集団となったのだ」(第45巻p.83)
2.自然薯居士の元ネタ?
それから、自然薯居士周辺の以下の内容も、この本が元である気がします。
・「つまり『自然薯居士は若いころ八宝行者と名のり 祈祷師として南蛮船に乗り組んでいた』」「というわけだな」(第28巻p.72)
・「六根清徹・三法忍・音響忍・柔順忍・無性法忍これ無量寿仏・威神力・本願力・満足願・明了願・堅固願・究竟願・如来十力・現在力・衆生得忍これ如来因果力」(第28巻p.80,121,124、第44巻p.128)
3.離縛の法の元ネタ?
さっき「あに・まに」のところで引用した部分に「ビラムバー(毗藍婆)が〝離縛〟の意」という内容がありましたよね。第28巻p.158で、自然薯居士の不動七縛ノ印をかけられた八方斎が、離縛の法として唱えるのが「毗藍婆 毗藍婆」なので、これももしかしたらという感じです。
ただ、重要なワードである「不動七縛ノ印」「離縛の法」がこの本には出て来ないようなので、たまたまかなとも思います。
※2022.03.31追記
「不動七縛ノ印」が載っているのを見つけました(p.56、役小角のところに押し入った賊を弟子の於戸が撃退するシーン)。すみません、出てきてましたね。
-----
過去に読んでいたはずなのですが、第50巻で伊作の陀羅尼呪を見た時に、これはあの本の!とはまったく思いませんでした。だいぶ後で読み返した時に見つけて驚いたくらいです。
風魔と自然薯居士については、別の資料が元になっている部分もあるようですので、この『忍者の系譜』の内容も含め、どこかでまとめる予定です。「不動七縛ノ印」などは手付かずですが、こちらも何かわかりましたら。
4.先生のリストに『忍者の系譜』がありました
ちなみにこの『忍者の系譜 漂泊流民滅亡の叙事詩』ですが、2021年の7~9月に尼崎市総合文化センターで開催された『尼子騒兵衛展 -落第忍者乱太郎・忍たま乱太郎はこうして生まれた!』で展示されていた〈忍者・忍術資料〉という先生手書きのメモ用紙に出て来ています。だから出典である可能性は高いかな?どうですかね?
図録をお持ちの方は、p.141の一番下にメモ用紙の写真が載っていますので確認してみてください。上から3つめの資料になります。出品リストには“011《メモ〈忍者・忍術資料〉》1993年頃 ペン、鉛筆、紙/257×182mm”とあります。
私は図録のみ購入したのですが、B5サイズの用紙の写真をだいぶ小さくして載せてあるので読み取れない字が多く(大きさのせいというより、近視、乱視、その他複合で目が悪いせいですが)、実際に会場へ行かれたNinjack編集長の嵩丸さんにだいぶ助けていただきました。その節はありがとうございました。
まとめ
忍者が「あに・まに・まね・ままね……」の陀羅尼呪を唱えながら薬を調合するという内容の出典は、『忍者の系譜 漂泊流民滅亡の叙事詩』ではないかということを書きました。
質問くださった方、とても嬉しかったです。そして、このようにまとめる機会をいただいてありがとうございました。何か追加で見つけたり、どなたかに教わったりして情報が増えましたら、またご連絡します(※noteにも追記などします)。
今回の記事は以上です。最後まで読んでくださってありがとうございました。
【お願い】
漏れや間違い、誤字、脱字、言葉の誤用等ありましたらご指摘いただけると助かります。noteのコメント欄の他、Twitter等どこからのメッセージでも大丈夫です(note記事へのコメントは、note登録者の方しかできません。TwitterのDMは開放しています)。よろしくお願いいたします。
