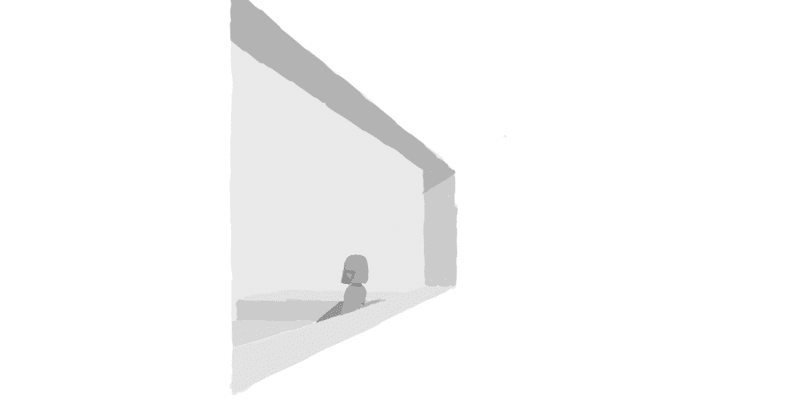
【小説】 声 (後編)
マンションに戻ると、エレベーターに故障中の貼り紙がついていたのでスズキは五階までゆっくり足を交互に振り上げてきつさを考えないように歩いていたが、上りきった瞬間、春野さんがそこにいたような気がしたのは、酸素が不足していたせいかもしれない。だって、そんなわけはないから。スズキはずっと前に好きだったひこにゃんのキーホルダーがついた鍵を玄関の鍵穴にさしこんだ。マンションといっても、狭めの八畳に一口コンロしかないキッチンのついたおもちゃのような部屋だが、未だにそこに自分が日々存在することが嬉しくて、鍵を回すたびに高揚感がある。しかし今日はそんな気分にはなれない。半ドンにかかわらず疲れているのは、なにも階段の上り下りを何度も強いられたせいばかりではないだろう。スズキはすぐにテレビをつけ、カバンを放り出してコートのままソファに沈み込んでいった。
たまたまつけたチャンネルには、ちょうど二時間サスペンスの、殺人が始まった瞬間が映し出され、殺された男が雪の中に倒れたところだった。刑事の登場、現場検証、目撃証言、お決まりのコースにリラックスしながらスズキはコートを脱いで手を洗って冷凍庫から凍った米を取り出しレンジに入れた。贅沢な日のためにとっておいた神戸牛レトルトカレーを湯煎しながらまたテレビに見入る。
ドラマの中で殺人の容疑をかけられたのは若い男だった。駅から見えるワンルームマンションで一人暮らしをしていて、殺害があった時刻、その部屋で寝ていた。つまり、アリバイがないのだ。そばに人がいないと、寝ていたことを人に知らしめることはできないというのは理不尽なものだ。いまスズキがここでカレーを食べていることも誰も知らない。せめて鍋でカレーを作っていればドアから匂いが漂うくらいはあるかもしれない。
そんな彼の無実を立証したのは、隣人がいびきを聞きつけたとか、寝ているときに電話がかかってきたとかではなくて、彼が部屋にいるのを電車の窓から見たという女の人が現れたからだった。とはいえ、窓を開けてタバコを吸っていたとか窓から寝ているのが見えたのではない。ベッドが窓際にあってカーテン全開になっていたとしても顔までは判別できない。
目撃者は、六階建てマンションの六階一番東端の彼の部屋のベランダの柵に、こうもり傘が干してあるのを見たと証言したのだった。各駅列車の車窓から流れていく建物を見るのが好きで、その時はとくに初めて乗る電車だったからよくよく窓の外を眺めていたら、その傘が見えた。それで、あの部屋の住人は今そこにいると、そう思った。他の部屋のことは知らないけれど、あの部屋だけは誰かがいると、その証拠があの傘だと思ったから覚えていた。
どうしてそう思ったか?
「だって、マンションの六階で傘を干しているんですよ?飛んでいったりしたら大変だから、自分なら絶対に留守にはしません」と、目撃者は主役の刑事に言った。四十年配の、ちょうとスズキと同じくらいの年の女。見たことのない顔の女優で、でも物語を見ているのだから、女優と思ったらいけない。彼女はあくまでも目撃者なのだ。いえ、そう思ったのはやはり彼女の名を知らないからだったが、それはドラマ好きのスズキにとってめずらしいことだから、かえってよかった。よかったといえば、容疑をかけられた傘の男の子も知らない。
かなり大きめの黒いこうもり傘だから、きっと男の人だろうと彼女は思った。電車から見えたマンションがなぜ容疑者の住まいだと特定できたかというと、電車は鈍行で、容疑者のマンションは駅のそばにあり電車の速度はかなりゆっくりだったこと。建物自体は焦げ茶の四角い形の平凡なものだったけれど、その奥に予備校があってその柱についていた丸い時計が午前十時半をさしていたこと。のちにそのマンションから男が出てきて歩いている姿が何度もニュースで映し出されたときに、あの部屋ではないかと確信したこと。
もちろん、傘を干していたからといって家にいた証拠にはならない。飛んでいく心配など一ミリもせず殺人に出向いたかもしれないし、あるいは証拠になるようにわざと干した可能性だってあったけれど、主役の刑事はどうしてもその証言が気になって、容疑者の部屋に行きベランダに自分の傘を引っ掛けてみたり、はずしてみたりした。それはとてもよく晴れた土曜日で、近づいてくる電車を見ながら刑事は犯人は別にいると確信し、容疑者にもう一度話を聞いた。
あの傘はどうしたのだ?
傘のことなんか初めて聞かれた彼は驚いたが、必死で考えて過去を辿った。 殺人が置きた前の晩、一人で遅くまで残業をしていると、雨が降ってきた。会社から駅までは十五分以上歩くのに、傘を持っていなかったから、同僚の置き傘を借りることにして、終電で家に帰った。月曜日に傘を返すためにベランダに引っ掛けて干していたが、飛んでいく云々は考えなかったそうだ。ただ、失敬した人にばれないように完全に乾かして月曜の朝こっそり返そうとだけ思っていた。前日が遅かったので、そのままもう一度布団に潜り込み、ほんの少しのつもりが、目が覚めると昼前になっていた。せっかくの土曜日を損したな、と思って出かけようとして戸締まりを確認したときに傘のことを思い出したという。
そのあと、主役の刑事は真犯人を探し当てるのだが、それはどうでもよくて、スズキはカレーを食べ終わったあとも傘のくだりが妙に気になっていた。ドラマは再放送で、放送されたのは五年前だ。マンションはもうないかもしれないが、駅はもちろん、予備校もそのままだと仮定してスズキは紙の地図を広げ、だいたいの検討をつけてからネットの地図を立ち上げた。ストリートビューをつかうと予備校はあっという間に見つかった。少し手こずったが、現場のマンションもそのまま残っていることが確認できた。
スズキは目撃者と同じように、そのマンションを見たくなった。よく晴れた土曜日の朝、電車の窓から見える黒い傘を引っ掛けたマンション。それはなぜか、スズキが遠かったころの暮らしを思い起こさせた。
駅はここからそう遠くない場所で、これからぶらぶら出かけても夜までに戻ってこれる。けれども、あのマンションはドラマの中に現れたもので、スズキはそこに本当に容疑者にされてしまった会社員の男の子が住んでいて、傘を干しながら昼寝をしていたのだと思うために、そこに行くことはなかった。
★
スズキだって、ずっと遠かったわけではないのだ。小学、中学校は家から歩いていくことができたし、高校も自転車で行けるぎりぎりの場所にあった。遠くなったのは大学からで、そこには映画一本に加えてドラマ一話分くらいの距離があり、職場も同様で、友達や同僚や付き合っていた彼の家はさらに遠かった。中心部に行こうとする者たちはいつも遠さを強いられたし、そこに関わって生きていくには、互いに両手を伸ばしきった遠さに住むしかなかったからだ。
スズキは電車で座席の一番端に座って、足をぴたりと閉じて手すりの冷たさを感じたものだ。隣のサラリーマンが読んでいる新聞は文字が大きくて、感嘆詞が多かった。電車が橋を通ると、眠っていても目が覚めた。川に落ちる木の葉が見える。欄干の隙間から通ってくる光はまぶしい。
各駅でも電車はスズキの歩く速度よりはずっとはやく、座っているだけなのに遠く運ばれるのは罪深いと思った。人は自分で歩いていけるところにしか行ってはいけないのではないか。それは甘い感傷なんかではなくて、毎日毎日遠い町へ行ったり来たりしているうちに積み重ねられた恐怖に近いものだった。
走る箱の中で、スズキはよく眠った。もたれかかっていたらしい隣の人につつかれて目を覚ますとき、少しくらいいいじゃないかと、眠たい頭が考えることは恐ろしい。帰りの列車にはなんの目的もなくて、足元からヒーターの熱がふきでて、ふくらはぎを温める。終電に近づくと、乗車客が少ないせいかヒーターが入っていないことがあって、スズキは自分の腕を抱きかかえるようにして、じっと時間が過ぎるのを待った。いや、時間が過ぎるのではなくて、電車が進むのを待つべきなのだが。
電車の窓には、自分が映っている。スズキは目を閉じて、いろんなことを夢想する。
たとえば蜂になってこの列車の中を飛びまわり、乗客の誰かの首筋をちくりと刺してやる。いててと悲鳴があがり、怒り出す乗客たちを見ながらスズキは飛び回る。でも、蜂は一度刺したら死んでしまうという。自分が死ぬのはともかく、蜂が死ぬのは良くない。テレビで猫が電車に乗っているのを見たことがあるが、座席に堂々と横になって、乗客たちは誰も気にしていなかった。猫は好きな駅からひらりと乗ってまた降りられるし、改札だってすっとぬけてしまう。猫になったら、人間にはなつきたくないと思う。これだけ人間をやったのだから猫とだけ一緒にいたい。
そんなことを考えていると、電車が駅に止まる。さっきまで向かいでぐっすり眠っていた女の子が目をこすりながら、あわいピンク色のトートバッグを持って立ち上がって降りていくのを見たスズキは頭の中で彼女に取って代わる。スズキは灯りのともる、誰かの待っている家に帰ったりはしなかった。こんな遅くまでどこに行ってたのなんて言われながら冷蔵庫からオレンジジュースを取り出すなんていやだから、改札を出たら、角を曲がって真新しいマンションに入っていくのだ。明るいエントランスホールに並ぶ郵便ポストはダイヤル式で、そこからたくさんの封筒を取り出して、銀色に光る細長いエレベータに乗り込むと、さっきまで真横に動かされていたスズキの体は縦に上昇していく。大きなキーホルダーのついた鍵をバッグからとりだして、真っ暗な部屋に入っていく。
遠ければ遠いほど、すぐそこにある家がスズキの家になった。どんなに、遠いところにいたって、スズキの体はスズキの中にあるのだ。だから家が欲しかった。
★
新しい年になると、春野さんは新学期明けの転校生みたいに、「ええと、春野さんは大阪支社に移動になりました」とか、「突然ですが、退職されました」なんてことはなくて、普通に出社していた。
スズキは、あの日備品室に彼女を残したまま戻ってしまったことを、ずっとというほどではないけれどもそれなりに気にしていたから、土産だという箱をウエイトレスみたいに左手に掲げて、中から個包装された和菓子を皆のデスクに配っている春野さんを見たときは、自分で思っていたより安堵していた。
「なんすか、これー」と尾関くんが聞いた。
「きびだんごです」と、春野さんは答えた。
「さるきじたぬきのやつですかー」
「ちがう、犬だよ。さるきじいぬ」
ああそうかー、と言いながら尾関くんは、もらった菓子の包を開いて一口で食べてしまった。スズキはもしかすると自分の机を春野さんは通り過ぎてしまうのではないかと思ったけれど、ちゃんと包をひとつくれた。
「春野さんって、岡山のひとなの?」
彼女は一瞬まぶしそうにスズキを見て、
「いいえ、旅行で岡山に行ったんですよー。もう最高でしたよ温泉」と答えた。
それは、備品室へと去っていった彼女と話す、十日ぶりの会話だった。
社内には、今年もよろしくおねがいしますの声があちこちで聞こえて、正月疲れとそれを振り払おうとするぎこちない活気が充満していた。春野さんは始終忙しそうで、とても、例の話はできそうもなかったため、スズキは休憩時間、一人で三階に行った。あの日と同じように、エレベーターではなく階段を降りて会議室にすべりこむ。耳をつけると、やっぱりふたつの声がする。
音というのは意外なところから聞こえることがあるらしい。とある団地で怪奇現象だと思われていた女の鳴き声が、実は数キロ離れた工場の水音だったという話をネットで見たことがあるが、それは嘘くさいにしても、たとえば気温の下がる冬の夜は、普段は聞こえない遠くの電車の音が聞こえると言うし、階下からだと思っていた音が上からだったり、人間の耳があてにならないのか、それとも音がさまよっているのかしらないが。
もしかすると、あの声だって隣から聞こえているのではないかもしれない。 スズキは会議室を出て備品室の前に立ち、引き戸に手をかけた。
記憶のままの、スチールラックが現れる。置いてあるものもそのままだ。狭くてまっすぐの部屋だから、誰もいないのは一目瞭然だった。やっぱり、声はここではないどこかから聞こえるのだろう。
廊下にいると聞こえないので、あるいは会議室でなければ拾えないのか。スズキはもう一度会議室に戻った。椅子を一脚とってきて壁のそばにつけ、朝コンビニで買ってきた黒ウーロン茶とツナおにぎりとたまごサンドとフィナンシェを取り出して、壁によりかかりながら食べ始めた。最初にたまごサンド、次にフィナンシェ、最後にツナの順で。その間、声は聞こえたり途切れたりしていた。
食べ終わると、スズキは声から距離をとるために椅子ごと会議室の端に移動した。目を閉じて、社内の人間の声をひとつひとつ耳に再生していく。これもまたスズキの得意技で、知っている声をいかようにも再生できる。つまらない仕事をしているときは、よく市原悦子の声でナレーションをしてもらう。
全部並べた声は、やはりふたつの誰とも違っていた。といっても、もし声がこことはまるで違う場所からするものなら誰にも当てはまるものではない。
ふと、春野さんの声を再生し忘れていたことに気づいた。真っ先に試して良かったはずなのにやっぱり後ろめたさがあったからか、それとも敬語ともタメ語ともつかない気味の悪い態度で接してきたからかとか、全然関係のないことを考えながら、スズキはもう一度目を閉じ、今日はバナナのヘアクリップをつけてきび団子を配っていた春野さんの声を再生しようとしたが、姿ははっきり見えるのに、どうしても声が浮かばない。
黄色が好きなんだね。
まあ、好きですよ、黄色は。
一番ではない、と。
そうですね、それは違うかな。
あの日、なにがあったのか教えてくれるかな。
べつに、なにもありませんでしたよ。
春野さんはそう言うと、会議室からひらりと出ていった。立ち上がって追いかけようとするのに、体が動かない。頭の中で聞いた二つの声は、混じり合いながら遠ざかって誰のものでもなくなってしまう。
ぬるくなった黒ウーロン茶を飲み干すと、ゴミをまとめて袋の口をきつく縛り、スズキはゆっくりと階段をのぼっていった。
★
この間、遠かった町がテレビで流れているのを見た。
あの頃は、自分はどうしてこんなにも遠いところに行かされる運命なんだろうと思っていたけれど、考えたらぜんぶ自分で選んだ結果なのだ。
景色を見ても、何ひとつ思い出せなかった。かろうじて覚えていたのは、いつも人が並んでいた角の道にあるたい焼き屋だけだった。でも、その店のあったあたりをテレビは流さなかったから、まだやっているのか閉店してしまったのか、それとも、もともとそんな店はなくて自分の思い違いなのかは、わからなかった。それ以上見つめていると、過去の何もかもが靄になって消えてしまいそうな気がして、テレビを消した。
★
風呂から出てくると、春野さんから留守番電話があったことをスマホが知らせていた。
メッセージはなく、ただ着信履歴が残っていただけだが、その時刻を見るにどうやらスズキはずいぶん長いこと風呂に入っていたらしい。まるで、彼女と話すことを避けていたみたいだと苦笑いをしつつ、そのあとはずっと目の届くところにスマホを置いていたが、それきり電話は鳴らなかった。急ぎの用ならもう一度かかってくるだろうし、メッセージを入れただろう。それに、こちらからかけるには、もう遅い。スマホを枕元に置いて眠り翌朝目が覚めるとすぐに確認してみたが、以降は何のアクションも残ってはいなかった。
出社したこちらの顔を見た春野さんは、いつもの顔でおはようございますと言っただけだたから、きっと間違えて名前を押してしまいそのことに気づいていないだけなのだ。これが内海さんなら何も考えずに昨日電話しましたかと聞けたのに、スズキはいつもと同じ顔をして挨拶を返しただけだった。
あの日彼女は備品室で何を見たのか。時間だけが過ぎて、切り出すには不自然なところまできてしまった。
昼休みになったので席を立ったら、春野さんが尾関くんのところにきて二人はスズキには意味不明の自転車レースの話をしはじめ、尾関くんがいつもは硬くなった餅をむりやり引き伸ばしたような話し方なのに、そのときはやけに早口で選手らしき名前を連発するのに対して、春野さんはその言い間違いや微妙なアクセントの違いなんかをいちいち指摘していた。スズキは春野さんが訂正したクフィアトコフスキという名前を一度で覚えられたのに、やっぱり彼女の声では再生できないことに気持ちが悪くなって、頭を振りながらトイレに入った。
三つ並んだ奥の個室に入ろうとしたとき、背後で誰かの声がした。
「なに?」
とっさに振り返ったが、洗面台の前にも入り口付近にも誰もいない。個室のドアは開いたままで、人のいないことはわかっている。スズキは個室に入ることなくトイレから出ると、社屋を出た。
声は、社内の人間のものではなかったし、備品室で聞いたのものとも違っていた。
スズキはコンビニでトイレを借り、棚を見もせずに飲み物とパンをつかんで会計すると、店を出た。U字パイプに寄りかかって、パンを咀嚼してお茶で飲み下しながら、あれはトイレの外をたまたま誰かが通りがかったのだと思った。だとしたら、自分は春野さんだけでなく他の誰かの声も聞き分けられなくなったということになる。それがなんだというんだと思ったが、社に戻ってからのスズキは、誰の声と顔も結びつかなくなっていた。誰とも話をしなくてすむような仕事ばかりをして、課長と目が会ったときなどは、逃げるようにコピー室に入ってしまった。すると、また誰かの声がした。
「なに?」
同じように問うたが、答えはなかった。入室するときに確かに見たけれど、コピー室にはスズキの他に人は誰もいなかった。コピーした書類をひったくるとそこを出て、体調が悪いので早退しますとだけ言ってカバンとコートをつかんで、スズキは家に帰った。
★
一口コンロは渦巻きの電気式で、大した調理はできないどころか湯を沸かすのさえためらわれ、スズキはマグカップに水を入れるとレンジで一分間温めて、ぬるい湯を飲んだ。カーテンを開けるとちょうど電車が走っていくのが見えて、あの中からこっちを見ている人はいるのか目を凝らしたが、はやくてよくわからない。
スズキはいつか見た二時間サスペンスに出てきたマンションを、もう一度ネットで表示させると地図をカラー印刷し、コートを着て部屋を出た。
あのころ遠かった場所に自分はいま来てしまって、だからといって、電車から見えた町を捕まえられたわけではなかった。だって、スズキがいるのは、あの夜でかくてそれ故に中に入っているものが迷子になりやすそうなピンクのトートバッグを抱えて、遠い場所で列車を降りていった女の子の家なのだから。
あの夜、電車ではなくエレベーターに乗って五階まで運ばれていった自分は、それから遠い町で暮らし、寒いからといって大掃除は年末ではなくて十月にやる会社で、三本百円で買った歯ブラシで水切りかごをこすっていた。
「サイズの合っていなさそうな帽子」と言った内海さんの声も、「ここにいたのか」と聞いた課長の声ももう思い出せないし、顔もわからないのに、流れていく電車の窓みたいに彼らの言葉が文字になっていつまでも消えない。ただひとつ、追いかけてきてくれたのは、春野さんの声だった。きっと、あの夜ピンク色のトートバッグを持っていたのが彼女だから。
帰らないと。
普段は折りたたまれているけれど、水をかけられたストローの袋みたいにひろひろっと出てくる声をスズキは見ることができる。妹には、それがどうしたのと言われたけれど。
今は遠い。電車から見えるのは、もう自分のいない焦げ茶色のマンション。空には、黒いこうもり傘が飛んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
