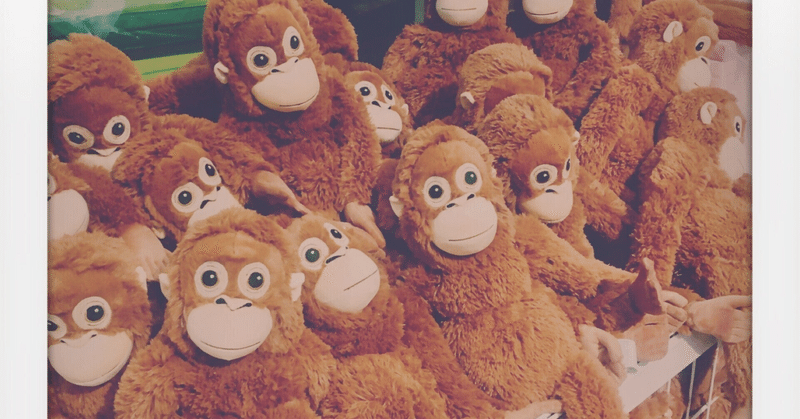
必ず登場する男
「あるところに売れない小説家がいたんだ」
彼が言った。
「その小説家の名前は…Sとしようか。Sは自分の作品にいつも同じ男を登場させていたんだ」
「同じ男?」
私は彼に聞き返した。
「ポアロとかホームズみたいに、同じ登場人物が出てくるっていうこと?」
「そういうことじゃない。同じ人物と言っても、それはSにとってだけで読者にはそれが同じ人物だとはわからないんだ」
「というと?」
そう聞きながらも、私は手を止めずにいた。そのとき私は、自分の部屋で静物画を描いていたのだ。鉛筆で花瓶と林檎とライムをスケッチしている間、彼はまるで自分の顔を描かれているように私を見ていた。
「たとえば」
と、彼は話を続けた。
「主人公がふらりと立ち寄った居酒屋の店員とか、道を尋ねた相手。ひとつ下の部屋の住人。そんなふうに毎回立場を変えて、男を登場させるんだ。名前はつけずに、物語の筋には直接関わらせない。ときには、男か女かさえわからないように書く。だから、読者にはそれが同じ男には見えない。それがわかるのは、ただ一人、Sだけだ」
「なるほど」
朝はよく晴れていたのに、急に風が出てきたようだ。彼は庭の木に視線を据えながら、話し始めた。
Sがかつて住んでいた町に、ぼんやり歩いていると知らずに足が重くなるゆるい坂道があった。
書くことに行き詰まると、Sはいつもその坂を行ったり来たりするのが習慣だった。何かいいアイデアが思いつくときもあったし、ただ足が疲れるだけの時もあった。
坂のとちゅうに薬屋があって、ガラス戸の奥には黒縁の眼鏡をかけた猫背の主人が立っていた。その日は何もよいアイデアが浮かばずあれこれ考えすぎて、頭が痛んでいた。Sは、薬屋の中に入って行った。
主人が顔をあげて「いらっしゃい」と言った。その低く、小さい声は今のSにはちょうどよかった。あまり人気のない店と見えて、商品にはうっすら埃がつもっている。薬の種類は少なかった。
「頭が痛いんです」
そう言うと、主人は頷いて、見たことのないメーカーの白い薬箱を出してきた。
「最近はいろんな薬が増えたけど、これがいちばん効きますよ」
なるほどそんなふうに言われると、かえって心が惹かれるものだ。あるいは在庫が少ないことの言い訳かもしれないが。
Sはそれをもらうと言った。主人はゆっくりと、レジスターに金額を打ち込んだ。その背後には店の名が入った大きな鏡がかけてあり、Sの顔と主人の背中がおさまっていた。Sにはなぜかそれが、まだ書いていない小説の一場面のように見えた。
頭痛薬は効き目を発揮し、Sは薬屋と鏡に映った二人の男について書いた。
物語は結局たいした話には仕上がらなかったが、その場面だけはやけに気に入って何度も読み返した。
次に書いた長編では、薬屋は宅配便を届けにきた男になった。年も違えば眼鏡もしていなかったが、Sの中ではあの男なのだ。以来、薬屋は老人や子供になることもあれば、無機物になることもあった。
小説に煮詰まると、男を登場させる。姿をかえて何度出てきたっていい。そのうちに男のことばかり考えている自分に気づいた。もう、男を登場させるのはやめようとSは決めた。
「それはあなたの話なの」
と私は聞いた。
「この話はつくりものだよ」
「誰がつくったの」
「さあ」
翌週も彼は私の部屋にやってきた。私はまだこの前の続きを描いていた。
「もうとうに描き上げたと思っていたよ」
「さぼっていたから」
「なぜ」
「さあね。絵筆を見るのも厭だったの。でも、人がいるとしたかなく描こうというか、描いている形をとるしかなくなるから今日は描くことにするけど。そういえば、この前の話だけど、いっそのことその男を主人公にすればいいのに」
「それはSも何度も考えたんだ。でも、それをやったらもう二度と書けなくなると思ったんだ」
「なぜ」
「さあね」と彼はさっきの私の口真似をした。
強い風が吹いている。木蓮の大きな葉がばさりばさりと落とされたあとで舞いあがって、大きな鳥のように見えた。私は静物画をやめて、スケッチブックに鳥の絵を描き始めた。黒くて堂々としているが飛べない鳥だ。
「そのあとはどうなったの」
「書くことから逃げるために男がいたのに、書かないと決めると、苦しかった。机もコップも時計も靴下も電車も空気も、何もかもが…」
彼は立ち上がり、テーブルの花瓶をそっと撫で、また窓際の椅子に腰かけた。
「それで現実を探しにあの町に帰ったんだ。住んでいたアパートはとうに空き地になっていた。坂をのぼりなから、薬屋もなくなっていたらどうしようと思ったけど、古い看板とガラス戸が見えて、奥にはあの男がいた。わけもなく息が苦しくなって急いで家に帰った。そしたら、昨日書いたはずの原稿は真っ白だった」
私は彼の顔を描きはじめた。彼はこちらをちっとも見ようとしないから。
「たしかに書いたんだよ。でも猛烈な勢いで消したんだね。僕はときどきそういうことをやるんだよ。それから後悔するけど…。ほら、よくドラマで作家が原稿用紙を丸めて捨てるシーンがあるだろ。あんなの嘘だ。みんな大事にとっておくよ。たとえ丸めてもそのあときれいにきれいに皺を伸ばすんだ。僕ならそうするよ。いいと思った原稿だって次の日にはどろどろのヘドロみたいに見えることがある。だとすれば、悪いと思った原稿もきらきらした金塊みたいに見えるかもしれないじゃないか。金塊?僕はなんて表現力がないんだろうね、いや、しゃべっているときは駄目なんだよ、僕は。だからって、書いているときもいいわけじゃないけど…」
彼が話をしているあいだに、私は顔を描き終えてしまった。
「どう、似てる?」
私はスケッチを彼に見せた。
「それは?」
あなたの顔、と言おうとしたとき彼は椅子から立ち上がった。
「どうしたの」
「君はなぜその男の顔を知ってるのさ」
「なにを言ってるの?」
「だって僕は、僕は、その男の顔を知らないんだよ。だいいち、この話はつくりものなんだ…」
「つくりものだとしたら、誰もその男の顔を知らないんじゃないの。それにこの顔は…」
「僕はもうだめだ。だってその顔を見てしまったから。いや、見たからこそいいのか。その絵をくれる?いや君の作品なのにそんなことは許されないよね」
「べつにいいわよ」
私はスケッチブックをめくると、無造作に彼に渡した。しかし、かえってそれが彼を傷つけたようだった。
「そうか、君にとってはこいつはそんなものなんだね」
それはあなたの顔だからあげたのに。
私はそう言おうとしてやめた。
彼は絵をうやうやしく受け取ると、部屋から出て行った。窓の外にはまた風が吹いている。しかし、木蓮の葉は昨日一枚残らず落ちていた。
それから私は、ようやく花瓶とライムと林檎を完成させた。
終わり
※本文とぜんぜん関係ないけど、我が家にこのお猿さんがふたりいて名前をつけて毎日戦わせてたらぐにゃぐにゃになってきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
