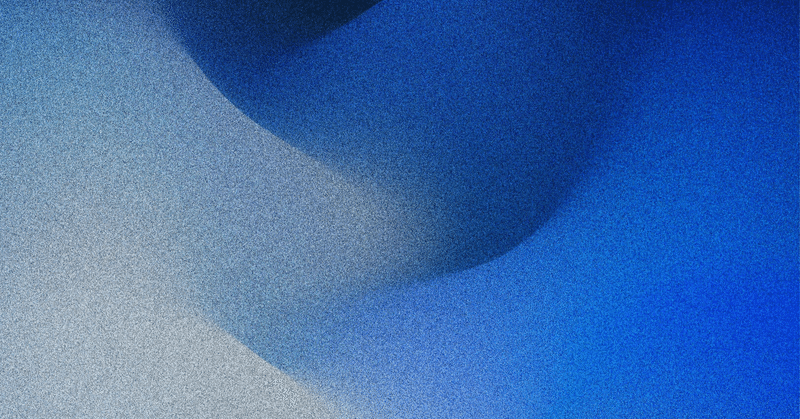
わたしの家 その二
約束の水曜、昼に出かけるはずがぐずぐずしているうちに夕飯どきになってしまった。
ホームセンターで買ったばかりの自転車は、ハンドルの動きもカゴとのバランスも慣れていないから、怖くて速く走れない。
実家に行くのは正月以来だ。里帰りは昔、生まれ変わりの儀式だったという。昔の人間は、蛇が脱皮するのを生まれ変わりだと信じて、菰のようなものを作って成人するとそこに閉じ込もり、蛇の脱皮になぞって生まれ変わりの儀式をしたのが、いつのまにか正月の里帰りとなったとか。
とは言え、いま私が向かっているのは私を産み出した家ではない。大学の一年の夏に父が事故で死んだとき私はアパートに一人で住んでいて、弟と母はマンションに移り住んだ。最初の家は、そこで産まれていない別の人物が住んでいる。
私にとっては、今の家も生まれた家も三角家も、なんなら緑マンションのエントランスホールですら自分の場所のような気がするし、そのどれも違うような気がすることがある。
川沿いの道に出るとそこは石畳で、振動がひどく何度も自転車が横に倒れそうになった。私は自転車をとめて川のなかを見た。大きな黒い鯉がうねるように泳いでいる。なるほど、あのように走ればいいのだと、私はまた自転車にまたがるとうねりに身を任せた。川が終わると平坦の道になり、自分はもう魚ではないのだからうねる必要はなくなり、いまは自転車に乗っているのではなく自分の家のソファに座っているのだと思ったらハンドル操作はいっぺんに楽になった。
「おそかったじゃん」
インターフォンごしに、弟の声がした。
「ごめん、自転車がパンクして」
玄関を開けた弟は、じろじろと自転車を見ている。
「おかあさんは?」
「五分前まで待ってたけど、あきらめて出かけたよ。ありったけの料理を作ってね」
ラップにくるまっていた料理は、パエリアではなく昔よく食べていたメニューばかりだ。一人でダイニングテーブルに座ってもそもそしていると、弟がほうじ茶を淹れてくれた。
「あたらしい家はどう」という。
「あの家は、あたらしくもないけどね。屋根裏に、誰かがいるらしい」
「いるって、誰が」
「家の元の持ち主は夜逃げしたらしいし、そのあと長いこと放置されていて設計図も残っていないんだよ。誰も歩かない廊下や、排便をしないトイレや、乾いた風呂や、空かない雨戸のことを考えてよ」
「それと誰かと、どんな関係があるわけ?」
「関係があるともないともいえないけど、どうやら屋根裏に誰かが住んでいるんだよね。便宜上、彼と言うけど、私が静かにしていると、彼が歩く。生きていないくせに自己主張の激しい家鳴りなんかじゃなくて、知られたくないと思っている者の足音」
弟はあきれたように、家は住まないとすぐに痛むらしいから換気をするようにと言った。
私は夜のなかをぬかりなく深く走り、三角家に戻った。自転車をとめながら二階を見上げたが、出窓は暗くて中が見えない。
私の家には、誰かがいるのだ。誰というより、名前のないもの。
弟は私をねえちゃんと呼び、私は弟を、ねえとかあのとか呼ぶが、なんと呼んでも弟は返事をする。私は大抵の人を頭の中で彼とか彼女とかあの人と呼んでいる。名前のない人間はエントランスホームの向こうにいる住人のように遠くて、実態がない。名前がある人には背景があり世界があるから、私はそこには入ってはいけない。
ぼんやり家を見上げていると、駅から歩いてきた女の人が私のそばに近づいてきた。
「あんた、なにやってんの」
かすれた声で、暗いから顔はよく見えない。今日は一ミリも雨が降っていないのに、ビニール傘を二本も持っている。
「人がいるみたいなんです」
大変よ警察、と騒ぎ立てそうもない人だったからか、するりとそんなことを言っていた。
「誰もいないみたいだけど」
「暗いから、きっとそんな気がしたんでしょうかね」
私がごまかすと、女の人があっと小さく叫んだ。
「いた。あれね」
「え?」
「○○だね」
私は急いで出窓に視線を戻したが、やはり暗くて何も見えなかった。
「あの、さっきなんて」
言いました?と振り返ったときには、女の人はもう公園に向かって歩き出していた。
引っ越して三か月が過ぎると、彼の気配が少しずつ濃くなってきた。近ごろではだいたい出窓にいる。その下に机があって、そのまたしたに鞄をいれる箱を置いていたら、出窓から机、机から箱とうつるのに便利にしている。私が歩いて行くと、出窓でゆっくり立ち上がって、机に移る。机のうえでしばらくじっとしているようだが、姿は見えない。できるだけ静かに机に背を向けるとゆっくりと箱に降りる。それが、はじめのうちは逃げているのかと思ったが、実は仕向けているとわかった。
箱に入りたい、そう思ったときはごとごと音を立てる。私が見にいくと、机にうつる。まずは存在を示しておいて、目の届くところに私を釘付けにしたまま箱に入るのだ。すんなりと一人で入るのが怖いのか。
ごとごとと音がするとすぐに隣に行く。そのうちに、机から箱に入るまでの動作が流れるようなはやさになった。何かしたいことがあるたびに音を出す。こちらが眠っていようと、おかまいなしだ。出かけているときは、どうしているのだろう。じっと、出窓にいるのか。
「ねえちゃん、あの家見に行こうぜ」
弟から電話があった。
「あの家?そういう言葉遣いだと全世界の家ってことになるよ」
「ちぇ」
「ちぇ、は辞めなさいって誰かに言われたでしょう」
「姉ちゃんと俺の生まれたところだよ」
「それを言うなら、病院」
「見に行くの、行かないの」
「行ってどうするわけ。いまは別の人が座っている部屋で、麦茶を飲むことはできない」
「麦茶なんか飲みたくないよ。姉ちゃんの話を聞いてたら、あの家が見たくなったんだ」
「自転車で行くけどかまわない?」
「構わないよ、じゃあ家の前にあった公園で二時ね」
会話が途切れるまで弟そのものみたいに思えていた受話器が、ぱっとライトを消して静まる。また、どごとこと音がする。階段を上がりかけて、少し腹が立ってきた。それで、曲がり角の三角形の踊り場に座りこんだ。家という居場所のなかで階段は途中だから、ここにいると途中になることができる。音はまだしていたが、そのまま座っていた。
わたしの家 その三 に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
