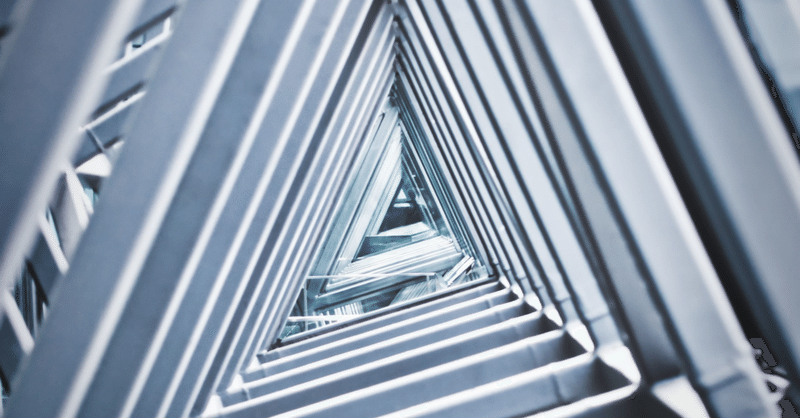
わたしの家 その一
K駅で降りた。
南北に分かれた改札の、北の階段を降りるとすぐに小さな不動産屋があって、家の写真と間取り図の印刷された紙が貼りつけてある。隣はマッサージ店でグレーの診察台と靴箱によく似た黒いスニーカーが二足。
道は左右にわかれる。左に折れてすこし歩いてまた折れて、線路沿いを進んでいく。線路の向かい側には、個人塾、クリーニング店、それから緑マンションという名の五階建ての建物があった。ぜんぶ、ネットの地図で見た通りだ。
ゆるいくだり坂をくだり終えたところに、切り分けたパイのような二階建ての小さな家が現れる。土地が狭いから、そんな形になったのだろう。
築は何年と書いてあったか忘れたが、かなり古い。家賃は管理費込みで七万円。一階に一間二階に二間と、アパートのような取り分しかないのが、いつまでも売れずに賃貸になった理由だろうか。
庭も柵もないから、家が小さいのにやけに目立っている。隣の土地には隙間もないほどみっしりと何かの木が植えられていた。
ひとまわりしてから、私はまた駅に向かって歩き出した。その足で不動産屋に行き、案内をしてもらった。中に入るとすぐに細い階段が現れ、階段の上の天井はエッシャーのだまし絵のように複雑に折れ曲がっていた。それを見て、私はこの家に住むのだと思った。
引越しの当日、手伝いにくる予定の弟が現れない。一人で引っ越し屋とともに走り回った。
家具のないまっさらな部屋を見てみたいと言うから、じゃあくればと答えただけだから、別にこなくてもかまわないのだ。弟はいま、母親とふたりで隣の町に暮らしながら大学に通っている。古いマンションだがリフォームをして中は新築のようにきれいである。
引っ越し屋が家具をトラックに詰め込んだころに、ようやく弟が紫色の缶ジュースを二本持って現れた。
「もうなんもないじゃん」
「あんたが遅いからだよ」
「よほど家具が少なかったんだろうな。ねえちゃん、面倒くさがりだから。ほい」
濡れている缶を一本受け取ってプルタブをひいて、一口流しこむと既知の味が流れ込んできた。
「ファンタグレープ」
「そうだよ、わかんないで飲んでたの」
弟はひと息で飲み干してしまったが、私は半分も飲めずに缶を流し台に置いた。そのあとは空になった部屋を二人して掃除した。弟がほうきではいていくあとから、追いかけまわすようにぞうきんで拭く。雑巾を動かしながら、飲みかけのファンタが散歩中の犬のように気になってしまう。てきとうにすませて、また缶を手に取ってぐいぐい飲むと紫色のしゅわしゅわが喉ではじけ、ほこりが光の粒になって部屋の中をまわっているのが見えた。
引っ越し屋を追いかけて、二人でK駅に行く。
踏み切りのまえを通るとき、焼けたゴムのような匂いがしたので弟にそう言うと、弟は鼻をひくつかせながら、首を傾げている。
「ねえちゃんは神経質だからな」
弟は、いつからおねえちゃん、ではなくねえちゃんと言うようになったのだろう。おがついていたときは、尾っぽのついた犬のように私を追いかけまわしていたものだが、おがなくなったとたん、私は安心して弟にあれこれ頼むようになった。
弟と三角家の掃除をしていると、通り過ぎる人がじろじろと見ていく。この家は空き家の時間が半年ほどあったので、雨戸が開いているのがめずらしいのかもしれない。
「みんなにとってこの景色がふつうになるまでは、カーテンをひいてやり過ごせばいいよ」
私が気にしていると思ったのか、弟がそう言った。
片づけが終わると、二人で近くの公園にまで歩くことにした。昔あふれた川をおさめるためにつくられたという公園にはコンクリートのなかを川が流れている。水鳥もいるしウシガエルもぶうぶうと野太い声で鳴く。
「たまにはうちにも帰ってきなよ。母ちゃんが飯作るって言ってるから」
公園をとりかこむマンションや鉄塔を見渡しながら、弟が言う。
「どんな飯?」
「いまはパエリアに凝ってる。量が多いから食べきれなくてあちこちから人を呼んで、そうすると足りなくて今度はポトフを煮てる」
「パーティみたい」
「くるの、こないの」
弟の顔が見たことのない形に変わりそうになり、行くよと答えてしまった。
「じゃ、来週の水曜ね」
午後、K駅に住む人達とともに改札を抜けた。
私の降りる北口に向かう人は南口に比べるとぐっと少ない。そこからさらに左右に道はわかれ、三角家のある道に折れる人はいつも数人しかいない。
土曜の午後なのに、人々の動きは速い。いちばん後ろになったと思いながらのったり歩いていると、うしろから近づいてくる足音がする。かしゃかしゃと、ビニールの音がするので、南口のコンビニで買い物をしてきた人かもしれない。
すぐに緑マンションが見えてきた。アパートとの違いは一階にエントランスホールがあることくらいだろうか。名前に反して一本の木も花も植わっていない。あるいは、オーナーの名前が緑なのかもしれない。
後ろからくる足音が急にせわしくなり、私を追い抜かしていった。白い長袖のシャツにコットンパンツの若い男の人だ。アイスとカップ麺が入っている袋を持って、左手でエントランスホールのガラス戸を押し開ける。
扉の奥を覗きこんだ。
左側にシルバーの集合ポスト、右側に管理人室らしい部屋の窓が見える。窓から見えたのは、テレビと事務用の椅子とテーブル。見える範囲に人の姿はなかった。
住人はポストに近づいて。すべてのポストにいったが、溜まったチラシを見てひとつため息をつくと、そのままポストを開けることもなく、奥に去って行ってしまった。
エントランスホール。知り合いの一人も住んでいないマンションの、見通せそうで見通せないガラス扉の向こうにある、別の世界への入り口。
世界には人がひしめいているというのに、そこだけはやけに広々として、いつ見ても誰もいない。中にいるのが実は人間ではないように思えてくる。
今、道に立っているのは私一人だ。あたりまを見まわして誰もいないことを確認すると、そっそガラス扉を押してみた。ポストに近づき、さっきの彼が見おろしていたチラシをそっと引き抜いた。海老メインのピザの写真。
三角家のポストには、いまだに一枚のはがきもチラシも届いていない。私はチラシを畳んでポケットにおさめると、エントランスホールを出た。
三角家に戻り、三種のチーズ盛りピザと黒ビールとアボガドとトマトのサラダを注文した。ピザ屋は三十分ぎりぎりに着いたが、私は自分の家が人から見つけられたことがうれしかった。
「俺、いつもは配達早い方なんすよ。でもこの家はなんか、見つけられなくて」
「でも、こうして見つけたんだ」
「もう絶対に見落としませんよ」
ピザを食べ終わったあとでビールを飲んでいると、二階のどこからか壊れかけた靴を履いて歩いているような、どこどこという音が聞こえてきた。木がきしむいわゆる家鳴りは耳にしていたが、こんな音ははじめてだ。
私はビールを手にしたまま、ゆっくり階段をのぼった。のぼっている間音はしなかったが、のぼりきったとたんにまたどこ、どこ、と少したどたどしい音がした。
この家は空き家だった期間が半年もあったので、野生動物が紛れ込んでいてもおかしくはない。けれど、さきほどの音は、獣ではなく人か、人に近いもののように思えた。なぜというに、意志のようなものを感じたから。それも、獣の意義のあるそれではなく、意味のない人のそれのような。
階段に坐り込み、ビールをすすった。この家は、外から見れば三角形でも部屋や廊下は四角い。三角なのはトイレと階段の踊り場と押入れの中だけで、そこには何を入れてもぴたりとおさまらない。隙間ができる。私は下見のときにエッシャーみたい、と思った天井を見つめたが、今ではそんな奇異なものではなくて、単に私がこの家の形をつかめないための複雑さなのだとわかる。
この家にはどこかに何かがいるのだ。自分がつかめない家の隙間に、きっと誰かがいる。
わたしの家 その二 に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
