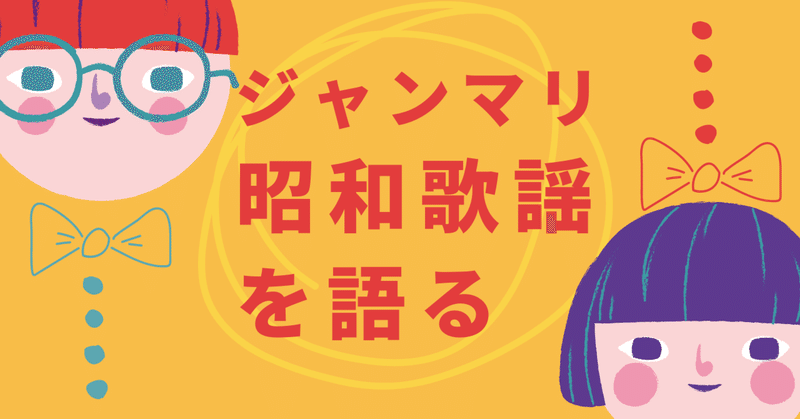
西條八十の美空ひばりへの想い
西條八十は50代後半に美空ひばりと出逢い、亡くなるまで彼女を見守り続けた。その類まれなる才能を少女の頃から見抜いていたし、大歌手になることを予感していた。
撮影所での出逢い
1950年、西條八十は「やまのかなたに」という映画の主題歌を依頼され、新東宝の撮影スタジオへ打ち合わせに出掛けた。帰る途中に友人の柳谷金語楼が主演の「向こう三軒両隣り」の撮影現場を通りかかった。ちょうど休憩時間で、セットの隅に小学生くらいの女の子が腰をかけていた。
「お嬢ちゃん、金五郎劇団の子かい?」と声をかけるとにっこりと笑った。そして、その娘が、「私、これでもコロビムアの専属歌手よ。」と言うので、八十は漸くその素性がわかった。
「ああ、君が...」
それは、当時天才少女と言われていた美空ひばりだった。
「君は、ひばりちゃんだね。僕はコロムビアの専属作詞家で西條と言います。よろしく。」
「あ、西條先生。気がつかなくてごめんなさい。」
ずいぶん、大人びた物言いだった。
そこへ、小柄で色黒の女性が近づいて来て、ひばりに「ジュース、買ってきたわよ。」と言った。
ステージママと呼ばれた加藤喜美枝。ひばりの母親だった。
さっそく加藤喜美枝が動き出した
暫くして、コロンビア・レコードから美空ひばりに正月向けの歌を書いてくれと八十に依頼があった。母の喜美枝が「是非とも西條先生に詞を書いていただきたい。」と言っているとのことだった。
今や作詞家として押しも押されぬ大御所となっていた西條に書いていただくことで、娘に箔(はく)が付くと考えたらしい。
商魂たくましい母親は気に入らなかったが、八十はひばりの才能を高く買っていたので、引き受けることにした。
そこで作詞したのが、「越後獅子の歌」だった。
レコーディングに立ち会った八十は、その歌唱力に舌を巻いた。見た目は子供なのに歌は大人びている。高音パートも裏声を使わずに地声で歌う。しかも、声に哀愁が漂う。背筋がゾクゾクして、不覚にも涙してしまったのだった。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
