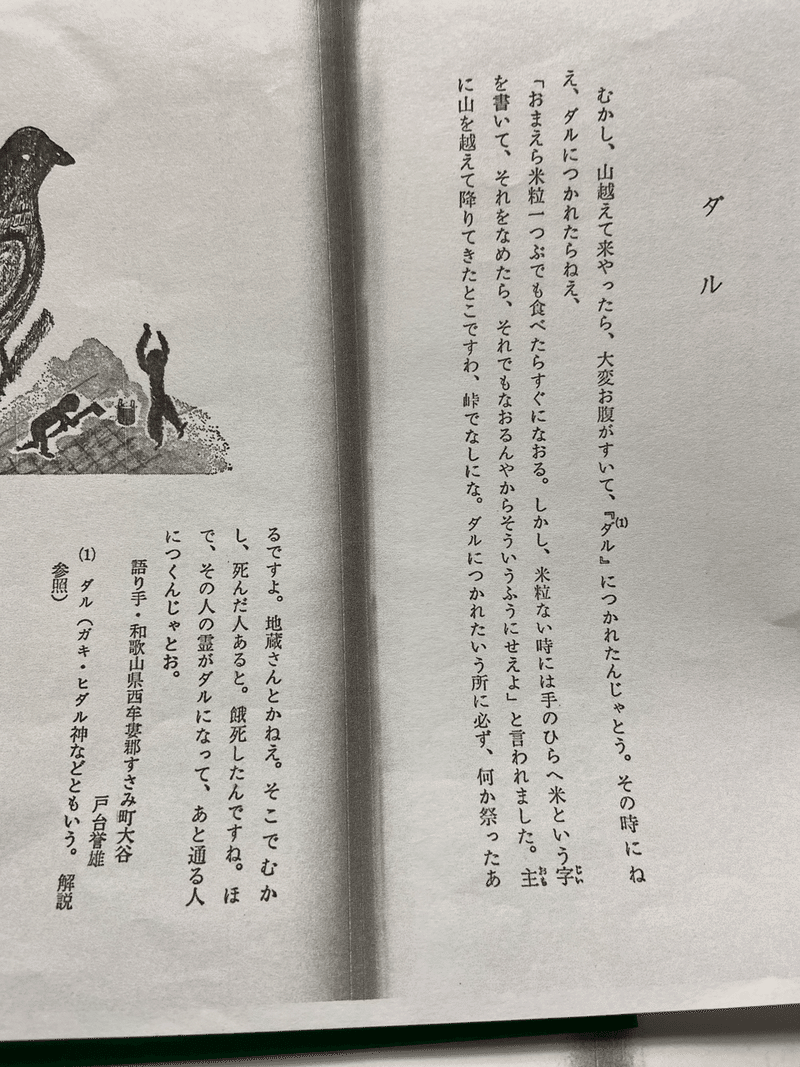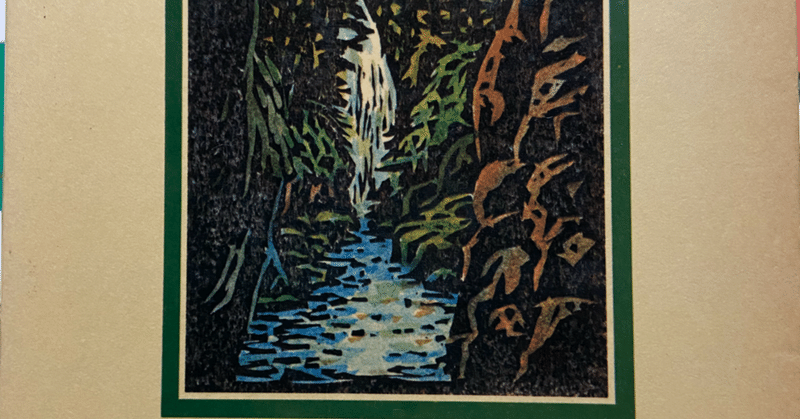
よむ という行為についての考察
むかしばなしを研究しておられる小澤俊夫先生の昔話大学に数年通っていた影響で、昔話の語りきかせはその人の「土地言葉」でよいと思っている。(小澤先生は「方言」という言葉をあえて使わず「土地言葉」と言われている)
小澤先生は、同じ出身でも両親の出身によっては言葉の使い方やイントネーションは変化するという。
その人の言葉で語ることの大切さを何度も言われた。
わたしも朗読劇を演出する場合、その人の使うアクセントやイントネーションはあまり気にしないほうだ。
語り手がそこを気にするのが声になって現れるので、こちらもそれが気になって話の世界に入れないのだ。
けれども私を含めて関西の人は学校の国語の時間の読みの影響で、読む時に喋り言葉のイントネーションを使わないことが多い。まず教科書がそんな言葉になっていないし、テレビの影響もあって標準語で喋ろうとする傾向さえある。(でも標準語にもなりきれないので中途半端なイントネーションになってしまうのだけど)
なので、喋っている言葉はコテコテの関西弁なのに、読むときだけ関西弁では読めないという人も多くいる。喋っている時とおんなじイントネーションで読んでいいですよ、と言っても読めないという。
読む、というスイッチと喋るというスイッチはどうやら違うらしい。
そんなこともあって、最近和歌山の教室では、昔話を自分の言葉に直して読む、ということをやり始めていた。
やってみると、はたして。すごく、おもしろかった!
昔話を自分の言葉で読むというのが、普段の読みとは違う手応えがあるのだ。
何話も何話もそうやって読みたくなってきた。
ところがこれは60代以上のメンバーにはあまりピンとこないらしい。
言われたほうは、やってみたけど、いいのかな〜、伝わってるのかなと、どこか不安げだ。わざわざ自分の言葉に直す必要があまりわからないです、と言われてしまう始末。
むむむ、そうなの?これをおもしろいと思うのは私だけなのか?とちょっと課題に思っていた。
3月20日の春分の日に熊野の森で文化祭を行う。
昨年から熊野の森でやりたい人が演奏したり、お話をしてくれるというイベントだ。
新今宮のフレル朗読劇団も去年から参加していて、今年もそれに参加する。
今回は和歌山の昔話を読むことに決めた。フレルのメンバーは関西地域で育った人がほとんどだ。
フレルの1月の稽古の時、それぞれが短い昔話を選んでもらい、自分の土地言葉に言い換えて読んでみてくださいとお願いした。
長くても2分くらいで読み終えてしまう短い話ばかりをあらかじめこちらで選んだけど、やってみるとみなさんなかなかどうして難しいようだった。
特に新今宮で生まれ育った60代のYさんは、苦戦していた。
Yさんはもともと読むのが苦手だ。小学生の頃は本当に読めなかったという。
今はボランティアで絵本の読み聞かせに行ったり狂言のワークショップに出たりと積極的だ。そしてその読み方はいつも独特なのだ。
毎回読み方が違う。言葉を覚えたばかりの子どもが読む読み方に少し似ている。それはとても素直で味があるのだ。
Yさんは「ダル」という昔話を選んだ。「ダル」とは熊野に伝わる有名な妖怪のことだ。
難しいという。
もともとYさんは言葉の意味をあらかじめとらえて読む、ことをしないで文字を目で追っていくように読む。そのよさは、語り手であるYさんが自分のイメージを押し付けてこないので、聞き手が自由に想像できるところにある。
けれど、今回は原本が口承なので、文法的に省略していることもあり、聴いてるものは何を言ってるのかよくわからなくなってくるのだ。
短い話なので、意味がわかるよう把握してから何度か練習してみましょうねというと、Yさんは納得し「練習してみます」と言い、その日はそれで終わった。
その夜、同じメンバーのカエルさんから「ちょっと気になって「ダル」を自分なりに言い換えてみた」というメッセンジャーが送られてきた。
読んでみると、なるほど、これはYさんではなく、カエルさんが語る言葉だと思った。
声に出して読んでみると、本当にカエルさんのお話のように思えてきた。
私だったらどんな言葉になるだろうとためしにやってみた。
はたして、カエルさんのお話と全然違った。
言葉足らずなところをどう解釈して自分の土地言葉で表すか、というところがミソだ。
語尾を何に選ぶかも大事かもしれないと思えてきた。
他の場所では、即興で自分の言葉に直して読んでいたのでそんなに思わなかったのだけど、いざ文字に起こしてみると、また感じが違い、何度も声に出しながら修正してより自分の言葉に近づけることをやってみた。
このより自分の言葉に近づける、というところがおもしろかった。
以下に書いてみる。元々の本文は和歌山の南、すさみ町に住んでいた人だ。出典は稲田浩二さん監修の日本の昔話13「紀伊半島の昔話」より
ダル(本文)むかし、山越えて来やったら、大変お腹がすいて、「ダル」につかれたんじゃとう。その時にねえ、ダルにつかれたらねえ、「おまえら米粒一つぶでも食べたらすぐになおる。しかし、米粒ない時には手のひらへ米という字を書いて、それをなめたら、それでもなおるんやからそういうふうにせえよ」と言われました。主に山を越えて降りてきたところですわ、峠でなしにな。ダルにつかれたいう所に必ず、何か祀ったあるですよ。地蔵さんとかねえ。そこでむかし、死んだ人あると。餓死したんですね。ほで、その人の霊がダルになって、あと通る人につくんじゃとお。
ダル(うり)むかし、山越えてきたらすごいお腹すいてしもて、よう「ダル」にとりつかれたんやって。その時にね、ダルにつかれたら「自分ら米一粒でも食べたらすぐになおる。せやけど米粒ない時には手のひらへ米という字書いて、それなめたらそれでなおるんやからそうしなさいよ」っていわれたんやて大体が山越えて降りてきたところでそうなるんやて。峠でなしに。ダルにつかれたっていうところに必ずなんか祀ってあるんやて。地蔵さんとかね。そこでむかし死んだ人あるんやって。餓死したらしいよ。
ほんで、その人の霊がダルになって、あと通る人につくんやって。
ダル(カエル)むかし、山、越えて来たら、えらいお腹減ってしもて「ダル」いうやつにつかれたんやて。そのダルにつかれらなぁ、「米粒、ひとつぶでも食べたらすぐなおる。米粒ないときは手のひらへ米いう字書いて、それなめたら、それでもなおるからそうせぇよ」って言われた。つかれるのは主に山降りてきたとこあたりやて。峠やないとこや。ダルにつかれたとこには、必ず何か祀ってある。地蔵さんとかな。そこでむかし死んだ人がいてるんや。餓死したんや。その人らの霊がダルになって、あと通る人らにつくんやて。
(このnoteに出す前に、わたしの文はもう一度修正をかけた)
関西に住んでいる方なら声に出して読み比べることをお勧めする。
この違い、わかるだろうか。
男女の違いもあるし、年代の違いもあるかもしれない。
カエルさんは私とおなじ和歌山だけど、私の住んでいるところは和歌山市内、彼の住んでいるところはそこから車で1時間ほど東へ行った橋本市だ。住んでいる場所の違いもあるだろう。
こんな長々と、それがどうした、と言われたらおしまいなのだけど、標準語で語る時と明らかに身体感覚がちがうのだ。やってみないとわからないことを言葉で言うことのもどかしさよ!
「身体感覚の違い」といえば、先日行ったくじらちゃんとのワークショップ「音の響き」の第1回目を思い出した!
その中で、くじらちゃんが選んだ短歌を身体で表現してみるという活動を急に思い出したのだ。
こんな短歌を一人ずつ身体でやってみた。
水仙と盗聴、わたしが傾くとわたしを巡るわずかなる水 服部真里子
もらった直後には、意味が全くわからなかったけれど、それを何度か口に出して、身体でやってみたところ、わからないなりに全員が何かをやっていて、それがこの短歌のどこにイメージを寄せたかがなんとなくわかるものだったことにびっくりしたのだった!!
「盗聴」に寄っていった者、「わたしの傾き」に寄っていった者、「水」に寄っていった者・・・。
それはこの短歌をどう解釈したかを言葉で話すよりもはるかに雄弁な時間だった。
そしてこの短歌に対する親近度が確かに深まったのを感じた。
くじらちゃん曰く、この短歌は短歌界の中で一石を投じた一首らしい。
よんだだけではすぐにわからない難解さが問題になったという。
でも身体でやってみたら、こんなにも雄弁に語っているものを全員拾えてるのですね、すごい!と提案した彼女自身がそのことに驚いていた。
「『よむ』という営みは、文字を追うこととは限らない。こころを、あるいは空気を『よむ』ともいう。(中略)本を読むというときにさえ私たちは、そこに記号を超えた何かを認識している。表記されている奥に隠れた意味があることを感じている。行間を読むとは、そうしたことを、どうにか言葉にしようと思った者が思い至った表現なのだろう。『よむ』という言葉には、どこか彼方の世界を感じ取ろうとする働きがある」
若松英輔さんの文章を読んでいたらふっとこんな文が流れてきた
もっともっと「よむ」ことを追求してみたい。そう思っている。