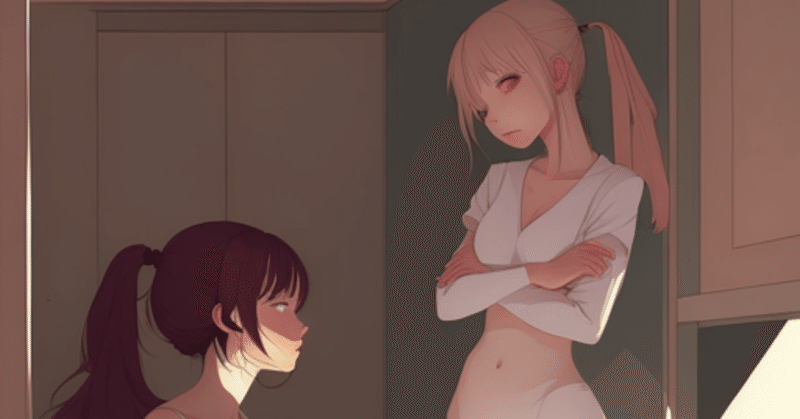
ドSな彼女Ⅱ 1
1
やっぱり、オナニー禁止はつらいな。
普通はどうか知らないけど、僕の場合三日我慢したらもうムラムラが止まらない。
授業中でも里緒菜さんのこと思い出して勃起が治まらなくなるのはしょっちゅうだ。
でも、向こうも大学あるし、僕も学校あるしで、会えるのは週に多くて二回が限度なのだ。
貞操帯装着されてるわけじゃないから、こっそりオナニーすることができないわけじゃないけど、里緒菜さんの信頼を裏切るのはいやだ。
だから、今日も前回から五日目だけど、何とか我慢して一日を終えようとしていた。
自転車置き場に来てみると、クラスメイトの上村加奈子が僕の自転車のところで待っていた。
今日は自転車部のジャージではないが、自転車に乗りやすいように体操着の短パンを履いていた。
上の制服はまだ夏服のままだ。
「今日はクラブないの?」
上村に聞いてみた。
「大会前だから上級生はみんな特錬に行ってるんだ。一年は足手まといだから行けないんだけど、一年だけでの練習は危険だから、今週はお休みなの。だから、ミチル君と一緒に帰りたいなって思って。方向も一緒だよね」
恐る恐るという感じで上村が言う。
一瞬うざいなと思ったけど、思い直した。
ちょうどいいかもしれない、聞いてみたい事があったのだった。
いいよ、と言って僕は自分のロードバイクのチェーンロックを開錠する。
上村加奈子には、二学期が始まったばかりの時にちょっとしたハプニングがあって、そのあと好きだって告白されていた。
僕には里緒菜さんという恋人がいるから、その時はそう言って断ったんだけど、友達でいいと言われたらそれ以上拒否することもできなかった。
別に教室でしゃべるくらいはどうってことないわけだし。
でも、一緒に下校とかはあんまり気が進まない。
どうして気が進まないのだろう。
考えるに、僕は里緒菜さん以外の女性に興味を持つことを怖がっているのではと思った。
恋人なんて、里緒菜さん以前にはできたことなかったし。
いや、里緒菜さんとの付き合い方が僕の想像していた男女交際とはかけ離れていたというのが一番の理由だろう。
普通の付き合いがしたいと考える僕の気持ちが、限界を超えることを恐れていたのだ。たぶん。
僕の前を走る加奈子のお尻を眺めていると、また僕の股間が反応しだした。
でも、今日は此間のような自転車ジャージじゃなくて体育用の短パンだから、そこまでエロくない。
何とか我慢できそうだ。
ちょっとそこで休もうよと、土手の道横の開けた場所を僕は指さした。
「実は、ちょっと聞きたいことがあってさ」
アスファルトの端の段差に二人で座った後、そう言う僕に、加奈子は小首をかしげて肯いた。
「ええと、前に言ってただろ。僕のこと、好きだからいじめたくなるとか」
僕がそう言うと、加奈子はクスリと笑った。
「大丈夫よ、もういじめないから」
「いや、そんなこと心配してるんじゃなくて、女子って好きな子に意地悪したくなるのかな? 一般論として」
加奈子はまた笑った。
「一般的にどうかなんて知らないけど、私はそんな性格だってことよ」
「宮田や竹田もって事?」
「ああ、そうか。あの子たちもそんな感じだったね。でも、一般的にそんな子が多いってことはないと思うけど。という事はミチル君がそんな子を寄せ付けるタイプなのかもね」
やっぱりそこに落ち着くのか。僕が引き寄せているのかな。
「どうして? 気になるの?」
そう聞かれたけど、どう答えるか迷う。
加奈子は相談相手としてふさわしいだろうか。里緒菜さんとのこと言っていいかな。
少し考えた後、相談してみることにした。ダメもとだ。特に失うものもないはずだし。
「実は、僕の彼女、夏休みの時に知り会った女子大生なんだけど、そんな性格みたいなんだ。僕のこといじめて楽しむタイプの、ドSな彼女なんだ」
加奈子がぷっと噴き出した。
「そう言えばあの時も言ってたよね。ドSな彼女だなんて、格好いいじゃない」
「まあ、実際かっこいい人なんだけど」
「何のろけてんのよ。それで、どんな事されてるの?」
ええと、ここから先はプライベートな問題だから、どうしよう。
「それ聞かないと、正常か異常か判断できないんですけど」
迷ってる僕に強気な加奈子が尋問する。さっきまで下手に出てた加奈子なのに。
ここだけの話だよ、秘密にしてねと言う僕に、大丈夫、私はミチル君のこと好きだから、味方だからと言われて決心した。
でも、この時もう少し疑うべきだったのかもしれない。
だって、相手は好きな子をいじめるのが趣味な女子なんだし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
