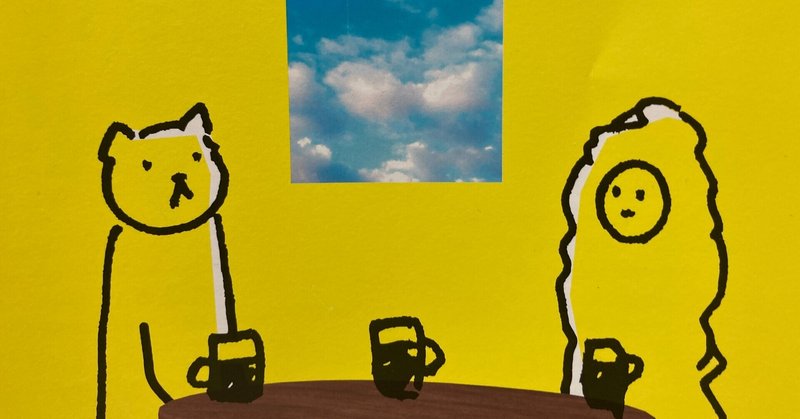
彼らは、僕らだ。ーー「あたらしい憲法のはなし3」
本日、演劇系大学連盟企画「あたらしい憲法のはなし3」を観させていただきました。対話を持ちかけられた者として、反応を示すべきと思ったので書きます。劇評ではなく、個人的に思ったことを詩的に述べるだけですので悪しからず。
当然、ネタバレがあります。ご注意ください。
そして途中、やや取り乱します。感情的な文章が苦手な方はブラウザバック(死語?)を・・・
クリーンな国、日本
まず、フライヤーやビジュアルが非常に鮮やかでポップだと思った。市役所のリーフレットコーナーに、「マイナンバーカードを作りましょう!」とあるような冊子にも似た印象を受けたが、これは「難しそう」なイメージの真逆にあるということだ。シンプルでとても良い。
場内でもらったパンフレットも充実して美しく、熟読に値すると思った。(まだ隅々まで読めていない)
この劇は、戦後の憲法制定とともに発行されてすぐ発禁されたという『あたらしい憲法のはなし』という中学校1年生向けの教科書から着想を得、2015年・柴幸男演出で上演された『あたらしい憲法のはなし』を、2021年の現代に向けて再解釈したものだ。
脚色・演出はシラカンの西岳。彼のコメントや作品を見るに、この作品を、観客の次なるアクションにつなげたいという意図があるようだった。
パンフレットでは「チャット」という言葉が目立ち、印象に残った。制作過程でも、カンパニー内でこの言葉への意識は大きかったという。チャット=文字情報のやりとり。いわんやこの劇が、常に観客の文語脳を刺激するものであったのも理にかなっている。
徹頭徹尾、この劇は「寓話」のスタンスをとる。乱暴に言えば、こんにちの日本を醸造するに至る過程を、これでもかというほど丁寧に積み上げていく劇だった。ひたすら積み上がっていく。事実が事実として積もっていき、舞台美術が見せる世界を証明するかのように、石柱の頂上、その断崖を作り出していく。
空間は無機質で、日本が世界に「見せたい」バーチャル的な東京の一面を想起する。俳優たちはその上で、過剰なほど個性的な衣装を纏ってこの寓話の世界で悪戦苦闘する。登場人物たちはそれぞれが担うアレゴリーに徹し、ドラマを持たず、0から始まって0で終わるこの劇を全うした。
真っ白い空間に、彼らが生きた証を何も残すことなく、真っ白いまま、舞台は終わった。引っ掻き傷ひとつない舞台が残り、俳優たちはそこで観客に頭を下げ、また去っていった。
私は思った。この劇は一体、憲法をどうしたかったのだろう?
憲法の成り立ちと、それによって狂っていく人間の模様や、それが破られる敗北感などが、どれもフラットに演じられ、観客はスタンスを定めることができず、いわば神の視点でこの劇を見送る。「象徴から元首へ」移ったあの人さえも俯瞰視し、私たちは何も言い返すことができぬまま、彼らの顛末を見届けた。
現実ならば言い返すことができる。だからそこで求められるのが対話なのかもしれない。しかしそれは私がこの劇の感触を再確認する過程で「過干渉して」ふと思ったことであり、劇が直接促したものではない。
真っ白な空間。真っ白な日本。これまでたくさんの人が生まれ、死に、残してきたはずの痕跡が「ない」場所、それが日本なのかもしれない。この「クリーンさ」の舞台裏には、忘れてはいけない彼ら/私たちの壮絶な過去があった。
そう、この劇の本質は、「舞台裏」にこそあったのだと思う。
舞台裏
推測だが、客入れと客出しには、舞台裏に仕込まれたマイクの音が拾われ、流されていたのではないだろうか。開演前と終演後で聞こえてくるざわめきのトーンが違った。開演前は緊張感が、終演後は開放感を感じた。
そして最後の屋台崩し演出。寺山オタクとしてはもう一押しと思ったところだが、あれこそまさに、劇の本質を劇中から劇外へ求める態度の現れだろう。
つまり演出者はこの劇を作る「彼ら」に最も目を向け、同時に、観客にもその目線を要求していたのではないだろうか。
演劇を学ぶ学生たちが、大学の垣根を超えて集まるこの企画。日本の演劇のこれからの土壌を作る大きな発射台であることは言うまでもない。そこで、挑戦と実験を許された彼らの存在と、その制作に励む時間。それらは非常にかけがえのないものだ。
「憲法について考える」という、想像するだけでも面倒くさそうなテーマがあり、そんなことを、世間の人々が仕事の合間を縫って考えることができないのも当然で、しかしそうして「積み上げて」できたこの風潮が、ここに来て最悪な最終進化を遂げようとしている。そこに警鐘を鳴らすための上演であることを想像していたのだが、どちらかというと、もう少し長い目で見た、「若者たちが考える」ことの尊さを提示するもののように私は感じた。
果たして、それでよかったのだろうか。
私たちはこの1年半に及び、むしろ舞台裏でしか活動できなかったと言っても過言ではない。そんな折に、まだ舞台裏を想像させる範疇でとどまってしまってよいのだろうか。想像しない者は何も想像しない。舞台は一体、どんな場所であるべきなのだろうか。いや、「べき」というのは存在しないだろう、少なくとも「私は」どう捉え、実践していくべきだろうか。
考えた。
持ちかけられた対話に、答えなければならないと思った。
永遠の対話、その一言目は?
この劇が飛翔寸前で墜落した理由は、圧倒的な一点に尽きる。
「一言目がなかった」
のである。
対話は、話そう、話そう、という意思だけでは始まらない。
また当然、話さなかった過去があるだけでも始まらない。
だから、この国からは対話が消えた。
なんでもいい、一言目が欲しかった。
「憲法読まない奴は帰れ」でも「憲法なんか読まなくていい」でもよかった。
多様性という概念が、包み紙のように覆っている私ちの「ソーシャル」において、その一言目に何を言うか、非常にセンシティブであることはわかっている。だが、だからこそ、日常での対話が難しい昨今だからこそ、舞台芸術の力が必要なのではないだろうか?
確かに最後の場面で、「自由」と「被害者」が語り合い、憲法読む読まないの話をするが、「自由」な彼が、読むのも自由、読まないのも自由と論じてそれに頷くしかない、そんな絶望的な顛末を見るために私たちは劇場に劇を求めるのだろうか?
冒頭で気持ち悪いほどにアメの被害を受けた被害者の彼女は、終盤、何もわからず戦後の日本に放り出される。そのぶった斬られたコンテクストが、今、「憲法について考えられない人」あるいは「読まない自由」を糾弾する力を持てたはずなのではないだろうか?
自由という言葉が、罪と罰、あらゆる言動を包み込む魔法の言葉になってはいけない。優生思想や奴隷政治に戻ってはいけないのと同じだ。私たちはこれから、そういうことを考えていかなくてはならないのではないのか?
それに、「別姓婚」の2人が辿り着いた境地が結局「同性の選択」だったのもわからない。なぜだ? あの劇の終末が、現在(WW2〜令和3年)の時点なのか、未来(新憲法が制定された後)の時点なのかがハッキリわからなかったため、2人の選択が「望ましいものだった」のか「誰かが助けてあげるべきだった」のか、わからない。私はヒントを見逃したのかもしれない。望ましいものだったならいいのだが、今憎むべき分断の発生源である別姓婚否定に対し、観客にどういうスタンスを提示したかったのか、謎だ。
なぜハッカアメなのか、それもわからなかった。ググってヒットしたのは、「ハッカアメがコロナに効く」という去年の記事だった。そういうことなのか? 結局民衆は踊らされていたという、そういうことなのか? わからない。それとも、彼らが何を巡って戦っていたのか、その視点を曇らせるための劇だったのか?
あるいはこれらの謎は、単に積み上げられたものの一部として提示され、いわゆる「カオスをカオスのままに表現する」という類のものなのだろうか。観客が、そのカオスの中から何かをつかみ出し、信じて貫き、この対話を始めるための一言目を発する勇気が湧くのを待つための劇なのか?
この劇は観客席にまで到達していない。彼らは苦しそうだった。学生は、あの無機質でクリーンな世界の中で、何かを掴もうと躍起になり、目を輝かせ、躍動し、真摯に舞台と向き合っていた。最後の屋台崩しを見ればそれはひしひしとわかる。彼らは真剣だった。リアルで、今、東京で、最も憲法改正について憂い、考え、不安し、怯え、戦っているというのに。彼らに、客席上空へ飛び立つための滑走路を用意できなかったのは誰だ?
そんなもろもろをこの劇によって与えられたので、私の怒りの矛先はいっそう明確になってしまった。
下の世代に何も課さないでくれ
若い奴ら、がんばれ!じゃないの。
若いエネルギー、すごい!じゃないの。
彼らは、僕らだった。
舞台の一番高いところで、客席を見下ろして、それでもそこはやっぱり客席で、「一市民」で。俳優で、演出の外に出られなくて。何か喋ると思えばマスクつけられて。もう切ない。悲しい。ハケる時だって結局舞台の奥へと去っていく。彼らは、紛れもなく僕らと同じくらい、どうしようもなく何もなすすべがなかった。コテンパンだ。
彼らに、対話の一言目を言うチャンスを与えたい。東京芸術劇場という大きな劇場の一室で、彼らが脇目もふらず、舞台という虚構の上で安心して飛沫を吹き飛ばし、ぶつかりあって涙でぐちゃぐちゃになる、体も魂も混ざり合って、ディスタンスもクソもない、最高にしょうもなく最高にシビれる作品を作り出せる環境を、この手で作ってあげたい。心の底からそう思った。あんまりだ。
彼らがどれだけひたむきに希望を見ようと足掻いているか。その彼らに与えた台詞が、物語が、あれで本当によかったのか?
大人たちは、「憲法というテーマに挑んで偉かった」とか絶対に言うなよ、ちゃんと評価して、あの劇が一体何を表していて、誰に届けるべきなのか(だったのか)、自分の胸に手を当てて考えるべきだ!
それとも、あれが演劇教育の限界なのだろうか?
マイナンバーカードを作らせる側にいることを黙認し、立派な「煙玉演劇」ができたぞとふんぞりかえっているのか?
書けば書くほど怒りが湧いてくる。散々だ。悔しい。
少なくともこれが私が言える対話の第一声です。
「下の世代に何も課さないでくれ!」
想像してもらう、から想像させる、へ
近代口語演劇が浸透してから、演劇のステージは「イメージの押し付け」を嫌い始めたと私は考える。つまり、「想像させる」から「想像してもらう」への移行だ。
「この舞台を観て、いろんな感想があると思います。」
「それぞれ自由に感じてもらえれば。舞台とはそういうものですので。」
とか、もはや常套句のように使われよく聞くが、果たしてこれはこんにちにおいて、「逃げの一手」としての機能が強くなったのではないだろうか。
「表現」は拡散的で自由、「デザイン」は収束的で合理。これらのバランスは舞台芸術において絶妙な感覚を持って織りなされる。ただ最近私が思うのは、表現とは観客にイメージの橋を渡すためにあり、デザインはその橋を叩いて固めるようなものなのではないか。つまり、どちらも適切に機能すべき要素なのではないかということだ。表現はあくまで創作の出発点であり、それによってもたらされるものがなんでもいいわけではない。
とりわけ舞台芸術という「積み上げ」の芸術は、その一挙手一投足に、人間存在の膨大な情報を詰め込むべく最高純度の圧縮が必要なのではないだろうか。劇場に来る観客は、もちろん劇を通してではあるが、究極「人間」を観に来ている。人間を提示するために様々な仕掛けを用意するのが演劇だ。
そのためには、人間をぽいっと舞台に置いただけでは、高濃度な人間情報を受け取ることができない。小一時間で、今までの人生数十年がまるっきり変わってしまうほどの濃い体験を観客は求めているからだ。舞台上の人間がどんな人で、何を纏い、どこに向かうのか、それを観客は一緒に味わったり、あるいは味わいたくないと思ったりする。
どんな要素でもいい。ああ、人間だ、という点に感動したい。私はそう思っている。
想像力の豊かな人は、今の一文からでも、人間の息や肌、脈や眼差しを想像して人間を感じ取れるだろう。しかし、社会生活で慣れて麻痺し、人間がわからなくなった観客には、目の前のものから人間を感じとるのは難しい。彼らに必要なのは「ケレン」や「物語」だったりする。どんな要素でもいい。共感できる入り口が欲しい。
この劇には、「共感」がなかった。巨大なアメという仕掛けも、いかにも何かが起こりそうで、観客の想像を上回るひらめきは与えられなかった。ひたすら観客に俯瞰視のスタンスを求め続け、舞台上のストーリーが大きくなればなるほど、観客は引いた目線で舞台を見下ろす。演出の狙いとしては、観客のアングルが宇宙規模に引き切ったところで屋台崩しを起し、一気に劇場に戻ってもらう算段だったのかもしれないが、どちらかというと観客は、「寓話」を見るスタンスで既にこの劇が劇であることを知り慣れて小一時間座っているので、パネルが下降するという変化だけでは、劇から飛び出るほどのエネルギーがなかった。何より、舞台上の彼らがどうなってしまうのか、そこに観客の興味が続いておらずアイドリング状態だっため、根拠なく俳優たちの舞台裏物語にリフォーカスできるほどの速度で走っていなかった。
つまり、この劇が一体なんなのか、観客は最後まで「想像する」必要があった。そしてさらに、この劇の原点である「憲法」という大きすぎるテーマと、そこに向かうための「永遠の対話」についても想像しなければならなかった。彼らと同様に、私たちもその「想像の入り口」を前に疲弊してしまった。そこが大問題だった。
よし、一緒に考えなくちゃ。
であるとか、
なんで彼らがこんな目に遭わなくちゃいけなかったんだ。
とか、
そういう感情は引き起こされず、ただひたすらに、「ああー憲法について考えるの果てしねえ〜」という絶望が浮かび上がるだけだった。
憲法改悪反対派の私でこれだ。想像できない人はこの入り口にさえ立てないのではないか。
想像させなくちゃいけない。奴らに。もっと。想像してもらうのを待ってる場合じゃない。
そのように誘導、すなわち演出、デザインしなければ。
と私は思うのだが、どうですか?
もう手遅れかもしれない
もう手遅れかもしれない、という昨今において、一日も猶予はないのではないか?
そう思って、私はこれを書くことにした。そして書いた。
上演中の作品で、しかも、しっかり向き合って戦った学生たちに突きつけるにはあまりに辛辣だ。彼らに無力感を与える意図はない。むしろその真逆で、どうしたらこの劇がもう一歩、客席に情熱の火の粉を飛ばす火薬になるのかを考えるための導火線であって欲しい。彼らには何も課したくないが、彼らには彼らの手で自由になる義務がある。
せりふは俳優のものだ。舞台は遊びに満ちている。あのクリーンな日本という舞台の上で、インスピレーションを絶やしてはいけない、日本の空気に負けてはいけない。
なぜ、この劇を上演するのか。その真の価値を、舞台裏にとどめておくのはもったいなすぎる。
手遅れなんてことはない。毎秒、人は考えられる。今は、あなたたちが対話のボールを持っている番だ。思う存分、投げていって欲しい。
今の演劇ファンは、ボールを投げられることに飢えているよ。
p.s
フライヤーの四角い空は、テレビなのかもしれないと、今思った。「自由」を塗り込められた壁。のんびりお茶してる「奴ら」にこそ届けたい劇なのだろう。じゃあ今回、そのギャップを誰が埋めることができたのか?
ここでサポートいただいたお気持ちは、エリア51の活動や、個人の活動のための資金とさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
