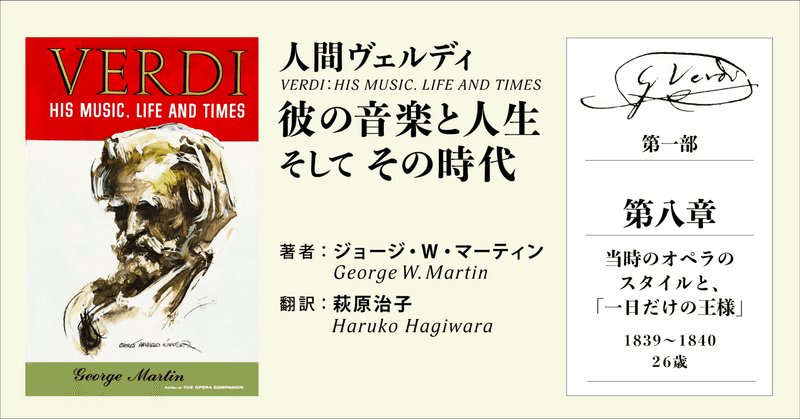
人間ヴェルディ:彼の音楽と人生、そして その時代(8)
著者:ジョージ・W・マーティン
翻訳:萩原治子
出版社:ドッド、ミード&カンパニー
初版 1963年
第一部
目次
第一章:ロンコレ村 (1813〜23年;0〜10歳)
第二章:ブセット町/その1(1823〜29年;10〜16歳)
第三章:ブセット町/その2(1829〜32年;16〜18歳)
第四章:ミラノ市 (1832〜33年;19歳)
第五章:ブセット町の音楽長職を巡っての抗争(1833〜36年;19〜22歳)
【翻訳後記】著者ジョージ・マーティンについて
第六章:音楽長のマエストロ(1836〜38年;22〜24歳)【翻訳後記】私のこの本との出逢い
第七章:ミラノでの戴冠式と「オベルト」初演
(1838〜39年;24〜26歳)
【翻訳後記】「オベルト」の舞台から
第八章:当時のオペラ・スタイルと一日だけの王様(1839〜40年;26歳)
オペラ・セリアとオペラ・ブッファの解説とカストラートの衰退。セリフ台本の新しい傾向と当時の恋愛の考え方。ロッシーニの影響。ヴェルディは次の新作に古い台本を選ぶ。妻のマルゲリータが急死。新作オペラは初演でヤジられ、閉幕。彼の絶望感。「1日だけの王様」を分析する。
【翻訳後記】「1日だけの王様」の舞台とカストラート
(順次掲載予定)
第九章:本人が語ったナブッコ初演までの様子 (1840〜42年;26〜28歳)

第8章:当時のオペラのスタイルと、
「一日だけの王様」
1839~1840年;26歳
オペラ・シリアとオペラ・ブッファの違い
メレッリとの新しい契約の下で、ヴェルディは喜劇オペラ、オペラ・ブッファではなく、深刻オペラ、オペラ・セリアが求められていた。1840年ごろにはまだはっきりと定義が決まっていない新しいタイプだった。ナポレオン時代とその後の政治的、社会的変革は、時には突如暴力的速度で、時にはゆったりと、イタリアの社会を変え、オペラの性格も変化してきていた。観客はそれを期待し、作曲家もセリフ台本作家もそれに応え、それ以前のイタリアン・オペラとは違ったものを提供してきていた。例えば、ワーテルロー以前は一般的にイタリア式喜劇オペラが好まれていたが、ワーテルロー以降は突然、ロッシーニが時代の寵児となる。理由の一つは、ロッシーニの天才的能力だが、もう一つは、ナポレオン戦争で疲弊した人々が心休まる話と、単純なお笑い劇でリラックスすることを望んだからだろう。
1840年にメレッリがヴェルディに深刻オペラを依頼したとき、多分彼はベルリーニの「ノルマ」(1831年)とかドニゼッティの「ランメルモールのルチア」(1835年)のような18世紀の深刻オペラとは違うものを考えていたと思われる。相違はどこを強調するかだったが、それが次第に流行りのスタイルとなっていた。実は1871年にヴェルディは「アイーダ」で、素晴らしい勝利のシーンを作曲して、18世紀スタイルのオペラ・ファンを喜ばせた。
18世紀の深刻オペラは、侯爵邸や王国領宮殿に集まる貴族を相手に、または一段下がって大都市の公共劇場の観客を対象にしていた。オペラの内容は神話または歴史的事件を基にして、オペラの後には夕食か、舞踏会が控えていたので、オペラは必ず、ハッピィ・エンドと決まっていて、劇中、活劇が必ず一箇所含まれていた。1755年のオペラ、「エジオ」は古代ローマ時代の勝利のシーンが有名で、軍隊の行進の謁見、一群の捕虜が引きずられ、民衆が歓喜する中、何百頭の馬が舞台を駆け抜けた。それから、100年以上経って、同系統のオペラは、ようやく「アイーダ」の勝利の行進に引き継がれる。
当時のオペラのスタイル
舞台上のスペクトルよりも、18世紀の深刻オペラの栄光は、アリア曲と歌い手にあった。台本作家は神話や史実からお話を取り上げて、筋書きを作るが、歌い手はその役になりきることなく、自分の美しい声と得意の技術を披露できるアリアをいくつも歌った。このタイプのオペラでは歌い手がスターで、台本作家は、バランスの取れたドラマ展開で、それをクライマックスに持ってくるなどの努力もしなかった。それより、観客はひとつ一つのアリアに興奮して、その前後の筋とのつながりなど、どうでもよかったのだ。
こうしたオペラでは歌い手の技量が求められ、技量のある歌い手は毎回アリアの歌い方に変化をつけて、観客を喜ばした。技量を発揮するのは、スケール、トリルやランなど、またはそのコンビネーションで、歌い手によってはアリアのそういう箇所では、なん百という音符を何分にもわたって披露して、ドラマはなかなか次に進まなかった。観客はそういう歌い手がより表現豊かと信じて、興味はその点に集中して、いかにドラマのムードとアリアの歌詞に合うアドリブや装飾音を入れるかで、歌い手を評価した。オーケストラは全く無用で、歌い手が即興的になると、弾くのをやめ、彼に思う存分歌わせるのが常だった。
カストラートの盛衰
こうした歌い手のスタイルは18世紀から1820年頃まで続いた。このスタイルの歌い手の絶頂期に、特にもてはやされたのはカストラートだった。こういう男性歌手は、少年の時に声変わりしないように、去勢されるので、彼らの声域は男声ソプラノまたはアルトだった。彼らは文句なしに、人類が聞いた最も美しい声と技術を持ち、もてはやされた。ナポレオンは1805年にウィーンを占拠した時、カストラートのジロラモ・クレッセンティーノが歌うのを聴き、感激して、彼に‘ロンバルディアの鉄十字架の騎士’という勲章を授与する。彼はさらにクレッセンティーノをパリに招待し、1806年から1812年まで、彼はテュイルリー皇帝宮殿の一番手の歌い手となる。
19世紀に入ると、声楽やオペラの流行は変わっていくのだが、ゆらりゆらりのスピードで、後になって振り返らないとわからないくらいだった。1824年にメイヤービアが「エジプトの十字軍」の中で、カストラートの役を入れ、人気歌手のヴェルーティによって歌われたが、彼は最後のカストラートの一人になった。なぜ、こういう変化が起こったかは、音楽史研究者の間で意見が別れる。歴史を紐解くと、1810年頃、突然カストラート歌手の数が減る。そして1820年には一人もいなくなる。ということは、1796年に始まったナポレオンのイタリア遠征により、半島の北から南までの音楽院は破滅状態で、音楽家を養成できなくなった。音楽院というのは、多かれ少なかれ、君主や貴族からの寄付に頼っていたのが、ナポレオンの革命軍が来るというので、国外に逃亡するか、または他のことにお金を使ったようだ。教授たちはバラバラになり、学生は入学できなかったか、徴兵にあったか、イタリアの音楽界は政治的混乱の犠牲になった。1815年にようやく混乱は治まったが、当時の批評家は、音楽界の上演と歌手、演奏者の質の低下を嘆いている。その中でカストラートの伝統は消え、それ以後、元に戻ることはなかった。
ナポレオンの登場で、社会は大きく変化して、オペラ鑑賞の観客の構成も大きく変わった。政治、文化において貴族の主導権は弱まり、商工業・通商の奨励などから、ミドル・クラスが台頭し、力をつけてきていた。観客は色白の貴族ばかりでなく、少し赤ら顔の平民が増え、全体がまだら’になったと古風な人々を嘆かせた。そのまだら基盤が社会全体に広がると、その傾向は地理的にも広がった。イタリアの町ごとにオペラ・ハウスが建設されたトレンドは、18世紀ではなく、19世紀の産物。バレッツィが50年前の人だったら、オペラは個人的に楽しむものではなかっただろうし、ウィーンの宮殿劇場とスカラ座の興行師だったメレッリは伯爵の爵位をもらっていただろう。事実スカラ座の彼の前任者、ヴィスコンティは伯爵だったように。
セリフ台本の新しい傾向と当時の恋愛の考え方
観客の構成が変わるにつれ、オペラ・セリアのシナリオも変わっていく。アリアドネやゼウスやハーキュリなどの神話の主人公は少なくなり、ヒロインは「ランメルモールのルチア」や「ノルマ」のように日常生活の中から現れた普通の人だった。古代の神話に基づく話をエンジョイしたり、そこからの隠喩を理解したり、現代と関係付けるには古典の知識が必要。新興ミドル・クラスはその点が欠けていた。ヴェルディに関していえば、彼は彼のオペラにギリシャ神話の主人公を使っていない。それは彼が観客の知識レベルを考慮したわけでなく、彼にとっても、古代ギリシャ神話ははるか彼方のことで、その点イタリアの史実については、彼は独学で勉強していたこともあり、すぐに共鳴した。当然の成り行きとして、彼の観客も同様の反応を示した。外国の圧政下にある民族として、歴史の一部だという感覚もあった。
オペラの主題が神話から民族の歴史へ移行したことは、カストラート役が少なくなったことを意味した。彼らの声は美しく、技術的に高かったが、現実離れした神話や、観客が個人的に知らないような歴史の中の登場人物にしか、適さなかった。オペラのドラマが現実的なものになり、ユグノー教徒の話でも、丘の上の城に住む家族の話でも、隣りの家の男の話でも、カストラートの出番はなかった。カストラートの声では、誰も隣に住む男の声だとは思わない。
オペラ・セリアに欠かせない主題、恋愛についても、18世紀の啓蒙思想から、19世紀のロマン派になると、見方が変わった。18世紀の恋は、人生のつけ足し、楽しいことだが、不可欠ではなかった。ある行動ルールに従う限り、いかなる手段の恋愛でも公に受け入れられた。そのような手段で有名な例は、ヴォルテールが1733年から1749年までの16年間、シャトレ公爵夫婦と幸せに暮らしたことだ。彼が自分の代役を夫人に紹介して、驚かせたが、彼女はそれぞれの誇りを傷つけず、ことを丸く収めたが、その男の子供の難産で死んでしまい、公爵も彼も悲愴な思いを抱く。このような恋愛についての見方は、モーツアルトの「フィガロの結婚」(1786年)でも見ることができる。伯爵夫人は伯爵の女道楽に深く悩みはするが、気が狂うとか、自殺を考えるほどではなく、庭園での恋愛ゲームで彼を取り戻そうとする。
ところが1840年までにロマン派時代が到来し、恋愛は少なくとも、オペラのセリフでは、ただのお楽しみではなく、必然の発作で、崇高な情熱を持って愛する人のみが対象となる。ヴォルテールのような手段は持ってのほかになる。悪い夫は城に閉じ込められ、彼のお供を追い払ってでも攻撃されなければならない。気が狂えば狂うほど、女の魅力は増した。男も女も失恋から絶望して自殺するのは、‘はしか’ほどに当たり前になった。
この感受性の高揚で、台本家のセリフは激しくなり、作曲家たちもそれに合ったスタイルで応じた。古典的な抑制ムードは、ロマンチックな激情のほとばしりに取って代わられ、ますますカストラートや、似たような歌い方の歌手の出番はなくなる。ギリシャ神話の主人公たちも暴力的になるが、それは自分自身の感情からではなく、一歩離れたところからの感情のことが多い。カストラートの落ち着いた、コントロールされたトーンは、オルフェオがエウリディーチェの死を悼んで嘆くのに合っている。この神話の最終シーンで、怒り狂った女性たちが彼の肋骨を一本ずつ折るシーンはオペラには含まれていない。1762年にグルックが「オルフェオとエウリディーチェ」を書いた時、彼は恋人同士がその後は永遠に幸せに暮らすという、18世紀型オペラ・セリアの典型的最終場面にした。1840年までには、作曲家も観客も、感情への直接攻撃の抑制を捨て去り、さらにトリルやスケールなどの術も捨てて、感情の表現の質を問題にした。それで、「ランメルモールのルチア」の最後、エドガルドが自殺するシーンのアリアは、技術的には単純だが、故意的にテノールの声の激しい動悸が感じられるものとなっている。この吹き出した激情はカストラートの静かなる歌とは全く別物だった。
「ランメルモールのルチア」の有名な‘狂乱’シーンは、激情表現の古きと新しきとが混在している。ソプラノはここでカストラートの伝統的な歌い方で歌っているのだ。ソプラノはさらにいくらでも、好きなだけ、トリルなどの修飾術を付けられ、観客もその技量で彼女の能力を評価する。同時に、乱れた髪とか、目をぐるりと回すとか、後ろでコーラスが同情的な歌を歌うとかいうロマン派オペラらしいところも見ることができる。それに比べ、1874年初演の「ボリス・ゴドノフ」のバスの狂乱シーンでは目をぐるりと回すが、カストラートの伝統的歌い方ではなく、ほとんど話し言葉に近い歌い方を聞かせる。
この頃の一番肝心な音楽的変化は、このように古いオペラ・セリアにオペラ・ブッファのテクニックが入り込んだことだった。
オペラ・ブッファは、2次的な出し物として始まった。その目的はオペラ・セリアの幕間に、観客の気分を転換させることにあった。音楽とはもともと人を高尚にする芸術で、正しい領域で感情の高貴な表現であった。ところが音楽に実際に携わる人々の中に、喜劇オペラの方が性に合っていると気づき始めて、彼らはオペラ・セリアの裏で実験を始めた。最初に成功した例はペルゴレージの「奥様女中」だった。1733年にペルゴレージは自分のオペラ・セリア「自惚れた囚人」の幕間に2度、インテルメッツォ(幕あい劇)を入れた。「奥様女中」では、登場人物は主人とメイドの2役と唖の召使いの3人で、1回目の幕間に4つのアリアとデュエットに加えて、行ったり来たりのレチタティーヴォの会話が入る。このイタリア語での会話は母音が多いことなどの特徴をうまく利用して、短い音楽の間に軽妙な短い会話がうまく嵌め込まれた。2回目の幕間の最後にメイドのセルピーナは年老いた主人のウベルトとの結婚を約束させることに成功する。
この小オペラはオペラ・ブッファ伝統の構成と成功の鍵の基を作った。お話は短く、家庭内のこと、または隣の男の話。早い筋とシーンの展開で、話は決着する。
ロッシーニの影響

モーツァルトは1786年に「フィガロの結婚」で、さらに1787年には‘「ドン・ジョヴァンニ」で、オペラ・セリアとオペラ・ブッファをくっつけて、新しいスタイル形成に成功して、現在でも人気を維持している。が、その手法はすぐには広まらなかった。イタリアでモーツァルトは人気にならなかった。ラヴィーニャやロッシーニは賞賛して、研究もしたが、彼のオペラはイタリアでは滅多に上演されていない。イタリアで音楽革命を起こしたのは、ロッシーニだった。もし、彼がそれほどの役割を果たしたように、見えないとすれば、彼の死後、彼の音楽キャリアの半分しか、我々は見ていないからだ。彼は陽気で、贅沢な生活を好み、美しい女性を追いかけ、何よりもフォアグラを好んだ。しかし、彼は自分の音楽を愛し、真の革命家のように、自分のアイデアのために戦った。
ロッシーニが1820年に作曲を始めたとき、オペラ・セリアとオペラ・ブッファは、まだ完全に別物で、それぞれ自立していた。彼は両方とも手がけた。しかし彼はオペラ・セリアの中で、当時の人気カストラートのヴェルッティが、あまりにも大胆にアドリブを入れすぎると感じ、抗議する。それ以後、彼は懇願したり、機転や癇癪で対抗した結果、歌い手は与えられた役から離れず、また書かれた曲からも逸れずに歌うようになっていく。彼がシェイクスピアのオテロを基にオペラ・セリアを作曲した時、彼は原作通り、不幸な結末のままにした。しかし彼以外は、オペラ・セリアでは決して不幸な結末のオペラはないと言い張った。あまりの反対に、彼は別の結末を作曲、その中ではデスデモーナが彼女は無実と、オテロを説得して、最後に二人のセンチメンタルなデュエットを入れた。それから4年後の1820年に彼は、再び不幸な結末のオペラ、「マモメット2世」を発表。この時はヴェニスの劇場だけが、ハッピーエンドの改訂版を求めた。次の「エジプトのモーゼ」では、紅海を舞台に、ハッピーエンドの素晴らしい音楽で、誰をも喜ばしたが、題名のモーゼ役をバス歌手にして、オペラ・セリアの正統派を動揺させる。彼はまた、どんどん下がってきていたオーケストラの質向上を要求したことはその第一歩だった。ローマ公演の時、床屋で髭を剃ってくれた男がオーケストラの第一クラリネット奏者と分かり、彼は失望して家に戻り、彼の演奏部分の難度を下げた。多分、当時のイタリアでは、ヴェニス、ミラノ、ローマ、ナポリ以外の都市では、モーツァルトのオペラを、弾きこなすオーケストラはなかったようだ。そしてロッシーニがラッパやドラムの出番を増やすごとに、歌い手たちからは、彼はドイツ的になって、オーケストラを大事にして、自分たちを犠牲にしていると文句がでた。
しかし、ロッシーニがオペラ・セリアの中に取り入れて、もっとも賞賛された手法は、アンサンブル重唱だった。4人、5人の重唱は美しいもので、さらにこうした重唱は、作曲家がセットできるセリフ台本に影響を与えた。明らかに、4、5人の登場人物が同時に舞台に立って、それぞれの立場を歌い、説明した方が、一人一人にソロ・アリアで歌わせ、ソロのセリフで説明させるより、手っ取り早く、話の筋を展開できる。この最も有名な場面がモーツァルトの「フィガロの結婚」だ。モーツァルトは第1幕と2幕の前半までは、一つ一つのアリアで話を展開しているので、誰もが話についていける。ところが2幕のフィナーレから、話は猛スピードで展開していき、それに慣れない観客は戸惑う。最終幕では、2重唱から始まり、だんだん、増えて、中頃には8人目の歌い手が入り、七重唱になる。この間、22分の間に、舞台に上の歌い手全てが一度は話す。
こうしてオペラ・ブッファの手法をオペラ・セリアに取り入れることで、セリフ台本は詰まったものになり、ドラマ的効果は上がる。初期には、これは古いオペラ・セリアの手法を復活させたと言われたが、後から見ると、これはイタリアン・ロマンティック・オペラの始まりだった。ロッシーニはワグナーのような革命家だったのだ。ベルリーニとドニゼッティにはそれが欠けていた。
ロッシーニの最後のオペラ「ウイリアム・テル」は1829年が初演で、そこには彼と、他のそれほど有名にならなかった作曲家たちが蒔いた種から、地上にはっきりと植物が育っているのが見える。このオペラは神話ではなく、誰にも親しまれたお話が主題になっている。その有名な前奏曲は、オーケストラの重要性を示している。ロッシーニの種々の楽器を駆使したこの曲は、豊かな音色で変化あるものになっていて、ロマンチックな地方色と自然が表現されている。スイスの愛国青年のテノールとオーストリア暴君の妹のソプラノの恋は、困難な問題にぶつかる。反オーストリアの偏見で、そのセリフは後年、ヴェルディが初期のオペラで使ったような政治的色合いを見せている。しかし、ウィリアム・テルはハッピーエンドだが、長すぎるし、セリフが全くよくない。それで、これは音楽専門家のためのオペラ、つまり他の音楽家たちがインスピレーションをもらうオペラになってしまっている。今日、このオペラはコンサートで、前奏曲と、1、2のアリア、それにバレエ曲が演奏されるだけに至っている。しかし、これはメレッリが思うところの理想的オペラ・セリアの良い例になっていた。その実現を彼はヴェルディに託した。最初のオペラ、「オベルト」は、短く、飾り気がないところで成功したが、次回は違ったものをトライするべきと彼はヴェルディに期待したのだ。
メレッリが推薦した台本作家は、1823年にロッシーニの「セミラーミデ」を書き、もっと後の1842年にはドニゼッティの「シャモニのリンダ」を書いたガエタノ・ロッシだった。メレッリはミラノとウィーンの劇場を取り仕切っていて、彼からの推薦は、契約済を意味し、彼はすぐに仕事に取り掛かった。彼は台本の筋書きとテキストの大部分を仕上げた。しかしヴェルディは気に入らなかった。それは「イル・プロスクリット(無法者)」という題で、その主題にヴェルディは惹かれなかった。それで彼はぐずぐずと音楽をいじり回し、メレッリがウィーンから戻るのを待った。
若い作曲家がメレッリの帰りを待っている間、姿をくらますというのは、微妙な状況だ。彼はヴェルディをオフィスに呼び、秋のシーズンに欲しいのは、オペラ・セリアでなく、オペラ・ブッファだと告げる。この変更は、今我々が考えるほど、非常識ではなかったようだ。イタリアの伝統では、作曲家は両方できることになっていた。19世紀ではロッシーニもドニゼッティも両方やっているし、20世紀の涙もろいプッチーニですら、「ジアンニ・シッチ」という喜劇のマスターピースを書いている。双方とも、観客は同じ人々、主力になりつつあったミドル・クラスで、彼らはオペラ・ブッファについても、感情的にはオペラ・セリア、またはロマンティック・オペラに近いものを好んだ。ドニゼッティの「愛の妙薬」の例をとってみると、これはその10年、20年前のロッシーニの喜劇に比べ、愛らしく、チャーミング。それに技量ある歌手が少なくなっていることもあり、ずっと歌いやすいものになっている。オペラ・セリアの台本に文句をつけようとしていたヴェルディは、急にオペラ・ブッファをやれと言われ、彼も前任者たちのように、両方やれると考えたようだ。メレッリは「夢遊病の女」と「愛の妙薬」の台本を書いたフェリーチェ・ロマーニの古い脚本のいくつかを、ヴェルディに渡し、彼が好きなものを選ぶことになった。これらが誰も使っていない台本かどうか、問題でなかった。それにつけられる音楽が、オペラ成功の鍵だったから。
ヴェルディはこの2番煎じの脚本のどれも、気に入らなかった。仕方なく、最終的に「偽のスタニスラウス王」を選ぶ。お話は1733年のフランスで、史実に基づき、スタニスラウスという王様は国難を避けて亡命するが、亡命先のポーランドでそこの国王に選ばれる。ロマーニというフランスに残された護衛騎士の一人が、国王のワルシャワ行脚の安全を願うあまり、フランスの宮廷で、国王の代役を勤める。これによって、彼が結婚しようとしていた婦人と問題が起こり、状況は複雑になる。1818年にオーストリア人の作曲家アダルバ-ト・ジロウエッツが、スカラ座のために音楽をつけたが、成功ではなかった。
ヴェルディとメレッリは題名を「一日だけの王様」に変えて、ヴェルディは作曲に取り掛かったが、すぐに病気になる。口峡炎だった。マルゲリータは彼をベッドに寝かせ、それから数週間、仕事はストップした。
しばらくして、彼は回復するが、5月末に今度はマルゲリータが病気になり、ヴェルディが看病する。彼女の病気は脳炎で、悪くなる一方だった。ヴェルディはバレッツィを呼んで、彼は6月18日にミラノに到着したが、そのすぐ後、彼女は死ぬ。彼女は27歳だった。残された二人はミラノ郊外のサン・ジョヴァンニーノの墓地に埋葬する。それから、バレッツィは、サンシモン通りの彼らの家を閉じて、ヴェルディをブセットに連れて帰る。
メレッリは、特に不親切だったわけではないが、契約があることを強調した。秋のオペラ・シーズンは8月半ばから始まるので、このオペラはすでにプログラムに発表されていた。ヴェルディは解約を懇願したが、メレッリは拒んだ。仕方なく、ヴェルディはミラノに戻り、自宅を開けて、オペラ作曲をした。
「一日だけの王様」は1840年9月5日に初演になり、結果は大フィアスコだった。観客は退屈で黙り込むか、ヤジッたり、ブーイングしたりした。ヴェルディは、慣習通り、オーケストラ・ピットに座っていた。幕が降りてから、舞台裏で、友人たちから祝福と激励を受けた。ミラノの友人の何人かは、欠席だった。翌日、町の批評家たちのコメントは手厳しかった。街の人々は「一日だけの王様」の冗談で皮肉った。そして、その後の公演はキャンセルになる。
ヴェルディは家に篭り、完璧に自制して、精神の暗黒を訴えた。スカラ座でのフィアスコ以前に、ブセットの友人はすでに彼の安否を気遣って、「マルゲリータが亡くなったあと、彼は心理的錯乱の一歩手前だった」と言っていた。彼は神経衰弱で、これ以上仕事はできなくなりそうだった。音楽は彼には慰めにはならない。彼はそれでも自制心は失わず、冷静に人生の再編成をした。
まず彼はメレッリとの契約破棄を試みる。メレッリはヴェルディの能力を十分認めていると、聞き入れなかった。彼は「一日だけの王様」をキャンセルして、「オベルト」を上演した。そして、1回の失敗などで屈するべきでないと言い張った。が、ヴェルディは静かに、そして礼儀正しく、彼はもう絶対に作曲をしないと宣言し、契約破棄の請願を続けた。最後にメレッリはヴェルディの要望を聞き入れた。そして、もしヴェルディが再びオペラを作曲するようなことがあれば、2ヶ月くれれば、上演してあげるとメレッリは約束する。
それから、ヴェルディはマルゲリータが集めた家具をブセットのバレッツィに送り、家を閉じ、彼はサン・ロマノ広場(現在存在しない)にある、家具付きアパートに移った。彼はそこで、来る週も、来る週も独りでゴロゴロしていた。時には、学生をとる話もあったが、彼は何もしなかった。彼は誰も訪問せず、誰も彼を訪問してこなかった。ラヴィーニャだったら、したかもしれないが、彼はすでに亡くなっていた。セレッティは彼を気遣っていたが、ほとんどの時間、ヴェルディは一人で家に篭り、他の人はどうしようもなかった。ミラノに知人、友人がそんなにいなかったのは、確かだが、それより、彼にはいい付き合いはできなかった。いつも彼は広場にあるトラットリアで一人で食事をするか、または自分の部屋で乾パンを水に浸して、食べた。
「一日だけの王様」に、なぜ観客があれほどひどい評価を下したか、今日考えても不可解な点だ。初演の20年後、ヴェルディはこう書いている:あの日以降、私は一度も「一日だけの王様」の楽譜を見たことがありません。あれは確かに、よくないオペラでしたが、同じようなオペラはいくらでも上演され、それなりに受け入れられているのですが」と。その後の上演から見て、特にここ10年に上演された結果、彼の見解は正しいことが証明されている。あの晩、スカラ座の観客は、正しく評価するとか、新米の作曲家に適当な賞賛で喜ばしたりすることを差し控えたらしい。ヴェルディにとって不幸にも、その反対方向に観客のムードは進行して、素っ気なく、そして、手厳しくこのオペラを見下した。
批評家は歌い手がよくなかったと書いている。イタリアのオペラ観客はいつも最上級の公演に慣らされていて、他の国より、手厳しい。またセリフ台本もよくない。オペラはオペラ・ブッファと書かれたが、その中には、笑うようなところは何もない。どちらかというと、メロドラマ的なロマンスで、ウィーンならシュトラウスとかレーハーなどが好んだお話。魅力的な貴族とハイクラスのブルジュアが、人違いからの混乱の中、ハッピーエンドまで、踊り続けて幕。音楽もそのようなものに似合っている。一番のアリアは、ソプラノがいつバリトンが愛を打ち明けてくれるか、待ち焦がれるほろ苦いもの。唯一喜劇的なシーンは、尊大な中年男二人が決闘を前に繰り広げる笑劇的なくだり。ここだけはヴェルディは、輝きのある曲で成功している。しかし、ロッシーニの生き生きしたオペラや、ドニゼッティのメロディックな魅力を期待していた観客には、明らかに失望だった。これはスカラ座でなく、田舎町の劇場か、ミラノでももっと小さな劇場で初演されるべきだった。この時だけは、ヴェルディが最高峰の劇場から出発したことが裏目に出た。

【翻訳後記】「1日だけの王様」の舞台とカストラート
私は2021年にこの本を訳しながら、彼のオペラのDVDを20位買いましたが、この「1日だけの王様」と「アルジーラ」という1845年初演のオペラだけはその中に入っていません。失敗作だからというより、良いDVDが手頃の値段でなかったからです。今回アマゾンを見たところ、2013年にヴェルディ生誕200年を記念して上演・録画・発売になった'Tutto Verdi (全てのヴェルディ)'の一つのDVDがあり、購入しました。YouTubeでは同じものはなく、その15年前パルマ市の宮廷オペラハウスで収録されたものがあったので、見たところ私のDVDは基本的に同じプロダクションだということがわかったので、ここに入れます。
2幕のこのオペラは、確かに悪くなく、特にデュエット、3重唱、6重唱など、ヴェルディらしい美しい曲がいくつも出てきます。これはロッシーニとか、モーツァルトのオペラに似ていると私は思います。会話の間に「ポロロン」とチェンバロが入るところは特に、そしてストーリー自体が「フィガロ」、または「コシ・ファン・トゥッテ」に近いコミック・オペラなのです。このプロダクションでは特に、男性は皆カツラを被り、17世紀の風俗です。音楽は決して悪くないですが、やはり筋が面白くないですね。ジョージ・マーティンが書いているように、ロマン派以前の恋愛は「フィガロ」のように人生の付け足し、「1日だけの王様」はその類のお話です。
音楽についてはとても楽しいものになっていますが、オーケストラの伴奏曲があまり良くないと感じました。ヴェルディも他の作曲家も、当時のオペラ作曲とは、アリアなどの歌唱部分を作曲することで、伴奏などは、リハーサルが始まってから、作曲する話が後に出てきます。その時のヴェルディのタイムラインを追うと、マルゲリータが亡くなるまでに、大方の歌唱部分は作曲していたでしょうが、6月末に彼女が亡くなってから、悲観にくれたヴェルディはブセットに帰り、作曲はストップします。が、メレッリからすでに9月5日初演のプログラムが公表されていたことを指摘され、仕方なくミラノに帰って完成させたということは、リハーサル、伴奏作曲などは2、3週間しか、時間がなかったと思われます。しかし、「不成功」の原因はそれより、このモーツァルト・スタイルのオペラ・ブッファのドラマに、彼だけでなく、観客も全く興味が湧かなかったことだと思います。
この章では、思いがけず、興味深いオペラの歴史が説明され、また私はカストラートに興味が湧きました。3年前にニューヨークのメトロポリタン・オペラで、フィリップ・グラスの「アクナーテン」が同ハウスで初めて上演されました。古代エジプトの話で、その三千年の歴史の中で、一人だけ太陽神を信仰しようとした謎のファラオ、アクナーテンの短い治世が主題。そのタイトル役がアンソニー・ロス・コスタンゾというカウンターテナーでした。確かに独特の美しさで、この役を演じるのにピッタリ(ジョージ・マーティンが言うところの‘隣の家の男’ではない!)。かなり評判になりました。
ジョージ・マーティンによると、彼らの歌は「人類が聞いた最も美しい声と技術で、」とあり、もっと聞いてみたくなり、調べてみると、バロック・オペラでは、現代でもカウンターテナーの歌手が活躍しているのです。バロック・オペラの代表的な作曲家はヴィヴァルディとヘンデルです。まずヴィヴァルディの「オーランド・フュリオソ」というオペラのアリアをフルートの伴奏でカストラートが歌っている素晴らしいものを見つけました。
私はこのvビデオに圧倒されました。ヴィヴァルディは「四季」とかで有名ですが、オペラは初めてです。ウイキペディアでオペラの歴史を読むと、バロック・オペラという言葉は使われず、‘バロック時代のオペラ’はとなっています。そして、ヘンデルは少し説明されていますが、ヴィヴァルディについては、全く触れていません。ところが彼はこのタイプの曲を多く作曲しているのです。
ヘンデルというと、生まれ故郷のドイツではあまり認められず、若い頃イタリアで修行した数年間に、イタリアン・オペラを作曲するようになり、その後イギリスに行って成功したことは私も知っていました。そしてクリスマスとなると彼の「メサイア」がどこでも演奏されますし、有名な曲としては「水上音楽」などもあります。ロンドンで1711年に発表した「リナルド」というオペラは評判になったようです。このオペラでカストラートが歌う場面をYouTubeで見つけたので、ここに入れます。彼の高音は女声のソプラノに近いのではないかと思います。
男性たちが皆ルイ14世的衣装とカツラで登場するこのオペラは、それでけでも、異様な雰囲気を醸し出しています。そしてこの顔を白く塗ったカストラートが歌う場面はさらに異様。でもこの「リナルド」のメロディーは独特の美しさがあって、オペラ専門のラジオでもよく放送されます。
私は彼のような高音を歌う声より、真ん中辺りのカストラートの声がジョージ・マーティンがいう、「この世のものと思えない美しい歌声」だと思います。そこでここにもう一つ、ヘンデルの「メサイア」の一部を入れます。
実は、2019年の冬、クリスマス前にニューヨーク・フィルの「メサイア」のコンサートに行った時、始まる直前に何か緊急事態をアナウンスするため女性が舞台に出てきたので、観客の頭には‘誰が病気?’と、不安な思いがよぎったのですが、彼女はこう言いました。「今晩は‘グッド・ニュース’と‘バッド・ニュース’があります。バッド・ニュースを先に言うと、アルト歌手が病気で欠席です。ですが、グッド・ニュースは代役として、隣のオペラ・ハウスで先週までアクナーテンを歌っていたアンソニー・コスタンザが、今晩代役を引き受けてくれたのです!」。この発表に観客はドッとどよめき、歓喜の声をあげ、このコンサートは特別のものになりました。
今回このビデオを見つけて、ヘンデルは元々カウンターテナーが歌うように作曲したのだと、今気がつきました。
クリスマスも近いことで、是非この部分をお楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
