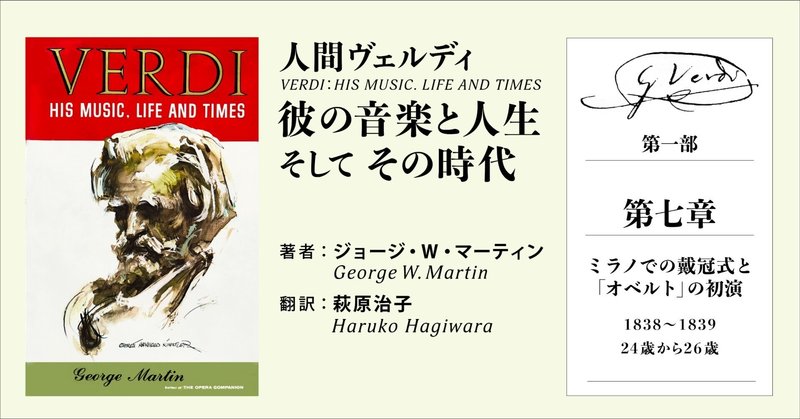
人間ヴェルディ:彼の音楽と人生、そして その時代(7)
著者:ジョージ・W・マーティン
翻訳:萩原治子
出版社:ドッド、ミード&カンパニー
初版 1963年
第一部
目次
第一章:ロンコレ村 (1813〜23年;0〜10歳)
第二章:ブセット町/その1(1823〜29年;10〜16歳)
第三章:ブセット町/その2(1829〜32年;16〜18歳)
第四章:ミラノ市 (1832〜33年;19歳)
第五章:ブセット町の音楽長職を巡っての抗争(1833〜36年;19〜22歳)
【翻訳後記】著者ジョージ・マーティンについて
第六章:音楽長のマエストロ(1836〜38年;22〜24歳)【翻訳後記】私のこの本との出逢い
第七章:ミラノでの戴冠式と「オベルト」初演
(1838〜39年;24〜26歳)
政治的背景と戴冠式の意味。革命家マッツィーニと彼の「青年イタリア党」。「オベルト」上演実現を目指したヴェルディの努力に成果。ブセット町の音楽長職を辞任。メレッリと慈善協会チャリティ公演。オペラ歌手達は「オベルト」を気に入るが、上演は延期になる。それでも彼はミラノに残る決意。リハーサルが始まった時、長男が夭折。「オベルト」を分析する。
【翻訳後記】「オベルト」の舞台から
(順次掲載予定)
第八章:当時のオペラ・スタイルと一日だけの国王(1839〜40年;26歳)
第九章:本人が語ったナブッコ初演までの様子 (1840〜42年;26〜28歳)

ミラノでの戴冠式と「オベルト」の初演
(1838〜39年;24〜26歳)
政治的背景と戴冠式の意味
ヴェルディとマルゲリータは戴冠式の週の真ん中にミラノに到着した。オーストリア帝国の皇帝、フェルディナンド1世はロンバルディア・ベネツィア国の国王として、ミラノの大寺院で、自ら王冠を乗せるために来ていた。その祝賀行事は絢爛豪華なものだった。ヴェルディがバレッツィに書いた最初の手紙は、典型的な観光客の感極まった様子が綴られている。
親愛なるお父上へ
私たちは8日の晩、無事にミラノに到着しました。私たちは自分たちの宿も、馬の宿も、見つけられませんでしたが、幸運にもセレッティ教授のご厚意で、彼の家に泊めてもらうことができました。皇帝の馬上からの軍隊謁見とか、パレードとか、宮廷舞踏会とか、大寺院の飾り付けとかについては、多分新聞でお読みでしょうから、何も書きません。スカラ座の前に列ができているので、出かけます。次は長い手紙を書きます。友人たちによろしく。ギータは元気です。心からキスを送ります。 親愛なる G。ヴェルディ
ミラノ市での戴冠式は1805年6月以来のことで、その時はナポレオン一世が同じ大寺院でイタリア王国の国王として戴冠した。その当時人気を博したそのイベントのことを、今回の祝賀中に持ち出すことは非礼行為だった。市全体として、特に貴族と聖職者たちは、時の政治的な問題などは、ほったらかして、祝賀に参加し、楽しんだ様子だった。
問題は多く存在していたが、オーストリア帝国の宰相メッテルニヒの策略で、戴冠式自体が問題解決への道を示していた。以前に神聖ローマ帝国が存在した。西暦962年から1806年まで続いた。その最後の皇帝だったフランツ2世は、その無意味な国名を批判して、潰した。帝国は2年として、同じではなかったが、理論としては、連盟メンバー国が、その皇帝を選出するヨーロッパ連盟だった。キリスト教の国々の統一と秩序のために結成された。カソリック教会総本山に対抗する、世俗的体制だった。さらに理論としては、連盟国の国主たちが合意したことで、それぞれの国民の合意も得たとした。古代ローマ帝国を引き継いた体制ということで、イタリア人は気を良くしたが、実際には1438年以降の皇帝は全員ハプスブルク家出身だった。宗教改革で全カソリック教会本山は侮辱されたにも関わらず、それでも、この体制は、政治的骨格を維持しながら、ある程度秩序ある社会を望むものたちに、それに人種、言語に関係なく兄弟愛で結ばれていることを好むものたちには歓迎された。
1803年の初め、ナポレオンがドイツになだれ込み、神聖ローマ帝国配下の都市、王国、プファルツ諸国や、何百とある自治体、諸侯領を次々と侵略して、境界を取り壊し、神聖ローマ帝国を事実上破綻させた。代わりに、ナポレオンはババリア地方を含むライン河流域と、彼に従順する全てを一つの連盟に形成した。その脅迫に対抗して、最後の神聖ローマ帝国皇帝のフランツ2世は、1804年に神聖ローマ帝国を解体して、代わりにオーストリア、ハンガリー、チェコスロバリアにポーランドとウクライナの一部を含むオーストリア帝国を結成する。ワーテルローのあとのウィーン会議で、フランツ2世はロンバルディア・ベネツィアを取り返し、ユーゴスラビアとルーマニアの一部を取り込んだ。それに加えて、イタリア内では、彼の親族が両シチリア王国、パルマ、モデナ、ピードモントとトスカニーの玉座に君臨していた。ハプスブルグ家はこうした国の君主と婚姻関係を結んでいたからだ。メッテルニヒは戴冠式を派手にやることで、イタリアの名前だけ独立の地方王国、公国、領国などを、オーストリア体制下に置き、人種と言語を超えた旧神聖ローマ帝国の後任として、イタリア人に協調を求めていた。

それへの協調を表明する目的かのように、戴冠式には地方の小さい諸侯やその取り巻きと、ミラノ市民が、豪華に飾られた馬車や騎兵隊の行進を見ようと、大通りを埋め尽くした。もちろん、ヴェルディの公国、パルマの領主、ナポレオンの未亡人であるマリールイーザの姿もあり、いかに平凡な容姿で、野暮ったいオバサンでも、否定しがたい魅力を漂わせていた。彼女は英雄と結婚したのだ。さらに彼が残したただ一人の嫡男を産んだ。他にもモデナ公国のフランチェスコ4世伯爵(もっとも残忍で、嫌われていた)と、トスカーナのレオポルド2世(最も革新派的で人気があった)、さらには将来的に重要なピードモンド・サルディニア王国の現国王、カルロ・アルベルトがいた。彼の従姉妹のマリアンナはオーストリア帝国の皇帝で、ロンバルディア・ベネツィア王国の新たに戴冠したフェルディナンド1世皇帝の夫人だった。両シチリア王国からは、フェルディナンド2世の代表が送られていた。彼の祖母と2番目の妻は両方ともオーストリア帝国の大伯爵夫人だった。ローマ法王庁からはローマ法王大使が来ていたし、その他、遠縁の貴族や、大使や特別代表団も出席していた。ミラノでは宮殿から出てくる要人たちは皆、馬車と騎兵隊のお供で移動した。
革命家マッツィーニと彼の「青年イタリア党」
メッテルニッヒの後年の惨敗は、ヨーロッパの政治機運が19世紀初頭から、国民的運動にどんどん進んでいたことを無視したことに起因している。イタリアではナポレオンがチサルピン共和国を設立したが、その後イタリア王国を設立したことで、その運動は見落されてしまった。それ以来、愛国派の活動と、18年後にまだモラヴィア要塞にあるハプスブルク家のスピルバーグ牢獄に繋がれたままのコンファルニエリ伯などの殉教者も出たことで、イタリア人の愛国感情は高揚していた。さらに重要な展開として、全イタリア半島に影響を及ぼしたジェノア出身の革命家、マッツィーニの出現がある。しかし、マッツィーニはイタリアを統一国家にしようとして何回か失敗し、1838年当時はロンドンに亡命中だった。彼は1848年に戻るまで11年間、外国亡命生活を送る。帰国の翌年、あの不運なローマ共和国の第一3人執政官を務めた。
メッテルニッヒが外交的に圧力をかけ、マッツィーニをうまくピードモントから追い出し、さらに亡命先のフランスからも、スイスからも追い出し、遠く英国に追いやったことで、影響力が弱化したと考えたのは間違いだった。遠くなった距離で、反対にますます影響力は強化された。マッツィーニ自身が武力革命行為を指揮するなど、具の骨頂だった。1834年に彼がスイスで400何人かの国際革命家たちを招集して、ピードモントを攻撃しようと計画したことがあったが、その半分も行動に参加できなかった。スイス警察は珍しくジュネーブ湖で湖上警備にあたり、1月の厳寒になるまで、革命の熱い血が冷えるのを待った。残りの半分の革命家たちは、国境は超えたが、革命声明文を読み上げるにも、ドラム演奏もなく、せいぜい自由進歩的思想を植え付けただけに終わった。このエピソードは「ある天気の良い日曜日に、、」を目撃しようと集まったスイス人の間の冗談になった。まず1月は革命に向かない。惨事を予測し、2日目には革命家たちはバラバラに散り、観光客を装って、逃亡した。革命のリーダーたちは、この失敗をある中心人物のせいにした。
イタリアでのマッツィーニの革命実現の試みは、そんな具合だったかもしれないが、パンフレット作家としては、亡命中、旧約聖書からの引用も入れた、力強いものだった。1831年から1834年まで、彼はマルセーユに住んで、新しいグループ、「青年イタリア」を結成した。イタリア半島の北から南まで、その事務所や連絡所が張りめぐらされた。彼らの行動は恒久的な結果は産まなかったが、マッツィーニは若いナポリ人、ローマ人、ジェノア人などに、自分たちはイタリア人で、半島はイタリア国で、ローマが首都、そして政治体制は共和国だと教育した。つまり、コンファロニエリ伯のような進歩派貴族も支持する広範な政治的ベースを造った。ヴェルディは秘密結社の支部に属さなかった。メッテルニッヒもだが、双方とも、マッツィーニのメッセージは聞いたし、理解していた。当時のイタリアの空気に中にあり、ミラノの戴冠式に集まった群衆の上に覆いかぶさっていた。
しかし、その分裂もそれぞれがどちらに忠誠心を持つかも、まだはっきり見えてなかった。国民の唯一の国語がフランス語で、それが公式言語でもあるサヴォイ県にある、ピードモント王国では、マッツィ―ニが説く統一イタリア国という考え方は、感情的にまだまだしっくりしてなかった。それよりピードモント王国はその歴史に誇りを持ち、フランス的民族意識とスイスの新宗教的思想にも多少染まった混成文化を誇っていた。ミラノ市はその歴史と政治的現実から、もっとオーストリア寄りだった。多くの家庭は教育のため子弟をウィーンに送っていたし、その中からオーストリア人との結婚も増えていた。さらに伝統があった。例えば、アンドリア・マッフェイは40歳の詩人で、ミラノの社交界のリーダーの一人だが、彼は神聖ローマ帝国の騎士の息子だった。彼は戴冠式を祝したカンタータの詩篇を書いた。メッテルニッヒは、多くのイタリア人がいまだにスピルバーグに政治犯として囚われていることで、嫌われていることは十分承知だったので、フェルディナンドは政治犯の恩赦を約束して、ミラノ入りしている。この恩赦発表で、若い詩人のテミストクル・ソレラはすぐに「恩赦」という詩を発表する。彼の父親は彼が子供の時、スピルバーグ行きの判決をもらっている。メッテルニッヒは少なくとも、この戴冠式をすることでミラノ市民と全世界に対して、オーストリア帝国管轄はいいことだということの見せつけに成功した。
庶民は政状がどうであれ、この機会に大いに楽しもうと決め込んだようだった。パレード見物に人々は大勢押しかけた。詩人たちは王家を讃え、アーティストたちは大きなキャンバスに、新国王の理想像を描き、彫刻家は象徴的な造形を創った。スカラ座の興行師メレッリは国王に敬意を表して、特別ゲイラ・プログラムを発表し、値段はいつもの倍にした。プログラムはロッシーニのオペラ4作とコッポラのオペラ、それにバレエの4点だった。最後のうち「ナブッコドナサー」というバレエは、優雅な背景の舞台とアントニオ・コルテシによる振り付けで、一番評判が良かった。全部で35回の公演で、オペラの第1幕の後に入り、オペラはその後再開され、夜遅くまで続いた。メレッリは9月2日の特別ゲイラ・プログラムで秋シーズンの幕開きとし、6日にフェルディナンドはミラノ大寺院で戴冠した。大寺院の内部は、スカラ座の舞台デザイナー、サンクイリコのデザインによって、飾り立てられた。9日には市が大舞踏会を開き、その1週間後、ミラノ市民はフェルディナンド王と彼の家臣一行がヴェニスへ向けて、発っていくのを見送った。ヴェニスでさらに祝賀会が予定されていた。彼がミラノに来たのはこれが最後だった。大寺院での戴冠式もこれが最後になった。
「オベルト」上演実現を目指したヴェルディの努力に成果
ヴェルディはもちろんこれら祝賀行事に招待されていない。彼は服装や、切符や儀礼事項などは全く頭になく、自分のオペラの話をしたかったが、会う人は皆、昨夜の舞踏会の、または次の舞踏会の話しかしなかった。友人のマッシーニとは話す機会があったが、彼はすでにアマチュア交響楽団の理事を降りていたので、あまり影響力はなかった。マッシーニは1834年に娘の結婚式のためヴェルディがカンタータを作曲してあげたバッロミオ伯爵と、技師のフランチェスコ・パセッティを紹介した。両人ともメレッリに話すことを約束する。もう一人の支持者、ヴィンセント・メリギという音楽院の教授で、スカラ座オーケストラの第1チェロ奏者は、一番強力な支持者だった。メレッリは彼の意見を尊重することで知られていた。
希望としては、シーズンの最後に「オベルト」上演を入れることを、メレッリに説得することだった。そのあと、演劇界慈善協会のチャリティ公演が始まる。これはメレッリの前任者のカルロ・ヴィスコンティ伯が始めた「聖なる演劇界団体」で、生活苦の声楽家、俳優を援助するのが目的。当然のことながら、スカラ座の常連客に人気があった。メレッリは理解ある観客で満席にするだろうと言われた。もし、オペラが成功すれば、上演を延長できるし、失敗作なら、初日の売り上げを慈善協会に寄付すれば良かった。戴冠式祝賀会で業績が良かったので、メレッリは多分、秋のチャリティ公演は中止するのではないかと町で噂されていた。
ヴェルディは、滞在が長引いて、持ち金もなくなりかけて(バレッツィはさらに送金したが)、すぐに何も起こりそうもないので、とりあえず、ブセットに帰ることにした。ところが、その時、突然事情が変わって、居残ることになる。どうもメリギに説得されたようで、メレッリは「オベルト」の楽譜を真剣に読んだ結果、多少の直しを入れて、1839年春の慈善協会行事に「オベルト」を上演すると約束したのだった。
ブセット町の音楽長職を辞任
このニュースを手にすると、ヴェルディとギータはすぐにブセットに戻った。戻ってすぐヴェルディはまずバレッツィに相談してから、町の音楽長職からの退職願を提出する。彼が書いた市長への手紙は不快なお願いを求める典型的な手紙だった。まず、雇用契約に基づき、退職の6ヶ月前に提出していることを強調し、さらにこの町を去ることについての遺憾の気持ちが表現されていた。最初の文章で、彼は始める前に期待されたほどの貢献を町にすることができなかったことは残念だとも書いた。
市長も慈善基金協会の理事も町の不幸な現状について、よくわかっていた。ブセットの教会ではいまだに音楽は演奏されず、毎日曜日や祝日には音楽をどうするかが議論され、強情な誰かが譲らないバカバカしさを嘆いた。理事たちはすぐにヴェルディの退職願を受理し、教会で音楽は必要なので、できないことを残念だとしたが、それぞれ、ヴェルディが町を離れることに、ある種の安堵を感じているようだった。ヴェルディは6ヶ月分の給料をもらって、すぐに離職を許可された。
ヴェルディとギータはクリスマスをブセットで過ごし、そのあと引越しの準備をした。ギータが荷物を片付け、ヴェルディはオペラに取り組んだ。当時のイタリアでは、結婚生活の中での役割分担は、家事と子供に関しては、すべて妻の役目だった。ロンコレ村の貧農の家庭でも、夫が皿を洗ったり、ベッドを直したり、オムツを替えたりすることはなかった。反対に、家にきたお客は必ず、先ずは夫人を丁重に扱うのが普通で、お客の前では女王のように扱われた。そして、一旦食事が終われば、夫人はキッチンか自室に入ってしまう。ヴェルディは皿洗いをしたことがなかったかもしれないが、ギータもしたことがなかったに違いない。当時労働力は安かった。貧農家庭の出遅れ娘、未亡人など、夫や家族がいない女性は、村では何もできないので、町に出て、裁縫師や洗濯女、料理番、メイドなどの仕事に携わった。マルゲリータはバレッツィ家の令嬢、多分、彼女には最初からメイドがいただろう。
ヴェルディが自分の音楽の上演の機会を求める限り、ブセットにはいられなかったことを、バレッツィは十分理解して、喜んでもいた。プロヴェージもラヴィーニャも言っていた通り、ヴェルディにはもっと広い世界が必要だった。しかしバレッツィ夫人は多分、悲しい思いもあっただろう。男性は時々、商用などの際、会うこともあるだろうが、彼女とマルゲリータにとって、これは別離を意味した。彼女は孫の成長が見られないが、次に妊娠した時は、ミラノに行くことになるだろう。マルゲリータ自身は喜びと悲しみを行き来した。彼女はどちらの町ででも家庭を作ることができただろうが、ブセットの方が、多分もっと楽しかっただろう。しかしヴェルディの仕事のためにはミラノに住む方がよく、そのためなら、たとえ、ミラノが外国で、違う方言を話すところでも、すでに2回も行ったのだから、また行きましょうと考えただろう。
1839年2月6日、ヴェルディはマルゲリータと、イチリオ・ロマノと一緒にブセットの町を後に、ミラノに引っ越した。彼はオペラに修正を入れ終えていて、早くミラノに行きたがっていた。近くにいることでメレッリに多少でも圧力になり、「オベルト」上演を絶対やってもらおうと意気込んでいた。ヴェルディは「見えなくなったら、思いも遠のく」という格言を知っていたし、事情が変わったという言い訳を恐れた。メレッリにとって、カーニバル・シーズンはうまく行ってなかった。彼が選んだ6つのオペラのうち、3つは失敗作で、うち2つは新作だった。噂ではメレッリは多分、それを取り返すため、春のシーズンは評判の良かったオペラを組み入れるだろうと言われていた。
メレッリと慈善協会のチャリティ公演
そういう事情で、メレッリは人気歌手を揃えてプログラムを発表した。男声の方では、イタリア一番のテノールのナポレオン・モリアニと、ドニゼッティで知られるバリトンのジョージオ・ロンコーニを選んだ。ソプラノには今評判で、ミラノ初登場のジョセッピーナ・ストレッポーニを選ぶ。彼女はミラノ音楽院で勉強して、1835年にトリエステでデビューした。それを皮切りに、フィレンツェ、ヴェニス、トリエステの小さめの劇場で歌い、そのあとのウイーン公演では大成功を収めた。その彼女が国際的歌手として、ミラノに来るというので、期待が高まっていた。ロンコーニと同様、彼女もドニゼッティを得意としていたから、そのシーズンはドニゼッティのオペラで占められると予想された。メレッリが最終的に演目を発表した。ドニゼッティの「ランメルモールのルチア」、「ピア・デ・トロメイ」と「愛の妙薬」に、ベルリーニの「清教徒」が入っていて、ストレッポーニはすべて歌うことになっていた。
このスケジュールはどんな歌手にとっても過酷だったが、当時、特にイタリアではそれが普通だった。1830年代のプリマドンナは、1890年代のような栄光の、独立した、そして著作権からの収入が入ることで、気に入った時にだけ歌うスターではなかった。ストレッポーニを例にとっても、彼女のキャリアはエージェントが勝手に彼女の承諾なしに、興行師のそのシーズンのニーズによって、貸し出される仕組みにあった。興行師は自分の劇場のシーズンしか頭になく、週に4回、5回歌わせることも多かった。結果として、声楽家としての生命は、華やかだが短かかった。アーティストたちはそれから脱出しようとはしたが、真に素晴らしい歌手のみがその罠から出ることができた。ストレッポーニは収入確保のことで、縛られていた。彼女は文盲で未亡人の母親と4人の兄弟姉妹、それに自分自身の私生児を養っていたのだ。
彼女の当時の手紙には、キャリアに関して、絶体絶命の状態の様子が描かれていたが、もちろん、ヴェルディも一般世間も全く知らないことだった。彼らは舞台に立つ、どちらかというと小柄の20代半ばこのソプラノは、スタイルがよく、透明な美しい声を持ち、さらに演技がうまいと評していた。スカラ座のシーズンでは、彼女は喜劇の「愛の妙薬」でも、悲劇の「ランメルモールのルチア」でも上手にこなすとみられていた。ヴェルディがぜひ彼女に、「オベルト」を歌ってもらいたいと考えたのは当然だった。
オペラ歌手たちは「オベルト」を気に入るが、上演は延期になる
一方、マッシーニとメヒギは、メレッリにこのオペラについて、圧力をかけようとする。彼が歌手たちに楽譜を見せたところ、彼らから好意的な評価をもらった。そこでメレッリは慈善協会のチャリティ公演に「オベルト」を上演すること、歌手はカーニバル・シーズンの3大歌手、プラス イグナチオ・マリーニと発表した。ヴェルディはリハーサルのスケジュールを渡され、それまで、楽屋をウロウロしていた痩せた男は、一夜にして、有名人になる。18ヶ月前は、誰か力量のあるマエストロが自分の作曲をみてくれたらと願っていたのが、突然スカラ座の舞台で、スター的歌手陣による上演で、一般市民に観てもらえることになったのだ。ところが、リハーサルが始まるか始まらないとき、テノールが病気になり、上演はキャンセルされる。
ヴェルディの思いは落胆から失望になった。彼を悩まし続けるこのオペラを投げ出したくなる。職なしでどうやってミラノでの生活を維持できるのか?または職なしでは、ブセットに帰ることもできない。しかし、マルゲリータと子供のことを考えると、ブセットに帰るほかないように思われた。このオペラの上演の見通しはなく、ミラノを去るのはこれで2回目。今回の方が前回より、見通しは悪い。
突然、メレッリは秋シーズンの演目に入れる
そのとき、演劇でよくある真っ暗なものが突然真っ白になるように、メレッリは秋のシーズンに「オベルト」を上演することを、ヴェルディに約束する。これは慈善協会のためのチャリティ公演とは違う。正規の演目に組み込まれたのだ。運が良いか悪いか、いずれにしても他のいくつかの演目と並んで、上演が予定されれば、他の劇場、都市からの興行師の目に触れるチャンスも多い。当然、ヴェルディはこの申し出でを受け入れ、家族をブセットに帰す話はキャンセルになる。
メレッリはどうも、秋のシーズンに2つのオペラしか、駒がなかったらしい。リッチと、もう一人はラヴィーニャの後を継いで、音楽院のチェロの教授であるパニッツァの作品だった。それでヴェルディが3番目に選ばれたのだった。メレッリはある晩、何かの公演中に舞台の袖で、バリトンとソプラノのおしゃべりを耳にしたと、ヴェルディに語った。その中でソプラノ、つまりストレッポーニは「オベルト」を賞賛して、バリトンも同意したという。それで、メレッリ自身もその楽譜と台詞台本を念入りに勉強したところ、セリフ台本はよくないが、音楽はいいと結論した。メレッリは若い頃、セリフ台本を何本も書いたことがあり、彼の意見は正しかった。ヴェルディは問題なく同意した。

メレッリの助言でソレラと修正作業
当時セリフ台本は皆、韻文で書かれた。メレッリはヴェルディにテミストクル・ソレラという若い詩人と、修正の仕事をすることを勧める。さらに修正だけでなく、第2幕に新に4重唱を入れることも。ソレラは脚本作家だけでなく、作曲もする男だから、韻文のシナリオから、もっと歌にあったセリフに修正できると考えられた。こうして、メレッリの承認を得ただけでなく、彼の助言に沿って、ヴェルディは「オベルト」の脚本を書いた新聞記者のピアッツァより、ずっと優秀な脚本作家と共同作業を始めることができた。
夏中、ヴェルディはオペラの修正と何曲かの短い歌曲を作曲する。その内3曲を出版社のカンティに送る。一つは3声部と、フルートとピアノのための曲で、ほか2曲は歌曲だった。どれも以前に書いたものほども優れていなかったが、その一つは「亡命」と題したソレラの詩だった。外国の海辺で夕日を見ながら、故郷への思いと親の頰に口づけすることを思い嘆く。ヴェルディは輝かしいものを創ろうとしたようだ。初めの夕日のシーンでは長い感情的なピアノで始まり、次に伴奏なしのソロでレチタティーヴォが入り、そこからはヴェルディらしい、ボイスとピアノの絡み合いになる。1839年のイタリアでは多くが亡命した家族を持っていたので、この主題自体はすぐに注目を浴びた。しかし、音楽も詩篇もよくなかった。
2番目の歌「誘惑」は滑稽なくらい良くない。この2曲はヴェルディの初期時代のよくない作品だが、ある意味ではヴェルディが徐々にそうした作曲の術を、学びつつあることを表している。1830年代の人々は皆、死と乙女にため息をつき、自然の美しさに目覚め、廃墟に魅せられ、ロマンティシズム時代にふさわしい思いにあふれていた。
ヴェルディとギータはまだアパートを借りていたが、それより安い家賃で一軒家が借りられるというので、引っ越しシーズンの9月に、その前払い金の工面をする。つまりバレッツィに手紙を書く。
1839年9月4日
親愛なる義理の父上へ
いつも私たちのために親切な心遣いをしてくださるのに甘えて、またお願いをする決心をしました。
現在私たちはまだ聖ミケーレ地区にいるのですが、一軒家に移るには、家賃の前払い金が必要になり、私には持ち金がありません。現在オペラに取り掛かっているので、他の仕事を探すわけにはいきません。私のオペラについて、お会いした時にはお話しますが、内緒で上演の話が進んでいることをお伝えします。今までで一番、良い上演条件です。
バレッツィは送金してあげた。しかしこのお金はヴェルディには知らされなかったが、実はブセットの後援者、ソルダティ男爵夫人からだった。そのお金でヴェルディは聖シモン通り3072番の小さな家に引っ越した。ティチネーゼ駅の近く、現在のシザー・コレンチ通りにあり、治安があまり良くない地域で、家族はひっそりと暮らした。
長男の夭折
10月の半ば、「オベルト」のリハーサルが始まろうとしていた時、イチリオ・ロマノが病気になった。家には医者代、薬代のお金がなく、ヴェルディはミラノの住むバレッツィの姪に手形を書いて、借金をしたが、無駄に終わった。10月22日、イチリオは短い生涯を閉じた。ヴァージニアの時と同様、病気の原因はわからない。両方とも16ヶ月で亡くなってしまった。2番目の子供の死はマルゲリータにはきつかった。ヴェルディはリハーサルなどで気を逸らすことが可能だが、マルゲリータは空っぽの家で、夫にも慰めてもらえない。
「オベルト」の初演
1839年11月17日の「オベルト」の初演には、バレッツィ、息子のジョヴァンニ、それに数人の友人たちがミラノに駆けつけ、オペラの出来がどうであろうと、拍手喝采して応援するつもりでやってきた。メレッリはキャンセルになった慈善協会のチャリティ公演の時ほどではなかったが、質の高い出演者を揃えてくれた。バスのマリーニはそのまま、ほかの出演者もまあまあのレベル。ソプラノの一人、メアリー・ショーはイギリス人で、彼女はヴェルディについての熱狂的なニュースを、初めてイギリスにもたらした人だった。当時の習慣に従って、公演中、ヴェルディはオーケストラの第1チェロ奏者とベース奏者の間に立ったので、そこから、観客の拍手もおしゃべりもよく聞こえた。
最後の幕が下りたとき、オペラ初演は大成功ではなかったが、まあ成功の部類に入った。秋のシーズン中で、メレッリは上演を14日も延長した。批評家たちは好意的で、もちろん良い点、良くない点、他の作曲家と似ている点などを指摘した。ある批評家はベルリーニと比較して、「メロディーが多い、いや多すぎる」と書いた。セリフ台本については、ピアッツァ、メレッリ、ソレラ、それにヴェルディも手を加えたわけだが、全体に弱いと批判された。オペラの筋は貴族女性が恋に落ちたが、捨てられ、地方の城の周りでの決闘もある恋愛もので、音楽が「魅力的」と書かれた。主人公のソプラノは、最後に恋人が父親を殺したことを知り、絶望の中で死を考えるが、バックでコーラスが天国から慰めの歌を歌うところで幕が降りる。現代において、このオペラはヴェルディの最初のオペラということで、興味が持たれ、フェスティバルなどで上演されることもある。
最初のオペラの上演とすると、悪くないスタートだったと言える。メレッリはすぐにあと3つのオペラの作曲の契約を、ヴェルディと交わし、スカラ座とウィーンの宮殿劇場で上演されることになった。彼は一つのオペラに4千リラを払い、著作権が売れたら、儲けは半々と約束する。これは駆け出し作曲家にしてはとても良い契約内容で、メレッリがヴェルディの才能を信じたことを物語る。他の劇場の興行師たちもヴェルディに近づき、「オベルト」の上演を申し込んだ。1840年のカーニバル・シーズンにはトリノで、1841年にはジェノアとナポリの上演が決まった。
このオペラでヴェルディの経済的問題が全て解決したわけではないし、死んだ子供は帰ってこない。だが、彼の仕事が認められたことで、家庭に希望と落ち着きをもたらした。彼とギータはまだ若く、健康なのだから、これからまた子供を作ることは可能。これからもミラノに残って生活を続け、ブセットからは離れた生活をしていくことになる。ギータはヴェルディが自宅で、時々このオペラの4重唱のメロディを歌うのに気がつく。

【翻訳後記】 「オベルト」の舞台から
やっとヴェルディの処女作の上演まで、漕ぎ着けました。ここでこの「オベルト」のオペラ全部を入れたいところですが、DVDの著作権の問題から、それはできません。そこでYouTubeで探したところ、ありました。私が買ったビルバオ・オペラ制作/上演のものの前奏曲と第2幕のバス歌手のアリア部分です。これのリンクを入れます。
一つ目は「オベルト」の「シンフォニア」と呼ばれる7分の前奏曲で、この中には、劇中に出てくるアリアなどのテーマ・メロディーが紹介されています。これは当時の慣習に従ったと言われています。なかなか、心地よいピースです。その後幕が開き、第1幕のコーラスとテノールのアリアが入っています。このテノール役は悪役です。
2つ目は第2幕の中頃、娘を唆した男への復讐を誓うオベルトのレチタティーヴォとアリアです。このバス歌手はイルダー・アブドラザコフという今人気のロシア人です。彼は声がいいだけでなく、堂々としていて、舞台での存在感があります。さらに演技が上手です。ロシアーウクライナ戦争で彼はどうしているか?気になりますが、ニュースにはなっていません。私は2016年にサンクトペテルブルクの新しいマリインスキー劇場で、ヴェルディの「アッティラ」を彼出演とワレリー・ゲルギエフ指揮の舞台で観ました(私の「この旅でいきいき」のVol. 4:ロシア編(3)でこの時のことを書きました。)。指揮者は世界的に有名で主にヨーロッパで活躍していましたが、プーチンと親しかったので、2022年2月に戦争が始まると、すぐに常任指揮者を務めていたドイツのオーケストラから辞任させられました。
私がこのオペラをDVDででも観たいと思ったのは、前章で紹介したあのテレビドラマで、ストレッポーニ(ヴェルディの第2夫人)が、ヴェルディから渡された楽譜を見ながら(初見で)歌うシーンがあり、変わった高音のメロディーのあと、2オクターブ下がるアリアを歌い、そこをもっと観たいと思ったことが始まりです。これが‘ヴェルディのソプラノ’の始まりだと言われています。しかし、これを上手に歌えるソプラノはなかなかいないらしく、マリインスキー劇場の「アッティラ」でも似たような部分のソプラノのアリアに私は‘ダメ’の評をしています。ビルバオの上演でも、ソプラノがイマイチで、その結果YouTubeに彼女の歌う部分は挙がってないのでしょう。
ジョージ・マーティンは、最後はこのレオノラが死を考えるが、天使のコーラスで思いとどめるように書いていますが、私のDVDでは、剣で胸を刺して、自殺します。ジョージ・マーティンが書いているように、このオペラは滅多に上演されません。ですから、彼は実際に舞台では観ていないと思います。
私が買ったDVDはスペインのバスク地方のビルバオのオペラ団による公演で、2007年に録画されたもの。私は2018年にここに行きました。ビルバオは現在グッゲンハイム美術館があり、フランク・ゲイリーの超モーダンな建物で有名なところです。この地方は18、19世紀には重工業で栄えたあと、20世紀後半には荒廃化したのですが、都市の再開発を大規模にやって、成功したようです。現在スペインでは5番目くらいの人口集中地方。そこのオペラ団が「ヴェルディを全部(Tutto Verdi)」という企画のもとで、この「オベルト」を制作したようです。
このDVDには「おまけ」として、指揮者のYves Abelがこのヴェルディの“処女作“を解説しています。それによると、彼はこれは当時人気があったロッシーニ、ベルリーニ、ドニゼッティをお手本に、優秀な音楽家が書いたものと言え、ヴェルディは初演で成功を目指して、当時のファンが喜びそうな音楽をつけたよう。音楽はベルカント・スタイルで、多少軍歌調、そして中世の騎士ものストーリーは「仇討ち」がテーマと言っています。その中にすでに後年のヴェルディ・スタイルの芽生えを聴くことできるというのが、彼だけでなく、大方の評価です。またヴェルディは父親と娘の関係を扱ったオペラが多いことで有名ですが、このオペラはたまたま知人から渡された台詞台本に曲をつけたのですが、図らずも父娘の話で、これもヴェルディの処女作にふさわしいドラマだったと言えますね。
題名のフル・ネームは「サン・ボニファッチョ伯爵オベルト」と物々しく、ストーリーも騎士と淑女の恋愛を扱う普通の’騎士もの’というより、騎士道が本題です。ですから、このビルバオ制作の舞台セットは、時代は中世のままでなかなかよくできています。時代物にするとお金がかかるので、最近は時代を近代に動かす演出も多いのですが、このように比較的簡単な舞台セットで、時代はそのままというのが、これからのオペラの方向だと思います。貴族女性のドレスはラファエル前派スタイルと評されています。確かに侍女は特にラファエル前派の絵に出てきそうな容姿です。
もう一つ、カラヤン指揮の「シンフォニア」を見つけたので、ここに入れます。オーケストラはベルリン・フィルで、指揮者はカラヤンです。多分1970年代のもので、動画はありませんが、写真が入っています。観るとこの頃のオーケストラの奏者はほとんど男性だったことがわかります。それでも女性も各部門に一人。二人見えます。2022年11月のニューヨーク・フィルでは初めて女性奏者の数が男性を追い抜いたそうです。時代は進化しています。
大オーケストラの定期コンサートは、この「シンフォニア」のような短めの曲で始めることが多いのですが、ベルリン・フィルのカラヤンがこの曲を選曲したことに注目したいと思います。でも、これに限らず、カラヤンが指揮したオペラを聴くと、なぜか彼はどれもテンポがとてもゆっくりなのが気になります。演奏の質はやはりベルリン・フィルの方が圧倒的にいいですが、前出のビルバオの演奏は、ドラマティックでメリハリがあリます。これはカラヤンの偉大さを理解していない、私の私見です。
最後にもう一つ、私のオブザベーション、このOpus ArteのDVDのケースの裏を読むと、TVE(多分TVヨーロッパでしょう)とNHKがテレビ放映元に入っています。NHK はこうしたプロジェクトに参加して、それで得た独占放映権で夜中に BSで放映しているのではないかということです。でも日本のオペラファンは非常に限られているので、もっといい時間帯に放映できないし、再放映もしないのではないでしょうか?この状況は、日本語字幕の入ったオペラのDVDが少ないこととも関係しているのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
